事例の要約
右変形性股関節症の進行により転倒し、股関節周囲の疼痛と機能障害を呈し、手術適応となった高齢女性の事例。入院5日目の介入。
基本情報
氏名はB氏とする。72歳女性で、身長152cm、体重58kg。家族構成は夫と長女の3人家族で、キーパーソンは夫である。職業は清掃業のパートタイマーとして週3日勤務している。性格は真面目で責任感が強く、家族思いである。感染症は特になく、アレルギーは卵アレルギーがある。認知力は正常で、MMSE28点と良好である。
病名
右変形性股関節症(末期)
既往歴と治療状況
10年前から右股関節痛があり、整形外科で変形性股関節症と診断されている。これまで内服薬による疼痛管理と理学療法を継続していたが、症状の進行により日常生活に支障をきたすようになった。高血圧症で降圧剤を内服中である。
入院から現在までの情報
自宅の階段で足を滑らせて転倒し、右股関節部に激痛と腫脹が出現した。立ち上がれずに救急搬送され、画像検査で股関節の著明な変形と関節裂隙の消失を認めた。入院後は安静を保っているが、疼痛により移動が困難な状態が続いている。理学療法士による筋力訓練と歩行訓練を開始しているが、疼痛のため十分な訓練ができていない。
バイタルサイン
来院時は血圧152/88mmHg、脈拍98回/分、体温37.2℃、呼吸数22回/分、SpO2 96%であった。現在は血圧138/82mmHg、脈拍82回/分、体温36.8℃、呼吸数18回/分、SpO2 98%と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を摂取し、嚥下機能に問題はなかった。喫煙歴はなく、飲酒は晩酌程度であった。現在は食欲が低下し、「口の中が苦い」と訴えて摂取量が減少している。毎食3分の1程度の摂取量で、家族が持参した和菓子を少量摂取している程度である。
排泄
入院前は自立しており、便秘傾向はなかった。現在は移動時の疼痛を恐れてトイレに行くことを躊躇し、水分摂取量も減少している。入院後3日間排便がなく、腹部膨満と腸蠕動音の減弱を認めている。
睡眠
入院前は6時間程度の睡眠をとっていた。現在は夜間の疼痛と病院環境により中途覚醒が多く、熟睡できていない。眠剤の使用は希望していない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼鏡使用で良好、聴力に問題なし。知覚は正常で、コミュニケーション能力も良好である。特定の信仰はない。
動作状況
歩行は疼痛により困難で、歩行器を使用した部分荷重歩行を実施している。移乗は介助が必要で、右側への体重移動時に強い疼痛を訴える。排泄は車椅子でトイレ移動し、一部介助が必要である。入浴は清拭で対応している。衣類の着脱は上肢は自立、下肢は介助が必要である。転倒歴は今回が初回である。
内服中の薬
- ロキソプロフェンナトリウム 60mg 1日3回 毎食後
- レバミピド 100mg 1日3回 毎食後
- アムロジピン 5mg 1日1回 朝食後
- ピコスルファートナトリウム 7.5mg 1日1回 就寝前(便秘時)
服薬状況
看護師管理で実施している。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(5日目) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 8,200 | 7,800 | 4,000-9,000 |
| CRP | 1.8 | 2.5 | <0.3 |
| K | 3.3 | 3.2 | 3.5-5.0 |
| LDL | 186 | 182 | <120 |
| HDL | 35 | 36 | >40 |
| 総コレステロール | 255 | 248 | <220 |
| Alb | 3.8 | 3.5 | 3.8-5.3 |
今後の治療方針と医師の指示
保存的治療では症状の改善が困難であり、人工股関節置換術の適応と判断された。手術は来週予定されており、術前検査と術前指導を実施中である。術前の理学療法継続と栄養状態の改善、便秘の解消が指示されている。
本人と家族の想いと言動
B氏は「手術は初めてで不安」「痛みがこんなに続くとは思わなかった」と話している。家族への負担を心配し、「夫に迷惑をかけて申し訳ない」「仕事を休んでいるが、早く復帰したい」と責任感の強さを示している。夫は「妻の痛みを見ているのが辛い」「手術で良くなってほしい」と話し、長女は「母の回復を信じて支えたい」と協力的である。
アセスメント
疾患の簡単な説明
B氏は右変形性股関節症末期により疼痛と機能障害を呈している。股関節疾患そのものは直接的な呼吸器疾患ではないが、疼痛による浅い呼吸や活動制限に伴う廃用症候群、さらに高齢による生理的変化が呼吸機能に影響を与える可能性がある。変形性股関節症患者では疼痛回避のための不動による肺合併症のリスクが高まることが知られている。
呼吸数、酸素飽和度、肺雑音、呼吸機能、胸部画像
現在の呼吸数は18回/分と正常範囲内であるが、来院時は22回/分と軽度頻呼吸を呈していた。酸素飽和度は98%と良好な値を示している。肺雑音に関する具体的な情報は記載されていないため、聴診による詳細な評価が必要である。72歳という高齢であることから、加齢による肺活量の低下や胸郭の可動性減少が生理的に生じている可能性がある。胸部画像所見についても具体的な記載がないため、術前検査として実施される胸部レントゲンや必要に応じて胸部CT検査の結果を確認する必要がある。長期臥床による肺底部の換気不全や痰の貯留リスクも考慮すべきである。
呼吸苦、息切れ、咳、痰
現在のところ明らかな呼吸苦や息切れの訴えは記載されていない。しかし、疼痛による活動制限により呼吸筋の廃用や心肺機能の低下が進行している可能性がある。理学療法時の呼吸状態や軽度の活動時における呼吸困難の有無について詳細な観察が必要である。咳嗽や喀痰の有無についても具体的な情報が不足しているため、気道クリアランスの状態を評価する必要がある。長期臥床により気道分泌物の排出が困難となり、肺炎のリスクが高まる可能性がある。
喫煙歴
喫煙歴はないとされており、これは呼吸器系にとって良好な要因である。受動喫煙の影響についても確認が必要であるが、現時点では呼吸器疾患のリスクファクターとしての喫煙の影響は除外できる。
呼吸に関するアレルギー
卵アレルギーがあることが記載されているが、吸入性アレルゲンや薬剤性アレルギーによる呼吸器症状の既往については明記されていない。術前麻酔や使用予定薬剤に対するアレルギー反応の可能性について詳細な確認が必要である。
ニーズの充足状況
現在の酸素飽和度98%から判断すると、基本的な酸素化は保たれている状態である。しかし、疼痛による体位制限や活動制限により、深呼吸や効果的な換気が阻害されている可能性がある。入院5日目という時点で、廃用症候群による呼吸筋力低下や肺活量減少が懸念される。人工股関節置換術という侵襲的手術を控えており、術後の呼吸器合併症予防のために術前からの呼吸機能維持・改善が重要である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、疼痛による呼吸抑制、長期臥床による呼吸筋力低下、術後肺合併症のリスクが挙げられる。看護介入では、疼痛コントロールを適切に行い深呼吸を促進すること、体位変換や可能な範囲での離床を促進すること、術前から呼吸リハビリテーションを実施することが重要である。また、術前の詳細な呼吸機能評価として胸部画像の確認、肺機能検査の実施、聴診による肺雑音の有無の確認を継続的に行う必要がある。水分摂取量の減少により気道分泌物の粘稠度が高まる可能性があるため、適切な水分バランスの維持も重要な介入点である。今後も呼吸状態の観察を継続し、わずかな変化も見逃さないよう注意深い観察が必要である。
食事と水分の摂取量と摂取方法
B氏の現在の食事摂取量は毎食3分の1程度と著しく減少している。入院前は普通食を摂取していたが、入院後は「口の中が苦い」という訴えにより食欲が低下し、摂取量が激減している。家族が持参した和菓子を少量摂取している程度で、主食や主菜の摂取が不十分である。水分摂取についても、トイレ移動時の疼痛を恐れて意識的に制限している状況がみられる。摂取方法は経口摂取で、嚥下機能に明らかな問題は認められていない。
食事に関するアレルギー
卵アレルギーがあることが確認されている。入院中の食事において卵を含む食品の除去が必要であり、栄養士との連携による代替食品の提供が行われている必要がある。他の食物アレルギーの有無については詳細な確認が必要である。
身長、体重、BMI、必要栄養量、身体活動レベル
身長152cm、体重58kgで、BMIは25.1kg/m²と軽度肥満の範囲にある。72歳女性という年齢を考慮すると、加齢に伴う筋肉量減少と脂肪量増加の影響が考えられる。現在の身体活動レベルは著しく低下しており、ベッド上安静が中心となっている。基礎代謝量は年齢と体重から推定すると約1200kcal程度であるが、現在の摂取量では明らかに不足している状態である。創傷治癒や術前術後の回復を考慮すると、通常よりも高い栄養必要量が見込まれる。
食欲、嚥下機能、口腔内の状態
食欲は著しく低下しており、「口の中が苦い」という味覚の変化を訴えている。これは疼痛による全身状態の悪化や薬剤の副作用、精神的ストレスの影響が考えられる。嚥下機能については明らかな問題は記載されていないが、高齢者であることから詳細な評価が必要である。口腔内の状態について具体的な情報が不足しているため、口腔乾燥、歯牙の状態、義歯の適合性などの確認が必要である。
嘔吐、吐気
現在のところ明らかな嘔吐や吐気の訴えは記載されていない。しかし、食欲低下の原因として潜在的な消化器症状の有無について詳細な観察が必要である。使用中のロキソプロフェンナトリウムは胃腸障害の副作用があるため、レバミピドとの併用により胃粘膜保護が図られているが、継続的な観察が重要である。
血液データ(総蛋白、アルブミン、ヘモグロビン、中性脂肪)
アルブミン値は入院時3.8g/dLから現在3.5g/dLに低下しており、軽度の栄養不良の傾向を示している。総蛋白、ヘモグロビン、中性脂肪の具体的な数値が記載されていないため、詳細な栄養状態の評価のために追加の情報収集が必要である。アルブミン値の低下は食事摂取量減少と炎症反応の影響が考えられる。
ニーズの充足状況
現在の栄養摂取状況は明らかに不十分である。必要エネルギー量の半分以下の摂取量となっており、蛋白質、ビタミン、ミネラルの不足が懸念される。特に術前という時期において、創傷治癒や感染抵抗力の維持に必要な栄養素が不足している。水分摂取量の減少により脱水のリスクも高まっている。低カリウム血症(3.2mEq/L)も食事・水分摂取量減少との関連が示唆される。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、食事摂取量の著しい減少、水分摂取制限による脱水リスク、術前の栄養不良が挙げられる。看護介入では、疼痛コントロールを適切に行い食欲改善を図ること、少量頻回の食事提供や嗜好に合わせた食事調整を行うこと、水分摂取を促進するための環境整備が重要である。また、栄養士との連携による個別栄養計画の立案、経口栄養補助食品の検討、必要に応じて補液による栄養・水分補給の検討が必要である。口腔ケアの充実により味覚改善を図り、家族の協力を得ながら食事環境を整えることも重要である。継続的な体重測定、血液データの監視、摂取量の正確な記録により栄養状態の変化を注意深く観察する必要がある。
排便回数と量と性状、排尿回数と量と性状、発汗
B氏は入院後3日間排便がない状態で、便秘の状態にある。入院前は便秘傾向はなかったとされているため、入院による環境変化、活動量低下、食事・水分摂取量減少が影響していると考えられる。排便の量や性状については現在情報が得られていない。排尿については、移動時の疼痛を恐れてトイレに行くことを躊躇している状況がみられ、回数や量の詳細な記録が必要である。発汗については具体的な記載がないため、体温調節機能や脱水の指標として観察が必要である。
水分出納バランス
水分摂取量は疼痛による移動制限のため意識的に制限されている状況である。正確な水分出納バランスの記録が不足しているため、詳細な測定と記録が必要である。低カリウム血症(3.2mEq/L)は水分・電解質バランスの異常を示唆しており、脱水による腎前性の影響も考慮すべきである。72歳という高齢であることから、加齢による腎機能の生理的低下も水分バランスに影響を与える可能性がある。
排泄に関連した食事、水分摂取状況
食事摂取量が毎食3分の1程度と著しく減少しており、特に食物繊維の摂取不足が便秘の一因となっている。水分摂取量の減少は便の硬化を招き、排便困難を助長している。また、活動量の低下により腸蠕動が減弱し、便秘が悪化している状況である。これらの要因が相互に影響し合い、排泄機能の低下を招いている。
麻痺の有無
明らかな麻痺の記載はないが、右股関節部の疼痛により移動が制限されている状況である。疼痛による体位制限や活動制限が、間接的に排泄機能に影響を与えている。神経学的な麻痺の有無について詳細な評価が必要である。
腹部膨満、腸蠕動音
腹部膨満と腸蠕動音の減弱が認められており、便秘による腸管内容物の停滞を示している。これらの所見は3日間の排便停止と一致しており、機械的イレウスや麻痺性イレウスの鑑別も含めた継続的な観察が必要である。腹部の触診や聴診による詳細な評価を継続する必要がある。
血液データ(尿素窒素、クレアチニン、糸球体濾過率)
腎機能に関する具体的な血液データが記載されていないため、詳細な評価が必要である。低カリウム血症の存在から、腎機能や電解質バランスの評価が重要である。高齢者であることから、加齢による腎機能低下の可能性も考慮し、尿素窒素、クレアチニン、推定糸球体濾過率の測定と評価が必要である。
ニーズの充足状況
排泄機能のニーズは明らかに充足されていない状況である。便秘により老廃物の適切な排出ができておらず、腹部膨満や不快感を引き起こしている。また、疼痛による排尿制限により、膀胱機能にも影響を与える可能性がある。水分・電解質バランスの異常も排泄機能の障害を示している。これらの状況は全身状態や術前準備にも悪影響を与える可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、便秘による老廃物排出障害、水分摂取制限による脱水と電解質異常、疼痛による排泄行動の制限が挙げられる。看護介入では、適切な疼痛管理により移動を促進し、規則的な排泄を支援することが重要である。ピコスルファートナトリウムの適切な使用と効果判定、水分摂取の促進、可能な範囲での活動量増加の支援が必要である。また、腹部マッサージや温罨法による腸蠕動促進、食物繊維を含む食事の調整も有効である。正確な水分出納バランスの測定と記録により、脱水の予防と電解質バランスの維持を図る必要がある。排便パターンの記録と腹部症状の継続的な観察により、イレウスなどの合併症の早期発見に努めることも重要である。術前という時期であることを考慮し、腸管準備の観点からも排便コントロールの重要性を患者・家族に説明し、協力を得ることが必要である。
日常生活動作、麻痺、骨折の有無
B氏の日常生活動作は著しく制限されている状況である。歩行は疼痛により困難で、歩行器を使用した部分荷重歩行を実施している段階である。移乗は介助が必要で、特に右側への体重移動時に強い疼痛を訴えている。排泄は車椅子でのトイレ移動となり、一部介助が必要である。入浴は清拭で対応している状況である。明らかな麻痺の記載はないが、疼痛による機能制限が主な要因となっている。骨折については、転倒による外傷の詳細な評価が必要である。
ドレーン、点滴の有無
現在のところドレーンや点滴に関する具体的な記載がないため、詳細な確認が必要である。人工股関節置換術を控えていることから、術前準備として点滴路確保の予定や、術後のドレーン管理について事前の説明と準備が必要である。これらの医療器具が設置された場合の移動制限についても考慮が必要である。
生活習慣、認知機能
B氏は真面目で責任感が強い性格であり、これまで清掃業のパートタイマーとして活動的な生活を送っていた。MMSE28点と認知機能は良好であり、指示理解や安全管理能力は保たれている。しかし、現在の活動制限により、これまでの生活習慣から大きく変化している状況である。72歳という年齢による身体機能の生理的低下も考慮すべき要因である。
日常生活動作に関連した呼吸機能
長期臥床により呼吸筋の廃用や心肺機能の低下が懸念される。理学療法時の呼吸状態について詳細な観察が必要である。疼痛による浅い呼吸や体位制限により、肺換気機能が低下している可能性がある。活動時の呼吸困難の有無や酸素飽和度の変動について継続的な評価が必要である。
転倒転落のリスク
B氏は自宅階段での転倒により今回の入院に至っており、転倒のリスクファクターを有している。高齢者であること、股関節疾患による歩行不安定、疼痛による注意力散漫、病院環境への不慣れなどが転倒リスクを高めている。特に夜間のトイレ移動時や、疼痛により焦りが生じた際のリスクが高い。認知機能は良好であるが、疼痛や不安により判断力が低下する可能性もある。
ニーズの充足状況
身体の位置を動かし良い姿勢を保持するニーズは大幅に制限されている状況である。疼痛により自由な体位変換や移動が困難となり、同一体位の継続による褥瘡リスクや関節拘縮のリスクが高まっている。また、活動制限により筋力低下や廃用症候群の進行が懸念される。理学療法により部分的な機能維持・改善を図っているが、十分なレベルには達していない。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、疼痛による著しい活動制限、転倒リスクの増大、廃用症候群の進行、術前の身体機能低下が挙げられる。看護介入では、適切な疼痛コントロールにより活動を促進し、安全な移動方法の指導と環境整備を行うことが重要である。定期的な体位変換により褥瘡予防を図り、可能な範囲での関節可動域訓練を実施する必要がある。転倒予防対策として、ベッド周囲の環境整備、ナースコールの確実な使用、夜間の照明確保、履物の検討などが必要である。理学療法士との連携により、段階的な機能訓練を進め、術後の早期離床に向けた準備を行うことが重要である。また、家族への移動介助方法の指導や、退院後の住環境整備についても早期から検討する必要がある。継続的な筋力評価と関節可動域の測定により、機能の変化を注意深く観察し、個別性に応じた介入計画の修正を行うことが必要である。
睡眠時間、パターン
B氏の睡眠は著しく障害されている状況である。入院前は6時間程度の睡眠をとっていたが、現在は夜間の中途覚醒が多く、熟睡できていない状態が続いている。睡眠の質の低下により、日中の疲労感や集中力低下が懸念される。72歳という高齢であることから、加齢による睡眠パターンの変化(深睡眠の減少、早朝覚醒の傾向)も影響している可能性がある。
疼痛、掻痒感の有無、安静度
夜間の疼痛が睡眠障害の主要因となっている。股関節部の疼痛により体位変換が困難となり、同一体位の継続による不快感が睡眠を妨げている。掻痒感については具体的な記載がないため確認が必要である。現在の安静度はベッド上安静が中心となっており、この活動制限も睡眠リズムの乱れに影響している可能性がある。
入眠剤の有無
現在、眠剤の使用は希望していないとされている。これは薬剤に対する不安や副作用への懸念が考えられる。しかし、睡眠障害が継続することにより、術前の体力低下や免疫機能の低下、精神的ストレスの増大が懸念されるため、非薬物的介入と併せて薬物療法の検討も必要である。
疲労の状態
睡眠不足により日中の疲労感が蓄積していると考えられる。理学療法時の表情が冴えないという記載からも、全身の疲労状態が推察される。慢性的な疼痛と睡眠不足の相乗効果により、疲労の回復が困難な状況にある。活動制限により身体的疲労は軽減されているものの、精神的疲労や疼痛による疲労が蓄積している。
療養環境への適応状況、ストレス状況
病院環境への適応が不十分な状況がみられる。同室者のナースコールなどの夜間の環境騒音により中途覚醒が生じており、療養環境が睡眠に適していない状況である。入院という新しい環境への不安、手術への恐怖、家族への心配などの精神的ストレスが睡眠障害を悪化させている。「手術は初めてで不安」「夫に迷惑をかけて申し訳ない」という発言からも、強いストレス状況が推察される。
ニーズの充足状況
睡眠と休息のニーズは明らかに充足されていない状況である。量的にも質的にも不十分な睡眠により、身体の回復や精神的安定が阻害されている。この状況が続くことにより、免疫機能の低下、創傷治癒の遅延、感染抵抗力の低下などの悪影響が懸念される。特に術前という重要な時期において、適切な睡眠による体力回復と精神的安定の確保が重要である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、疼痛による睡眠障害、療養環境への不適応、精神的ストレスによる入眠困難、術前の体力低下が挙げられる。看護介入では、夜間の疼痛コントロールを適切に行い、就寝前の鎮痛剤使用のタイミング調整が重要である。療養環境の改善として、静かな環境の確保、室温・湿度の調整、照明の工夫、同室者への配慮などが必要である。非薬物的な睡眠促進法として、就寝前のリラクゼーション、軽い足浴、背部マッサージ、音楽療法などの導入を検討する。また、日中の適度な活動により自然な疲労感を促し、夜間の睡眠を改善することも重要である。精神的不安の軽減のため、手術や治療に関する十分な説明と傾聴、家族との面会時間の確保、カウンセリングの提供なども有効である。睡眠パターンの詳細な記録により、睡眠の質と量を客観的に評価し、必要に応じて医師と連携した薬物療法の検討も行う必要がある。継続的な睡眠状態の観察と評価により、個別性に応じた介入の調整を行うことが重要である。
日常生活動作、運動機能、認知機能、麻痺の有無、活動意欲、点滴・ルート類の有無
B氏の衣類着脱能力は部分的に制限されている状況である。上肢は自立しているが、下肢は介助が必要な状態となっている。これは右股関節部の疼痛と可動域制限により、下肢への前屈動作や股関節の屈曲が困難なためである。認知機能はMMSE28点と良好であり、衣類選択の判断力や着脱方法の理解は保たれている。明らかな麻痺はないが、疼痛による機能制限が主な要因となっている。活動意欲については、疼痛や不安により低下している可能性がある。現在のところ点滴やルート類に関する記載はないが、術前準備として点滴路確保の予定があり、これが着脱動作に影響を与える可能性がある。
発熱、吐気、倦怠感
現在の体温は36.8℃と正常範囲内であり、明らかな発熱は認められていない。吐気については具体的な訴えは記載されていないが、食欲低下との関連で潜在的な消化器症状の可能性もある。倦怠感については、睡眠不足や疼痛、食事摂取量減少により生じている可能性が高い。これらの全身症状は衣類着脱への意欲や持久力に影響を与える要因となる。
ニーズの充足状況
衣類着脱のニーズは部分的に充足されている状況である。上肢機能は保たれているため、上半身の着脱は自立して行えるが、下半身については疼痛による制限により介助が必要となっている。これにより、自立への欲求や自尊心に影響を与えている可能性がある。また、病院着という慣れない衣類により、心理的な違和感や不安を感じている可能性もある。入院前は自立していた基本的な日常生活動作が制限されることで、依存への不安や焦燥感を抱いている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、下肢の疼痛による着脱困難、自立性の制限による心理的影響、術前後の機能変化への対応が挙げられる。看護介入では、疼痛コントロールを適切に行い、着脱時の負担軽減を図ることが重要である。着脱しやすい衣類の選択指導として、前開きの衣類、ゆったりとしたサイズ、伸縮性のある素材、簡単な留め具の衣類を推奨する必要がある。段階的自立支援として、可能な部分は自分で行ってもらい、困難な部分のみ介助することで、自尊心の維持と機能低下の予防を図る。また、着脱方法の工夫として、座位での着脱、健側から患側への順序、補助具の使用などを指導する。術後を見据えたリハビリテーションの一環として、作業療法士との連携により、日常生活動作訓練を計画的に実施することも重要である。家族への指導により、退院後の着脱介助方法や環境整備についても早期から準備する必要がある。心理面への配慮として、プライバシーの確保、羞恥心への配慮、患者の意向を尊重した介助方法の選択が重要である。継続的な機能評価により、自立度の変化を把握し、介助レベルの調整を適切に行うことが必要である。
バイタルサイン
B氏の体温は来院時37.2℃から現在36.8℃と正常範囲内に安定している。来院時の軽度発熱は外傷による炎症反応や疼痛ストレスの影響と考えられ、現在は改善傾向にある。血圧は138/82mmHg、脈拍82回/分、呼吸数18回/分と安定しており、循環動態に大きな異常は認められていない。72歳という高齢であることから、体温調節機能の生理的低下や感染に対する反応の鈍化が考慮すべき要因である。
療養環境の温度、湿度、空調
病院環境の温度・湿度・空調に関する具体的な情報が不足しているため、詳細な確認が必要である。高齢者は体温調節機能が低下しているため、適切な室温管理(22-24℃程度)と湿度調整(50-60%程度)が重要である。特に術前術後の体温管理において、環境要因が大きく影響する可能性がある。活動制限により体温産生能力が低下していることも考慮すべき要因である。
発熱の有無、感染症の有無
現在明らかな発熱は認められていないが、CRP値が1.8mg/dLから2.5mg/dLに上昇しており、潜在的な炎症反応の持続が示唆される。この炎症反応は外傷による組織損傷や長期臥床による影響が考えられるが、感染症の可能性も除外できない。特に高齢者では感染症状が非定型的に現れることがあるため、継続的な観察が必要である。
日常生活動作
活動制限により体温産生能力が低下している状況である。ベッド上安静が中心となり、筋肉活動による熱産生が減少している。これにより、外界温度の変化に対する適応能力が低下している可能性がある。理学療法時の活動により一時的に体温上昇がみられる可能性もあるため、運動前後の体温変化の観察が重要である。
血液データ(白血球数、C反応性蛋白)
白血球数は入院時8,200/μLから現在7,800/μLと正常範囲内で推移している。しかし、CRP値の上昇(1.8→2.5mg/dL)は注意を要する所見である。この上昇が単純な外傷性炎症なのか、感染症の初期症状なのかの鑑別が重要である。高齢者では免疫機能の低下により、感染症に対する反応が遅延する可能性もある。
ニーズの充足状況
現在のところ体温は正常範囲内に維持されており、基本的な体温調節のニーズは充足されている。しかし、炎症反応の持続や活動制限による体温調節機能の低下により、今後の変化に注意が必要である。特に手術という侵襲的処置を控えており、術中術後の体温管理が重要な課題となる。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、潜在的な炎症反応の持続、活動制限による体温調節能力の低下、術前術後の体温管理、高齢による体温調節機能の生理的低下が挙げられる。看護介入では、定期的なバイタルサイン測定により体温変化を早期に発見することが重要である。環境調整として、適切な室温・湿度の維持、寝具の調整、衣類の適切な選択を行う必要がある。炎症反応の監視として、CRP値や白血球数の推移を注意深く観察し、感染徴候の早期発見に努める。体温上昇時の対応として、冷罨法の準備、適切な解熱剤の使用、水分補給の促進などの準備が必要である。また、活動制限による体温調節能力低下に対して、可能な範囲での適度な運動により筋肉活動を促進し、体温産生能力の維持を図ることも重要である。術前準備として、手術室の温度管理、術中の体温モニタリング、術後の復温対策について他職種と連携した計画立案が必要である。継続的な体温測定と記録により、個人の体温パターンを把握し、わずかな変化も見逃さないよう注意深い観察を継続することが重要である。
自宅・療養環境での入浴回数、方法、日常生活動作、麻痺の有無、鼻腔・口腔の保清、爪
B氏の入浴に関する入院前の詳細な情報が不足しているため、追加の情報収集が必要である。現在は疼痛と移動制限により清拭で対応している状況である。日常生活動作の制限により、自立した入浴は困難な状態となっている。明らかな麻痺はないが、右股関節部の疼痛により前屈動作や下肢の洗浄が困難である。鼻腔・口腔の保清については具体的な記載がないため、詳細な評価が必要である。特に食欲低下や「口の中が苦い」という訴えから、口腔内の状態について注意深い観察が必要である。爪の状態についても、自己管理能力や感染リスクの観点から確認が必要である。
尿失禁の有無、便失禁の有無
現在のところ明らかな尿失禁や便失禁の記載はない。しかし、移動時の疼痛によりトイレに行くことを躊躇している状況があり、今後失禁のリスクが高まる可能性がある。また、3日間の便秘により便失禁のリスクも考慮すべきである。高齢者であることから、膀胱機能や括約筋機能の低下も潜在的なリスクファクターとなる。
ニーズの充足状況
身体を清潔に保つニーズは部分的にのみ充足されている状況である。疼痛と移動制限により、通常の入浴ができず清拭による清潔保持となっている。これは患者の快適性や自尊心に影響を与えている可能性がある。72歳という高齢であることから、皮膚の脆弱性や乾燥傾向があり、適切なスキンケアの必要性が高まっている。長期臥床により、特に圧迫部位の皮膚状態に注意が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、活動制限による清潔保持の困難、皮膚の脆弱性と褥瘡リスク、口腔衛生の低下、自尊心への影響が挙げられる。看護介入では、安全で効果的な清拭方法の実施により、患者の快適性と清潔保持を図ることが重要である。部分浴の可能性について、疼痛管理と移動方法を工夫することで検討する必要がある。皮膚の観察と保護として、圧迫部位の定期的な観察、褥瘡予防のためのマットレスや体位変換、保湿剤の使用などが必要である。口腔ケアの充実により、味覚改善と感染予防を図り、食欲回復にも寄与することができる。また、整容行為(髪の手入れ、ひげ剃り、化粧など)により、患者の自尊心と意欲の向上を支援することも重要である。家族との協力により、患者の好みに応じた身だしなみの支援を行うことで、心理的安定にも寄与する。術前準備として、手術部位の清潔保持と皮膚準備についても計画的に実施する必要がある。継続的な皮膚状態の観察により、発赤、損傷、感染徴候の早期発見に努め、個別性に応じたスキンケア計画を立案することが重要である。
危険箇所(段差、ルート類)の理解、認知機能、術後せん妄の有無
B氏の認知機能はMMSE28点と良好であり、危険箇所の理解や安全に関する判断力は基本的に保たれている。しかし、自宅階段での転倒により今回の入院に至っており、環境に対する危険認識や注意力に課題がある可能性が示唆される。現在は術前の状態であり、術後せん妄は発生していないが、高齢者の手術という条件から術後せん妄のリスクファクターを有している。疼痛や不安、睡眠不足などの要因が認知機能に影響を与える可能性もある。
皮膚損傷の有無
転倒による膝部擦過傷が認められるが、上皮化が進行し感染徴候はない状態である。打撲部の皮下出血と圧痛があるものの、腫脹や熱感は認められていない。これらの外傷は現在治癒過程にあると考えられるが、継続的な観察が必要である。高齢者の皮膚は脆弱であるため、軽微な外力でも損傷を受けやすく、治癒も遅延する傾向がある。
感染予防対策(手洗い、面会制限)
具体的な感染予防対策に関する記載が不足しているため、詳細な確認が必要である。術前という時期において、手術部位感染の予防は重要な課題である。患者・家族・医療従事者の手指衛生の徹底、適切な面会制限の実施、環境清拭の実施などが必要である。また、長期臥床による感染リスクの増大も考慮すべき要因である。
血液データ(白血球数、C反応性蛋白)
白血球数は7,800/μLと正常範囲内であるが、CRP値が2.5mg/dLに上昇しており、炎症反応の持続が認められる。この上昇が外傷による炎症なのか、潜在的な感染による炎症なのかの鑑別が重要である。感染リスクの評価と継続的な監視が必要な状況である。
ニーズの充足状況
安全確保のニーズは部分的に充足されている状況である。認知機能は良好であるが、身体機能の制限により自己防御能力が低下している。転倒リスクが高く、移動時の安全確保が重要な課題となっている。また、術前という時期において、感染予防や術後合併症の予防など、より高度な安全管理が求められている。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、転倒・転落リスクの増大、感染リスクの存在、術後せん妄の潜在的リスク、皮膚損傷の治癒遅延リスクが挙げられる。看護介入では、転倒予防対策として、ベッド周囲の環境整備、適切な履物の選択、夜間照明の確保、ナースコールの確実な使用指導が重要である。移動時は必ず付き添いを行い、歩行器や車椅子の適切な使用方法を指導する必要がある。感染予防対策として、手指衛生の徹底、創部の適切な管理、口腔ケアの実施、面会者への感染予防指導を行う必要がある。術後せん妄の予防として、見当識の維持、睡眠リズムの調整、疼痛コントロール、家族の面会促進などが有効である。皮膚損傷部位の継続的な観察により、感染徴候や治癒遅延の早期発見に努める必要がある。また、リスクアセスメントを定期的に実施し、転倒リスクスコアや感染リスクの評価を行い、個別性に応じた安全対策を計画することが重要である。医療従事者間での情報共有により、統一したアプローチで安全管理を行うことも必要である。継続的な安全教育により、患者・家族の安全意識を高め、自己管理能力の向上を図ることが重要である。
表情、言動、性格は問題ないか、家族や医療者との関係性
B氏は真面目で責任感が強い性格であり、家族思いな人柄が窺える。しかし、現在は疼痛と不安により表情が冴えない状況がみられ、特に歩行練習時には疼痛による辛そうな表情を示している。言動については「手術は初めてで不安」「夫に迷惑をかけて申し訳ない」「仕事を休んでいるが、早く復帰したい」など、自分の状況を適切に表現できている。家族との関係性は良好で、夫は「妻の痛みを見ているのが辛い」、長女は「母の回復を信じて支えたい」と協力的である。医療者との関係性についても、現在のところ大きな問題は認められていない。
言語障害、視力、聴力、メガネ、補聴器
言語障害は認められておらず、適切な言葉でコミュニケーションを取ることができている。視力は老眼鏡使用で良好、聴力に問題なしとされており、基本的なコミュニケーション手段は確保されている。補聴器の使用についての記載はない。これらの感覚機能が保たれていることは、効果的なコミュニケーションや療養指導において有利な要因である。
認知機能
MMSE28点と認知機能は良好であり、状況理解や判断力は保たれている。自分の病状や治療内容について適切に理解し、感情や不安を言葉で表現することができている。記憶力や注意力も基本的には保たれているが、疼痛や不安により一時的に集中力が低下する可能性がある。
面会者の来訪の有無
家族の面会状況について具体的な記載が不足しているため、詳細な確認が必要である。夫と長女が主要なサポート者として関わっていることは確認できるが、面会頻度や時間、面会時の様子などの情報が必要である。家族のサポートは患者の心理的安定や回復意欲に大きく影響するため、面会環境の整備が重要である。
ニーズの充足状況
コミュニケーションのニーズは基本的には充足されている状況である。認知機能や言語機能が良好であり、自分の感情や不安を適切に表現することができている。しかし、疼痛や不安により精神的な負担が大きく、十分な情緒的サポートが必要な状況である。家族との良好な関係性は心理的支えとなっているが、医療者との治療的関係性の構築がさらに重要である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、手術への強い不安、家族への責任感による心理的負担、疼痛による表情の変化、情緒的サポートの必要性が挙げられる。看護介入では、積極的な傾聴により患者の不安や気持ちを受け止め、感情表現を促進することが重要である。手術に関する十分な説明と情報提供により、不安の軽減を図る必要がある。家族への負担感に対しては、家族全体のサポート体制を整備し、患者が安心して治療に専念できる環境を作ることが重要である。治療的コミュニケーションを通じて、患者の価値観や希望を理解し、個別性に応じた関わりを行う必要がある。また、疼痛コントロールにより身体的苦痛を軽減することで、精神的余裕を生み出し、より良いコミュニケーションが可能となる。家族との面会時間の確保や、必要に応じてカウンセリングや心理的サポートの提供も検討する必要がある。医療チーム全体で統一したアプローチにより、患者との信頼関係を構築し、治療への積極的参加を促進することが重要である。継続的な精神状態の観察により、うつ状態や不安の増強を早期に発見し、適切な介入を行うことが必要である。
信仰の有無、価値観、信念、信仰による食事
B氏について特定の信仰はないとされているが、霊的ニーズや価値観については詳細な情報が不足している。日本の高齢者の多くは、明確な宗教的信仰を持たない場合でも、伝統的な価値観や生活習慣に基づいた精神的支えを持っていることが多い。B氏の価値観として、家族への責任感や勤勉さが強く表れており、これらが彼女の精神的支柱となっている可能性がある。信仰による食事制限は現在のところ確認されていないが、卵アレルギー以外の食事に関する価値観や習慣について確認が必要である。
治療法の制限
特定の信仰による治療法の制限は現在のところ確認されていない。しかし、人工股関節置換術という人工物を体内に埋め込む手術に対する価値観や抵抗感について確認が必要である。また、輸血に対する考え方や、疼痛管理における薬物療法への価値観なども重要な要素である。高齢者特有の生死観や医療に対する考え方も治療選択に影響を与える可能性がある。
ニーズの充足状況
霊的ニーズについては詳細な評価が不十分な状況である。特定の宗教的信仰がないとされているが、人生の意味や価値、家族との絆、健康への願いなど、広義の霊的ニーズは存在すると考えられる。現在の病気や手術への不安、家族への心配、将来への懸念などは、霊的な苦痛として捉えることができる。これらのニーズが適切に満たされているかについて、より深い評価が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、霊的ニーズの詳細な把握不足、病気の意味づけや受容への支援、家族関係における価値観の尊重、死生観への配慮が挙げられる。看護介入では、価値観の探索として、患者にとって大切なものや信念について丁寧に聞き取りを行うことが重要である。病気や治療に対する意味づけの支援により、患者が自分なりに状況を受け入れられるよう援助する必要がある。家族への責任感が強い患者の価値観を尊重しながら、適切な役割調整を支援することも重要である。また、人生の振り返りや今後の希望について話し合う機会を提供し、精神的安定を図る必要がある。必要に応じて、宗教家やスピリチュアルケアの専門家との連携も検討する。治療選択における価値観の尊重として、十分な情報提供と意思決定支援を行い、患者の自律性を尊重することが重要である。家族との絆を大切にする価値観を支援するため、面会環境の整備や家族との時間確保に配慮する必要がある。継続的な関わりを通じて、患者の価値観や霊的ニーズの変化を把握し、個別性に応じた支援を提供することが重要である。
職業、社会的役割、入院
B氏は清掃業のパートタイマーとして週3日勤務しており、これが彼女の社会的役割の一部を担っている。また、家庭内では主要な家事担当者として「私しか家事できない」と述べており、家族にとって重要な役割を担っている。72歳という年齢でありながら就労を継続していることは、経済的必要性と社会参加への意欲の両方を示している。入院により、これらの役割を一時的に果たすことができなくなり、強い責任感から「夫に迷惑をかけて申し訳ない」「早く復帰したい」という気持ちを抱いている。
疾患が仕事・役割に与える影響
右変形性股関節症と今回の転倒により、身体機能の著しい制限が生じている。清掃業という身体労働への復帰については、手術後の回復状況により大きく左右される。現在の歩行困難や疼痛は、立位作業や重量物の取り扱いが必要な清掃業務の継続を困難にしている。家事についても、「娘が卒業するまでは働かないと」という経済的プレッシャーがあり、役割継続への強い動機がある一方で、身体的制限により実行が困難な状況である。
ニーズの充足状況
達成感をもたらす仕事や役割のニーズは現在充足されていない状況である。入院により職業的役割と家庭内役割の両方を果たすことができず、これが患者の自己効力感や自尊心に悪影響を与えている。特に責任感の強い性格により、役割を果たせないことへの罪悪感や焦燥感が強く現れている。社会参加からの一時的な離脱により、生活の意味や目的に対する不安も生じている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、役割喪失による心理的影響、職業復帰への不安、経済的プレッシャー、家族役割の再調整が挙げられる。看護介入では、段階的な役割復帰計画の立案により、患者の不安軽減と現実的な目標設定を支援することが重要である。作業療法士との連携により、職業復帰に向けたリハビリテーションを計画的に実施し、身体機能の段階的回復を図る必要がある。家族との話し合いを促進し、家事分担の再調整や夫の家事参加により、患者の負担軽減を図ることも重要である。職場との連携により、復帰時期や業務内容の調整について相談し、段階的復帰の可能性を探る必要がある。また、社会保障制度の活用や経済的支援について、ソーシャルワーカーとの連携により情報提供を行うことも重要である。入院中においても、可能な範囲で小さな役割や達成体験を提供し、自己効力感の維持を図る必要がある。例えば、病室の整理整頓、他患者との交流支援、治療への積極的参加などを通じて、達成感を得られる機会を作ることが有効である。将来への希望を維持するため、手術の成功例や回復事例の情報提供、リハビリテーションの進歩などについて説明し、前向きな気持ちを支援することが重要である。継続的な心理的サポートにより、役割変化への適応を促進し、新しい生活様式の受容を支援することが必要である。
趣味、休日の過ごし方、余暇活動
B氏の趣味や余暇活動について具体的な情報が不足しているため、詳細な情報収集が必要である。「コンサートに行けなくなるかも」という発言から、音楽鑑賞や外出を伴う文化的活動を楽しんでいたことが推察される。この発言は、趣味活動への参加が困難になることへの不安を示しており、患者にとって重要な生活の一部であったことが窺える。72歳という年齢を考慮すると、同世代との交流や地域活動への参加もあった可能性があるが、詳細は不明である。
入院・療養中の気分転換方法
現在の入院生活における気分転換方法について具体的な記載が不足している。家族がカステラを差し入れており、これが精神的な支えや気分転換の一助となっている可能性がある。しかし、疼痛や不安により積極的な気分転換活動への参加は困難な状況と考えられる。病院環境での娯楽活動や気分転換の機会について評価と提供が必要である。
運動機能障害
右股関節の著しい機能障害により、これまで楽しんでいた可能性のある身体的レクリエーション活動への参加が困難となっている。歩行困難により外出を伴う活動や、立位を必要とする活動への制限が生じている。また、疼痛により集中力を要する活動への参加も困難な状況である。
認知機能、日常生活動作
認知機能はMMSE28点と良好であり、知的なレクリエーション活動への参加能力は保たれている。しかし、日常生活動作の制限により、これまで楽しんでいた活動への参加が物理的に困難となっている。特に外出を伴う活動や、準備に手間のかかる活動への参加が制限されている状況である。
ニーズの充足状況
レクリエーションのニーズは明らかに充足されていない状況である。疼痛と活動制限により、楽しみや気分転換の機会が大幅に減少している。コンサートへの参加不安に象徴されるように、将来の楽しみに対する希望も失いかけている状況である。このような状況は、生活の質の低下や抑うつ状態のリスクを高める要因となっている。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、趣味活動からの離脱による生活の質の低下、将来の楽しみに対する不安、気分転換機会の不足、社会的交流の減少が挙げられる。看護介入では、患者の興味や趣味の詳細な把握を行い、入院中でも可能な活動を見つけることが重要である。音楽への関心があることから、音楽療法や音楽鑑賞の機会を提供することが有効である。ベッドサイドでできる軽い手工芸や読書、テレビ・ラジオの活用などにより気分転換を図る必要がある。また、段階的な活動参加として、回復に応じて車椅子での外出や院内レクリエーション活動への参加を促進することも重要である。家族との面会時間の充実により、社会的交流を維持し、精神的支えを得られる環境を整える必要がある。将来への希望を維持するため、手術後の回復見通しや活動再開の可能性について具体的な情報提供を行うことが重要である。他患者との交流や病棟内でのグループ活動への参加により、新しい人間関係の構築と気分転換を図ることも有効である。継続的な精神状態の観察により、レクリエーション活動への意欲や興味の変化を把握し、個別性に応じた活動提案を行うことが必要である。退院後の地域活動への復帰支援も含めた長期的な視点での介入計画が重要である。
発達段階
B氏は72歳女性であり、エリクソンの発達段階理論における老年期(統合性対絶望)の段階にある。この時期は、これまでの人生を振り返り、自分の人生に意味を見出すことが重要な発達課題となる。B氏は家族への責任感が強く、現在も清掃業として社会参加を続けており、生産的な老年期を過ごしている状況である。しかし、今回の疾患により身体機能の低下と将来への不安が生じており、発達課題への取り組みに影響を与えている可能性がある。
疾患と治療方法の理解
B氏は認知機能が良好(MMSE28点)であり、疾患や治療に関する理解力は十分に保たれている。右変形性股関節症の診断と人工股関節置換術の必要性について基本的な理解はあると考えられるが、手術への強い不安と恐怖を示している。「手術は初めてで不安」「痛いのでは」という発言から、手術に関する詳細な理解や術後の回復過程について十分な知識が不足している可能性がある。
学習意欲、認知機能、学習機会への家族の参加度合い
認知機能は良好であり、学習能力は保たれている。しかし、現在は疼痛や不安により学習への意欲や集中力が低下している可能性がある。家族は協力的であり、夫は「妻の痛みを見ているのが辛い」、長女は「母の回復を信じて支えたい」と述べており、家族全体で治療に取り組む姿勢がみられる。家族の学習機会への参加度合いについては具体的な情報が不足しているため、詳細な確認が必要である。
ニーズの充足状況
学習・発達のニーズは部分的に充足されていない状況である。疾患や治療に関する基本的な情報は提供されていると考えられるが、患者の不安レベルから判断すると、十分な理解と納得には至っていない可能性がある。また、疼痛や不安により新しい情報を受け入れ、処理する能力が一時的に低下している。高齢者の学習特性を考慮した個別的なアプローチが必要な状況である。
健康管理上の課題と看護介入
主な課題として、手術に対する知識不足と不安、学習への意欲低下、家族への教育不足、高齢者特有の学習特性への配慮不足が挙げられる。看護介入では、個別性に応じた患者教育として、患者の理解度や不安レベルに合わせた情報提供を段階的に行うことが重要である。視覚的教材や模型、パンフレットなどを活用し、高齢者にとって理解しやすい方法で説明する必要がある。手術への不安軽減のため、術前オリエンテーションを丁寧に実施し、手術室見学や麻酔科医との面談機会を提供することが有効である。家族への教育として、術後の回復過程、リハビリテーション、退院後の生活について具体的な指導を行い、家族全体でサポートできる体制を整える必要がある。反復学習の機会を提供し、疑問や不安に対してはその都度丁寧に対応することが重要である。また、同じ手術を経験した患者との交流機会を設けることで、実体験に基づく情報提供と不安軽減を図ることも有効である。学習評価として、理解度の確認や疑問点の聞き取りを定期的に行い、必要に応じて追加説明を実施する必要がある。退院後の継続学習として、定期受診時の指導や電話相談の体制整備により、長期的な健康管理をサポートすることが重要である。患者の主体的な学習参加を促進するため、質問しやすい環境作りと十分な時間確保を行うことが必要である。
看護計画
看護問題
疾患に伴う疼痛に関連した活動耐性低下
長期目標
退院時に疼痛が軽減し、歩行器を使用して自立歩行ができる
短期目標
1週間以内に疼痛スケール3以下となり、車椅子での移動が安全にできる
≪O-P≫観察計画
・疼痛の部位、性質、強度(数値評価スケール使用)
・疼痛の出現パターンと持続時間
・鎮痛剤使用前後の疼痛レベルの変化
・体位変換時や移動時の疼痛の程度
・表情や行動による疼痛の表出
・活動制限の程度と日常生活動作の自立度
・理学療法時の疼痛と参加状況
・夜間の疼痛による睡眠への影響
・疼痛に対する患者の対処行動
・バイタルサインの変化(特に血圧と脈拍)
・冷罨法実施時の効果と皮膚状態
・疼痛による食欲や気分への影響
≪T-P≫援助計画
・医師の指示に基づく鎮痛剤の確実な投与
・疼痛軽減に効果的な体位の工夫と保持
・冷罨法の適切な実施と効果の評価
・移動時の安全な介助方法の実践
・疼痛増強要因の除去と環境調整
・理学療法への参加支援と疼痛への配慮
・疼痛時の精神的支援と安心感の提供
・適切な休息時間の確保
・疼痛日誌の記録支援
・家族への疼痛状況の説明と協力要請
・疼痛軽減のためのリラクゼーション技法の実施
・夜間の疼痛軽減のための就寝環境の整備
≪E-P≫教育・指導計画
・疼痛スケールの使用方法と自己評価の指導
・効果的な体位変換の方法と注意点の説明
・鎮痛剤の正しい使用方法と副作用の説明
・疼痛軽減のための呼吸法やリラクゼーション法の指導
・理学療法の重要性と疼痛との付き合い方の説明
・家族に対する疼痛時の対応方法の指導
看護問題
疾患に伴う機能障害に関連した転倒・転落リスク状態
長期目標
退院時に転倒することなく、安全に移動手段を使用できる
短期目標
1週間以内に安全な移乗方法を習得し、転倒リスクを軽減できる
≪O-P≫観察計画
・歩行時のバランスと安定性
・移乗時の安全性と介助の必要度
・下肢筋力と関節可動域の状態
・起立性低血圧の有無と程度
・認知機能と判断力の状態
・ふらつきや眩暈の訴えの有無
・使用している歩行補助具の適合性
・転倒に対する恐怖心や不安の程度
・病室環境の安全性(段差、障害物等)
・夜間の移動パターンと頻度
・履物の適切性と滑り止めの状態
・転倒リスクアセスメントスコアの変化
≪T-P≫援助計画
・ベッド周囲の環境整備と安全確保
・適切な歩行補助具の選択と調整
・移乗時の確実な介助と見守り
・滑り止めのある適切な履物の準備
・夜間照明の確保と安全な導線の整備
・ベッドの高さ調整と手すりの適切な使用
・理学療法士との連携による筋力訓練の支援
・転倒予防のための下肢筋力強化運動の実施
・起立時の段階的な体位変換の援助
・ナースコールの確実な設置と使用確認
・転倒リスクの定期的な評価と見直し
・家族への安全な介助方法の実演指導
≪E-P≫教育・指導計画
・転倒の危険性と予防の重要性の説明
・安全な移動方法と歩行補助具の使用法の指導
・適切な履物の選択基準の説明
・夜間移動時の注意点と安全対策の指導
・筋力維持のための運動方法の指導
・家族に対する転倒予防と安全な介助方法の指導
看護問題
手術に伴う不安に関連した睡眠パターン障害
長期目標
手術後1週間以内に不安が軽減し、6時間程度の連続した睡眠がとれる
短期目標
3日以内に夜間の中途覚醒が減少し、4時間程度の連続睡眠がとれる
≪O-P≫観察計画
・夜間の睡眠時間と睡眠の質
・中途覚醒の回数と覚醒時間
・入眠までの時間と入眠困難の有無
・手術に対する不安の内容と程度
・日中の眠気や疲労感の状態
・睡眠に影響する環境要因(騒音、照明等)
・不安による身体症状の出現
・家族への心配や責任感の表出
・睡眠薬使用への意向と効果
・夜間の疼痛による覚醒の有無
・睡眠時の呼吸状態と体位
・日中の活動量と疲労の程度
≪T-P≫援助計画
・静かで快適な睡眠環境の整備
・就寝前の疼痛コントロールの実施
・不安軽減のための傾聴と共感的態度
・手術に関する適切な情報提供と説明
・リラクゼーション技法の実施支援
・就寝前の軽い足浴や背部マッサージの提供
・同室者への配慮と環境調整の依頼
・夜間の不必要な訪室の調整
・日中の適度な活動と日光浴の促進
・家族との面会時間の確保と調整
・必要時の睡眠薬投与と効果の観察
・手術室見学や術前オリエンテーションの調整
≪E-P≫教育・指導計画
・手術の流れと安全性についての詳細な説明
・術前術後の経過と回復見通しの説明
・不安軽減のための呼吸法やリラクゼーション法の指導
・良質な睡眠をとるための生活習慣の指導
・家族に対する患者の心理状態と支援方法の説明
・術後の痛みの管理方法と回復過程の説明
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
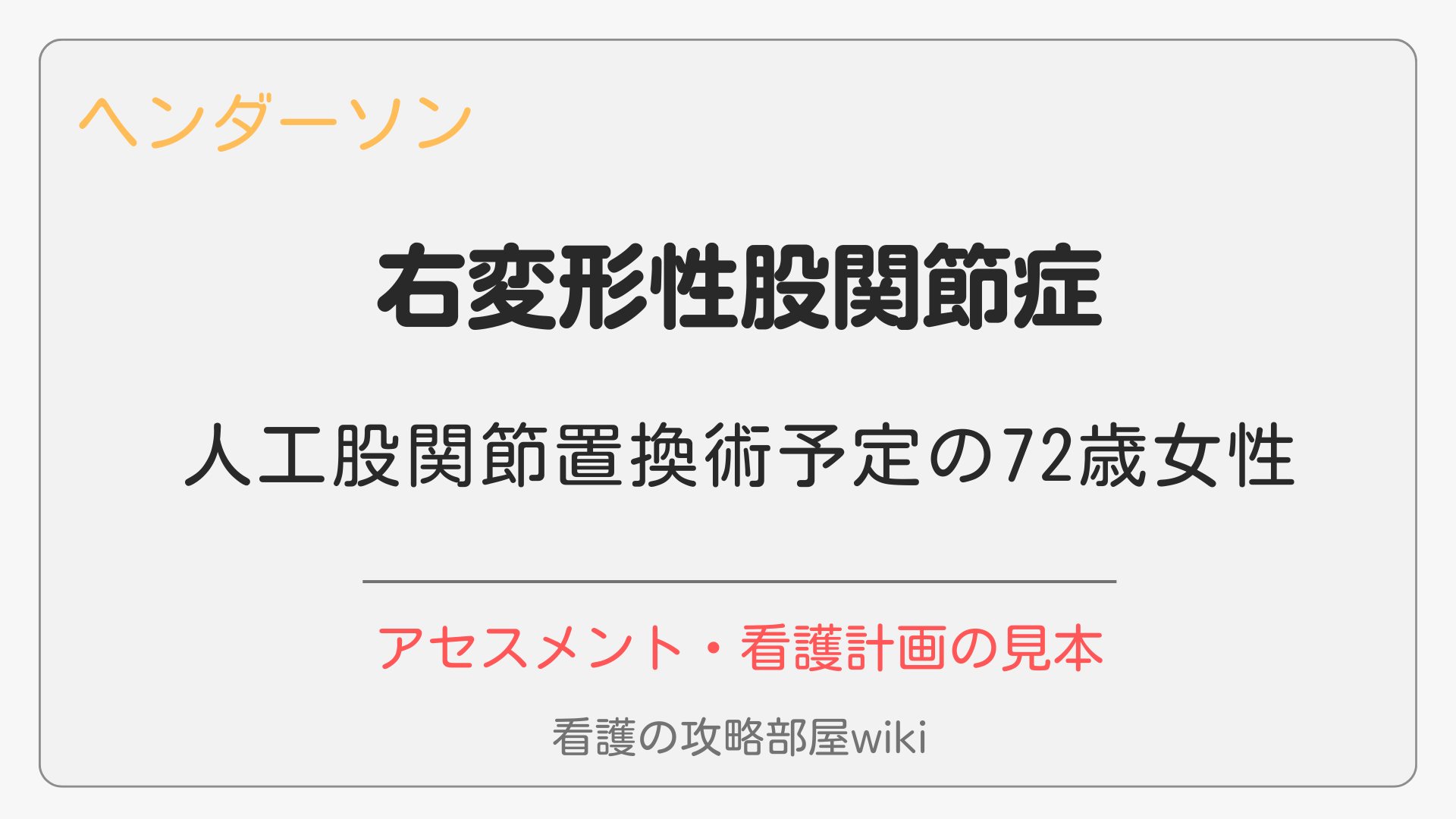
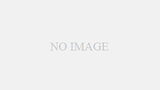
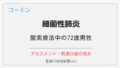
コメント