事例の要約
肺炎による呼吸困難と日常生活動作の制限という事例。入院後3日目の介入
基本情報
A氏、72歳男性、身長168cm、体重62kg。妻と二人暮らしで、キーパーソンは妻である。退職前は製造業で働いていた。性格は温厚で協調性があり、医療者の説明をよく聞く姿勢を見せる。感染症やアレルギーの既往はない。認知機能に問題はなく、MMSE 28点と正常範囲内である。
病名
細菌性肺炎
既往歴と治療状況
糖尿病があり、メトホルミン500mgを1日2回内服でコントロールしている。また、脂質異常症に対してアトルバスタチン10mgを1日1回夕食後に内服している。
入院から現在までの情報
3日前から咳嗽と発熱が出現し、徐々に呼吸困難感が増強したため救急外来を受診した。胸部X線検査で右下葉に浸潤影を認め、細菌性肺炎と診断されて入院となった。入院時は39.2℃の高熱と著明な呼吸困難を呈していたが、抗菌薬治療と酸素療法により現在は症状が改善傾向にある。
バイタルサイン
来院時は体温39.2℃、脈拍112回/分、血圧148/92mmHg、呼吸数28回/分、SpO2 88%(室内気)であった。現在は体温37.2℃、脈拍88回/分、血圧132/78mmHg、呼吸数20回/分、SpO2 94%(酸素2L/分カニューラ)となっている。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を摂取していたが、25年間の喫煙歴があり1日20本程度喫煙していた。飲酒は晩酌程度で日本酒1合程度であった。現在は食欲不振と呼吸困難感のため食事摂取量が少なく、全粥食の5割程度の摂取となっている。嚥下機能に問題はない。
排泄
入院前は排尿・排便ともに自立していた。現在はトイレ歩行は可能だが、歩行時に息切れが強くなるため、ポータブルトイレの使用も検討されている。排便は便秘気味で、酸化マグネシウム330mgを1日3回内服している。
睡眠
入院前は23時頃に就寝し6時間程度の睡眠をとっていた。現在は咳嗽と呼吸困難感のため夜間の睡眠が浅く、3-4時間程度の断眠状態が続いている。ゾルピデム5mgを頓用で使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼鏡使用で問題なく、聴力も正常である。知覚に異常はなく、コミュニケーションは良好である。特定の信仰はない。
動作状況
歩行は酸素療法下で可能だが、10m程度で息切れが強くなる。移乗は自立しているが、排泄時は歩行による酸素飽和度低下のため注意が必要である。入浴は現在禁止されており、清拭で対応している。衣類の着脱は自立している。転倒歴はない。
内服中の薬
- セフトリアキソン 2g 1日1回 点滴静注
- メトホルミン 500mg 1日2回 朝・夕食後
- アトルバスタチン 10mg 1日1回 夕食後
- 酸化マグネシウム 330mg 1日3回 毎食後
- ゾルピデム 5mg 1日1回 就寝前(頓用)
服薬状況
点滴薬は看護師が管理し、内服薬は看護師管理で配薬している。
検査データ
| 項目 | 入院時 | 現在(3日後) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 12,800/μL | 9,200/μL | 3,300-8,600 |
| CRP | 18.5 mg/dL | 8.2 mg/dL | 0.0-0.14 |
| Hb | 12.1 g/dL | 11.8 g/dL | 13.7-16.8 |
| 血糖値 | 158 mg/dL | 142 mg/dL | 70-109 |
| BUN | 22 mg/dL | 18 mg/dL | 8-20 |
| Cr | 0.9 mg/dL | 0.8 mg/dL | 0.65-1.07 |
今後の治療方針と医師の指示
抗菌薬治療を継続し、炎症反応の改善を図る。呼吸機能の回復に合わせて酸素療法を段階的に減量する予定である。食事摂取量の改善と体力回復を目指し、理学療法士による呼吸リハビリテーションも開始する。禁煙指導も並行して実施する方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「息苦しくて夜も眠れない。早く家に帰りたい」と不安を訴えている。妻は「タバコをやめてほしいと何度も言っていたのに」と複雑な心境を吐露しながらも、「しっかり治療を受けて元気になってほしい」と回復への期待を表している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は細菌性肺炎により入院している。肺炎は肺胞や間質に炎症が生じる疾患であり、細菌、ウイルス、真菌などの病原体が原因となる。細菌性肺炎の場合、肺胞内に炎症性滲出液が貯留し、ガス交換障害を引き起こすため、発熱、咳嗽、呼吸困難などの症状が現れる。高齢者では免疫機能の低下や基礎疾患の存在により重症化しやすく、適切な抗菌薬治療と支持療法が必要である。
健康状態
A氏の現在の健康状態は、入院時と比較して改善傾向にある。体温は39.2℃から37.2℃へ下降し、炎症反応を示すCRPも18.5mg/dLから8.2mg/dLへ低下している。しかし、酸素療法を必要とする呼吸機能の低下が継続しており、SpO2は酸素2L/分投与下で94%を維持している状況である。72歳という年齢を考慮すると、加齢による肺機能の生理的低下に加えて、25年間の喫煙歴による慢性的な肺損傷が回復を遅延させている可能性がある。白血球数は12,800/μLから9,200/μLへ減少しているものの、依然として基準値上限を超えており、感染に対する生体反応が継続していることを示している。
受診行動、疾患や治療への理解、服薬状況
A氏は3日前から症状が出現した際、適切なタイミングで医療機関を受診している。これは良好な受診行動を示しており、健康問題に対する適切な判断力を有していると評価できる。医療者の説明をよく聞く姿勢を示し、協調性のある性格であることから、治療に対する理解度も良好と考えられる。服薬状況については、糖尿病と脂質異常症に対する既往薬を適切に内服しており、現在は看護師管理下で確実な服薬が行われている。ただし、疾患や治療に対する具体的な理解度については詳細な情報が不足しており、病状説明の理解度や治療への不安、今後の生活への影響に関する認識について追加的な情報収集が必要である。
身長、体重、BMI、運動習慣
A氏の身長は168cm、体重は62kgで、BMIは21.9kg/m²と正常範囲内である。これは適正体重を維持していることを示しており、栄養状態は良好と評価できる。しかし、現在は食欲不振により食事摂取量が5割程度に減少しており、今後の体重減少や栄養状態の悪化が懸念される。運動習慣については具体的な情報が不足しているため、入院前の身体活動レベルや運動習慣の有無について詳細な情報収集が必要である。特に、25年間の喫煙歴を有することから、運動耐容能の低下や心肺機能への影響について評価が重要である。
呼吸に関するアレルギー、飲酒、喫煙の有無
A氏は感染症やアレルギーの既往がないことから、呼吸器系アレルギーのリスクは低いと考えられる。しかし、25年間の喫煙歴があり、1日20本程度を喫煙していたことは、今回の肺炎発症と回復遅延の重要な要因である。喫煙は気道上皮の繊毛運動を阻害し、肺の自浄作用を低下させるため、感染症に対する易感染性を高める。また、慢性的な気道炎症により肺胞の構造破壊が進行し、ガス交換機能の低下を招く。飲酒については晩酌程度で日本酒1合程度であり、過度な飲酒による免疫機能への影響は限定的と考えられる。72歳という年齢における加齢変化として、肺活量の低下、気道の弾性低下、咳嗽反射の減弱が生じており、これらが喫煙による影響と相まって今回の重症化に寄与している可能性がある。
既往歴
A氏は糖尿病と脂質異常症の既往を有している。糖尿病は免疫機能の低下を招き、感染症に対する易感染性を高める重要な危険因子である。高血糖状態では白血球の機能低下、血管内皮機能障害、組織修復能力の低下が生じるため、肺炎の発症リスクが高くなる。現在の血糖値は142mg/dLと軽度高値を示しており、感染によるストレスが血糖コントロールに影響を与えている可能性がある。脂質異常症は動脈硬化の進行を促進し、心血管系への負担を増大させる。肺炎による呼吸困難は心臓への負荷を増加させるため、既往の脂質異常症が心血管合併症のリスクを高める可能性がある。両疾患ともに適切な薬物療法が継続されており、コントロール状態は比較的良好と評価できる。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の健康管理における主要な課題は、喫煙習慣の継続と感染症に対する易感染性である。25年間の喫煙歴は肺機能の慢性的な低下を招き、今回の肺炎発症と回復遅延の主要因となっている。禁煙指導と支援が最も重要な看護介入となる。また、糖尿病による免疫機能低下は感染症のリスクを高めるため、血糖管理の継続と感染予防対策の指導が必要である。現在の食事摂取量減少は栄養状態の悪化と免疫機能のさらなる低下を招く可能性があるため、栄養管理と食事指導も重要である。呼吸機能の回復に向けては、段階的な離床と呼吸リハビリテーションの実施が必要である。治療への理解度と不安の程度について継続的な評価を行い、患者教育と心理的支援を提供する必要がある。退院後の生活管理についても、妻を含めた家族への指導と支援体制の構築が重要である。炎症反応と呼吸機能の改善状況については継続的な観察と評価が必要であり、合併症の早期発見と対応に努める必要がある。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏の現在の食事摂取状況は著しく低下している。入院前は普通食を摂取していたが、現在は食欲不振と呼吸困難感により全粥食の5割程度の摂取に留まっている。これは肺炎による全身状態の悪化、発熱による代謝亢進、呼吸困難による食事動作の困難さが複合的に影響していると考えられる。水分摂取についても詳細な情報が不足しているが、食事摂取量の低下に伴い水分摂取量も減少している可能性が高い。摂取方法については経口摂取が可能であり、嚥下機能に問題はないため、栄養補助食品や高エネルギー食品の活用により摂取量の改善が期待できる。72歳という年齢では味覚や嗅覚の低下、消化機能の減退などの加齢変化が食欲低下に寄与している可能性もある。
好きな食べ物・食事に関するアレルギー
A氏の好きな食べ物や食事嗜好については情報が不足している。アレルギーについては感染症やアレルギーの既往がないことから、食物アレルギーのリスクは低いと考えられる。しかし、詳細な食事嗜好、食習慣、食物アレルギーの有無について追加的な情報収集が必要である。特に、栄養改善のための食事指導を行う上で、患者の嗜好を考慮した食事内容の検討が重要となる。
身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
A氏の身長は168cm、体重は62kgで、BMIは21.9kg/m²と正常範囲内を維持している。しかし、現在の食事摂取量の低下により体重減少のリスクが高い状況である。72歳男性の基礎代謝量は約1,200-1,300kcal/日と推定され、現在の安静状態を考慮すると必要エネルギー量は約1,500-1,600kcal/日と考えられる。しかし、肺炎による炎症反応と発熱により代謝が亢進しているため、通常よりも高いエネルギー需要がある。現在の食事摂取量では必要エネルギー量を大幅に下回っており、栄養不足状態に陥る可能性が高い。身体活動レベルは安静臥床が中心であるが、トイレ歩行は可能な状態である。
食欲・嚥下機能・口腔内の状態
A氏は食欲不振を呈しており、これは肺炎による全身状態の悪化、発熱、呼吸困難感が主な要因と考えられる。嚥下機能については問題がないとされているが、詳細な嚥下評価の情報は不足している。口腔内の状態についても具体的な情報が不足しており、口腔乾燥、歯の状態、義歯の有無、口腔衛生状態について評価が必要である。特に、72歳という年齢では唾液分泌量の減少、咀嚼機能の低下などの加齢変化が認められる可能性があり、これらが食事摂取に影響を与えている可能性がある。
嘔吐・吐気
現在のところ嘔吐や吐気の症状についての記載はないが、抗菌薬治療による副作用として消化器症状が出現する可能性がある。また、呼吸困難感により食事摂取時に不快感や軽度の吐気を感じている可能性もある。これらの症状の有無について継続的な観察と評価が必要である。
皮膚の状態、褥創の有無
皮膚の状態と褥創の有無について詳細な情報が不足している。現在はトイレ歩行のみ許可されており、ベッド上安静が中心となっているため、褥創発生のリスクが高い状況である。72歳という年齢では皮膚の弾力性低下、皮下脂肪の減少、血管の脆弱性などの加齢変化により褥創発生リスクがさらに高まる。また、栄養状態の悪化は皮膚の修復能力を低下させ、褥創発生と治癒遅延のリスクを増大させる。定期的な皮膚観察と褥創予防対策の実施が重要である。
血液データ
血液データの詳細な情報が限定的であるが、現在の血糖値は142mg/dLと軽度高値を示している。これは糖尿病の既往に加えて、感染によるストレスが血糖コントロールに影響を与えていることを示している。アルブミン、総蛋白、赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、電解質、脂質、HbA1cなどの詳細な栄養・代謝関連の検査データが不足しており、これらの情報収集が急務である。特に、アルブミンと総蛋白は栄養状態の評価に重要な指標であり、現在の食事摂取量低下による蛋白質栄養状態の評価が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の栄養・代謝面における主要な課題は、食事摂取量の著しい低下と栄養不足状態のリスクである。呼吸困難感と食欲不振により必要エネルギー量を大幅に下回る摂取量となっており、体重減少と栄養状態の悪化が懸念される。看護介入としては、まず詳細な栄養アセスメントの実施が必要である。血液検査による栄養指標の評価、食事嗜好の聞き取り、口腔内状態の観察を行う必要がある。食事摂取量の改善に向けては、少量頻回摂取の提案、高エネルギー・高蛋白質の栄養補助食品の活用、食事環境の整備が重要である。また、呼吸困難感を軽減するための適切な体位の工夫や酸素療法下での食事摂取の安全性確保も必要である。褥創予防のための定期的な体位変換と皮膚観察、口腔ケアの実施も重要な介入となる。糖尿病管理については、感染時の血糖変動に注意し、必要に応じて医師と連携して治療調整を行う必要がある。栄養状態と食事摂取量については継続的な観察と評価を行い、管理栄養士との連携による個別的な栄養指導の実施が必要である。
排便と排尿の回数と量と性状
A氏の排泄状況について、排便は便秘気味の状態が認められている。具体的な排便回数や便の性状についての詳細な情報は不足しているが、酸化マグネシウム330mgを1日3回内服していることから、慢性的な便秘傾向があると推察される。72歳という年齢では腸管の蠕動運動低下、腹筋力の減弱などの加齢変化により便秘が生じやすくなる。また、現在の安静臥床中心の生活と食事摂取量の低下は便秘をさらに悪化させる要因となっている。排尿については自立しているとされているが、具体的な排尿回数、尿量、尿の性状についての詳細な情報が不足しており、これらの情報収集が必要である。
下剤使用の有無
A氏は酸化マグネシウム330mgを1日3回毎食後に内服している。酸化マグネシウムは塩類下剤であり、腸管内で水分を保持して便を軟化させ、腸管の蠕動運動を促進する作用がある。現在の使用量は一般的な範囲内であるが、便秘の程度や排便状況に応じて用量調整が必要となる可能性がある。また、脱水状態では効果が減弱するため、適切な水分摂取が重要である。
in-outバランス
in-outバランスについて具体的な測定値の記載がないため、詳細な評価ができない状況である。現在は食事摂取量が5割程度に低下しており、水分摂取量も減少している可能性が高い。一方で、発熱による不感蒸泄の増加、呼吸困難による呼吸数増加に伴う水分喪失の増加が考えられる。入院時から現在にかけての体重変化、尿量測定、水分摂取量の詳細な記録が必要である。特に、脱水状態のリスクが高い状況であり、継続的なin-outバランスの監視が重要である。
排泄に関連した食事・水分摂取状況
A氏の現在の食事摂取量は全粥食の5割程度と著しく低下している。食物繊維の摂取不足は便秘を悪化させる主要な要因となる。また、水分摂取量の詳細は不明であるが、食事摂取量の低下に伴い水分摂取量も減少していると推察される。水分摂取不足は便の硬化を招き、便秘をさらに悪化させる可能性がある。72歳という年齢では口渇感の低下により水分摂取量が不足しがちであり、意識的な水分摂取の促進が必要である。
安静度・バルーンカテーテルの有無
A氏の現在の安静度はトイレ歩行のみ許可されている状態である。バルーンカテーテルの挿入はなく、排尿は自力で行っている。しかし、歩行時にSpO2が低下し息苦しさを感じるため、排泄動作に伴う身体的負担が大きい状況である。この制限された活動レベルは腸管蠕動の低下を招き、便秘の悪化要因となっている。また、呼吸困難感により排便時の怒責が困難となる可能性もある。
腹部膨満・腸蠕動音
腹部膨満感や腸蠕動音についての具体的な情報が不足している。便秘気味の状態であることから、腹部膨満感の有無、腸蠕動音の聴取状況について詳細な評価が必要である。便秘が進行すると腹部膨満感、腹痛、食欲不振などの症状が現れ、既に低下している食事摂取量をさらに悪化させる可能性がある。定期的な腹部の視診、触診、聴診による評価が重要である。
血液データ(BUN、Cr、GFR)
血液データについて、BUN 22mg/dL(入院時)から18mg/dL(現在)、クレアチニン0.9mg/dL(入院時)から0.8mg/dL(現在)と、いずれも正常範囲内で推移している。これは腎機能が保たれていることを示しており、水分バランスの調整能力も維持されていると考えられる。しかし、糖尿病の既往があることから、長期的な腎機能の監視が重要である。GFRの具体的な値は記載されていないが、年齢と血清クレアチニン値から推定すると軽度の低下が予想される。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の排泄面における主要な課題は、慢性的な便秘とin-outバランスの潜在的な不均衡である。便秘は食事摂取量の低下、活動制限、加齢変化が複合的に影響して生じており、腹部膨満感や食欲不振をさらに悪化させる可能性がある。看護介入としては、まず詳細な排泄アセスメントの実施が必要である。排便記録の開始、腹部の観察、in-outバランスの正確な測定を行う必要がある。便秘の改善に向けては、可能な範囲での離床促進、腹部マッサージの実施、水分摂取の促進が重要である。酸化マグネシウムの効果と副作用の観察を行い、必要に応じて医師と連携して用量調整を検討する。排泄時の安全確保のため、ポータブルトイレの使用検討や酸素療法下での排泄介助の準備も必要である。水分摂取については、呼吸困難感を考慮した少量頻回摂取の工夫や、嗜好に合わせた水分の提供を行う。腎機能については糖尿病性腎症の進行リスクを考慮し、継続的な監視を行う必要がある。排泄パターンとin-outバランスについては毎日の観察と記録を継続し、異常の早期発見に努める必要がある。
ADLの状況、運動機能、運動歴、安静度、移動・移乗方法
A氏の現在のADL状況は大幅に制限されている。トイレ歩行のみ許可されており、その他の活動は主にベッド上で行っている状態である。移乗については自立しているが、歩行は酸素療法下で10m程度まで可能であり、それ以上の距離では息切れが強くなる。衣類の着脱は自立しているが、入浴は現在禁止されており清拭で対応している。退職前は製造業で働いていたことから、入院前はある程度の身体活動能力を有していたと推察される。しかし、25年間の喫煙歴により慢性的な呼吸機能低下があり、基礎的な運動耐容能が低下していた可能性が高い。72歳という年齢では筋力低下、関節可動域制限、バランス能力低下などの加齢変化が認められる可能性があり、これらが現在の活動制限をさらに増強している。具体的な運動歴や入院前の活動レベルについては詳細な情報収集が必要である。
バイタルサイン、呼吸機能
A氏のバイタルサインは入院時と比較して改善傾向にある。現在の安静時バイタルサインは体温37.2℃、脈拍88回/分、血圧132/78mmHg、呼吸数20回/分と比較的安定している。しかし、**SpO2は酸素2L/分投与下で94%**を維持している状況であり、呼吸機能の著明な低下が認められる。歩行時にはSpO2がさらに低下し、息苦しさが増強することから、運動耐容能が大幅に制限されている。肺炎による急性の呼吸機能低下に加えて、25年間の喫煙歴による慢性的な肺損傷が重複しており、回復には時間を要すると予想される。72歳という年齢における肺機能の生理的低下も回復を遅延させる要因となっている。
職業、住居環境
A氏は退職前に製造業で働いていたという情報があるが、具体的な職業内容や退職時期については詳細が不明である。製造業では立位作業や重量物の取り扱いなど、ある程度の身体活動を伴う作業が多いため、退職前はそれなりの運動機能を維持していたと推察される。現在は妻と二人暮らしであるが、住居環境の詳細(階段の有無、バリアフリー対応、住居形態等)については情報が不足している。退院後の生活を考慮すると、住居環境の評価と必要に応じた環境整備の検討が重要である。
血液データ(RBC、Hb、Ht、CRP)
血液データについて、ヘモグロビンは入院時12.1g/dL、現在11.8g/dLと軽度の低下を示している。これは感染による影響や食事摂取量低下による鉄分不足の可能性が考えられる。赤血球数とヘマトクリットの具体的な値は記載されていないが、ヘモグロビン値から軽度の貧血状態が推察される。CRPは18.5mg/dLから8.2mg/dLへ改善しているものの、依然として高値を維持しており、炎症反応が継続していることを示している。これらの血液データは運動耐容能に直接影響を与えており、貧血による酸素運搬能力の低下と炎症による全身状態の悪化が活動制限の要因となっている。
転倒転落のリスク
A氏の転倒転落リスクは高い状況にある。主要なリスク要因として、歩行時のSpO2低下による息切れとふらつきの可能性、72歳という年齢による筋力低下とバランス能力の低下、酸素チューブによる動作制限、入院環境への不慣れ、夜間の睡眠不足による注意力低下などが挙げられる。また、呼吸困難感により注意が呼吸に集中しがちで、歩行に対する注意力が分散する可能性もある。トイレ歩行時は特にリスクが高く、排泄の切迫感により焦りが生じやすい状況である。転倒歴はないとされているが、現在の身体状況と環境要因を考慮すると継続的なリスク評価が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の活動・運動面における主要な課題は、呼吸機能低下による著明な運動耐容能の制限と廃用症候群発生のリスクである。現在のトイレ歩行のみという活動制限は、筋力低下、関節拘縮、心肺機能のさらなる低下を招く可能性がある。看護介入としては、まず安全な範囲での段階的な活動拡大が重要である。理学療法士と連携した呼吸リハビリテーションの実施、ベッド上での関節可動域訓練、座位耐性の向上を図る必要がある。歩行時は酸素飽和度の継続的な監視を行い、SpO2が90%以下に低下した場合は即座に休息を取る指導が必要である。転倒予防対策として、歩行時の付き添い、適切な履物の着用、環境整備(手すりの活用、障害物の除去)、夜間のナースコール使用の徹底を行う。栄養状態の改善により筋力低下の予防を図り、貧血の改善に向けた医師との連携も重要である。段階的な離床計画を作成し、患者の体調と酸素飽和度の変化に応じて活動レベルを調整する。退院に向けては住居環境の評価と必要な環境整備の検討、家族への介護指導も必要である。呼吸機能と運動耐容能については継続的な評価を行い、回復状況に応じたリハビリテーションプログラムの調整が必要である。
睡眠時間、熟眠感、睡眠導入剤使用の有無
A氏の睡眠状況は著しく悪化している。入院前は23時頃に就寝し約6時間の睡眠を確保していたが、現在は咳嗽と呼吸困難感により夜間の睡眠が浅く、3-4時間程度の断眠状態が続いている。これは入院前の睡眠時間の半分程度に短縮されており、慢性的な睡眠不足状態にある。熟眠感についても呼吸症状により深い睡眠が得られず、頻回の覚醒により睡眠の質が大幅に低下していると推察される。睡眠導入剤としてゾルピデム5mgを頓用で使用しているが、呼吸器症状による覚醒が主要因であるため、薬剤による睡眠導入効果は限定的と考えられる。72歳という年齢では睡眠構造の変化(深睡眠の減少、中途覚醒の増加)が生理的に認められるため、加齢変化と疾患による影響が重複して睡眠障害を悪化させている。
日中・休日の過ごし方
A氏の日中の過ごし方について詳細な情報は不足しているが、現在の安静度がトイレ歩行のみに制限されていることから、大部分の時間をベッド上で過ごしている状況である。退職前は製造業で働いていたことから、入院前は規則正しい生活リズムを保っていたと推察される。しかし、現在は入院という環境変化と身体症状により、従来の生活リズムが大きく乱れている可能性が高い。日中の活動量が制限されることで、夜間の自然な睡眠欲求が減少し、睡眠覚醒リズムの乱れが生じている可能性がある。また、呼吸困難感や倦怠感により日中も十分な休息が取れていない状況が推察される。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の睡眠・休息面における主要な課題は、呼吸器症状による睡眠障害と睡眠覚醒リズムの乱れである。3-4時間程度の断眠状態は免疫機能の低下、創傷治癒の遅延、精神的ストレスの増大を招き、肺炎からの回復を遅延させる可能性がある。看護介入としては、まず呼吸症状の軽減に向けた対策が最優先となる。適切な体位の保持(半座位やファウラー位)による呼吸困難感の軽減、酸素療法の適切な管理、咳嗽に対する対症療法の実施が重要である。睡眠環境の整備として、静かな環境の確保、適切な室温と湿度の調整、照明の調節を行う必要がある。日中の活動と夜間の休息のメリハリをつけるため、可能な範囲での日中の離床促進、規則正しい食事時間の維持、日光の活用による概日リズムの調整が重要である。ゾルピデムの使用については、呼吸抑制のリスクを考慮しながら効果と副作用を継続的に評価し、必要に応じて医師と連携して調整を行う。不安や心配事が睡眠を阻害している場合は、傾聴と心理的支援を提供する。家族との面会時間の調整により精神的安定を図ることも重要である。睡眠時間と質については毎日の評価を行い、改善状況に応じて介入方法を調整する必要がある。呼吸機能の回復に伴い睡眠状況も改善することが期待されるため、継続的な観察と支援が必要である。
意識レベル、認知機能
A氏の意識レベルは清明であり、見当識や判断力に問題は認められない。MMSE 28点という結果は正常範囲内であり、認知機能は良好に保たれている。72歳という年齢を考慮すると、軽度認知機能低下のリスクがある年代であるが、現時点では明らかな認知機能障害は認められない。医療者の説明をよく聞く姿勢を示していることからも、理解力や注意力は維持されていると評価できる。ただし、現在の睡眠不足状態(3-4時間程度の断眠)は注意力や集中力の低下を招く可能性があり、継続的な評価が必要である。また、呼吸困難感により注意が呼吸症状に集中しがちで、他の情報処理能力に影響を与えている可能性もある。
聴力、視力
A氏の聴力は正常とされており、コミュニケーションに支障はない。視力については老眼鏡使用で問題なく読書や日常生活に必要な視覚的作業が可能である。72歳という年齢では加齢性難聴や白内障、緑内障などのリスクが高まる時期であるが、現時点では大きな問題は認められない。ただし、入院環境での視覚・聴覚情報の変化や、酸素チューブによる聴覚への軽微な影響の可能性について継続的な観察が必要である。
認知機能
前述の通り、A氏の認知機能はMMSE 28点と良好に保たれている。見当識、記憶力、計算力、言語機能いずれも年齢相応またはそれ以上のレベルを維持している。協調性のある性格で医療者の説明をよく聞く態度からも、理解力と判断力は適切に機能していると評価できる。しかし、現在の睡眠不足、呼吸困難感、入院という環境変化は認知機能に軽微な影響を与える可能性があり、特に注意力や集中力の変化について注意深い観察が必要である。
不安の有無、表情
A氏は「息苦しくて夜も眠れない。早く家に帰りたい」と訴えており、呼吸症状に対する不安と入院生活への適応困難を抱えていることが明らかである。表情についての詳細な記載はないが、呼吸困難感と睡眠不足により疲労感や不安感が表情に現れている可能性が高い。72歳という年齢では変化への適応能力が低下する傾向があり、入院という環境変化と身体症状が心理的ストレスを増大させている。また、25年間の喫煙歴に対する後悔や今後の健康への不安も潜在的に存在している可能性がある。妻の「タバコをやめてほしいと何度も言っていた」という発言からも、家族関係における複雑な感情が推察される。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の認知・知覚面における主要な課題は、呼吸症状に関連した不安と入院環境への適応困難である。認知機能は良好に保たれているものの、睡眠不足と身体症状により認知機能の一時的な低下のリスクがある。看護介入としては、まず不安の軽減に向けた心理的支援が重要である。病状や治療の進行状況について分かりやすく説明し、回復への見通しを示すことで不安の軽減を図る。呼吸困難感に対する対処方法(適切な体位、呼吸法)を指導し、症状のコントロール感を高める。入院環境への適応を促すため、日課の説明、環境の案内、スタッフとの信頼関係の構築を行う。視力・聴力については継続的な評価を行い、必要に応じて補助具の調整や環境整備を実施する。認知機能については睡眠状況の改善と共に回復することが期待されるが、日常的な評価を継続し、混乱や見当識障害の兆候がないか観察する。家族との面会を促進し、精神的支援を得られる環境を整備する。禁煙に対する罪悪感や今後の生活への不安についても傾聴し、必要に応じて専門職(医師、薬剤師、ソーシャルワーカー)との連携を図る。表情や言動の変化について継続的に観察し、抑うつ症状や不安症状の悪化がないか注意深く評価する必要がある。
性格
A氏は温厚で協調性がある性格とされており、医療者の説明をよく聞く姿勢を示している。これは治療への積極的な参加と良好な医療者患者関係の構築に寄与する重要な特性である。製造業での勤務経験からも、規則正しい生活と責任感のある行動パターンを有していたと推察される。しかし、現在の入院という状況下では、従来の自律的な生活から医療者に依存する状況への変化により、自己効力感の低下や無力感を感じている可能性がある。温厚な性格ゆえに、不満や不安を表出することが少なく、内に秘めがちな傾向があることも考慮する必要がある。
ボディイメージ
A氏のボディイメージについて直接的な情報は限定的であるが、現在の身体状況から推察すると著しい変化を経験していると考えられる。入院前は自立した日常生活を送っていたが、現在は酸素チューブを装着し、トイレ歩行のみという活動制限を受けている。この急激な身体機能の低下と医療機器への依存は、自身の身体に対する認識に大きな影響を与えている可能性がある。特に、歩行時の息切れや呼吸困難感は、従来の身体能力との落差を強く実感させ、身体への信頼感や有能感を損なっている可能性が高い。72歳という年齢において、加齢による身体変化を受け入れる過程にあったところに急性疾患が重なり、ボディイメージの再構築が困難な状況にある。
疾患に対する認識
A氏は適切なタイミングで医療機関を受診し、医療者の説明をよく聞く姿勢を示していることから、疾患に対する基本的な理解は有していると考えられる。しかし、「息苦しくて夜も眠れない。早く家に帰りたい」という発言からは、現在の症状の辛さと回復への焦りが感じられる。25年間の喫煙歴が今回の肺炎発症に関与していることについて、どの程度認識し受け入れているかは明確でない。妻の「タバコをやめてほしいと何度も言っていた」という発言から推察すると、喫煙の健康への影響について家族からの指摘はあったものの、十分な行動変容には至らなかった可能性がある。疾患の重篤性や今後の経過、必要な生活変更について、より詳細な理解度の評価が必要である。
自尊感情
A氏の自尊感情について、製造業での勤務経験や妻との安定した結婚生活から、従来は適切な自尊感情を維持していたと推察される。しかし、現在の状況では複数の要因により自尊感情の低下のリスクが高い。25年間の喫煙継続に対する後悔や罪悪感、家族の忠告を聞かなかったことへの自責感が自尊感情を損なっている可能性がある。また、身体機能の著明な低下により自立性が失われ、医療者や家族への依存を余儀なくされていることが、自己価値感や有用感の低下を招いている可能性がある。「早く家に帰りたい」という発言には、現在の依存的な状況からの脱却への強い願望が表れている。
育った文化や周囲の期待
A氏の育った文化的背景や価値観について詳細な情報は不足しているが、72歳という年齢から戦後復興期から高度経済成長期を経験した世代であると推察される。この世代は勤勉性や責任感を重視する価値観を持つことが多く、自分の健康管理についても自己責任として捉える傾向がある。そのため、今回の肺炎発症について自己責任として強く受け止め、自責感を抱いている可能性が高い。また、家族や社会に迷惑をかけることへの懸念も強く、早期の回復と自立への焦りにつながっている可能性がある。男性としての役割期待(家庭の支えとなる、強くあるべき)と現在の身体的脆弱性との間でジレンマを感じている可能性もある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の自己知覚・自己概念面における主要な課題は、急激な身体機能低下による自己効力感の低下と喫煙に関連した罪悪感・自責感である。従来の自立した生活から医療依存状態への急激な変化は、自尊感情とボディイメージに大きな影響を与えている。看護介入としては、まず患者の感情や思いを十分に傾聴し、現在の困難な状況を理解していることを伝える。喫煙に関する罪悪感については、過去を責めるのではなく今後の行動変容に焦点を当てた支援を行う。身体機能の回復過程において、小さな改善や進歩を共に認識し、自己効力感の回復を図る。可能な範囲での自己決定や選択の機会を提供し、主体性の維持を支援する。家族との関係性において生じている複雑な感情について話し合う機会を設け、必要に応じて家族カウンセリングの検討も行う。ボディイメージの再構築に向けて、現在の身体状況を現実的に受け入れながらも希望を持ち続けられるよう支援する。文化的背景や価値観を尊重しながら、過度な自己責任感による精神的負担を軽減する。退院に向けた具体的な目標設定により、回復への希望と自信の回復を図る。自己概念の変化について継続的に評価し、必要に応じて心理的専門職との連携も検討する必要がある。
職業、社会役割
A氏は退職前に製造業で働いていたという情報があるが、具体的な職種、勤務年数、退職時期については詳細が不明である。72歳という年齢から推察すると、現在は退職しており、地域社会での役割や活動についての情報が不足している。製造業での勤務経験は規則正しい生活習慣と責任感のある行動パターンを形成していたと考えられ、退職後もこれらの特性を維持していた可能性が高い。しかし、現在の入院により、従来の日常的な役割や責任から一時的に離脱している状況である。地域活動、趣味活動、ボランティア活動などの社会参加の状況について詳細な情報収集が必要である。今回の入院により、これらの社会的役割の継続が困難となり、社会的アイデンティティの混乱や孤立感を感じている可能性がある。
家族の面会状況、キーパーソン
A氏のキーパーソンは妻であり、同い年で同居している。妻は「タバコをやめてほしいと何度も言っていたのに」と複雑な心境を吐露しながらも、「しっかり治療を受けて元気になってほしい」と回復への期待を表している。これは長年の夫婦関係における愛情と心配、そして喫煙継続に対する複雑な感情が混在していることを示している。具体的な面会頻度や面会時の様子についての詳細な情報は不足しているが、妻が主要な支援者として機能していると推察される。子どもの有無や他の家族との関係については情報が不足しており、家族システム全体の把握が必要である。72歳という年齢では、親の介護や孫との関係など、多世代にわたる家族役割を担っている可能性もある。
経済状況
A氏の経済状況について具体的な情報は提供されていない。72歳という年齢から年金受給者と推察されるが、製造業での勤務期間や退職金、貯蓄状況、医療費負担能力については不明である。今回の入院に伴う医療費や、退院後の通院費用、必要に応じた住環境整備費用などの経済的負担について評価が必要である。また、妻も同年代であることから、夫婦ともに収入は限定的である可能性が高く、経済的不安が治療や生活に与える影響について配慮が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の役割・関係面における主要な課題は、夫婦関係における複雑な感情の調整と社会的役割からの一時的離脱による孤立感である。妻との関係では、25年間の喫煙継続に対する複雑な感情が存在し、これが回復過程に影響を与える可能性がある。看護介入としては、まず家族関係の詳細な評価を行い、夫婦間のコミュニケーションパターンや支援体制を把握する必要がある。妻の心理的負担や介護不安についても評価し、必要に応じて家族支援を提供する。喫煙に関する過去の確執について、建設的な話し合いの機会を設け、今後の健康管理に向けた協力関係の構築を支援する。退院後の生活において妻が過度な負担を負わないよう、利用可能な社会資源の情報提供や介護保険制度の活用について検討する。経済状況については、医療ソーシャルワーカーとの連携により医療費負担軽減制度や社会保障制度の活用を検討する。社会的役割の維持については、体調回復に伴い段階的に地域活動や趣味活動への復帰を支援する。家族以外の支援ネットワーク(友人、近隣住民、地域組織)についても評価し、社会的孤立の予防を図る。退院前には家族を含めた退院指導を実施し、在宅での継続的な健康管理体制を整備する。夫婦関係の調整と家族機能の向上については継続的な評価を行い、必要に応じて家族療法や夫婦カウンセリングの活用も検討する必要がある。
年齢、家族構成、更年期症状の有無
A氏は72歳男性であり、生殖機能においては既に生殖可能年齢を超えている。同い年の妻と二人暮らしをしており、長期間の夫婦関係を維持している。男性の更年期症状(LOH症候群:加齢男性性腺機能低下症候群)については、一般的に40歳代後半から60歳代にかけて出現することが多いため、現在の年齢では既に安定期に入っていると考えられる。ただし、72歳という年齢ではテストステロン値の低下による身体的・精神的変化(筋力低下、骨密度低下、性欲減退、抑うつ傾向など)が認められる可能性がある。これらの加齢変化は今回の肺炎からの回復過程にも影響を与える可能性があり、特に筋力低下や免疫機能低下の要因となっている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の性・生殖面における課題は、加齢による性機能の変化と夫婦関係への影響が主となる。72歳という年齢では、性機能の低下、性的欲求の減退は自然な変化であるが、これらが夫婦関係や自己概念に与える影響について配慮が必要である。現在の呼吸困難感と体力低下は、性的活動に対する不安や回避を生じさせる可能性がある。看護介入としては、まず患者や夫婦のプライバシーを尊重しながら、必要に応じて性機能や夫婦関係について相談できる環境を整備することが重要である。直接的な性機能の評価や介入は一般的な看護ケアの範囲を超える場合が多いが、患者が関連する悩みや不安を表出した際には適切に対応する準備が必要である。加齢による身体変化について正しい情報を提供し、必要に応じて専門医(泌尿器科医、内分泌科医)への紹介を検討する。夫婦関係の質的向上については、コミュニケーションの促進、相互理解の深化、身体的接触以外の親密性の表現方法について支援を行う。退院後の生活において、体力回復に伴う性的活動の再開については、心肺機能の状態を考慮した段階的なアプローチを指導する。プライバシーを保護しながら、性・生殖に関する健康問題について継続的な相談支援を提供する体制を整備する必要がある。
入院環境
A氏にとって入院は大きな環境変化となっている。「早く家に帰りたい」という発言からも、入院環境への適応困難と自宅への強い帰属意識が感じられる。病院という医療機関特有の環境(騒音、照明、プライバシーの制限、時間的制約など)は、72歳という年齢では特に適応が困難となりやすい。また、酸素チューブの装着や活動制限により、従来の自由な生活スタイルから大きく制約された状況への変化がストレス要因となっている。入院3日目という時点では、まだ環境への完全な適応は達成されておらず、継続的な適応支援が必要な状況である。同室者の有無、病室の環境、面会制限の状況など、具体的な環境要因についての詳細な評価が必要である。
仕事や生活でのストレス状況、ストレス発散方法
A氏は現在退職しているため、仕事関連のストレスは限定的と考えられる。しかし、25年間の喫煙習慣は重要なストレス対処行動であった可能性が高い。喫煙は多くの場合、ストレス発散や気分転換の手段として使用されるため、現在の禁煙状態は従来のストレス対処方法を失った状況と言える。妻からの禁煙要請に対して長期間応えられなかったことは、家庭内でのストレス要因となっていた可能性もある。現在の主要なストレス要因は、呼吸困難感、睡眠不足、活動制限、入院環境への不適応、家族への心配などが挙げられる。従来のストレス発散方法(趣味活動、友人との交流、身体活動など)についての詳細な情報が不足しており、これらの評価が必要である。
家族のサポート状況、生活の支えとなるもの
A氏の主要な支援者は妻であり、長年の夫婦関係が生活の重要な支えとなっている。妻の「しっかり治療を受けて元気になってほしい」という発言からは、基本的な愛情と支援意欲が感じられる。しかし、「タバコをやめてほしいと何度も言っていた」という複雑な感情も存在し、完全に無条件の支援とは言えない状況もある。72歳という年齢の妻も、夫の看病や介護に対する身体的・精神的負担を抱えている可能性が高い。子どもや孫の存在、親族のサポート、友人関係、地域コミュニティとのつながりなど、家族以外の支援ネットワークについての情報が不足している。生活の支えとなる価値観、信念、趣味、生きがいについても詳細な評価が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のコーピング・ストレス耐性面における主要な課題は、従来のストレス対処方法(喫煙)の喪失と入院環境への適応困難である。25年間継続していた喫煙という対処行動を失ったことで、ストレス耐性が低下している可能性が高い。看護介入としては、まず現在のストレス要因を詳細に評価し、患者の感情や困難を十分に傾聴する。喫煙に代わる健康的なストレス対処方法の開発を支援し、深呼吸法、リラクゼーション技法、音楽療法、読書などの代替手段を提案する。入院環境への適応を促進するため、日課の説明、環境の調整、プライバシーの確保に努める。家族関係におけるストレスについては、夫婦間の建設的なコミュニケーションを促進し、相互理解の深化を支援する。妻の介護負担についても評価し、必要に応じて家族支援や社会資源の活用を検討する。従来の趣味や楽しみについて聞き取りを行い、入院中でも可能な活動を見つけて気分転換を図る。退院後の生活における新しいライフスタイルの構築について話し合い、禁煙継続のための具体的な対処戦略を立案する。ストレス反応の兆候(不安、抑うつ、怒り、睡眠障害など)について継続的に観察し、必要に応じて心理的専門職との連携を図る。社会復帰に向けて段階的な目標設定を行い、自己効力感の回復を支援する必要がある。
信仰、意思決定を決める価値観・信念、目標
A氏は特定の信仰を持たないとされているが、これは現代日本の多くの高齢者に見られる一般的な状況である。しかし、宗教的信仰がないからといって、精神的な支えや人生観が欠如しているわけではない。72歳という年齢は戦後復興期から高度経済成長期を経験した世代であり、勤勉性、責任感、家族への献身という価値観を強く持っている可能性が高い。製造業での勤務経験からも、規則正しい生活、責任感のある行動、協調性を重視する価値観が形成されていたと推察される。医療者の説明をよく聞く協調性のある態度からも、他者との調和や社会的責任を重視する価値観が伺える。
意思決定において重要な要因として、家族の幸福と迷惑をかけないことが最優先される可能性が高い。「早く家に帰りたい」という発言には、家族への負担軽減と自立への強い意志が表れている。また、妻との長年の結婚生活を維持していることから、夫婦関係や家庭の安定を重視する価値観を有していると考えられる。25年間の喫煙継続については、健康への影響を理解しながらも継続していたことから、短期的な快楽や習慣を優先する傾向があった可能性もある。しかし、今回の入院を機に、健康の重要性を再認識し、価値観の優先順位に変化が生じている可能性がある。
現在の目標については、「早く家に帰りたい」という発言から、早期回復と退院が最優先の目標となっている。これは単なる入院環境からの逃避ではなく、自立した生活の回復と家族との正常な関係の再構築への強い願望を示している。長期的な目標として、健康な生活の維持、夫婦関係の改善、残りの人生の質的向上などが重要となる可能性が高い。ただし、これらの具体的な目標設定や優先順位については、詳細な情報収集と話し合いが必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の価値・信念面における主要な課題は、健康に対する価値観の再構築と人生の意味や目標の再設定である。25年間の喫煙継続から今回の肺炎発症に至った経験は、従来の価値観や行動パターンの見直しを迫る重要な転機となっている。これまで家族への責任感を重視しながらも、健康管理については相対的に優先度が低かった可能性があり、今回の入院を機に健康の重要性を再認識する必要がある。
看護介入としては、まず患者の価値観や人生観について十分に傾聴し、理解を深めることが重要である。これまでの人生で大切にしてきたこと、誇りに思うこと、後悔していることなどを話し合う機会を提供する。喫煙継続について自責感を抱いている可能性があるため、過去を責めるのではなく、今後の健康的な生活への価値観の転換を支援する。家族への責任感や迷惑をかけたくないという気持ちを尊重しながら、適切な依存と自立のバランスについて話し合う。
宗教的信仰がないとしても、精神的な支えとなるものを見つける支援を行う。自然への感謝、家族との絆、人生経験の意味、次世代への貢献など、各個人にとって意味のある価値を見出す手助けをする。退院後の生活における新しい目標設定については、現実的かつ達成可能な短期目標から始めて、段階的に長期的な人生目標まで拡大していく。
禁煙継続を価値観の変化として位置づけ、単なる我慢ではなく新しい生き方の選択として捉えられるよう支援する。健康管理を家族への愛情表現の一つとして認識できるよう、価値観の再構築を促進する。人生の意味や存在価値について話し合い、残りの人生をより充実したものにするための価値観の明確化を支援する。
必要に応じて、スピリチュアルケアや宗教者との面談の機会も提供し、精神的な支えを得られる環境を整備する。価値観の変化は時間を要するプロセスであるため、継続的な支援と評価を行い、患者の内的成長を促進する必要がある。
看護計画
看護問題
肺炎による肺胞の炎症に関連した呼吸困難
長期目標
退院時までに酸素投与なしで日常生活に必要な活動が安全に行える
短期目標
1週間以内に酸素投与下で歩行時の酸素飽和度が92%以上を維持できる
≪O-P≫観察計画
・呼吸数、呼吸パターン、呼吸音の変化である
・安静時および活動時の酸素飽和度の変化である
・チアノーゼの有無と程度である
・咳嗽の頻度、性状、痰の量と色調である
・呼吸困難感の程度と持続時間である
・バイタルサインの変化(体温、脈拍、血圧)である
・胸部症状(胸痛、圧迫感)の有無である
・活動時の症状増悪の程度である
・食事摂取時の呼吸状態である
・睡眠時の呼吸パターンと中途覚醒の有無である
・血液検査データ(白血球数、CRP値)の推移である
・胸部レントゲン所見の変化である
≪T-P≫援助計画
・酸素療法の適切な管理と流量調整を行う
・半座位またはファウラー位での体位保持を支援する
・深呼吸や咳嗽の促進を図る
・痰の喀出を促すための体位ドレナージを実施する
・処方された抗菌薬の確実な投与を行う
・水分摂取を促進して痰の粘稠度を下げる
・室内環境の調整(適切な温度、湿度の維持)を行う
・活動時の酸素飽和度監視と休息の促進を図る
・呼吸困難感軽減のための安楽な環境を整備する
・必要時の吸引や口腔ケアを実施する
・段階的な活動拡大の支援を行う
・呼吸リハビリテーションの実施を支援する
≪E-P≫教育・指導計画
・効果的な咳嗽方法と深呼吸法を指導する
・呼吸困難時の対処方法と体位の取り方を説明する
・酸素療法の必要性と安全な取り扱い方法を指導する
・痰の観察方法と異常時の対応について説明する
・感染予防のための手洗いとマスク着用を指導する
・禁煙の重要性と継続方法について指導する
看護問題
呼吸困難感と食欲不振に関連した栄養摂取不足
長期目標
退院時までに必要栄養量の8割以上を経口摂取できる
短期目標
1週間以内に食事摂取量を現在の5割から7割まで増加させる
≪O-P≫観察計画
・食事摂取量と摂取内容の記録である
・体重の変化と栄養状態の推移である
・食欲の程度と食事に対する意欲である
・嚥下機能と咀嚼機能の状態である
・消化器症状(嘔気、嘔吐、腹部膨満感)の有無である
・口腔内の状態(乾燥、口内炎、歯の状態)である
・血液検査データ(アルブミン、総蛋白、血糖値)の変化である
・皮膚の状態と創傷治癒能力である
・活力や意欲の変化である
・排便状況と腸蠕動音である
・水分摂取量とバランスの状態である
・食事時間と摂取にかかる時間である
≪T-P≫援助計画
・少量頻回食の提供と摂取支援を行う
・食事前の口腔ケアと環境整備を実施する
・患者の嗜好に配慮した食事内容の調整を図る
・食事時の適切な体位の保持を支援する
・高エネルギー・高蛋白質の栄養補助食品を提供する
・食事摂取を阻害する症状の緩和を図る
・食事時間の調整と個別対応を行う
・水分摂取の促進と脱水予防を図る
・食事摂取量の正確な記録と評価を行う
・管理栄養士との連携による栄養指導を実施する
・便秘予防のための対策を講じる
・食欲増進のための環境作りを行う
≪E-P≫教育・指導計画
・栄養の重要性と回復への影響について説明する
・少量頻回摂取の方法とその効果を指導する
・食事摂取時の注意点と安全な方法を説明する
・水分摂取の重要性と適切な量について指導する
・退院後の食事管理と栄養バランスについて指導する
・家族に対する食事援助の方法を指導する
看護問題
活動制限と呼吸困難感に関連した睡眠パターンの障害
長期目標
退院時までに夜間6時間以上の連続した睡眠が確保できる
短期目標
1週間以内に夜間の睡眠時間を4-5時間まで延長する
≪O-P≫観察計画
・夜間の睡眠時間と睡眠の質である
・中途覚醒の回数と覚醒の要因である
・日中の傾眠や疲労感の程度である
・咳嗽や呼吸困難による睡眠への影響である
・睡眠導入剤の効果と副作用である
・睡眠環境(騒音、照明、温度)の状況である
・睡眠前の不安や心配事の有無である
・日中の活動量と運動量である
・排尿パターンと夜間頻尿の有無である
・疼痛や不快症状の有無である
・生活リズムと就寝・起床時間である
・睡眠に対する満足度と熟眠感である
≪T-P≫援助計画
・呼吸困難感を軽減する体位の調整を行う
・夜間の静かな環境作りと騒音の軽減を図る
・適切な照明調整と就寝環境の整備を行う
・就寝前のリラクゼーション技法を提供する
・睡眠導入剤の適切な投与と効果の評価を行う
・日中の活動と夜間の休息のメリハリをつける
・咳嗽や痰による覚醒の軽減策を講じる
・不安や心配事に対する傾聴と支援を行う
・規則正しい生活リズムの確立を支援する
・夜間の排尿援助と安全確保を図る
・室温や湿度の調整を行う
・睡眠記録の作成と睡眠パターンの評価を行う
≪E-P≫教育・指導計画
・良質な睡眠のための生活習慣について指導する ・睡眠環境の整備方法と注意点を説明する ・リラクゼーション技法や深呼吸法を指導する ・睡眠導入剤の適切な使用方法について説明する ・日中の活動と夜間の休息の重要性を指導する ・家族に対する睡眠環境作りの協力を依頼する
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
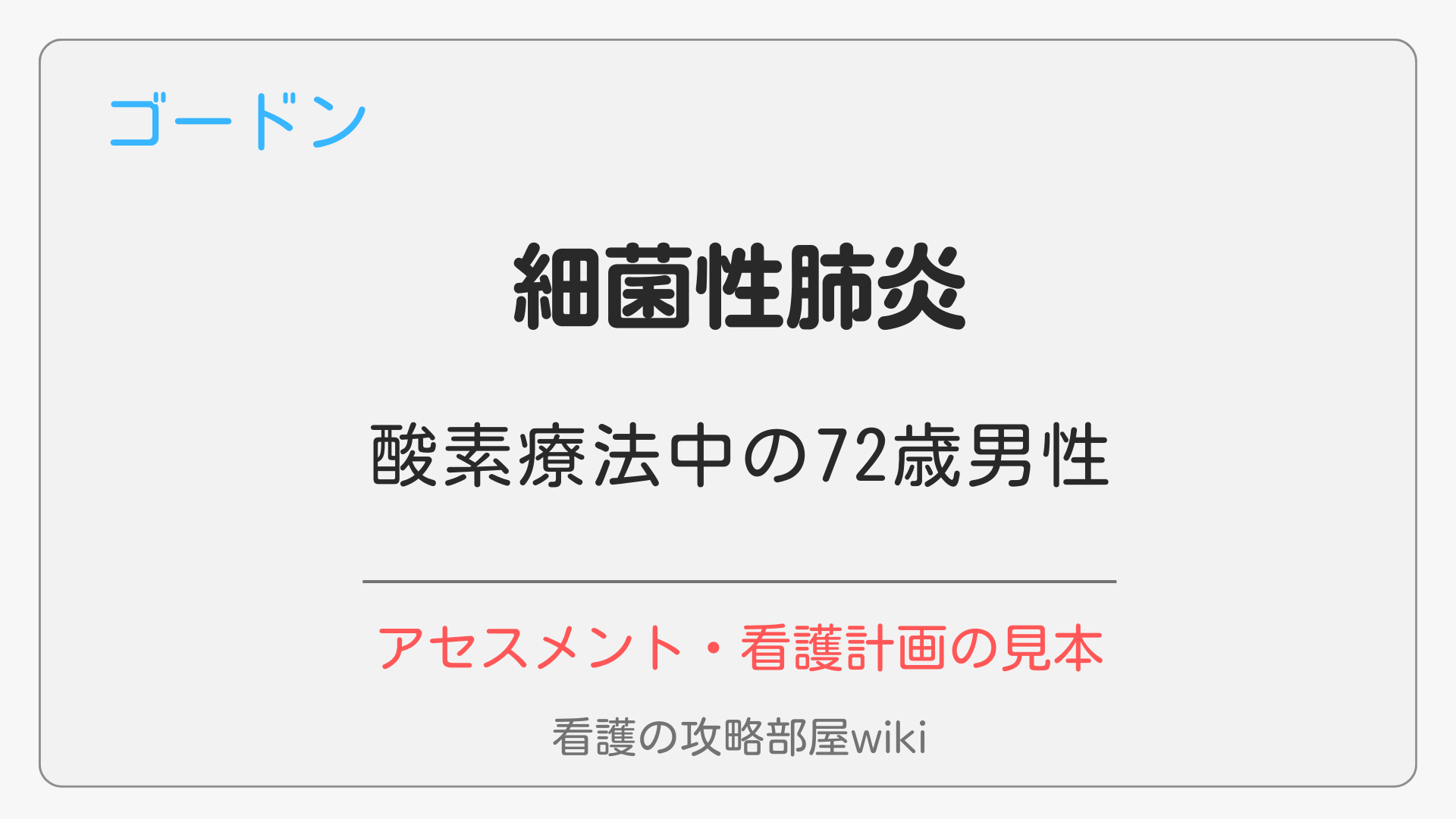
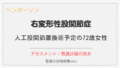
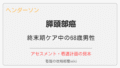
コメント