事例の要約
進行性膵頭部癌により終末期ケアを受けている患者の疼痛管理と家族支援という事例である。入院から45日目、介入32日目の状況を示している。
基本情報
A氏は68歳男性で、身長165cm、体重は入院時62kgから現在48kgまで減少している。家族構成は妻と長男夫婦、孫2人の5人家族で、キーパーソンは妻である。元建設会社の現場監督として働いており、責任感が強く頑固な性格だが、家族思いの一面もある。感染症は特になく、アレルギーも特記すべきものはない。認知力は保たれており、病状についても理解している。
病名
膵頭部癌(ステージIVb)、多発肝転移、腹膜播種
既往歴と治療状況
3年前に高血圧症と診断され、内服治療を継続している。2年前に糖尿病を発症し、食事療法と内服薬で管理していた。今回の膵癌は1年前に腹部不快感から発見され、手術適応外のため化学療法を施行していたが、効果が乏しく6か月前に治療を終了した。
入院から現在までの情報
45日前に腹痛と食欲不振の悪化により入院となった。入院時より疼痛が強く、モルヒネの持続投与を開始した。徐々に全身状態が悪化し、約2週間前から終末期ケアに移行している。家族は病室に付き添い、最期の時間を共に過ごしている。現在は意識レベルの低下がみられ、会話は困難な状況である。
バイタルサイン
来院時は血圧138/82mmHg、脈拍96回/分、体温37.2℃、呼吸数20回/分、酸素飽和度96%であった。現在は血圧90/55mmHg、脈拍112回/分、体温36.8℃、呼吸数24回/分、酸素飽和度92%と循環動態の不安定さがみられる。
食事と嚥下状態
入院前は食欲不振により食事摂取量が減少していたが、普通食を摂取していた。現在は嚥下機能の低下により経口摂取は困難で、点滴による輸液管理のみ行っている。喫煙は20歳から1日20本を40年間続けていたが、5年前に禁煙した。飲酒は機会飲酒程度であった。
排泄
入院前は自立していたが、便秘傾向があった。現在は膀胱留置カテーテルを挿入し、尿量は減少傾向にある。排便は2日に1回程度で、浣腸を要することがある。下剤としてマグネシウム製剤を使用している。
睡眠
入院前は夜間の腹痛により睡眠が浅くなっていた。現在は意識レベルの低下により、ほぼ終日臥床状態で、明確な睡眠覚醒のリズムは不明瞭である。疼痛管理のためのモルヒネ投与により、比較的安静を保っている。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力、聴力に特記すべき異常はなかった。現在は意識レベルの低下により、言語的コミュニケーションは困難だが、声かけに対する反応はわずかにみられる。宗教的信仰は特にない。
動作状況
入院前は歩行可能だったが、疼痛により活動量は低下していた。現在は寝たきり状態で、体位変換は全介助が必要である。移乗、排尿、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて全介助である。転倒歴は特にない。
内服中の薬
- モルヒネ硫酸塩徐放錠 30mg 1日2回朝夕食後
- アムロジピン 5mg 1日1回朝食後
- メトホルミン塩酸塩 500mg 1日2回朝夕食後
- 酸化マグネシウム 1000mg 1日2回朝夕食後
- ランソプラゾール 15mg 1日1回朝食前
現在は経口摂取困難のため、疼痛管理は持続点滴によるモルヒネ投与に変更している。その他の薬剤は中止している。
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 白血球数 | 8,500/μL | 12,000/μL | 4,000-9,000 |
| 赤血球数 | 3.2×10⁶/μL | 2.8×10⁶/μL | 4.2-5.4×10⁶ |
| ヘモグロビン | 8.2g/dL | 7.1g/dL | 13.5-17.0 |
| 血小板数 | 12万/μL | 8万/μL | 15-35万 |
| 総蛋白 | 5.8g/dL | 4.9g/dL | 6.7-8.3 |
| アルブミン | 2.8g/dL | 2.1g/dL | 3.8-5.3 |
| 総ビリルビン | 3.2mg/dL | 5.8mg/dL | 0.2-1.2 |
| AST | 185U/L | 298U/L | 10-40 |
| ALT | 142U/L | 201U/L | 5-45 |
| 尿素窒素 | 28mg/dL | 45mg/dL | 8-22 |
| クレアチニン | 1.2mg/dL | 1.8mg/dL | 0.6-1.2 |
| CRP | 8.5mg/dL | 15.2mg/dL | <0.3 |
今後の治療方針と医師の指示
積極的治療は行わず、疼痛管理と症状緩和を中心とした終末期ケアを継続する。モルヒネの持続投与により疼痛コントロールを図り、必要に応じて用量調整を行う。脱水に対する輸液は最小限とし、家族の希望に応じて対応する。呼吸困難が出現した場合は、モルヒネの増量や酸素投与を検討する。
本人と家族の想いと言動
A氏は病状について理解しており、「家族に迷惑をかけたくない」「痛みだけは取ってほしい」と話していた。妻は「最期まで一緒にいたい」「痛みがないようにしてほしい」と涙ながらに話し、長男は「父らしく最期を迎えさせてあげたい」と述べている。家族は交代で付き添い、A氏の手を握りながら声かけを続けている。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は膵頭部癌(ステージIVb)で多発肝転移と腹膜播種を認める終末期患者である。癌の進行により全身状態が悪化し、呼吸機能にも影響を与えている。膵癌は消化器癌の中でも予後が極めて不良な疾患であり、進行例では腹膜播種による腹水貯留や胸水貯留が呼吸機能を圧迫する可能性がある。また、終末期における全身の代謝機能低下と循環動態の不安定化が呼吸パターンに変化をもたらしている。
呼吸数、酸素飽和度、肺雑音、呼吸機能、胸部レントゲン
現在の呼吸数は24回/分と軽度頻呼吸を呈しており、来院時の20回/分から増加している。酸素飽和度は92%と軽度低下がみられ、室内気では十分な酸素化が困難な状況である。肺雑音については情報が不足しているため、聴診による詳細な評価が必要である。特に下肺野の湿性ラ音の有無や胸水による呼吸音の減弱について確認が重要である。呼吸機能については、終末期の全身衰弱により呼吸筋力の低下が推測される。胸部レントゲンの所見についても情報収集が必要であり、胸水の有無、肺野の透過性、心拡大の程度などを確認する必要がある。
呼吸苦、息切れ、咳、痰
A氏の呼吸苦や息切れの程度について詳細な情報が不足している。意識レベルの低下により自覚症状の訴えが困難であるため、客観的な観察による評価が重要である。表情の変化、不穏状態、補助呼吸筋の使用、鼻翼呼吸などの呼吸困難の兆候について継続的な観察が必要である。咳や痰の性状についても情報収集が必要であり、終末期では喀痰の喀出困難により気道クリアランスが低下する可能性がある。
喫煙歴
A氏は20歳から1日20本を40年間喫煙していたが、5年前に禁煙している。累積喫煙量は40パックイヤーと高値であり、長期喫煙による慢性閉塞性肺疾患の合併リスクが高い。また、喫煙歴は膵癌発症の危険因子でもあり、現在の病状との関連性も考慮される。禁煙から5年経過しているものの、長期喫煙による肺機能への不可逆的な影響が残存している可能性があり、現在の呼吸機能低下の一因となっている可能性がある。
呼吸に関するアレルギー
A氏にはアレルギーの既往は特記されていない。しかし、終末期ケアにおいて使用される薬剤や医療材料に対するアレルギー反応の可能性については継続的な観察が必要である。特にモルヒネ投与による呼吸抑制や、その他の薬剤による気管支攣縮などの副作用について注意深い観察が求められる。
ニーズの充足状況
A氏の呼吸に関するニーズは十分に充足されているとは言い難い状況である。酸素飽和度92%は軽度低下を示しており、組織への酸素供給が不十分な可能性がある。呼吸数の増加は代償機転として現れていると考えられるが、呼吸筋の疲労により持続困難となる可能性がある。68歳という年齢に加え、終末期の全身衰弱により呼吸予備能が著しく低下している状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の呼吸機能に関する主要な課題は、終末期における呼吸機能低下と呼吸困難の予防・緩和である。継続的な呼吸状態の観察として、呼吸数、呼吸パターン、酸素飽和度、呼吸困難の兆候について定期的な評価が必要である。体位管理による呼吸機能の改善を図り、セミファーラー位や側臥位などの安楽な体位を提供する。口腔ケアによる気道感染予防と、必要に応じた酸素投与による症状緩和を検討する。また、家族への呼吸状態の説明と精神的支援も重要な看護介入である。モルヒネ投与による呼吸抑制のリスクと疼痛緩和のバランスを考慮し、医師との密な連携による薬剤調整が必要である。呼吸困難が出現した場合の対応について、事前に医師の指示を確認し、迅速な症状緩和ができる体制を整備しておく必要がある。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は現在経口摂取が困難な状態であり、嚥下機能の低下により食事摂取は不可能である。入院前は食欲不振により摂取量が減少していたものの、普通食を摂取していた。現在は点滴による輸液管理のみで栄養と水分を補給している状況である。具体的な輸液の種類や投与量についての詳細情報が必要である。終末期における消化機能の低下と意識レベルの低下により、経口摂取の再開は困難な状況と考えられる。
食事に関するアレルギー
A氏には食事に関するアレルギーの既往は特記されていない。しかし、現在は経口摂取を行っていないため、アレルギーによる直接的な影響は少ないと考えられる。輸液や薬剤投与時におけるアレルギー反応については継続的な観察が必要である。
身長、体重、身体質量指数、必要栄養量、身体活動レベル
A氏の身長は165cm、体重は入院時62kgから現在48kgまで14kgの著明な体重減少がみられる。現在の身体質量指数は17.6kg/m²と著しい低体重状態である。入院時の身体質量指数も22.8kg/m²であり、もともと標準的な体格であったことから、疾患による急激な栄養状態の悪化が示されている。68歳男性の基礎代謝量は約1200kcal程度と推定されるが、現在の身体活動レベルは寝たきり状態であり、エネルギー消費量は著しく低下している。しかし、癌による代謝亢進や炎症反応により、実際の栄養必要量は基礎代謝量を上回る可能性がある。
食欲、嚥下機能、口腔内の状態
A氏は入院前から食欲不振がみられており、現在は意識レベルの低下により食欲の評価は困難である。嚥下機能については著明に低下しており、誤嚥のリスクが極めて高い状況である。口腔内の状態について詳細な情報が不足しているため、口腔乾燥、舌苔の付着、歯牙の状態、口腔粘膜の状態について評価が必要である。終末期における口腔ケアの重要性を考慮し、継続的な観察と適切なケアが求められる。
嘔吐、吐気
現在の嘔吐や吐気の有無について具体的な情報が不足している。意識レベルの低下により自覚症状の訴えは困難であるが、客観的な観察による評価が重要である。終末期における消化器症状として、嘔吐反射の低下や胃内容物の逆流のリスクがあるため、継続的な観察が必要である。また、使用中のモルヒネによる消化器副作用の可能性についても考慮する必要がある。
血液データ(総蛋白、アルブミン、ヘモグロビン、中性脂肪)
血液データは著明な栄養状態の悪化を示している。総蛋白は入院時5.8g/dLから現在4.9g/dLまで低下し、アルブミンは入院時2.8g/dLから現在2.1g/dLと重度の低アルブミン血症を呈している。これらの値は重度の栄養不良状態を示している。ヘモグロビンは入院時8.2g/dLから現在7.1g/dLと進行性の貧血がみられ、これは栄養不良と疾患進行の両方の影響と考えられる。中性脂肪の値については情報が不足しており、脂質代謝の評価のために追加検査が必要である。
ニーズの充足状況
A氏の栄養摂取に関するニーズは著しく充足されていない状況である。経口摂取が不可能であり、現在の輸液のみでは必要な栄養素とエネルギーの供給が不十分と考えられる。体重減少、低アルブミン血症、貧血の進行は重度の栄養不良状態を示しており、生命維持に必要な最低限の栄養補給も困難な状況である。68歳という年齢に加え、終末期の代謝変化により栄養状態の改善は極めて困難である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の栄養管理における主要な課題は、終末期における適切な栄養補給と症状緩和のバランスである。積極的な栄養補給よりも症状緩和と安楽を重視した対応が重要である。口腔ケアによる口腔内環境の維持と感染予防を継続的に実施する。輸液量の調整については、浮腫や呼吸困難の増悪を避けるため、医師と連携し慎重に検討する必要がある。家族に対しては栄養状態の現状と今後の見通しについて丁寧な説明を行い、精神的支援を提供する。また、嚥下機能の評価と誤嚥予防のための体位管理を継続し、口腔内の分泌物や逆流による気道閉塞を予防する。栄養状態の改善よりも患者の尊厳と安楽を最優先とした看護介入が求められる。
排便回数と量と性状、排尿回数と量と性状、発汗
A氏の排便は2日に1回程度であり、便秘傾向がみられる。排便量や性状の詳細について情報が不足しているため、継続的な観察が必要である。膀胱留置カテーテルが挿入されており、尿量は減少傾向にある。具体的な時間尿量や24時間尿量の記録が必要である。終末期における腎機能低下により、尿量減少と尿の濃縮がみられていると考えられる。発汗については詳細な情報が不足しているが、体温36.8℃と平熱範囲内であることから、異常発汗は認められていないと推測される。しかし、終末期における体温調節機能の変化について継続的な観察が重要である。
水分出納バランス
A氏の水分出納バランスについて具体的な記録が不足している。現在点滴による輸液管理のみを行っているが、輸液量と尿量、不感蒸泄を含めた詳細な水分出納の評価が必要である。尿量減少傾向がみられることから、水分貯留の可能性があり、浮腫や呼吸困難の増悪リスクを考慮する必要がある。終末期における腎機能低下と循環動態の不安定化により、水分出納バランスの維持が困難となっている可能性が高い。
排泄に関連した食事、水分摂取状況
A氏は現在経口摂取が困難であり、食事や水分の経口摂取は行っていない。点滴による輸液のみで水分補給を行っている状況である。入院前は食欲不振により摂取量が減少していたが、これが便秘傾向の一因となっていた可能性がある。現在の輸液量が腸蠕動や排便に与える影響について評価が必要である。経口摂取の中止により、消化管への刺激が減少し、便秘が悪化する可能性がある。
麻痺の有無
A氏に明らかな麻痺の記載はないが、終末期の全身衰弱により運動機能が著しく低下している。現在は寝たきり状態であり、自力での体位変換や排泄動作は困難である。68歳という年齢と疾患の進行により、筋力低下と神経機能の低下が排泄機能に影響を与えている可能性がある。具体的な運動機能や感覚機能の評価が必要である。
腹部膨満、腸蠕動音
腹部膨満や腸蠕動音について具体的な情報が不足している。膵癌による腹膜播種があることから、腹水貯留による腹部膨満の可能性がある。また、消化管機能の低下により腸蠕動の減弱が生じている可能性が高い。腹部の視診、触診、聴診による詳細な評価が必要である。腹膜播種による腸管の癒着や狭窄の可能性についても考慮し、継続的な観察が重要である。
血液データ(尿素窒素、クレアチニン、糸球体濾過率推算値)
血液データは腎機能の低下を示している。尿素窒素は入院時28mg/dLから現在45mg/dLまで上昇し、クレアチニンは入院時1.2mg/dLから現在1.8mg/dLと著明に上昇している。これらの値から推算される糸球体濾過率は著しく低下していると考えられる。68歳という年齢による生理的な腎機能低下に加え、疾患の進行と循環動態の悪化により腎機能が急速に悪化している状況である。
ニーズの充足状況
A氏の排泄に関するニーズは十分に充足されていない状況である。便秘傾向と腎機能低下により、正常な排泄機能が維持できていない。膀胱留置カテーテルにより排尿は確保されているが、尿量減少により老廃物の適切な排泄が困難となっている。腸蠕動の低下により排便が困難となり、腹部不快感や腹部膨満のリスクがある。68歳という年齢と終末期の状態により、生理的な排泄機能の維持が極めて困難な状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の排泄機能に関する主要な課題は、終末期における腎機能低下と消化管機能低下への対応である。膀胱留置カテーテルの管理として、感染予防と閉塞予防のための適切なケアを継続する。尿量と尿性状の観察を定期的に行い、腎機能悪化の早期発見に努める。便秘対策として、腹部マッサージや体位変換による腸蠕動の促進を図る。必要に応じて下剤や浣腸の使用について医師と相談する。水分出納バランスの管理として、輸液量の調整と浮腫の観察を継続する。腹部膨満や腹痛の有無について定期的に評価し、腹膜播種による消化管症状の変化を早期に発見する。家族に対しては排泄機能の現状と今後の見通しについて説明し、精神的支援を提供する。患者の尊厳を保持しながら、安楽な排泄環境を提供することが重要である。
日常生活動作、麻痺、骨折の有無
A氏は現在寝たきり状態であり、すべての日常生活動作において全介助が必要である。入院前は歩行可能であったが、疼痛により活動量は低下していた。体位変換、移乗、排尿、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて全介助が必要な状況である。明らかな麻痺の記載はないが、終末期の全身衰弱により運動機能が著しく低下している。骨折の既往は特記されていないが、長期臥床による骨萎縮と骨折リスクの増加が懸念される。68歳という年齢と疾患による筋肉量の減少と筋力低下が日常生活動作の自立度に大きく影響している。
ドレーン、点滴の有無
A氏には膀胱留置カテーテルが挿入されており、点滴による輸液管理が行われている。これらの医療器具により体位変換や移動時の制約が生じている。カテーテルや点滴ルートの屈曲や抜去を防ぐための注意深い体位管理が必要である。特に体位変換時には、医療器具の確認と固定を十分に行う必要がある。その他のドレーンの挿入については情報が不足しているため、詳細な確認が必要である。
生活習慣、認知機能
A氏は元建設会社の現場監督として働いており、活動的な生活習慣を有していた。責任感が強く頑固な性格であることから、現在の身体機能低下に対する心理的ストレスが大きいと推測される。認知力は保たれており、病状についても理解しているため、自身の身体機能の変化を十分に認識している可能性が高い。しかし、意識レベルの低下がみられ、コミュニケーションが困難な状況となっている。
日常生活動作に関連した呼吸機能
A氏は現在寝たきり状態であり、体位変換や移動に伴う身体活動はほとんどない。しかし、わずかな体位変換でも呼吸状態に影響を与える可能性がある。現在の酸素飽和度92%と軽度低下がみられることから、体位変換時の呼吸状態の悪化リスクを考慮する必要がある。長期臥床による肺機能の低下と、40年間の喫煙歴による慢性的な肺機能障害が相互に影響している可能性がある。
転倒転落のリスク
A氏は現在寝たきり状態であり、自力での起き上がりや移動は困難である。そのため、ベッドからの転落リスクが主要な安全上の課題となる。意識レベルの低下により、自身の身体状況を適切に判断することが困難であることから、不穏状態や体動時の転落リスクが高い。また、医療器具の装着により、体動時の引っかかりや絡まりによる二次的な転落リスクも考慮する必要がある。68歳という年齢によるバランス機能の低下と、疾患による全身状態の悪化が転落リスクを増大させている。
ニーズの充足状況
A氏の運動と姿勢保持に関するニーズは著しく充足されていない状況である。自力での体位変換が不可能であり、適切な姿勢保持のためには継続的な介助が必要である。長期臥床による廃用症候群の進行により、関節可動域の制限、筋萎縮、褥瘡のリスクが高まっている。呼吸機能や循環機能への悪影響も懸念され、生命維持に必要な基本的機能への影響が生じている。終末期の状態により、運動機能の改善は期待できない状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の運動・姿勢保持に関する主要な課題は、終末期における安楽な体位保持と合併症予防である。定期的な体位変換により褥瘡予防と呼吸機能の維持を図る。体位変換時には医療器具の安全確保と呼吸状態の観察を十分に行う。関節可動域訓練により関節拘縮の予防に努めるが、患者の状態と苦痛を考慮し無理のない範囲で実施する。転落防止対策として、ベッド柵の適切な使用とベッド周囲の安全確認を継続する。褥瘡予防のためのマットレスや体位保持用具の使用を検討する。家族に対しては体位変換の方法と注意点について指導し、協力を得る。患者の尊厳と安楽を最優先とし、苦痛を最小限に抑えた体位管理を実施する。また、呼吸困難や循環動態の変化に注意しながら、適切な体位保持を継続する必要がある。
睡眠時間、パターン
A氏は現在意識レベルの低下により、ほぼ終日臥床状態である。明確な睡眠覚醒のリズムは不明瞭となっており、生理的な睡眠パターンの評価が困難な状況である。入院前は夜間の腹痛により睡眠が浅くなっていたことから、疼痛による睡眠の質の低下がみられていた。現在はモルヒネの持続投与により比較的安静を保っているが、これが自然な睡眠なのか薬剤による鎮静状態なのかの判別が重要である。終末期における睡眠パターンの変化として、浅い眠りや覚醒と睡眠の境界が不明瞭になることが一般的である。
疼痛、掻痒感の有無、安静度
A氏は膵頭部癌による強い疼痛を有しており、入院時よりモルヒネの持続投与を開始している。疼痛コントロールが睡眠と休息に大きく影響している状況である。現在のモルヒネ投与により比較的安静を保っているとあるが、疼痛の程度や疼痛による覚醒の有無について継続的な評価が必要である。掻痒感については情報が不足しているが、終末期における皮膚の乾燥や黄疸による掻痒感の可能性がある。総ビリルビン値が5.8mg/dLと著明に上昇していることから、黄疸による掻痒感が睡眠を妨げる可能性が考慮される。
入眠剤の有無
現在の入眠剤の使用について具体的な情報が不足している。モルヒネの持続投与により鎮静効果が得られているが、専用の睡眠薬の併用については確認が必要である。入院前の睡眠薬使用歴についても情報収集が重要である。終末期における薬剤使用については、患者の苦痛緩和と安楽を最優先とした選択が必要である。
疲労の状態
A氏は終末期の全身衰弱により著しい疲労状態にある。体重が入院時62kgから現在48kgまで14kg減少していることからも、重度の消耗状態であることが示されている。癌による代謝亢進と栄養不良により、慢性的な疲労感が持続していると考えられる。しかし、意識レベルの低下により疲労感の自覚的評価は困難であり、客観的な観察による評価が重要である。呼吸数24回/分と軽度頻呼吸がみられることも、全身の疲労状態を反映している可能性がある。
療養環境への適応状況、ストレス状況
A氏は入院から45日目であり、長期入院による環境への慣れはあると考えられる。しかし、終末期という状況と家族の付き添いにより、心理的ストレスは大きいと推測される。責任感が強く頑固な性格であることから、自身の状況変化に対する心理的負担が大きい可能性がある。家族が交代で付き添いをしているため、環境的には安心感があると考えられるが、病室という非日常的環境でのストレスも考慮する必要がある。
ニーズの充足状況
A氏の睡眠と休息に関するニーズの充足状況は複雑な評価を要する状況である。モルヒネ投与により疼痛はコントロールされているが、これが自然な休息なのか薬剤による鎮静なのかの判別が重要である。意識レベルの低下により睡眠の質の評価が困難であるが、表情や呼吸パターン、体動の有無から安楽性を評価する必要がある。終末期における休息の概念は、通常の睡眠とは異なり、苦痛からの解放と安らぎが重要な要素となる。68歳という年齢による生理的な睡眠パターンの変化も考慮する必要がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の睡眠・休息に関する主要な課題は、終末期における安楽な休息の確保と苦痛の緩和である。疼痛コントロールの継続的評価により、適切なモルヒネ投与量の調整を医師と連携して行う。環境調整として、照明や音響、温度の管理により安らかな環境を提供する。家族の付き添いを考慮し、家族も休息できる環境作りに配慮する。黄疸による掻痒感の有無を観察し、必要に応じて皮膚ケアや薬剤による対症療法を検討する。体位変換により褥瘡予防と安楽な体位の維持を図る。呼吸困難や不穏状態の早期発見により、適切な症状緩和を行う。睡眠覚醒パターンの観察を継続し、患者の状態変化を把握する。家族に対しては患者の状態の説明と心理的支援を提供し、最期の時間を安らかに過ごせる環境作りに協力する。患者の尊厳と安楽を最優先とした看護介入が求められる。
日常生活動作、運動機能、認知機能、麻痺の有無、活動意欲
A氏は現在寝たきり状態であり、衣類の着脱を含むすべての日常生活動作において全介助が必要である。終末期の全身衰弱により運動機能が著しく低下しており、上肢や手指の細かい動作も困難な状況である。認知機能については病状について理解しているとあるが、現在は意識レベルの低下がみられ、コミュニケーションが困難な状況となっている。明らかな麻痺の記載はないが、全身の筋力低下により自力での衣類着脱は不可能である。元建設会社の現場監督として活動的であった背景から、現在の身体機能低下に対する心理的ストレスがあったと推測されるが、現在は意識レベルの低下により活動意欲の評価は困難である。
点滴、ルート類の有無
A氏には膀胱留置カテーテルが挿入されており、点滴による輸液管理が行われている。これらの医療器具により衣類着脱時の制約が生じている。特に上肢への点滴ルートがある場合、衣類の袖通しが困難となる可能性がある。カテーテルや点滴ルートの屈曲や抜去を防ぐための注意深い衣類着脱が必要である。その他の医療器具の装着については詳細な情報が必要であり、モルヒネの持続投与のためのルートについても確認が重要である。
発熱、吐気、倦怠感
A氏の現在の体温は36.8℃と平熱範囲内であるが、終末期における体温調節機能の変化について継続的な観察が必要である。吐気については具体的な情報が不足しているが、モルヒネ投与による消化器副作用の可能性がある。終末期の全身衰弱により著しい倦怠感があると考えられ、これが衣類着脱への協力度に影響している。体重が14kg減少していることからも、重度の消耗状態であることが示されており、わずかな身体活動でも疲労が増強する可能性がある。
ニーズの充足状況
A氏の衣類着脱に関するニーズは著しく充足されていない状況である。自力での衣類選択や着脱が不可能であり、すべて看護師による介助が必要である。医療器具の装着により着脱が複雑化しており、適切な衣類の選択と着脱方法の工夫が必要である。体温調節機能の低下により、適切な衣類による温度管理が重要となっている。皮膚の脆弱性や褥瘡リスクを考慮した衣類の選択が求められるが、現在の状況では基本的なニーズの充足が困難な状況である。68歳という年齢と終末期の状態により、自立した衣類着脱の回復は期待できない状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の衣類着脱に関する主要な課題は、終末期における適切な衣類管理と患者の尊厳保持である。医療器具に配慮した衣類の選択として、前開きの衣類や袖が取り外し可能な衣類の使用を検討する。体温調節のため、容易に調整できる重ね着や軽量な素材の使用が重要である。皮膚保護のため、縫い目や硬い部分が褥瘡好発部位に当たらない衣類を選択する。着脱時の安全確保として、医療器具の確認と固定を十分に行い、患者の苦痛を最小限に抑えた着脱方法を実施する。家族の参加により、患者が愛用していた衣類の使用や家族の希望を取り入れた衣類選択を行う。清潔保持のため、汚染時の迅速な交換と適切な洗濯管理を行う。患者の尊厳と快適性を最優先とし、プライバシーの保護と羞恥心への配慮を十分に行う。また、体位変換時の衣類のずれや圧迫に注意し、定期的な衣類の整理を実施する必要がある。
バイタルサイン
A氏の現在の体温は36.8℃と平熱範囲内を保っているが、来院時の37.2℃から軽度低下がみられる。血圧は来院時138/82mmHgから現在90/55mmHgと著明に低下しており、循環動態の不安定化を示している。脈拍は96回/分から112回/分と頻脈傾向がみられ、呼吸数も20回/分から24回/分と軽度頻呼吸を呈している。終末期における循環機能の低下により、体温調節に必要な血流分布や代謝機能が著しく低下している可能性がある。68歳という年齢に加え、疾患の進行により体温調節中枢の機能低下も考慮される。
療養環境の温度、湿度、空調
病室の温度、湿度、空調設備について具体的な情報が不足している。終末期患者の体温調節機能の低下を考慮し、適切な環境温度の維持が重要である。一般的に病室温度は22-26℃、湿度は50-60%が推奨されるが、患者の状態に応じた個別調整が必要である。家族の付き添いがあることも考慮し、患者と家族の両方が快適に過ごせる環境作りが重要である。空調による直接的な風当たりを避け、温度変化を最小限に抑える環境調整が求められる。
発熱の有無、感染症の有無
現在の体温36.8℃は発熱を示していないが、白血球数が12,000/μLと上昇しており、何らかの炎症反応や感染の可能性が示唆される。炎症反応蛋白が15.2mg/dLと著明に高値であることからも、全身の炎症状態が存在する可能性が高い。終末期における免疫機能の低下により、感染に対する抵抗力が著しく低下している状況である。膀胱留置カテーテルによる尿路感染や、長期臥床による肺炎のリスクが高い状況である。また、癌の進行による炎症反応の可能性も考慮される。
日常生活動作
A氏は現在寝たきり状態であり、体温調節に必要な自発的な活動が困難である。自力での衣類調整や体位変換ができないため、環境温度の変化に対する適応能力が著しく制限されている。筋肉量の減少により熱産生能力が低下し、皮下脂肪の減少により保温能力も低下している。体重が14kg減少していることからも、体温調節に必要な身体的条件の著明な悪化が示されている。
血液データ(白血球数、炎症反応蛋白)
白血球数は入院時8,500/μLから現在12,000/μLまで著明に上昇している。炎症反応蛋白も入院時8.5mg/dLから現在15.2mg/dLとさらに上昇している。これらの値は活動性の炎症や感染を示唆しており、発熱のリスクが高い状況である。終末期における免疫機能の低下により、感染に対する防御機構が破綻している可能性がある。また、癌の進行や組織壊死による炎症反応の可能性も考慮される。
ニーズの充足状況
A氏の体温調節に関するニーズは部分的に充足されているが、リスクが高い状況である。現在は平熱を保っているものの、体温調節機能の著明な低下により、環境変化に対する適応能力が極めて限定的である。自力での体温調節行動が不可能であり、看護師による継続的な環境管理と観察が必要である。炎症反応の上昇により発熱のリスクが高く、循環動態の不安定化により体温維持が困難となる可能性がある。68歳という年齢と終末期の状態により、生理的な体温調節機能の回復は期待できない状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の体温調節に関する主要な課題は、終末期における体温調節機能低下への対応と感染予防である。定期的な体温測定により、体温変化の早期発見に努める。環境温度の適切な管理として、室温、湿度、空調の調整を継続的に行う。衣類や寝具による保温調節を適切に実施し、患者の快適性を確保する。感染予防対策として、手指衛生の徹底、カテーテル管理、口腔ケア、褥瘡予防を継続する。炎症反応の監視により、感染の早期発見と適切な治療介入を図る。循環動態の観察を継続し、血圧低下や頻脈による体温調節への影響を評価する。家族への指導として、患者の体温調節能力の低下について説明し、環境調整への協力を求める。発熱時の対応について事前に医師の指示を確認し、迅速な症状緩和ができる体制を整備する。患者の安楽性を最優先とし、過度な治療介入を避けながら、適切な体温管理を継続する必要がある。
自宅・療養環境での入浴回数、方法、日常生活動作、麻痺の有無
A氏の入院前の入浴習慣について具体的な情報が不足している。現在は寝たきり状態であり、入浴を含むすべての清潔ケアにおいて全介助が必要である。終末期の全身衰弱により運動機能が著しく低下しており、自力での清拭や洗顔も困難な状況である。明らかな麻痺の記載はないが、全身の筋力低下により清潔保持のための身体動作は不可能である。ベッド上での全身清拭が主要な清潔ケア方法となっており、入浴や シャワー浴は困難な状況である。
鼻腔、口腔の保清、爪
鼻腔、口腔の状態について詳細な情報が不足している。現在は経口摂取が困難であり、口腔乾燥や舌苔の付着、口腔粘膜の状態悪化が懸念される。終末期における唾液分泌の減少により、口腔内環境の悪化と感染リスクの増加が予想される。鼻腔についても、呼吸機能の変化に伴う分泌物の性状変化や乾燥が生じている可能性がある。爪の状態についても詳細な評価が必要であり、長期臥床による爪の伸長や巻き爪のリスクが考慮される。栄養状態の悪化により爪の脆弱化も懸念される。
尿失禁の有無、便失禁の有無
A氏には膀胱留置カテーテルが挿入されているため、尿失禁の直接的な問題はないが、カテーテル周囲の皮膚トラブルや感染のリスクがある。便失禁については具体的な記載がないが、意識レベルの低下により便意の自覚が困難な可能性がある。2日に1回程度の排便があるものの、便秘傾向がみられることから、便失禁のリスクは比較的低いと考えられる。しかし、浣腸の使用により軟便となった場合の失禁リスクについて考慮が必要である。
ニーズの充足状況
A氏の清潔保持に関するニーズは著しく充足されていない状況である。自力での清潔保持が不可能であり、すべて看護師による介助が必要である。長期臥床による皮膚トラブルのリスクが高く、褥瘡予防のための適切な清潔ケアが重要である。口腔ケアの必要性が高いにも関わらず、詳細な実施状況が不明である。医療器具の装着により清潔ケアが複雑化しており、感染予防の観点からも十分な清潔保持が求められる。栄養状態の悪化と免疫機能の低下により、わずかな不潔でも感染のリスクが高い状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の清潔・身だしなみに関する主要な課題は、終末期における適切な清潔保持と皮膚保護である。全身清拭を定期的に実施し、皮膚の観察と保湿ケアを継続する。特に褥瘡好発部位の重点的なケアにより、皮膚トラブルの予防に努める。口腔ケアを定期的に実施し、口腔内感染の予防と快適性の向上を図る。義歯の有無の確認と適切な口腔ケア用品の選択が重要である。鼻腔ケアにより呼吸の快適性を確保し、分泌物による皮膚トラブルを予防する。爪切りを定期的に実施し、皮膚損傷の予防に努める。膀胱留置カテーテル周囲の清潔保持により、尿路感染と皮膚トラブルを予防する。陰部洗浄を適切に実施し、感染予防と快適性の確保を図る。寝衣や寝具の清潔保持により、皮膚への刺激を最小限に抑える。家族の参加により、患者が好んでいた整容習慣や身だしなみの維持に努める。患者の尊厳とプライバシーを十分に配慮し、羞恥心を最小限に抑えた清潔ケアを実施する。また、皮膚の脆弱性を考慮し、過度な摩擦や刺激を避けた優しいケアを心がける必要がある。
危険箇所(段差、ルート類)の理解、認知機能
A氏は認知力は保たれており、病状についても理解しているが、現在は意識レベルの低下がみられ、コミュニケーションが困難な状況である。そのため、環境の危険因子に対する認識や回避行動は期待できない状況となっている。膀胱留置カテーテルと点滴ルートが装着されており、これらの医療器具による引っかかりや絡まりのリスクが存在する。寝たきり状態であることから段差による転倒リスクは低いが、ベッドからの転落や医療器具の事故抜去が主要な安全上の課題となっている。68歳という年齢による判断力の低下と、終末期の状態による意識レベルの変動が安全管理を困難にしている。
術後せん妄の有無
A氏は手術歴がないため術後せん妄は該当しないが、終末期におけるせん妄のリスクが高い状況である。モルヒネの持続投与や代謝機能の低下により、薬剤性せん妄や代謝性せん妄の可能性がある。意識レベルの低下がみられることから、既にせん妄状態にある可能性も考慮される。夜間の不穏や幻覚の有無について継続的な観察が必要である。家族の付き添いにより見当識の維持に努めているが、環境や時間の認識困難が生じている可能性がある。
皮膚損傷の有無
皮膚損傷の具体的な情報が不足している。長期臥床による褥瘡のリスクが極めて高い状況である。体重14kgの減少により皮下脂肪が減少し、骨突出部位の圧迫による皮膚損傷のリスクが増大している。栄養状態の悪化(アルブミン2.1g/dL)により皮膚の修復能力が低下している。医療器具による圧迫や摩擦による皮膚損傷のリスクも高い。循環動態の悪化により末梢循環が低下し、皮膚の脆弱性が増している可能性がある。
感染予防対策(手洗い、面会制限)
膀胱留置カテーテルによる尿路感染のリスクが高い状況である。免疫機能の低下により、わずかな感染源でも重篤な感染につながる可能性がある。長期臥床による肺炎のリスクも高く、痰の喀出困難により気道感染が懸念される。医療従事者の手指衛生と家族への感染予防指導が重要である。面会者の制限や体調管理により、外部からの感染源を遮断する必要がある。口腔ケア不良による口腔内感染のリスクも考慮される。
血液データ(白血球数、炎症反応蛋白)
白血球数は12,000/μLと正常上限を超えて上昇しており、活動性の感染や炎症を示唆している。炎症反応蛋白は15.2mg/dLと著明に高値であり、全身の炎症状態が存在する。これらの値は感染に対する脆弱性を示しており、免疫機能の低下と感染リスクの増大を表している。終末期における炎症反応の可能性もあるが、二次感染の予防が重要である。
ニーズの充足状況
A氏の安全管理に関するニーズは著しく充足されていない状況である。自力での危険回避行動が不可能であり、すべて看護師による安全管理が必要である。医療器具による事故のリスクが高く、継続的な観察と予防対策が必要である。感染に対する抵抗力の著明な低下により、厳重な感染予防対策が求められる。皮膚損傷のリスクが極めて高い状況であり、予防的ケアが重要である。意識レベルの変動により、予期しない行動による事故のリスクも考慮される。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の安全管理に関する主要な課題は、終末期における包括的な安全対策と感染予防である。転落防止対策として、ベッド柵の適切な使用とベッド周囲の安全確認を継続する。医療器具の安全管理により、カテーテルや点滴ルートの固定確認と事故抜去の予防を徹底する。褥瘡予防として、定期的な体位変換と圧迫軽減用具の使用を継続する。感染予防対策として、手指衛生の徹底、カテーテル管理、口腔ケア、環境整備を実施する。面会者の健康管理と感染予防指導により、外部感染源を遮断する。せん妄の予防と早期発見により、不穏状態による事故を防止する。皮膚の継続的観察により、皮膚損傷の早期発見と対処を行う。環境整備により、ベッド周囲の整理整頓と危険物の除去を継続する。家族への安全管理指導により、協力体制の構築を図る。緊急時の対応体制を整備し、迅速な医療介入ができる環境を維持する。患者の尊厳を保持しながら、適切な安全管理を継続する必要がある。
表情、言動、性格は問題ないか
A氏は責任感が強く頑固な性格だが、家族思いの一面もある。病状について理解していた際には「家族に迷惑をかけたくない」「痛みだけは取ってほしい」と自身の想いを明確に表現していた。しかし、現在は意識レベルの低下により、言語的コミュニケーションは困難な状況となっている。声かけに対する反応はわずかにみられることから、完全に意識を失っているわけではない可能性がある。表情の変化や非言語的表現について継続的な観察が必要である。元建設会社の現場監督として人をまとめる立場にあったことから、コミュニケーション能力は高い人物であったと推測される。
家族や医療者との関係性
A氏と家族の関係性は良好であり、妻と長男夫婦が交代で付き添いをしている状況である。妻は「最期まで一緒にいたい」「痛みがないようにしてほしい」と涙ながらに話し、長男は「父らしく最期を迎えさせてあげたい」と述べており、家族の絆の強さが示されている。家族は手を握りながら声かけを続けていることから、継続的なコミュニケーションの試みがなされている。医療者との関係性については具体的な情報が不足しているが、病状について理解していたことから、医療者との信頼関係は構築されていたと考えられる。
言語障害、視力、聴力、メガネ、補聴器
言語障害、視力、聴力について具体的な情報が不足している。現在の言語的コミュニケーション困難は、言語障害ではなく意識レベルの低下によるものと考えられる。68歳という年齢を考慮すると、加齢による視聴覚機能の低下がある可能性がある。メガネや補聴器の使用について情報収集が必要である。声かけに対する反応がわずかにみられることから、聴覚機能は部分的に保たれている可能性がある。
認知機能
A氏は認知力は保たれており、病状についても理解しているとあるが、現在は意識レベルの低下により認知機能の評価が困難な状況である。終末期における意識変容により、認知機能が変動している可能性がある。モルヒネの持続投与による意識レベルへの影響も考慮される。家族の声かけに対するわずかな反応から、完全に認知機能が失われているわけではない可能性がある。
面会者の来訪の有無
家族が交代で付き添いをしており、継続的な面会がなされている状況である。妻と長男夫婦が主要な面会者であり、孫2人の存在も記載されているが、孫の面会状況については詳細不明である。最期の時間を共に過ごしていることから、家族にとって重要な時間となっている。その他の親族や友人の面会については情報が不足している。
ニーズの充足状況
A氏のコミュニケーションに関するニーズは部分的に充足されているが、制限が大きい状況である。言語的コミュニケーションは困難であるが、家族との非言語的コミュニケーションは継続されている。家族の愛情に満ちた関わりにより、孤独感や不安の軽減が図られていると考えられる。しかし、自身の想いや感情の表現が困難であり、内的体験の共有ができない状況である。医療者とのコミュニケーションについても制限があり、症状や苦痛の表現が困難となっている。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のコミュニケーションに関する主要な課題は、終末期における非言語的コミュニケーションの促進と家族支援である。非言語的サインの観察により、患者の状態や苦痛の程度を評価する。表情の変化、体動、呼吸パターンの変化などから患者の内的状態を推測し、適切な対応を行う。家族とのコミュニケーション促進として、手を握る、声かけ、音楽などの感覚刺激を通じた関わりを支援する。家族への指導により、患者との効果的なコミュニケーション方法を提供する。環境調整により、静かで落ち着いた雰囲気を作り、家族との時間を大切にできる環境を整備する。医療者からの情報提供として、患者の状態変化について家族に適切に説明し、理解と受容を支援する。プライバシーの確保により、家族が安心して患者との時間を過ごせる環境を提供する。患者の尊厳を保持し、意識レベルが低下していても人格を尊重した関わりを継続する。疼痛や苦痛のサインを見逃さないよう、継続的な観察と評価を行い、適切な症状緩和を図る。また、家族の心理的負担に配慮し、グリーフケアの観点からも支援を提供する必要がある。
信仰の有無、価値観、信念、信仰による食事
A氏には宗教的信仰は特にないとされている。しかし、元建設会社の現場監督として働いていた背景から、責任感や仕事への誇りなどの個人的な価値観や信念を持っていたと推測される。家族思いの一面があることからも、家族を大切にする価値観が強いと考えられる。「家族に迷惑をかけたくない」という発言からも、他者への配慮を重視する信念が窺える。宗教的な食事制限は特にないが、現在は経口摂取困難であり、食事に関する信仰的配慮は必要ない状況である。終末期における魂の平安や人生の意味づけについて、宗教的信仰がない場合でも精神的支援が重要である。
治療法の制限
特定の宗教的信仰がないため、宗教的理由による治療法の制限は特に想定されない。しかし、患者と家族の価値観に基づく治療選択の希望について確認が必要である。終末期における治療方針として、積極的治療よりも症状緩和と安楽を重視する方針が選択されているが、これは医学的判断と患者家族の意向が一致した結果と考えられる。延命処置に対する考え方や最期の迎え方について、患者と家族の価値観を尊重した対応が重要である。
ニーズの充足状況
A氏の宗教・信仰に関するニーズについては、特定の宗教的実践の必要性はないが、精神的な平安と意味づけのニーズは存在すると考えられる。現在は意識レベルの低下により、精神的ニーズの表出は困難であるが、家族との絆が精神的支えとなっている可能性がある。人生の最終段階における尊厳と意味のある時間の過ごし方について、宗教的信仰がなくても重要なニーズとして考慮される。家族の価値観や信念が患者のケアに反映されることで、間接的にニーズが充足される可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の宗教・信仰に関する主要な課題は、宗教的信仰がない場合の精神的支援である。患者の価値観と尊厳の尊重により、その人らしい最期の時間を支援する。家族の信念や価値観の確認を行い、患者ケアに反映させる。人生の振り返りや意味づけの支援として、家族との対話や思い出の共有を促進する。精神的な安らぎの提供として、静かで落ち着いた環境の整備と家族との時間の確保を図る。死への恐怖や不安の軽減について、必要に応じてチャプレンやカウンセラーなどの専門職への相談を検討する。家族の精神的支援として、グリーフケアの観点から継続的な関わりを提供する。患者の人生の尊重として、職業や家族への思いなど、その人らしさを大切にしたケアを実施する。最期の時間の質の向上を図り、平安で尊厳ある死を支援することが重要である。宗教的信仰がない場合でも、人間としての尊厳と価値を最大限に尊重した看護介入が求められる。
職業、社会的役割、入院
A氏は元建設会社の現場監督として働いており、責任感が強い性格であることから、仕事に対する誇りと達成感を持っていたと推測される。現場監督という職業は人をまとめる指導力と責任ある判断力が求められる職種であり、社会的役割への強い自覚があったと考えられる。入院から45日が経過しており、長期間の療養により職業的アイデンティティからの分離が生じている。68歳という年齢から、既に退職している可能性もあるが、仕事への誇りや価値観は人格の重要な部分を占めていると考えられる。
疾患が仕事・役割に与える影響
膵頭部癌の進行により、A氏の職業活動は完全に中断されている。1年前の癌発見から徐々に仕事への参加が困難となり、現在は終末期状態で職業復帰は不可能である。「家族に迷惑をかけたくない」という発言からも、家族を支える役割を果たせないことへの心理的負担があったと推測される。現場監督として培った責任感と現在の依存的な状況との間に、大きなギャップと喪失感が存在していたと考えられる。終末期における意識レベルの低下により、現在は仕事への思いを表現することも困難な状況である。
ニーズの充足状況
A氏の仕事・達成感に関するニーズは全く充足されていない状況である。現在は寝たきり状態であり、仕事はもちろん、日常的な達成感を得られる活動も不可能である。意識レベルの低下により、過去の仕事への誇りや達成感を振り返ることも困難となっている。職業的アイデンティティの喪失と社会的役割の消失により、自己価値感の低下が生じていた可能性がある。責任感の強い性格であったことから、役割を果たせない状況への失望感は大きかったと推測される。終末期の現在では、従来の意味での達成感は期待できない状況である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の仕事・達成感に関する主要な課題は、職業的アイデンティティの尊重と人生の価値の確認である。患者の職歴と仕事への誇りについて家族から情報収集し、その人らしさを理解する。家族との対話促進により、患者の仕事への思いや人生における達成について振り返る機会を提供する。職業的アイデンティティの尊重として、現場監督としての経験や知識を価値あるものとして認識し、家族にもその価値を伝える。小さな達成感の提供として、可能な範囲で患者ができることや反応できることを見つけ、肯定的に評価する。家族への支援として、患者の仕事への誇りや家族への貢献について語り合える環境を整備する。人生の意味づけ支援により、仕事を通じて築いた人間関係や社会への貢献を価値あるものとして確認する。尊厳の保持として、患者を一人の職業人として尊重し、病気になった人としてのみ見ない姿勢を維持する。終末期における価値観の転換を支援し、存在すること自体の価値を家族と共に確認することが重要である。現在は意識レベルが低下しているが、患者の人生と仕事への敬意を示した関わりを継続する必要がある。
趣味、休日の過ごし方、余暇活動
A氏の具体的な趣味や余暇活動について詳細な情報が不足している。元建設会社の現場監督という職業背景から、仕事中心の生活を送っていた可能性が高い。責任感が強い性格であることから、休日も仕事に関連した活動や家族との時間を重視していたと推測される。68歳という年齢を考慮すると、定年後の趣味や楽しみを見つけていた可能性もあるが、1年前の癌発見により余暇活動も制限されていたと考えられる。家族思いの一面があることから、孫との時間や家族との団らんが主要な楽しみであった可能性がある。
入院、療養中の気分転換方法
入院から45日目の長期療養中における気分転換方法について具体的な情報が不足している。現在は意識レベルの低下により、積極的な気分転換活動は困難な状況である。家族が交代で付き添いをしていることから、家族との時間が唯一の気分転換となっている可能性がある。疼痛コントロールのためのモルヒネ投与により、苦痛は軽減されているが、楽しみや喜びを感じる余裕は乏しい状況と考えられる。病室という限られた環境での療養生活において、音楽、テレビ、ラジオなどの利用状況についても情報収集が必要である。
運動機能障害
A氏は現在寝たきり状態であり、すべての日常生活動作において全介助が必要である。終末期の全身衰弱により運動機能が著しく低下しており、体位変換も全介助が必要な状況である。入院前は歩行可能であったが、疼痛により活動量は低下していた。68歳という年齢に加え、体重14kgの減少により筋力と体力が著しく低下している。長期臥床による廃用症候群も進行しており、関節可動域の制限も懸念される。これらの運動機能障害により、従来の余暇活動への参加は完全に不可能な状況である。
認知機能、日常生活動作
A氏は認知力は保たれており、病状についても理解しているが、現在は意識レベルの低下により、コミュニケーションが困難な状況である。声かけに対する反応はわずかにみられることから、完全に認知機能が失われているわけではない可能性がある。しかし、レクリエーション活動に必要な注意集中力や理解力は著しく低下していると考えられる。日常生活動作はすべて全介助が必要であり、自発的な活動や参加は期待できない状況である。
ニーズの充足状況
A氏のレクリエーション・余暇活動に関するニーズは全く充足されていない状況である。現在の身体状況と意識レベルでは、従来の意味でのレクリエーション活動への参加は不可能である。楽しみや喜びを感じる能力も著しく制限されており、生きる楽しみや希望を見出すことが困難な状況である。終末期における余暇の概念は健常時とは大きく異なり、安らぎや平安が主要なニーズとなっている。家族との時間が唯一の慰めとなっている可能性があるが、意識レベルの低下により、その享受も限定的である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のレクリエーション・余暇活動に関する主要な課題は、終末期における安らぎと慰めの提供である。従来の趣味や楽しみについて家族から情報収集し、患者の人となりを理解する。音楽療法として、患者が好んでいた音楽やなじみのある曲を流すことで、心地よい刺激を提供する。家族との思い出話を促進し、過去の楽しい時間を振り返る機会を作る。感覚刺激として、優しい手のマッサージや香りなどを用いて、快適な感覚体験を提供する。環境調整により、季節感を感じられる飾りや家族の写真などを配置し、親しみやすい雰囲気を作る。家族の参加促進として、孫の描いた絵や家族の声の録音などを活用し、家族との絆を感じられる工夫を行う。安らぎの提供として、静かで落ち着いた環境を整備し、ストレスの少ない時間を確保する。小さな喜びの発見として、患者の表情の変化や穏やかな瞬間を大切にし、家族と共有する。終末期における生活の質を高めるため、苦痛の緩和を最優先としながら、可能な限りの心地よい体験を提供することが重要である。
発達段階
A氏は68歳男性であり、エリクソンの発達段階における老年期に該当する。この段階では統合性対絶望という発達課題があり、人生を振り返り、自分の人生に意味と価値を見出すことが重要である。元建設会社の現場監督として働き、家族を築いてきた人生には多くの達成と貢献があったと考えられる。しかし、終末期という状況において、人生の統合と受容という最終的な発達課題に直面している。現在の意識レベルの低下により、この発達課題への取り組みは困難な状況にあるが、家族との絆を通じて人生の意味づけが行われている可能性がある。
疾患と治療方法の理解
A氏は認知力は保たれており、病状についても理解しているとされていた。膵頭部癌(ステージIVb)の進行性の疾患であることを理解し、積極的治療から緩和ケアへの移行についても受け入れていたと考えられる。「痛みだけは取ってほしい」という発言からも、現実的な病状理解と症状緩和への希望を示していた。現在は意識レベルの低下により、追加的な疾患説明や治療方針の理解は困難な状況である。家族への病状説明が継続的に行われており、家族を通じた理解の共有が重要となっている。
学習意欲、認知機能、学習機会への家族の参加度合い
A氏の学習意欲については、終末期の状況において従来の意味での学習への関心は低下していると考えられる。現在は意識レベルの低下により、新たな学習や情報収集は困難な状況である。認知機能については、病状理解ができていたことから、以前は良好であったが、現在は著しく低下している。家族の参加度合いは高く、妻と長男夫婦が交代で付き添いをしており、医療者からの説明を聞き、患者の状況を理解しようとする姿勢がみられる。家族が患者の代弁者として機能しており、患者の価値観や希望を代弁する役割を果たしている。
ニーズの充足状況
A氏の学習・発達に関するニーズは大幅に変化している状況である。従来の学習ニーズ(新しい知識の習得や技能の向上)は終末期の状況により意味を失っている。しかし、人生の統合と意味づけという発達的ニーズは依然として重要である。現在の意識レベルでは能動的な学習は困難であるが、家族との関わりや過去の人生の振り返りを通じて、間接的な発達課題への取り組みが行われている可能性がある。好奇心の満足については、日常的な刺激への反応という形で最小限のニーズが存在する可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の学習・発達に関する主要な課題は、終末期における人生の統合支援と家族学習の促進である。人生の振り返り支援として、家族との対話を通じて患者の人生の意味と価値を確認する機会を提供する。家族への教育支援により、終末期ケアの理解と患者との関わり方について学習機会を提供する。発達課題の支援として、人生の統合感を家族と共に確認し、患者の人生の価値を肯定的に評価する。感覚刺激による学習として、音楽、触覚、聴覚を通じた刺激により、環境への反応を促進する。家族の学習ニーズに対応し、グリーフケアや終末期の過ごし方について情報提供と支援を行う。尊厳の保持により、患者を学習能力のない存在として扱わず、人格を持った存在として尊重する。記憶の共有として、家族が患者との思い出や患者から学んだことを語り合える環境を整備する。最期の学びとして、死への準備や家族への最後のメッセージを伝える機会があれば支援する。終末期における発達の概念を理解し、死に向かう過程も人生の重要な学習段階として捉えた看護介入が重要である。患者自身の能動的な学習は困難であっても、家族との関係性や人生の意味づけを通じて、最終的な発達課題への取り組みを支援する必要がある。
看護計画
看護問題
疾患の進行に伴う疼痛に関連した安楽の障害
長期目標
・療養期間を通して適切な疼痛コントロールにより、患者が安楽で穏やかな時間を過ごすことができる
短期目標
・1週間以内に疼痛による表情の変化や不穏状態が軽減する
・2週間以内に家族が患者の安楽な状態を確認できる
≪O-P≫観察計画
・表情の変化や苦痛様顔貌の有無である
・不穏状態や体動の変化である
・呼吸パターンや呼吸数の変化である
・血圧、脈拍数の変動である
・発汗や皮膚の色調変化である
・モルヒネ投与量と効果の関係である
・副作用(呼吸抑制、便秘、嘔気)の出現である
・睡眠覚醒パターンの変化である
・家族の疼痛に対する理解と不安の程度である
・体位変換時の反応や表情の変化である
・口腔内の乾燥や舌苔の状態である
・尿量減少や循環動態への影響である
≪T-P≫援助計画
・医師と連携してモルヒネ投与量の調整を行う
・定期的な体位変換により圧迫部位の除圧を図る
・安楽な体位の工夫と体位保持用具の使用である
・環境調整により騒音や光刺激を最小限に抑える
・口腔ケアにより口腔内の快適性を保持する
・優しいタッチングやマッサージによる安楽の提供である
・室温や湿度の調整により快適な環境を維持する
・家族との面会時間を十分に確保する
・疼痛時の迅速な対応体制を整備する
・非薬物的疼痛緩和法(音楽、アロマ)の活用である
・呼吸困難時の酸素投与準備を行う
・便秘予防のための腹部マッサージを実施する
≪E-P≫教育・指導計画
・家族に対して疼痛の特徴と現在の治療方針について説明する
・モルヒネ使用の目的と効果について家族の理解を促進する
・疼痛の兆候(表情、体動、呼吸)の観察方法を家族に指導する
・家族ができる安楽ケア(手を握る、声かけ)について指導する
・疼痛悪化時の対応と看護師への連絡方法について説明する
・終末期における疼痛管理の重要性と患者の尊厳について説明する
看護問題
終末期状態に伴う意識レベル低下に関連したコミュニケーション障害
長期目標
・療養期間を通して家族との非言語的コミュニケーションにより、患者と家族の絆を維持することができる
短期目標
・1週間以内に家族が患者との効果的な関わり方を習得する
・2週間以内に患者の反応に対する家族の理解が深まる
≪O-P≫観察計画
・意識レベルの変化と反応の程度である
・声かけに対する反応(表情、体動、開眼)である
・家族の声に対する特別な反応の有無である
・瞬きや眼球運動の変化である
・握手に対する反応や手の動きである
・呼吸パターンの変化や深いため息である
・家族の関わり方と患者の反応の関係である
・家族の心理状態と不安の程度である
・面会時間中の患者の様子の変化である
・聴覚機能の残存程度である
・せん妄や不穏状態の有無である
・薬剤による意識への影響の程度である
≪T-P≫援助計画
・家族との面会時間を最大限確保する
・静かで落ち着いた環境を整備する
・家族が患者に話しかけやすい雰囲気を作る
・患者の手を握る機会を家族に提供する
・家族の声かけ時の患者の反応を一緒に観察する
・患者が好んでいた音楽を流す環境を整える
・家族の写真や馴染みのある物品を配置する
・家族のプライバシーを確保できる空間を提供する
・家族の疲労に配慮した面会時間の調整を行う
・患者への尊重的な関わりを家族と共に実践する
・非言語的コミュニケーションの機会を増やす
・家族の感情表出を支援し傾聴する
≪E-P≫教育・指導計画
・意識レベル低下時でも聴覚は最後まで残ることを説明する
・効果的な声かけの方法(ゆっくり、明瞭に)について指導する
・患者の反応の読み取り方について家族に説明する
・手を握ることや優しく触れることの効果について指導する
・一方的な会話でも患者に届いている可能性について説明する
・家族自身の感情を素直に表現することの大切さを伝える
看護問題
長期臥床に伴う運動機能低下に関連した皮膚統合性障害リスク
長期目標
・療養期間を通して褥瘡の発生を予防し、皮膚の統合性を維持することができる
短期目標
・1週間以内に褥瘡好発部位の皮膚状態を良好に保つ
・2週間以内に効果的な褥瘡予防ケアを継続する
≪O-P≫観察計画
・褥瘡好発部位(仙骨部、踵部、肘部)の皮膚状態である
・皮膚の色調変化(発赤、紫斑、蒼白)である
・皮膚の温度や硬結の有無である
・皮膚の乾燥や湿潤状態である
・栄養状態(体重、血清アルブミン値)の変化である
・浮腫の程度と分布である
・体位変換時の皮膚への圧迫状況である
・寝具や衣類による摩擦や圧迫である
・失禁による皮膚への影響である
・医療器具による圧迫部位の状態である
・循環状態と末梢の血流である
・関節可動域と筋肉の萎縮程度である
≪T-P≫援助計画
・2時間ごとの定期的な体位変換を実施する
・圧迫軽減マットレスや体位保持用具を使用する
・褥瘡好発部位の除圧と保護を行う
・皮膚の清潔保持と適切な保湿ケアを実施する
・栄養状態の改善に向けた輸液管理を行う
・関節可動域訓練により循環改善を図る
・適切な寝衣の選択と皺の除去を行う
・医療器具の固定方法を工夫し圧迫を避ける
・陰部洗浄により局所の清潔を保持する
・マッサージにより血液循環の促進を図る
・褥瘡予防用品(ドレッシング材)の適用を検討する
・家族と協力した体位変換の実施である
≪E-P≫教育・指導計画
・褥瘡の原因と予防の重要性について家族に説明する
・体位変換の方法と注意点について家族に指導する
・皮膚観察のポイントと異常の早期発見について説明する
・適切なマッサージの方法と禁忌について指導する
・清潔保持の重要性と感染予防について説明する
・栄養状態と皮膚の関係について家族の理解を促進する
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
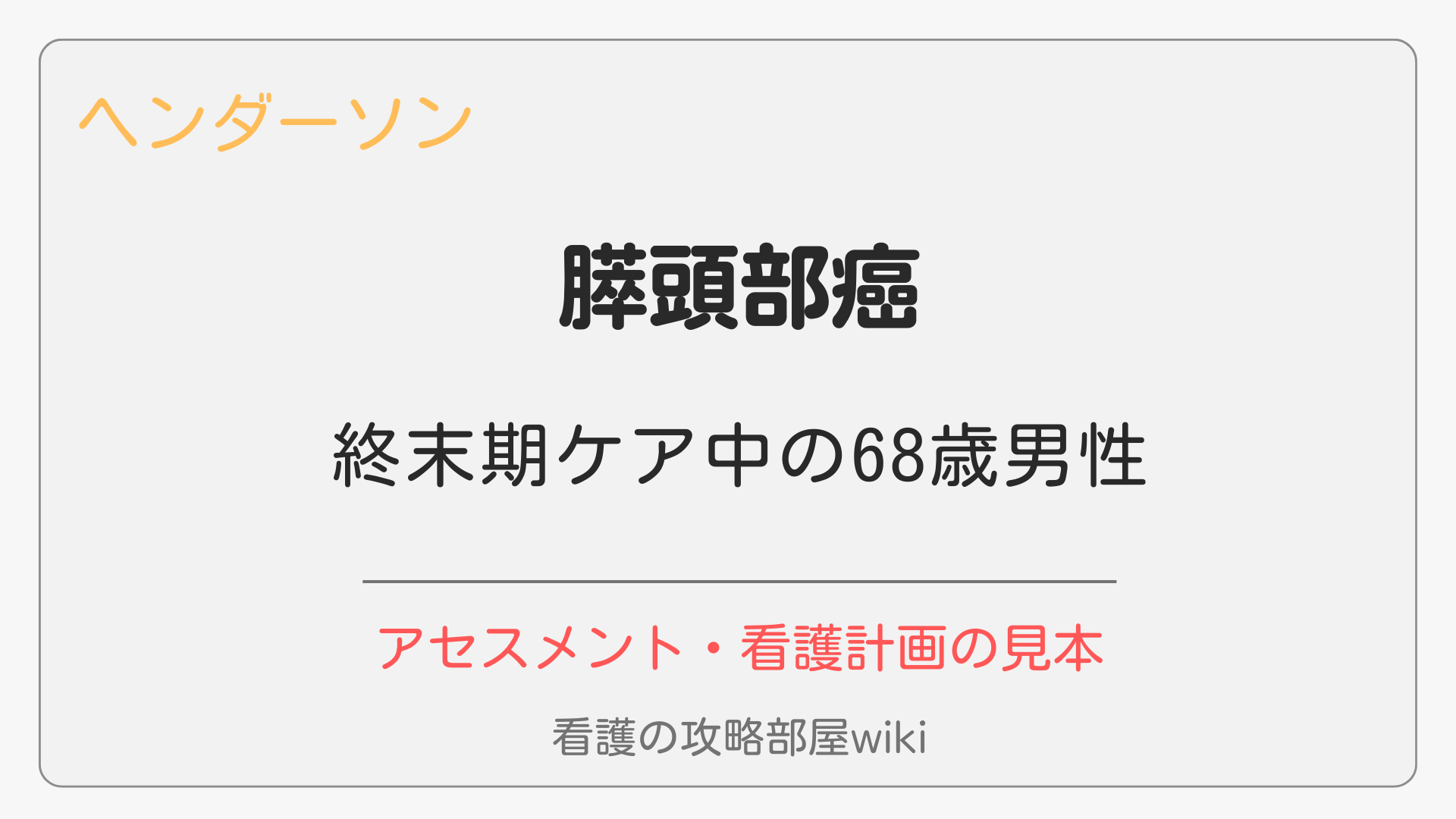
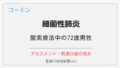
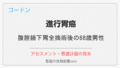
コメント