事例の要約
胃癌に対して腹腔鏡下胃全摘術を実施し、術後2日目から積極的な離床と経口摂取開始に向けた看護介入を行った事例。介入日は12月15日、術後2日目である。
基本情報
A氏は68歳男性で、身長165cm、体重58kg(術前62kg)である。家族構成は妻と長男夫婦、孫2人の6人家族で、キーパーソンは妻となっている。職業は元建設業で現在は年金生活を送っており、性格は温厚で協調性があり、医療スタッフの指示にも素直に従う傾向がある。感染症の既往はなく、薬物アレルギーとして造影剤に軽度の発疹の既往がある。認知力は正常で、MMSE 28点、HDS-R 27点と良好な状態を保っている。
病名
進行胃癌(T2N1M0 Stage IIA)に対して腹腔鏡下胃全摘術+Roux-en-Y再建術を実施した。
既往歴と治療状況
既往歴として高血圧症があり、ACE阻害薬で良好にコントロールされている。また、糖尿病の既往もあり、メトホルミンとDPP-4阻害薬による治療を受けている。その他、脂質異常症に対してスタチン系薬剤を内服している。
入院から現在までの情報
12月10日に入院し、術前検査と全身状態の評価を行った。12月13日に腹腔鏡下胃全摘術を実施し、手術時間は4時間30分、出血量は150mlであった。術後は集中治療室で管理され、翌日12月14日に一般病棟へ転棟した。現在術後2日目で、疼痛は軽度から中等度で、創部の状態は良好である。
バイタルサイン
来院時は血圧138/82mmHg、脈拍78回/分、体温36.4℃、呼吸数18回/分、SpO2 98%(室内気)であった。
現在は血圧125/75mmHg、脈拍85回/分、体温37.1℃、呼吸数20回/分、SpO2 97%(室内気)で、軽度の発熱と頻脈傾向がみられる。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を摂取しており、嚥下機能に問題はなかった。喫煙歴は20本/日×45年間で、入院1か月前に禁煙を開始した。飲酒は日本酒2合/日程度を長期間継続していたが、診断後は禁酒している。
現在は絶食中で、術後2日目より水分摂取から開始予定である。嚥下機能は保たれているが、胃全摘術後のため食事摂取方法の指導が必要である。
排泄
入院前は排便は1日1回規則的で、排尿も特に問題なかった。
現在は尿道カテーテルが挿入されており、尿量は良好で1500ml/日程度である。排便はまだみられておらず、腸蠕動音は微弱である。下剤の使用は現在のところ不要である。
睡眠
入院前は22時頃就寝し、6時頃起床する規則正しい生活を送っていた。
現在は手術侵襲と環境変化により睡眠が浅く、頻回に覚醒する状態である。疼痛により夜間の睡眠が妨げられることがあり、必要時にゾルピデム5mgを使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼鏡使用で問題なく、聴力も正常である。知覚に異常はなく、コミュニケーションは良好で、質問に対して適切に応答できる。特定の宗教的信仰はない。
動作状況
歩行は術前は自立していたが、現在はベッド上安静で、術後1日目より離床を開始している。移乗は看護師1名介助で可能で、排尿は尿道カテーテル管理中である。排泄は現在のところ該当なし。入浴は清拭で対応し、衣類の着脱は上肢の軽度介助が必要である。転倒歴は特にない。
内服中の薬
- エナラプリルマレイン酸塩 5mg 1日1回 朝食後
- メトホルミン塩酸塩 500mg 1日2回 朝夕食後
- シタグリプチンリン酸塩水和物 50mg 1日1回 朝食後
- アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg 1日1回 夕食後
- ゾルピデム酒石酸塩 5mg 1日1回 就寝前(必要時)
現在は絶食中のため内服は中止しており、必要な薬剤は注射で投与している。退院後は自己管理の予定である。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(術後2日目) |
|---|---|---|
| WBC (/μL) | 6,800 | 12,500 |
| RBC (×10⁴/μL) | 435 | 385 |
| Hb (g/dL) | 12.8 | 10.2 |
| Hct (%) | 38.5 | 30.8 |
| PLT (×10⁴/μL) | 28.5 | 25.2 |
| TP (g/dL) | 7.2 | 6.1 |
| Alb (g/dL) | 3.8 | 2.9 |
| T-Bil (mg/dL) | 0.9 | 1.2 |
| AST (U/L) | 28 | 35 |
| ALT (U/L) | 32 | 38 |
| BUN (mg/dL) | 18 | 22 |
| Cr (mg/dL) | 0.8 | 0.9 |
| Na (mEq/L) | 140 | 138 |
| K (mEq/L) | 4.2 | 3.8 |
| Cl (mEq/L) | 105 | 103 |
| CRP (mg/dL) | 0.3 | 8.5 |
今後の治療方針と医師の指示
術後2日目より離床を積極的に進め、腸蠕動の回復を促進する方針である。水分摂取から段階的に経口摂取を開始し、術後3日目より流動食、術後5日目より五分粥へと段階的に食事を進行させる予定である。疼痛管理は硬膜外カテーテルによる持続鎮痛を継続し、感染予防のため抗生剤投与を行う。血糖値のモニタリングを継続し、必要に応じてインスリン投与を行う。尿道カテーテルは術後3日目に抜去予定である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「手術が成功してほっとしている。早く家に帰りたい」と話し、回復への意欲を示している。また、「食事ができるようになるか心配」と胃全摘術後の食生活への不安を表現している妻は「主人の回復を信じて支えたい。退院後の食事の準備方法を教えてほしい」と述べ、積極的に看護に参加する意志を示している。長男は「仕事の関係で平日は来院できないが、週末は必ず来る」と家族の協力体制を表明している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は進行胃癌に対して腹腔鏡下胃全摘術を実施された68歳男性である。胃癌は本邦において発生頻度の高い悪性腫瘍であり、進行度によって治療法が選択される。A氏の場合、T2N1M0 Stage IIAの進行胃癌であり、根治的切除術の適応となった。腹腔鏡下手術により低侵襲での治療が可能となったが、胃全摘術による消化機能の大幅な変化が生じるため、術後の栄養管理や消化機能の適応が重要な課題となる。
健康状態
A氏の術前の健康状態は比較的良好であったが、複数の生活習慣病を有していた。高血圧症、糖尿病、脂質異常症という代謝性疾患の合併は、68歳という年齢と長期間の喫煙歴、飲酒習慣が関与している可能性が高い。これらの基礎疾患は適切な薬物療法によりコントロールされており、術前検査でも特に問題となる異常値は認められなかった。しかし、術後は手術侵襲による炎症反応として白血球数の増加やC反応性蛋白の上昇がみられ、貧血の進行も認められる。これらの変化は術後の正常な反応であるが、継続的な観察が必要である。
受診行動、疾患や治療への理解、服薬状況
A氏は胃部不快感を自覚した際に速やかに医療機関を受診し、早期発見に至った適切な受診行動を示している。疾患に対する理解は良好であり、医師からの説明に対して適切な質問を行い、治療方針についても理解を示している。服薬状況については、慢性疾患の管理薬を規則正しく内服しており、服薬コンプライアンスは良好である。ただし、胃全摘術後の食事摂取方法や栄養管理について不安を表明しており、具体的な指導が必要である。
身長、体重、BMI、運動習慣
A氏の身長は165cm、術前体重は62kg、現在の体重は58kgであり、BMIは術前で22.8kg/m²、現在は21.3kg/m²である。術前のBMIは標準範囲内であったが、術後4kgの体重減少が認められる。これは手術侵襲による一時的な減少と考えられるが、今後の栄養状態の維持が重要な課題となる。運動習慣については、建設業という職業柄、日常的に身体活動量は多かったが、退職後は特定の運動習慣は持っていなかった。
呼吸に関するアレルギー、飲酒、喫煙の有無
A氏は造影剤に対する軽度の発疹の既往があり、アレルギー体質の可能性が示唆される。呼吸器系の特異的アレルギーは認められない。喫煙歴は20本/日×45年間という長期間の重度喫煙者であったが、診断確定後1か月前に禁煙を開始した。飲酒習慣は日本酒2合/日程度を長期間継続していたが、現在は禁酒している。長期間の喫煙歴は術後の呼吸器合併症のリスクを高める要因となるため、継続的な呼吸機能の観察が必要である。
既往歴
A氏は高血圧症、糖尿病、脂質異常症という代謝症候群の構成要素を有している。これらの疾患は相互に関連し合い、動脈硬化の進行や心血管疾患のリスクを高める。また、長期間の喫煙と飲酒習慣は胃癌発症の危険因子であると同時に、術後合併症のリスクを高める要因でもある。68歳という年齢による生理機能の低下も加わり、術後の回復過程において慎重な管理が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の健康管理上の主要な課題は、胃全摘術後の栄養管理と消化機能の適応である。胃を失うことによる消化機能の変化に対応するため、段階的な食事摂取の指導と栄養状態の継続的評価が必要である。また、術後合併症の予防として、呼吸器合併症や感染症の早期発見と対応が重要である。基礎疾患である糖尿病管理については、術後の血糖値変動に注意し、必要に応じてインスリン療法の調整を行う必要がある。さらに、禁煙継続への支援と適切な運動療法の導入により、今後の生活習慣病管理を強化する必要がある。継続的な観察項目として、栄養状態の評価、消化器症状の有無、血糖値の推移、創部の治癒状況を重点的に確認していく必要がある。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は術前まで普通食を摂取していたが、現在は術後2日目で絶食中である。胃全摘術による消化管の再建が完了しているものの、腸蠕動の回復と縫合部の治癒を待つため、段階的な摂取開始が計画されている。術後2日目より水分摂取から開始し、術後3日目に流動食、術後5日目に五分粥へと段階的に進行する予定である。現在の水分摂取は静脈内輸液により維持されており、1日約2000ml程度の輸液が投与されている。
好きな食べ物と食事に関するアレルギー
A氏は和食を好み、特に魚料理や野菜を中心とした食事を摂取していた。肉類よりも魚類を好む傾向があり、アルコール類では日本酒を嗜んでいた。食物アレルギーは特に認められないが、造影剤に対する軽度の発疹の既往があることから、アレルギー体質の可能性を考慮する必要がある。今後の食事指導において、胃全摘術後の消化機能に適した食品選択と、個人の嗜好を考慮した食事計画の立案が重要である。
身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
A氏の身長は165cm、術前体重62kg、現在体重58kgで、BMIは術前22.8kg/m²から現在21.3kg/m²に減少している。4kgの体重減少は手術侵襲と絶食による一時的な変化と考えられるが、今後の栄養状態維持が課題である。68歳男性の基礎代謝率を考慮すると、必要栄養量は約1600-1800kcal/日と推定される。現在の身体活動レベルは術後安静により低下しているが、離床進行に伴い段階的に向上する見込みである。胃全摘術後は消化吸収能力の低下により、従来の1.2-1.5倍程度の栄養摂取が必要となる可能性がある。
食欲・嚥下機能・口腔内の状態
術前の食欲は良好であったが、現在は絶食中のため食欲の評価は困難である。嚥下機能については、68歳という年齢による軽度の機能低下は考えられるものの、明らかな嚥下障害は認められない。口腔内の状態は、絶食による口腔乾燥が軽度認められるが、口腔ケアにより清潔に保たれている。義歯の使用はなく、咀嚼機能に問題はない。今後の経口摂取開始時には、嚥下機能の再評価と適切な食形態の選択が必要である。
嘔吐・吐気
現在のところ明らかな嘔吐や吐気の症状は認められない。胃全摘術後は迷走神経の切除により消化管運動の変化が生じるため、今後の経口摂取開始時には注意深い観察が必要である。特に、ダンピング症候群の発症により、食後の吐気や嘔吐が生じる可能性があるため、摂取速度や食事内容の調整が重要となる。
皮膚の状態、褥創の有無
A氏の皮膚状態は、軽度の乾燥が認められるものの、全体的に良好である。68歳という年齢による皮膚の弾性低下や薄化は見られるが、明らかな異常所見はない。褥創の発生は認められないが、術後安静により褥創発生のリスクが高まっているため、定期的な体位変換と除圧が実施されている。栄養状態の低下により今後褥創発生リスクが増加する可能性があるため、継続的な皮膚状態の観察が必要である。
血液データ
血清アルブミン値は術前3.8g/dLから現在2.9g/dLに低下しており、手術侵襲による急性期反応と考えられる。総蛋白も7.2g/dLから6.1g/dLに減少している。赤血球数は435×10⁴/μLから385×10⁴/μL、ヘマトクリットは38.5%から30.8%、ヘモグロビンは12.8g/dLから10.2g/dLに低下し、術後貧血の状態を示している。電解質では、ナトリウム140mEq/Lから138mEq/L、カリウム4.2mEq/Lから3.8mEq/Lと軽度低下している。糖尿病の既往があるため、血糖値とHbA1cの継続的モニタリングが必要であるが、現在のデータでは具体的な数値の記載が不足している。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の栄養・代謝面での主要な課題は、胃全摘術後の段階的な栄養摂取の確立である。現在の血液データから栄養状態の低下が示唆されるため、適切な栄養評価と補給が急務である。具体的な看護介入として、経口摂取開始時のダンピング症候群の予防と早期発見、少量頻回食の指導、咀嚼の十分な励行が重要である。また、体重測定と栄養指標の継続的モニタリングにより、栄養状態の改善を評価する必要がある。長期的には、在宅での食事管理方法の指導と家族への教育が不可欠である。血糖値管理については、術後の代謝変化を考慮したインスリン療法の調整と血糖値の頻回測定が必要である。今後も皮膚状態の観察と褥創予防対策を継続し、栄養状態改善に伴う創傷治癒の促進を図る必要がある。
排便と排尿の回数と量と性状
A氏の排尿については、現在尿道カテーテルが挿入されており、尿量は1500ml/日程度と良好な状態を示している。尿の性状は淡黄色で混濁はなく、正常範囲内である。術前の排尿パターンは特に問題なく、夜間の排尿回数も1-2回程度であった。排便については、術後2日目で排便は認められていない。術前は1日1回規則的な排便があり、便の性状も正常であった。現在は腸蠕動音が微弱な状態であり、手術侵襲と麻酔の影響による腸管機能の一時的低下が考えられる。
下剤使用の有無
術前において下剤の常用はなく、自然な排便パターンを維持していた。現在は絶食中であり、腸蠕動の回復を待っている状況のため、下剤の使用は行っていない。今後、経口摂取開始後の排便状況を観察し、必要に応じて緩下剤の使用を検討する予定である。68歳という年齢と手術侵襲による腸管機能の変化を考慮すると、術後の排便コントロールには注意深い管理が必要である。
in-outバランス
現在のin-outバランスは、輸液による水分投与が約2000ml/日、尿量が1500ml/日で、その他不感蒸泄を考慮すると概ね適切なバランスが保たれている。術後の水分バランス管理は重要であり、脱水や浮腫の予防のため継続的な観察が必要である。胃全摘術後は消化液の分泌や吸収に変化が生じるため、今後の経口摂取開始時にはより詳細なin-outバランスの管理が求められる。
排泄に関連した食事・水分摂取状況
現在は絶食中のため、食事による排泄への影響は評価できない状況である。術前の食事内容は和食中心で繊維質の摂取も適度にあり、排便状況は良好であった。今後の経口摂取開始時には、胃全摘術後の消化機能の変化を考慮した食事内容の調整が必要である。特に、水分摂取量と排尿パターンの関係、食物繊維摂取と排便機能の関係について詳細な観察と指導が重要となる。
安静度・バルーンカテーテルの有無
現在は術後安静の状態にあるが、術後1日目より段階的な離床が開始されている。バルーンカテーテル(尿道カテーテル)が挿入されており、術後3日目に抜去予定である。安静度の制限は排泄機能に影響を与える要因であり、特に腸蠕動の促進と排便機能の回復には適度な活動が必要である。離床進行により腹筋力の回復と腸管運動の改善が期待される。
腹部膨満・腸蠕動音
現在、軽度の腹部膨満が認められ、腸蠕動音は微弱な状態である。これは手術侵襲と麻酔による一時的な腸管麻痺の状態と考えられる。術後の正常な経過として、通常2-3日で腸蠕動音の回復が期待される。聴診による腸蠕動音の確認と腹部の視診・触診による膨満の評価を継続的に行い、腸管機能の回復を慎重に観察している。
血液データ
腎機能に関する血液データでは、BUN(血中尿素窒素)が入院時18mg/dLから術後22mg/dLに軽度上昇し、クレアチニンも0.8mg/dLから0.9mg/dLに軽度上昇している。これらの値は正常範囲内であるが、手術侵襲による一時的な腎機能への影響を示している可能性がある。68歳という年齢による腎機能の生理的低下も考慮する必要があり、継続的な腎機能のモニタリングが重要である。推定糸球体濾過量(GFR)については具体的なデータの記載がないため、追加の情報収集が必要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の排泄機能における主要な課題は、術後の腸管機能回復の促進と適切な排泄パターンの再確立である。現在の腸蠕動音微弱と排便停止は術後の正常な経過であるが、早期離床による腸管機能の促進が重要である。具体的な看護介入として、定期的な腹部の観察、腸蠕動音の聴診、腹部マッサージによる腸管機能の促進を行う必要がある。尿道カテーテル管理においては、感染予防と適切な抜去時期の判断が重要である。また、カテーテル抜去後の自然排尿の確認と残尿測定により、排尿機能の評価を行う必要がある。今後の経口摂取開始時には、水分バランスの詳細な管理と排便パターンの観察を継続し、必要に応じて排便コントロールのための食事指導や緩下剤の適用を検討する。腎機能については、定期的な血液検査による評価と尿量・尿性状の継続的観察により、腎機能の維持を確認していく必要がある。
ADLの状況、運動機能、運動歴、安静度、移動・移乗方法
A氏の術前のADLは完全に自立しており、建設業という職業特性から身体機能は良好な状態を保っていた。現在は術後2日目で部分的な安静が必要な状況であるが、術後1日目より段階的な離床が開始されている。移乗は看護師1名の介助で可能であり、ベッドサイドでの座位保持も短時間であれば可能である。運動歴については、建設業での長年の身体労働により基礎的な筋力と体力は維持されていたが、退職後は特定の運動習慣はなかった。現在の安静度はベッド上安静から離床開始段階にあり、歩行は看護師付き添いのもとで短距離であれば可能である。
バイタルサイン、呼吸機能
現在のバイタルサインは血圧125/75mmHg、脈拍85回/分、体温37.1℃、呼吸数20回/分、SpO2 97%(室内気)である。軽度の頻脈と発熱が認められるが、これは術後の正常な反応範囲内と考えられる。呼吸機能については、長期間の喫煙歴(20本/日×45年間)による潜在的な呼吸機能低下のリスクがあるが、現在のSpO2は良好である。しかし、術後1か月前の禁煙開始により、気道クリアランス機能の改善途中である可能性が高い。深呼吸や咳嗽による痰の喀出能力については、手術創部の疼痛により十分に行えない状況がある。
職業、住居環境
A氏は元建設業で現在は年金生活を送っている。建設業での長年の経験により、重労働に対する耐性と身体的な忍耐力を身につけているが、68歳という年齢による体力の低下は否めない。住居環境については、6人家族での生活であり、家族からのサポートが期待できる環境にある。自宅の構造や段差の有無、バリアフリー対応については詳細な情報収集が必要である。退院後の生活環境の整備と家族への介護指導が重要な課題となる。
血液データ
活動・運動に関連する血液データでは、赤血球数が術前435×10⁴/μLから現在385×10⁴/μLに減少し、ヘモグロビンも12.8g/dLから10.2g/dL、ヘマトクリットも38.5%から30.8%に低下している。この術後貧血により、運動耐容能の低下が懸念される。C反応性蛋白(CRP)は0.3mg/dLから8.5mg/dLに上昇しており、炎症反応による全身状態への影響が示唆される。これらの血液データの変化は、活動量の制限と段階的な運動負荷の調整の必要性を示している。
転倒転落のリスク
A氏の転倒転落リスクについて、現在複数のリスク要因が存在している。術後貧血による酸素運搬能力の低下、軽度の頻脈、手術創部の疼痛による動作制限、68歳という年齢による身体機能の低下、入院環境への不慣れなどが主要なリスク要因である。また、尿道カテーテルの挿入により歩行時の安全性にも注意が必要である。現在は看護師付き添いでの移動を実施しており、転倒転落防止対策が適切に行われている。今後の離床進行に伴い、リスクアセスメントの継続的な評価が重要である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の活動・運動面での主要な課題は、安全で効果的な離床の促進と術後合併症の予防である。現在の貧血状態と炎症反応を考慮し、個人の体力に応じた段階的な活動量の増加が必要である。具体的な看護介入として、バイタルサインの継続的モニタリング、活動前後の身体状況の評価、疼痛コントロールによる活動促進を行う必要がある。呼吸機能の維持・改善のため、深呼吸・咳嗽指導と体位排痰法の実施が重要である。転倒転落予防として、環境整備、適切な履物の着用、移動時の付き添い、夜間の見守り強化を継続する必要がある。長期的な課題として、在宅での活動レベルの維持と適切な運動療法の導入について、理学療法士との連携による指導が必要である。また、家族への移乗介助方法の指導と住環境の評価・改善についても検討が必要である。呼吸機能については、禁煙継続の支援と呼吸リハビリテーションの導入により、長期的な改善を図る必要がある。
睡眠時間、熟眠感、睡眠導入剤使用の有無
A氏の術前の睡眠パターンは22時頃就寝、6時頃起床の規則正しい生活リズムを維持しており、約8時間の睡眠時間を確保していた。熟眠感も良好で、中途覚醒は少なく質の良い睡眠をとることができていた。しかし、現在は手術侵襲と環境変化により睡眠が浅く、頻回に覚醒する状態が続いている。疼痛により夜間の睡眠が妨げられることがあり、睡眠時間は断続的で3-4時間程度に短縮している。必要時にゾルピデム5mgを使用しているが、使用頻度は連日ではなく、症状に応じた頓用での使用となっている。68歳という年齢による生理的な睡眠の質の変化も影響している可能性がある。
日中・休日の過ごし方
術前のA氏は年金生活を送っており、比較的ゆとりのある生活を送っていた。建設業を退職後は、家庭菜園や散歩などを楽しみ、規則正しい生活リズムを維持していた。休日は家族との時間を大切にし、孫との交流も生活の楽しみの一つであった。日中の活動量は適度で、夜間の良好な睡眠につながっていた。現在は入院環境での生活となり、日中の活動が制限されている状況である。ベッド上での安静時間が長く、昼夜の区別が曖昧になりやすい環境にある。術後の疼痛と不安により、日中も十分な休息がとれない状況が続いている。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の睡眠・休息面での主要な課題は、術後の睡眠の質の改善と正常な睡眠リズムの回復である。現在の睡眠障害は、手術創部の疼痛、入院環境への適応困難、術後の不安、日中の活動量不足などの複合的要因によるものと考えられる。具体的な看護介入として、適切な疼痛管理により夜間の痛みによる覚醒を最小限に抑える必要がある。環境調整として、病室の騒音軽減、適切な室温・湿度の維持、照明の調整により睡眠に適した環境を整備することが重要である。睡眠衛生指導として、日中の適度な離床活動、カフェイン摂取の制限、就寝前のリラクゼーションの促進が必要である。睡眠導入剤の適切な使用について、依存性の予防と効果的な使用方法の指導を行う必要がある。68歳という年齢を考慮し、加齢に伴う睡眠パターンの変化についての説明と受容を促進する必要がある。また、家族との面会時間の調整により、精神的安定を図ることも睡眠の質の向上に寄与する。長期的には、退院後の生活リズムの再構築について指導し、在宅での睡眠環境の整備についても家族と協議する必要がある。ストレス管理と不安の軽減のため、心理的サポートと情報提供により、手術に対する不安の解消を図ることが重要である。今後の離床進行に伴い、日中の活動量増加による自然な疲労感の獲得により、夜間の睡眠の質の向上が期待される。
意識レベル、認知機能
A氏の意識レベルは清明で、見当識も良好である。時間、場所、人物の見当識は保たれており、現在の状況について適切に理解している。MMSE 28点、HDS-R 27点と認知機能検査の結果も良好で、68歳という年齢に対して認知機能の低下は認められない。手術前後を通じて、医療スタッフからの説明に対する理解力も良好で、質問に対して適切な応答ができている。記憶力についても、近時記憶、遠隔記憶ともに問題なく、日常的な会話や指示の理解に支障はない。ただし、術後の疼痛や不安により、時折集中力の低下が認められることがある。
聴力、視力
A氏の聴力は年齢相応で正常範囲内にあり、日常会話に支障はない。医療スタッフとのコミュニケーションも良好で、聴力補助具の使用は不要である。視力については、老眼鏡使用で問題なく読書や文字の確認が可能である。68歳という年齢による水晶体の弾性低下は見られるが、日常生活に大きな支障をきたすレベルではない。入院中の検査結果の確認や説明書類の読解も、老眼鏡使用により適切に行うことができている。
認知機能
A氏の認知機能は全般的に良好である。判断力や問題解決能力も年齢相応に保たれており、治療方針についての意思決定も適切に行うことができている。抽象的思考や計算能力にも問題はなく、服薬管理や治療スケジュールの理解も良好である。学習能力も維持されており、術後の食事指導や生活指導に対する理解と実践が期待できる。ただし、手術という大きなストレス下にあるため、一時的な集中力の低下や情報処理速度の軽度低下が認められることがある。
不安の有無、表情
A氏は軽度から中等度の不安を抱えている状況である。表情は概ね穏やかで協調的であるが、時折心配そうな表情を見せることがある。特に、「食事ができるようになるか心配」という発言からも分かるように、胃全摘術後の生活への不安が主要な要因となっている。手術が成功してほっとしているという安堵の気持ちがある一方で、今後の生活変化への適応について不安を感じている。早く家に帰りたいという希望的な発言も聞かれ、回復への意欲は良好である。不安の程度は日中と夜間で変動があり、夜間に不安が増強する傾向がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の認知・知覚面での主要な課題は、術後の不安管理と認知機能の維持である。現在の認知機能は良好であるが、手術侵襲と環境変化によるストレスが認知機能に与える影響を継続的に観察する必要がある。具体的な看護介入として、不安の軽減のため、十分な情報提供と質問に対する丁寧な説明を行うことが重要である。特に、胃全摘術後の食事管理について段階的で具体的な説明を行い、不安の解消を図る必要がある。コミュニケーションの促進として、積極的な傾聴と共感的態度により、A氏の気持ちを受け止めることが大切である。視聴覚機能の維持のため、老眼鏡の適切な使用と聴力の定期的評価を継続する必要がある。68歳という年齢を考慮し、加齢に伴う感覚機能の変化について観察を続けることが重要である。認知機能の維持のため、日常的な会話や簡単な計算、読書などの知的活動を促進する必要がある。夜間の不安増強に対しては、環境調整と心理的サポートにより安心感の提供を図る必要がある。また、家族との面会や電話での会話により、精神的安定を促進することも重要である。長期的には、在宅での生活指導において、認知機能を活用した自己管理能力の向上を支援し、QOLの維持・向上を図る必要がある。
性格
A氏は温厚で協調性がある性格で、医療スタッフの指示にも素直に従う傾向がある。建設業での長年の経験により、忍耐力があり責任感が強いという特徴を持っている。他者との関係性を重視し、家族や医療従事者との関わりにおいても穏やかで礼儀正しい態度を示している。困難な状況に対しても前向きに取り組む姿勢があり、「手術が成功してほっとしている」という発言からも、現実受容能力が良好であることが伺える。一方で、心配性の一面もあり、将来への不安を抱えやすい傾向がある。
ボディイメージ
A氏のボディイメージは、胃全摘術により大きな変化を経験している。術前は建設業での身体労働により健康で丈夫な身体というイメージを持っていたが、現在は癌患者としての身体、手術創のある身体として認識している可能性がある。体重の4kg減少や手術創の存在により、従来の身体イメージとの乖離を感じている可能性がある。「食事ができるようになるか心配」という発言は、消化機能の変化に対する身体イメージの混乱を示している。68歳という年齢による加齢変化への適応と疾患による身体変化への適応が同時に求められている状況である。
疾患に対する認識
A氏は胃癌という診断を適切に理解しており、手術の必要性についても受け入れている。「手術が成功してほっとしている」という発言から、疾患の深刻さを理解した上で、治療に対する期待と安堵を感じていることが分かる。根治的手術により治癒の可能性があることを理解しており、前向きな治療への取り組みを示している。一方で、胃全摘術後の生活変化については不安を抱えており、現実的な課題への対処について支援が必要な状況である。
自尊感情
A氏の自尊感情は概ね良好であるが、疾患と手術による影響を受けている可能性がある。建設業での長年の経験と家族の大黒柱としての役割により、自己効力感を維持してきた。現在も「早く家に帰りたい」という発言から、家族への責任感と回復への意欲を示している。しかし、身体機能の一時的低下や依存的な状況により、一時的な自尊感情の低下が生じている可能性がある。年金生活への移行という人生の転換期にあることも、自己概念の再構築に影響を与えている。
育った文化や周囲の期待
A氏は日本の伝統的な家族観の中で育ち、男性が家族を支えるという価値観を持っている。建設業という職業選択も、勤勉さと責任感を重視する文化的背景を反映している。家族からの期待として、「主人の回復を信じて支えたい」という妻の発言からも分かるように、家族の中心的存在として期待されている。孫との関係も良好で、祖父としての役割への期待もある。一方で、68歳という年齢により、徐々に支えられる立場への移行も必要な時期にある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の自己知覚・自己概念面での主要な課題は、疾患と手術による自己概念の再構築と 自尊感情の維持・向上である。ボディイメージの変化への適応支援として、胃全摘術後の身体変化について段階的で具体的な説明を行い、新しい身体との調和を促進する必要がある。自尊感情の維持のため、A氏の強みや経験を認める声かけを行い、自己効力感の回復を支援することが重要である。疾患に対する適切な認識の維持のため、継続的な情報提供と質問への丁寧な回答により、現実的で前向きな疾患理解を促進する必要がある。家族役割の再調整について、段階的な役割の変化を受け入れられるよう支援し、新しい家族関係の構築を促進する必要がある。文化的背景の尊重として、A氏の価値観や信念を理解し、それに配慮した看護を提供することが大切である。長期的には、在宅での新しい生活様式において、自己概念の再構築とQOLの維持を支援し、充実した老年期の生活を送れるよう継続的な関わりが必要である。
職業、社会役割
A氏は元建設業で現在は年金生活を送っており、働き盛りの時期から退職後の新しい生活段階への移行期にある。建設業での長年の経験により、責任感が強く勤勉な人柄が形成され、地域社会での信頼も厚い存在であったと推測される。現在は年金受給者として経済的には安定した状況にあるが、社会的役割の変化に適応している過程にある。家族の精神的支柱としての役割は継続しており、妻や子ども、孫からの信頼と依存を受けている。疾患の診断と手術により、従来の役割遂行能力に一時的な制限が生じているが、回復への意欲は強い。
家族の面会状況、キーパーソン
A氏の家族構成は妻と長男夫婦、孫2人の6人家族で、キーパーソンは妻となっている。妻は「主人の回復を信じて支えたい。退院後の食事の準備方法を教えてほしい」と述べており、積極的な看護参加の意志と強い支援意欲を示している。長男は平日の来院は困難であるが、「週末は必ず来る」と述べており、家族の協力体制が整っている。面会状況は良好で、家族の訪問により精神的安定が図られている。妻との関係は長年の夫婦関係により信頼関係が築かれており、相互支援の関係が成立している。孫との関係も良好で、祖父としての役割にも意欲を示している。
経済状況
A氏の経済状況は年金収入により概ね安定していると考えられる。建設業での長年の勤務により、厚生年金等の受給が可能な状況にあると推測される。6人家族での生活を維持しており、基本的な生活費は確保されている状況である。しかし、医療費の負担や術後の食事管理に伴う費用、通院費用などの追加的な経済的負担については詳細な情報収集が必要である。高額療養費制度の利用や医療費控除などの社会保障制度の活用についても確認が必要である。長男夫婦との同居により、家計の分担や相互支援が可能な環境にある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の役割・関係面での主要な課題は、疾患による役割変化への適応と家族関係の再調整である。家族の精神的支柱から一時的に支えられる立場への役割変化について、段階的な受容を支援する必要がある。妻への支援として、退院後の食事管理方法や日常生活支援技術について具体的な指導を行い、介護負担の軽減を図る必要がある。家族全体への教育として、胃全摘術後の生活変化について説明し、家族の理解と協力を促進することが重要である。長男夫婦との関係調整について、平日の支援体制や緊急時の連絡体制を整備する必要がある。経済的支援として、医療費に関する社会保障制度の情報提供と手続きの支援を行う必要がある。社会復帰への支援として、体力回復に応じた社会参加の方法について検討し、生きがいの維持を支援することが重要である。孫との関係維持により、祖父役割の継続と世代間交流の促進を図り、家族内での存在意義の維持を支援する必要がある。長期的には、在宅での新しい家族関係の構築を支援し、相互支援システムの確立により、安定した家族生活の継続を目指す必要がある。地域社会との関係についても、体力回復後の社会参加や 地域活動への復帰について検討し、社会的役割の再構築を支援することが重要である。
年齢、家族構成、更年期症状の有無
A氏は68歳男性で、妻と長男夫婦、孫2人の6人家族として生活している。男性の場合、女性のような明確な更年期症状はないが、加齢に伴う男性ホルモン(テストステロン)の緩やかな低下により、性機能の変化や身体機能の低下が生じている可能性がある。68歳という年齢は老年期前期に該当し、性的な関心や活動の低下が一般的に認められる時期である。長年の夫婦関係を維持しており、妻との親密な関係性は良好に保たれていると考えられる。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の性・生殖面での主要な課題は、加齢と疾患による性機能への影響と夫婦関係の維持である。68歳という年齢により生理的な性機能の低下は避けられないが、胃癌の診断と手術という大きなストレスが性的関心や機能にさらなる影響を与えている可能性がある。手術侵襲による体力低下や術後の疼痛、栄養状態の変化は、性機能に一時的な影響を与える要因となる。看護介入として、プライバシーの尊重を最優先とし、必要に応じて適切な情報提供を行う必要がある。夫婦関係の維持について、病気による一時的な変化であることを説明し、回復に伴う改善の可能性について情報提供することが重要である。妻への支援として、夫の体調変化への理解と適切な距離感の保持について相談に応じる必要がある。心理的支援として、男性としての自尊心や夫としての役割について配慮し、尊厳を保った関わりを心がける必要がある。体力回復に伴い、夫婦関係の自然な改善が期待されるため、全身状態の改善を第一に看護を行う必要がある。また、必要に応じて専門医への紹介やカウンセリングの提案も検討し、包括的な支援を提供することが重要である。情報収集については、デリケートな内容であるため、患者の意向を尊重し、必要最小限の情報にとどめることが適切である。
入院環境
A氏は入院環境への適応において、概ね良好な状態を示している。協調性のある性格により、病院のルールや医療スタッフの指示に素直に従っており、環境への適応能力は比較的高い。しかし、自宅での規則正しい生活から病院での制約のある生活への変化により、軽度のストレスを感じている状況である。プライバシーの制限や騒音などの環境要因により、特に夜間の睡眠が妨げられる状況がある。6人家族での生活から個室または相部屋での生活への変化により、孤独感を感じる可能性もある。早く家に帰りたいという発言からも、在宅への強い希望が伺える。
仕事や生活でのストレス状況、ストレス発散方法
A氏は建設業を退職し現在は年金生活を送っているため、仕事関連のストレスは基本的にない状況である。退職後は家庭菜園や散歩などを楽しみ、規則正しい生活を送ることでストレス管理を行っていた。胃癌の診断という大きなストレスに直面し、現在は疾患と治療に関連したストレスが主要な問題となっている。従来のストレス発散方法である身体活動や屋外での活動が制限されているため、新しいストレス管理方法の模索が必要な状況である。長期間の喫煙習慣はストレス対処法の一つであった可能性があり、禁煙によるストレスも考慮する必要がある。
家族のサポート状況、生活の支えとなるもの
A氏の家族のサポート状況は非常に良好である。妻の積極的な支援意欲「主人の回復を信じて支えたい」や、長男の継続的な関わり「週末は必ず来る」により、強固な家族支援システムが構築されている。孫との関係も良好で、祖父としての役割が生きがいの一つとなっている。6人家族での生活により、相互支援の関係が成立しており、情緒的支援と手段的支援の両方が期待できる状況である。生活の支えとなるものとして、家族との絆、孫の存在、回復への希望、家庭復帰への願いなどが挙げられる。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のコーピング・ストレス耐性面での主要な課題は、疾患診断と手術による急性ストレスへの対処と効果的なストレス管理方法の確立である。現在の主要なストレス要因は、胃全摘術後の生活変化への不安、入院環境での制約、身体機能の一時的低下、禁煙継続のストレスなどである。看護介入として、ストレス要因の特定と軽減を図るため、十分な情報提供により不安の軽減を行う必要がある。効果的なコーピング方法の指導として、深呼吸法やリラクゼーション技法、気分転換の方法について指導することが重要である。家族支援システムの活用により、面会時間の調整や家族との電話連絡を促進し、情緒的支援の継続を図る必要がある。入院環境の調整として、プライバシーの確保、騒音の軽減、個人的な物品の持ち込みにより、環境ストレスの軽減を図ることが重要である。新しいストレス発散方法の模索として、読書、音楽鑑賞、軽い運動、手工芸などの院内で可能な活動を提案し、気分転換の機会を提供する必要がある。禁煙継続の支援として、禁煙の意義の再確認と代替的なストレス管理方法の指導を行う必要がある。段階的な目標設定により、回復過程での小さな達成感を積み重ね、自己効力感の向上を図ることが重要である。長期的には、在宅でのストレス管理について指導し、新しい生活様式に適応できるよう継続的な支援を提供する必要がある。社会復帰への支援として、体力回復に応じた活動参加により、生きがいの回復とストレス耐性の向上を図る必要がある。
信仰、意思決定を決める価値観・信念、目標
A氏は特定の宗教的信仰はないが、日本の伝統的な価値観に基づいた生活を送っている。家族を大切にするという価値観が強く、家族の幸福と安定を最優先に考える傾向がある。勤勉さと責任感を重視し、建設業での長年の経験により努力と忍耐による問題解決を信念としている。「手術が成功してほっとしている」という発言からも、医療への信頼と科学的治療への期待を持っていることが分かる。意思決定の基準として、家族への影響、経済的負担、回復の可能性を総合的に考慮する傾向がある。早く家に帰りたいという希望は、家族との時間を大切にする価値観の表れである。
現在の主要な目標は、疾患からの回復と家族との生活の再開である。「食事ができるようになるか心配」という発言から、日常生活の回復への強い願いが伺える。長期的な目標として、孫の成長を見守ること、妻との残りの人生を穏やかに過ごすこと、家族の負担にならないことなどが考えられる。禁煙の継続や健康的な生活習慣の維持についても、家族のためという動機が強い。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の価値・信念面での主要な課題は、疾患体験による価値観の再構築と新しい生活目標の設定である。家族中心の価値観は維持されているが、自分自身の健康管理の重要性についての認識を深める必要がある。看護介入として、A氏の価値観の尊重を基盤とし、家族を大切にする気持ちを自己の健康管理への動機として活用することが重要である。意思決定支援として、十分な情報提供と選択肢の提示により、A氏の価値観に基づいた判断ができるよう支援する必要がある。目標設定の支援として、短期目標と長期目標を明確化し、段階的な達成により希望の維持を図ることが重要である。家族との価値観の共有を促進し、治療方針や生活目標について家族全体での合意形成を支援する必要がある。スピリチュアルケアとして、人生の意味や目的について考える機会を提供し、疾患体験を通じた価値観の深化を支援することが重要である。文化的背景の尊重として、日本の伝統的価値観に配慮した看護を提供し、A氏のアイデンティティを尊重する必要がある。希望の維持として、回復の可能性と将来への展望について現実的で前向きな情報提供を行い、生きる意欲の向上を図る必要がある。長期的には、新しい人生段階における価値観の再構築を支援し、充実した老年期の生活を送るための価値観の明確化を促進する必要がある。社会貢献への意欲や次世代への継承など、より広い視野での価値観の発展についても支援し、人生の統合性の達成を目指すことが重要である。
看護計画
看護問題
胃全摘術に伴う消化機能の変化に関連した栄養摂取不足
長期目標
退院時までに胃全摘術後の消化機能に適応した食事摂取方法を習得し、栄養状態の改善が図れる
短期目標
術後1週間以内に段階的な経口摂取を開始し、消化器症状なく流動食から五分粥まで摂取できる
≪O-P≫観察計画
・体重測定による栄養状態の変化である
・血清アルブミン、総蛋白値の推移である
・ヘモグロビン値とヘマトクリット値の変化である
・食事摂取量と摂取状況の観察である
・嘔吐、吐き気、腹部膨満感の有無である
・ダンピング症候群の症状出現の確認である
・腸蠕動音の回復状況である
・創部の治癒状況と感染徴候の有無である
・血糖値の変動と糖尿病管理状況である
・皮膚の色調、弾性、乾燥状態の観察である
・口腔内の状態と嚥下機能の評価である
・食欲の程度と食事に対する意欲である
≪T-P≫援助計画
・段階的な経口摂取開始の調整と管理である
・少量頻回食の提供と摂取支援である
・食事摂取時の体位調整と環境整備である
・嘔吐時の気道確保と口腔ケアの実施である
・静脈栄養管理と輸液バランスの調整である
・血糖値測定とインスリン投与の管理である
・口腔ケアによる口腔内環境の整備である
・体重測定の定期実施と記録である
・栄養士との連携による食事内容の調整である
・家族への食事介助方法の指導である
・食事摂取記録の作成と評価である
・消化器症状出現時の適切な対応である
≪E-P≫教育・指導計画
・胃全摘術後の消化機能の変化についての説明である ・ダンピング症候群の症状と予防方法の指導である ・適切な食事摂取方法と咀嚼の重要性の説明である ・少量頻回食の必要性と実践方法の指導である ・退院後の食事管理と調理方法の指導である ・栄養バランスを考慮した食品選択の指導である ・体重測定の重要性と自己管理方法の説明である ・血糖値管理と食事の関係についての指導である
看護問題
手術侵襲に伴う疼痛と不安に関連した睡眠パターンの障害
長期目標
退院時までに疼痛が軽減し、夜間の十分な睡眠が確保でき、日中の活動に支障がない状態となる
短期目標
術後1週間以内に夜間の中途覚醒が減少し、連続して4時間以上の睡眠が確保できる
≪O-P≫観察計画
・疼痛の程度と性質の評価である
・睡眠時間と睡眠の質の観察である
・夜間の覚醒回数と覚醒原因の確認である
・日中の傾眠状況と活動レベルである
・不安の程度と表情の変化である
・バイタルサインの変動状況である
・鎮痛薬と睡眠薬の効果と副作用である
・環境要因による睡眠への影響である
・家族面会時の精神状態の変化である
・創部の状態と感染徴候の有無である
・排尿パターンと夜間の排尿回数である
・食事摂取量と消化器症状の有無である
≪T-P≫援助計画
・疼痛スケールを用いた疼痛評価の実施である
・硬膜外カテーテルによる鎮痛管理である
・体位変換による圧迫部位の除圧である
・睡眠に適した環境の整備である
・病室の騒音軽減と照明調整である
・睡眠薬の適切な投与と効果の評価である
・リラクゼーション技法の提供である
・日中の離床活動の促進である
・家族面会による精神的支援の調整である
・夜間の見回り回数の調整である
・快適な寝具の提供と環境整備である
・入眠前の口腔ケアと清拭の実施である
≪E-P≫教育・指導計画
・術後疼痛の原因と経過についての説明である
・疼痛時の適切な訴え方の指導である
・深呼吸やリラクゼーション方法の指導である
・睡眠衛生に関する基本的な知識の提供である
・退院後の疼痛管理方法の指導である
・家族への精神的支援方法の指導である
・睡眠環境の整備方法の説明である
・ストレス軽減方法の指導である
看護問題
術後安静と腸管機能低下に伴う排便パターンの変調
長期目標
退院時までに規則的な排便パターンが確立し、消化器症状なく自然排便が可能となる
短期目標
術後1週間以内に腸蠕動音が回復し、経口摂取開始とともに自然排便が認められる
≪O-P≫観察計画
・腸蠕動音の聴診による腸管機能の評価である
・腹部膨満の程度と腹部症状の観察である
・排便の有無と便の性状の確認である
・排ガスの有無と腹部の張りの状態である
・腹部の触診による圧痛と硬度の評価である
・水分摂取量と尿量のバランス観察である
・経口摂取開始後の消化器症状である
・離床状況と活動レベルの変化である
・尿道カテーテル抜去後の排尿状況である
・血液検査による電解質バランスの確認である
・腹部レントゲン検査結果の確認である
・下剤使用の必要性と効果の評価である
≪T-P≫援助計画
・腸蠕動音の定期的な聴診の実施である
・腹部マッサージによる腸管機能の促進である
・段階的離床による腸管運動の促進である
・水分摂取量の調整と管理である
・尿道カテーテル抜去のタイミング調整である
・排便しやすい体位の指導と介助である
・腹部の温罨法による血流改善である
・下剤使用時の効果と副作用の管理である
・食物繊維を含む食事への段階的移行である
・プライバシーに配慮した排泄環境の整備である
・排便記録の作成と評価である
・経口摂取開始のタイミング調整である
≪E-P≫教育・指導計画
・術後の腸管機能回復の過程についての説明である
・離床と歩行による腸管機能促進効果の指導である
・適切な水分摂取量と摂取方法の指導である
・腹部マッサージの方法と効果の説明である
・排便を促進する食品と食事方法の指導である
・退院後の排便管理と生活習慣の指導である
・下剤の適切な使用方法と注意点の説明である
・便秘予防のための日常生活の工夫の指導である
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
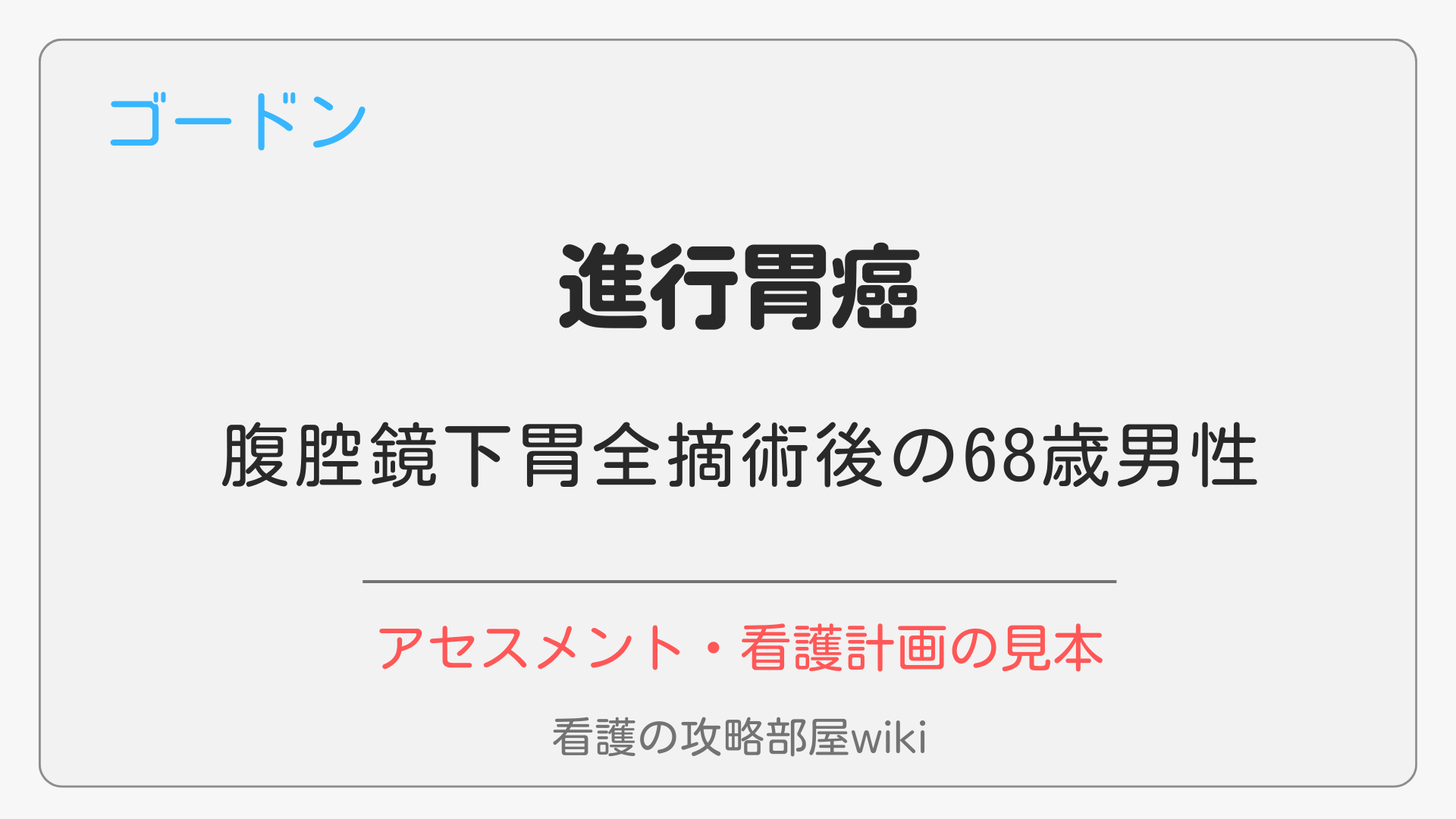
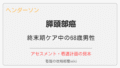
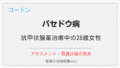
コメント