事例の要約
本事例は、バセドウ病による甲状腺機能亢進症の症状が悪化し、動悸や体重減少、発汗過多等の症状により日常生活に支障をきたしたため入院加療となった事例である。介入日は5月15日、入院3日目である。
基本情報
A氏は28歳の女性で、身長158cm、体重は入院前の52kgから現在45kgまで減少している。家族構成は両親と同居しており、母親がキーパーソンとして関わっている。職業は会計事務所の事務員として勤務していたが、症状悪化により現在は休職中である。性格は几帳面で責任感が強く、完璧主義的な傾向がある。感染症歴は特になく、薬物アレルギーも現在のところ確認されていない。認知力は正常で、見当識や記憶力に問題はない。
病名
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
既往歴と治療状況
既往歴として、2年前に甲状腺機能の軽度異常を指摘されたが、当時は経過観察となっていた。今回、症状の悪化により精密検査を実施し、バセドウ病と診断された。現在は抗甲状腺薬による内科的治療を開始している。
入院から現在までの情報
入院時、A氏は著明な頻脈(心拍数120回/分)と発汗過多、手指振戦、眼球突出の症状を呈していた。入院後、抗甲状腺薬の投与を開始し、β遮断薬による症状緩和治療も併用している。現在、心拍数は100回/分前後まで改善しているが、依然として易疲労感と食欲亢進にもかかわらず体重減少が続いている状況である。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、体温37.8℃、血圧148/95mmHg、心拍数120回/分、呼吸数26回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在は体温36.8℃、血圧135/85mmHg、心拍数100回/分、呼吸数20回/分、SpO2 99%(室内気)と、治療により改善傾向にある。
食事と嚥下状態
入院前は食欲亢進により通常の1.5倍程度の食事量を摂取していたが、体重は継続的に減少していた。嚥下機能に問題はなく、現在も食欲は旺盛である。病院食は完食しており、間食も希望することが多い。
排泄
入院前は軟便傾向で1日3-4回の排便があり、腹部不快感を訴えることが多かった。現在も1日2-3回の軟便が続いているが、腹痛は軽減している。下剤の使用は必要なく、むしろ止痢剤の投与を検討している状況である。
睡眠
入院前は不眠と中途覚醒が頻繁にあり、1日の睡眠時間は3-4時間程度であった。現在は軽度の睡眠導入剤(ゾルピデム5mg)を使用し、6時間程度の睡眠が確保できるようになっている。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼とも1.0で、眼球突出は認められるが視野障害はない。聴力に問題はなく、知覚も正常である。コミュニケーション能力は良好で、やや早口になる傾向があるが意思疎通に支障はない。特定の宗教的信仰はない。
動作状況
歩行は自立しているが、易疲労感により長距離の歩行では休息を要する。移乗は自立しており、排尿・排便動作も問題ない。入浴は発汗過多のため1日2回のシャワー浴を希望している。衣類の着脱は自立している。転倒歴は特にない。
内服中の薬
- メルカゾール(チアマゾール)15mg 1日3回 毎食後
- インデラル(プロプラノロール)30mg 1日3回 毎食後
- ゾルピデム5mg 1日1回 就寝前
現在は看護師管理のもと、確実な服薬ができている。退院後は自己管理となる予定である。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(5月15日) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| TSH | 0.01以下 | 0.02 | 0.35-4.94 μIU/mL |
| FT3 | 15.8 | 8.2 | 1.71-3.71 pg/mL |
| FT4 | 4.8 | 2.9 | 0.70-1.48 ng/dL |
| TRAb | 25.4 | 18.6 | <2.0 IU/L |
| Hb | 9.8 | 10.5 | 11.3-15.2 g/dL |
| WBC | 3,200 | 4,100 | 3,500-8,500 /μL |
| 総蛋白 | 5.9 | 6.2 | 6.7-8.3 g/dL |
| アルブミン | 3.2 | 3.6 | 3.8-5.3 g/dL |
今後の治療方針と医師の指示
現在の抗甲状腺薬による治療を継続し、甲状腺機能の正常化を目指す。TRAb値の推移を観察し、寛解の可能性を評価する。症状の改善が認められれば、2週間程度での退院を予定している。退院後は外来でのフォローアップを月1回実施し、薬物療法の調整を行う。放射性ヨウ素治療や手術療法についても、内科的治療の効果を見極めた上で検討する方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「こんなに食べているのに痩せてしまって心配」「仕事に早く復帰したい」と話しており、病気に対する不安と仕事への責任感を強く感じている。母親は「娘が急に痩せて心配で仕方がない」「きちんと治療を受けて元気になってほしい」と話しており、A氏の治療に対して協力的な姿勢を示している。家族全体としては、完全な回復を強く願っており、医療スタッフとの連携を大切にしたいと表明している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏はバセドウ病による甲状腺機能亢進症を発症している。バセドウ病は甲状腺刺激ホルモン受容体に対する自己抗体が産生され、甲状腺が過度に刺激されることで甲状腺ホルモンが過剰に分泌される自己免疫疾患である。本疾患では甲状腺ホルモンの過剰分泌により全身の代謝が亢進し、頻脈、発汗過多、体重減少、手指振戦、眼球突出などの特徴的な症状が出現する。A氏の場合、TRAb値が25.4 IU/Lと著明に高値を示しており、自己免疫反応の活性化が確認されている。
健康状態
A氏の現在の健康状態は、甲状腺機能亢進症による全身症状が顕著に現れている状態である。入院時の甲状腺機能検査において、TSH値が0.01以下μIU/mLと著明に低値を示し、FT3が15.8 pg/mL、FT4が4.8 ng/dLと基準値を大幅に超えて上昇している。これらの検査結果は重篤な甲状腺機能亢進状態を示しており、治療開始後も依然として異常値が持続している。身体症状としては、入院時の心拍数120回/分の頻脈、発汗過多、手指振戦、眼球突出が認められ、これらの症状は甲状腺ホルモン過剰による交感神経系の過度な刺激に起因している。また、代謝亢進により7kgの体重減少が短期間で生じており、栄養状態の悪化も懸念される。治療開始後は心拍数が100回/分前後まで改善しているものの、完全な症状改善には至っていない状況である。
受診行動、疾患や治療への理解、服薬状況
A氏は2年前に甲状腺機能の軽度異常を指摘されていたが、当時は経過観察のみで積極的な治療は行われていなかった。今回の症状悪化により精密検査を受け、バセドウ病と診断されたが、この経過から初期の軽微な異常を放置していた可能性が考えられる。現在は医師から病気の説明を受け、抗甲状腺薬による治療の必要性については理解を示している。A氏は「仕事に早く復帰したい」との発言があり、治療への意欲は高いものの、疾患の慢性経過や長期治療の必要性について十分な理解が得られているかは不明である。服薬状況については、現在は看護師管理下で確実な服薬が行われているが、A氏の几帳面で責任感の強い性格特性を考慮すると、退院後の自己管理においても良好な服薬アドヒアランスが期待される。ただし、完璧主義的傾向があるため、症状の改善が思うように進まない場合の心理的負担についても注意が必要である。
身長、体重、BMI、運動習慣
A氏の身長は158cm、現在の体重は45kgであり、BMIは18.0 kg/m²と低体重の状態にある。入院前の体重は52kgであったため、7kgの体重減少が短期間で生じている。この体重減少は甲状腺機能亢進症による代謝亢進が主要因であり、食欲亢進にもかかわらず体重減少が続いている状況は疾患の重篤さを示している。運動習慣については詳細な情報が不足しているが、現在は易疲労感により長距離歩行でも休息を要する状態であり、通常の運動は困難な状況である。甲状腺機能亢進症では筋力低下や筋萎縮も生じやすく、A氏の現在の身体活動レベルや筋力の評価、適切な運動療法の検討が必要である。
呼吸に関するアレルギー、飲酒、喫煙の有無
A氏には薬物アレルギーは現在のところ確認されておらず、呼吸器系のアレルギーについても特記すべき事項はない。喫煙習慣はなく、飲酒は月に1-2回程度のワインを少量摂取する程度と適度な範囲内である。現在は入院中のため禁酒している。喫煙歴がないことは、甲状腺機能亢進症における心血管系合併症のリスク軽減要因として評価できる。ただし、甲状腺機能亢進症では呼吸困難感や頻呼吸が生じることがあるため、呼吸器症状の詳細な評価と、アレルギー歴についてのより詳細な情報収集が必要である。
既往歴
A氏の既往歴として、2年前に甲状腺機能の軽度異常を指摘されているが、当時は経過観察のみで積極的な治療は行われていなかった。この経過は、今回のバセドウ病発症の前駆状態であった可能性が高い。甲状腺機能異常の家族歴についての情報は不足しており、バセドウ病には遺伝的素因が関与することが知られているため、家族歴の詳細な聴取が必要である。また、自己免疫疾患の既往歴や他の内分泌疾患の有無についても確認が必要である。A氏は28歳の若年女性であり、妊娠・出産歴についても聴取し、女性ホルモンとの関連性についても評価する必要がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の健康管理上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による全身症状の管理と合併症の予防である。現在も甲状腺機能の正常化には至っておらず、継続的な薬物療法と症状モニタリングが必要である。第二に、7kgの体重減少と低BMIによる栄養状態の改善が急務であり、適切な栄養管理と栄養状態の評価が重要である。第三に、A氏の几帳面で完璧主義的な性格特性を考慮した心理的サポートと、疾患の慢性経過についての教育的支援が必要である。
看護介入としては、まず甲状腺機能と全身症状の継続的な観察を行い、頻脈、発汗、振戦などの症状変化を詳細に記録する必要がある。栄養面では、高カロリー・高蛋白食の提供と摂取量の評価、体重測定による栄養状態のモニタリングを実施する。服薬管理については、退院後の自己管理に向けた服薬指導と、薬物の作用・副作用についての教育を行う。また、A氏の心理的負担を軽減するため、疾患の理解を深める教育的支援と、治療への不安や仕事復帰への焦りに対する心理的サポートを提供する。
さらに、家族歴や妊娠・出産歴、運動習慣、呼吸器症状等の詳細な情報収集を継続し、個別性を重視した看護計画の立案が必要である。甲状腺機能の改善に伴う症状変化の観察を続け、合併症の早期発見と対応についても継続的な注意が必要である。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は甲状腺機能亢進症による代謝亢進の影響で食欲亢進の状態にあり、通常の1.5倍程度の食事量を摂取している。病院食は完食しており、間食も頻繁に希望している状況である。しかし、食欲亢進にもかかわらず体重減少が継続していることは、甲状腺ホルモン過剰による著明な代謝亢進を示している。水分摂取については、発汗過多により脱水リスクが高いものの、具体的な摂取量の詳細な記録が不足している。経口摂取は問題なく行えており、嚥下機能に異常は認められない。摂取方法は自立しているが、代謝亢進による栄養需要の増大に対して摂取量が不十分である可能性が高い。
好きな食べ物/食事に関するアレルギー
A氏の食事の嗜好や食事に関するアレルギーについては詳細な情報が不足している。薬物アレルギーは現在のところ確認されていないが、食物アレルギーの有無については確認が必要である。甲状腺機能亢進症ではヨウ素制限が治療上重要であるため、海藻類や昆布だし等のヨウ素を多く含む食品の摂取状況について詳細な聴取が必要である。また、カフェインは甲状腺機能亢進症の症状を悪化させる可能性があるため、コーヒーや茶類の摂取習慣についても確認が必要である。
身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
A氏の身長は158cm、現在の体重は45kgでBMIは18.0 kg/m²と低体重の状態にある。入院前の52kgから7kgの体重減少が短期間で生じており、これは甲状腺機能亢進症による代謝亢進が主要因である。28歳女性の基礎代謝量は約1,200 kcal/日であるが、甲状腺機能亢進症では代謝率が30-60%増加するため、必要栄養量は1,800-2,000 kcal/日以上と推定される。現在の身体活動レベルは易疲労感により低下しているが、代謝亢進による内因性のエネルギー消費は著明に増加している。適正体重は49-55kg程度であり、現在の体重は4-10kg不足の状態である。
食欲・嚥下機能・口腔内の状態
A氏は甲状腺機能亢進症による食欲亢進が顕著であり、病院食の完食に加えて間食も頻繁に希望している。嚥下機能に問題はなく、誤嚥や咽頭違和感等の症状は認められない。口腔内の状態については詳細な観察記録が不足しているが、甲状腺機能亢進症では口渇や唾液分泌の変化が生じることがあるため、口腔粘膜の乾燥や炎症の有無について詳細な評価が必要である。また、やや早口になる傾向があることから、咀嚼や嚥下の際の注意深い観察が必要である。
嘔吐・吐気
現在のところ嘔吐や吐気の症状は認められていない。しかし、甲状腺機能亢進症では消化管運動の亢進により軟便傾向が見られており、1日2-3回の軟便が継続している。嘔吐や吐気がないことは栄養摂取の継続において好材料であるが、消化管症状の変化については継続的な観察が必要である。抗甲状腺薬の副作用として消化器症状が生じる可能性もあるため、薬物治療開始後の症状変化について注意深い監視が必要である。
皮膚の状態、褥創の有無
A氏は甲状腺機能亢進症による発汗過多が著明であり、1日2回のシャワー浴を希望している。皮膚は湿潤状態が続いており、皮膚トラブルのリスクが高い状況である。現在のところ褥創の発生はないが、体重減少により骨突出部の皮膚への圧迫が増加している可能性がある。発汗過多により電解質バランスの異常や皮膚の炎症が生じるリスクがあるため、皮膚の詳細な観察と適切なスキンケアが必要である。また、甲状腺機能亢進症では皮膚の温感や紅潮が見られることがあり、皮膚の色調や温度についても継続的な評価が必要である。
血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1C、BS)
現在の血液データにおいて、総蛋白は5.9 g/dL(基準値6.7-8.3)、アルブミンは3.2 g/dL(基準値3.8-5.3)と低値を示しており、蛋白質の栄養状態の悪化が確認されている。これは甲状腺機能亢進症による蛋白質代謝の亢進と摂取不足が原因と考えられる。ヘモグロビンは9.8 g/dL(基準値11.3-15.2)と軽度の貧血を呈している。白血球数は3,200 /μLと軽度低値であるが、これは抗甲状腺薬の副作用の可能性もある。電解質、脂質、血糖値については詳細なデータが不足しており、栄養状態の包括的評価のために追加の検査データ収集が必要である。治療開始後、総蛋白6.2 g/dL、アルブミン3.6 g/dLと改善傾向にあるが、依然として基準値を下回っている。
栄養代謝上の課題と看護介入
A氏の栄養代謝上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による代謝亢進に対応した適切な栄養供給の確保である。現在の7kgの体重減少と低BMI、低蛋白血症は栄養状態の著明な悪化を示している。第二に、発汗過多による水分・電解質バランスの管理が重要である。第三に、ヨウ素制限を含む甲状腺機能亢進症に適した食事療法の実施が必要である。
看護介入としては、まず高カロリー・高蛋白食の提供と摂取量の詳細な記録を行い、必要栄養量(推定2,000 kcal/日以上)の確保を図る必要がある。体重測定を毎日実施し、栄養状態の改善を評価する。水分摂取量と発汗による喪失量を考慮した適切な水分バランスの維持を行う。ヨウ素制限食の指導と、カフェイン制限についても教育的支援を提供する。
血液データの継続的なモニタリングにより、蛋白質栄養状態、貧血、電解質バランスの改善を評価し、必要に応じて栄養補助食品の使用も検討する。皮膚の観察を継続し、発汗過多による皮膚トラブルの予防と早期発見に努める。また、食事の嗜好や食物アレルギーの詳細な聴取、電解質や血糖値等の追加検査データの収集を行い、個別性を重視した栄養管理計画の立案が必要である。
排便と排尿の回数と量と性状
A氏は甲状腺機能亢進症による消化管運動の亢進により、入院前から軟便傾向が継続している。入院前は1日3-4回の排便があり、現在も1日2-3回の軟便が続いている状況である。便の性状は軟便から泥状便であり、血便や粘液便は認められていない。排便回数の増加と軟便は甲状腺ホルモン過剰による腸管運動亢進の典型的な症状である。排尿については、甲状腺機能亢進症による頻脈や代謝亢進、発汗過多の影響で体内水分バランスが変化しているが、具体的な排尿回数や尿量についての詳細な記録が不足している。尿の性状についても色調や混濁の有無等の詳細な観察記録が必要である。
下剤使用の有無
A氏は現在下剤の使用は必要なく、むしろ軟便の改善のために止痢剤の投与が検討されている状況である。甲状腺機能亢進症による腸管運動亢進のため、通常の便秘対策とは逆の対応が必要となっている。入院前の下剤使用歴についても詳細な確認が必要であるが、現在の症状から推測すると下剤の使用は不要であったと考えられる。今後の治療経過において、甲状腺機能の改善に伴い腸管運動が正常化した際の排便パターンの変化について注意深い観察が必要である。
in-outバランス
A氏は甲状腺機能亢進症による発汗過多により、不感蒸泄が著明に増加している状況である。1日2回のシャワー浴を希望するほどの発汗があり、水分の喪失量が通常より大幅に増加していると推定される。しかし、具体的な水分摂取量と尿量の詳細な記録が不足しており、正確なin-outバランスの評価ができていない。発汗による水分・電解質の喪失を考慮すると、脱水や電解質異常のリスクが高い状況である。体重減少の一部は脱水による可能性もあり、適切な水分バランスの評価と管理が急務である。
排泄に関連した食事・水分摂取状況
A氏は甲状腺機能亢進症による食欲亢進により通常の1.5倍程度の食事量を摂取している。食物繊維の多い食品の摂取が軟便の一因となっている可能性もあるが、主要因は甲状腺ホルモン過剰による腸管運動亢進である。水分摂取については、発汗過多により必要量が増加しているにもかかわらず、具体的な摂取量の記録が不十分である。カフェインを含む飲料は甲状腺機能亢進症の症状を悪化させる可能性があるため、摂取状況の確認が必要である。また、ヨウ素制限の観点から、海藻類等の摂取状況についても排泄機能への影響を含めて評価が必要である。
安静度・バルーンカテーテルの有無
A氏の安静度は特に制限されておらず、歩行は自立している。しかし、易疲労感により長距離歩行では休息を要する状態である。バルーンカテーテルの留置はなく、排尿は自立している。移動や排泄動作は自立しているが、頻脈や動悸により活動時の負担が大きい可能性がある。トイレまでの移動や排泄動作時のバイタルサインの変化について観察が必要である。また、軟便の頻度を考慮すると、トイレへの近接性や迅速なアクセスの確保が重要である。
腹部膨満・腸蠕動音
A氏は入院前から腹部不快感を訴えていたが、現在は軽減している状況である。甲状腺機能亢進症による腸管運動亢進のため、腸蠕動音は亢進していると推定される。しかし、具体的な腸蠕動音の聴取記録や腹部の詳細な観察記録が不足している。腹部膨満の有無についても明確な記録がなく、腹部の視診・触診・聴診による包括的な評価が必要である。軟便が継続していることから、腸管の炎症や感染の可能性についても考慮し、腹痛や腹部圧痛の有無について詳細な評価が必要である。
血液データ(BUN、Cr、GFR)
腎機能に関する血液データ(BUN、クレアチニン、GFR)についての記録が不足している。甲状腺機能亢進症では腎血流量の増加や糸球体濾過率の変化が生じることがあり、腎機能の評価は重要である。また、発汗過多による脱水や電解質異常が腎機能に影響を与える可能性もある。現在の電解質データも不足しており、ナトリウム、カリウム等の電解質バランスの評価が必要である。軟便による電解質の喪失も考慮し、包括的な水分・電解質バランスの評価が急務である。
排泄機能上の課題と看護介入
A氏の排泄機能上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による軟便の管理と腸管運動亢進への対応である。1日2-3回の軟便により日常生活への影響が懸念される。第二に、発汗過多による水分・電解質バランスの異常と脱水リスクの管理が重要である。第三に、正確なin-outバランスの評価と適切な水分管理の実施が必要である。
看護介入としては、まず排便・排尿の回数、量、性状の詳細な記録を開始し、排泄パターンの把握を行う必要がある。水分摂取量と尿量の正確な測定により、in-outバランスの評価を実施する。発汗量を考慮した適切な水分補給の指導と、電解質バランスの維持を図る。軟便に対しては、止痢剤の使用を検討するとともに、肛門周囲の皮膚保護と清潔保持を行う。
腹部の詳細な観察(視診・触診・聴診)を継続的に実施し、腸管運動の状態や腹部症状の変化を評価する。腎機能検査(BUN、クレアチニン、GFR)と電解質検査の実施により、水分・電解質バランスと腎機能の評価を行う。また、甲状腺機能の改善に伴う排泄パターンの変化について継続的な観察を行い、必要に応じて排泄ケアの調整を図る必要がある。トイレ環境の整備と、緊急時の対応についても配慮が必要である。
ADLの状況、運動機能、運動歴、安静度、移動/移乗方法
A氏のADLは基本的に自立しているが、甲状腺機能亢進症による易疲労感により活動耐性が低下している。歩行は自立しているものの、長距離歩行では休息を要する状態であり、日常生活動作における持久力の低下が認められる。移乗動作は問題なく自立しており、排尿・排便動作も自立している。入浴については、発汗過多のため1日2回のシャワー浴を希望している状況である。衣類の着脱は自立しているが、発汗により頻繁な衣類交換が必要となっている。運動歴については詳細な情報が不足しているが、現在は易疲労感により通常の運動は困難な状況である。安静度に特別な制限はないが、心拍数120回/分の頻脈があるため、活動時の心負荷について注意が必要である。
バイタルサイン、呼吸機能
A氏のバイタルサインは甲状腺機能亢進症の影響で著明な変化を示している。入院時の心拍数は120回/分と頻脈を呈しており、現在も100回/分前後と正常上限を超えている。血圧は入院時148/95mmHgから現在135/85mmHgと軽度高値が持続している。体温は入院時37.8℃の微熱があったが、現在は36.8℃と改善している。呼吸数は入院時26回/分から現在20回/分と改善傾向にあるが、依然として軽度頻呼吸の状態である。SpO2は室内気で98-99%と良好であるが、手指振戦が認められており、甲状腺機能亢進症による交感神経系の過度な刺激が持続している。呼吸機能については詳細な評価が不足しており、運動時の呼吸困難の有無や呼吸筋力について確認が必要である。
職業、住居環境
A氏は会計事務所の事務員として勤務していたが、症状悪化により現在は休職中である。事務職という職業特性から、日常的な身体活動量は比較的少ないと推定される。住居環境については、両親と同居しており家族のサポートが期待できる状況である。しかし、住居の構造や階段の有無、職場復帰時の通勤方法等、具体的な環境についての詳細な情報が不足している。復職に向けては、易疲労感や頻脈等の症状が業務遂行能力に与える影響について評価が必要である。また、職場での理解とサポート体制についても確認が必要である。
血液データ(RBC、Hb、Ht、CRP)
血液データにおいて、ヘモグロビンは入院時9.8 g/dLから現在10.5 g/dLと軽度改善しているが、依然として軽度貧血の状態にある(基準値11.3-15.2 g/dL)。この貧血は甲状腺機能亢進症による骨髄機能への影響や栄養状態の悪化、慢性的な炎症等が原因と考えられる。赤血球数やヘマトクリット値については具体的なデータが不足している。CRP値についても記録がなく、炎症状態の評価ができていない。貧血により組織への酸素供給能力が低下し、易疲労感や活動耐性低下の一因となっている可能性が高い。白血球数は入院時3,200 /μLと軽度低値であったが、現在は4,100 /μLと改善傾向にある。
転倒転落のリスク
A氏の転倒転落リスクについては、複数のリスク要因が存在する。第一に、手指振戦により巧緻性が低下しており、物をつかむ動作や細かい作業に支障が生じている。第二に、易疲労感により急激な体力低下が生じる可能性がある。第三に、頻脈により起立性の症状や動悸が生じ、ふらつきの原因となる可能性がある。第四に、軽度貧血により立ちくらみや めまいが生じるリスクがある。現在のところ転倒歴は特にないが、甲状腺機能亢進症の症状により転倒リスクは高い状況である。また、眼球突出により視野や視覚に影響が生じている可能性もあり、詳細な評価が必要である。
活動運動機能上の課題と看護介入
A氏の活動運動機能上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による易疲労感と活動耐性低下への対応である。頻脈や軽度貧血により、日常生活動作や職業復帰に必要な身体機能が低下している。第二に、手指振戦や眼球突出等の症状による巧緻性や視覚機能への影響である。第三に、転倒転落リスクの管理と安全な活動環境の確保が重要である。
看護介入としては、まず活動時のバイタルサインの変化を詳細に観察し、心拍数や血圧の上昇、呼吸困難の有無を評価する必要がある。活動と休息のバランスを調整し、段階的な活動量の増加を図る。転倒予防のため、環境整備(滑り止め、手すりの設置等)を行い、移動時の見守りや介助を提供する。手指振戦による日常生活への影響を評価し、必要に応じて補助具の使用を検討する。
貧血の改善に向けて、栄養状態の改善と必要に応じた鉄剤等の投与を検討する。呼吸機能の詳細な評価を実施し、運動時の呼吸困難や酸素飽和度の変化を監視する。職場復帰に向けては、段階的な活動量の増加と職場環境の調整について検討する。また、住居環境や通勤方法等の詳細な情報収集を行い、個別性を重視した活動支援計画の立案が必要である。眼球突出による視覚への影響についても詳細な評価を行い、必要に応じて眼科的な精査を検討する必要がある。
睡眠時間、熟眠感、睡眠導入剤使用の有無
A氏は甲状腺機能亢進症による交感神経系の過度な刺激により、入院前から深刻な睡眠障害を呈している。入院前の睡眠時間は3-4時間程度と著明に短縮しており、不眠と中途覚醒が頻繁に生じていた。この睡眠不足は甲状腺ホルモン過剰による精神的興奮状態と身体的症状(頻脈、発汗、振戦)が原因である。現在は軽度の睡眠導入剤(ゾルピデム5mg)を就寝前に使用することで、6時間程度の睡眠が確保できるようになっている。しかし、熟眠感については詳細な評価が不足しており、睡眠の質的な改善についてはさらなる評価が必要である。甲状腺機能亢進症では睡眠の質が低下しやすく、浅い睡眠や易覚醒性が継続している可能性が高い。
日中/休日の過ごし方
A氏は現在休職中であり、入院により日常の生活リズムが大きく変化している。入院前の日中の過ごし方については詳細な情報が不足しているが、甲状腺機能亢進症による易疲労感と睡眠不足により、日中の活動量が制限されていたと推定される。やや早口になる傾向や精神的興奮状態から、落ち着いた休息が困難であった可能性が高い。現在の入院環境では、医療処置や検査、面会等により一定の日課があるが、十分な休息時間の確保が重要である。休日の過ごし方についても具体的な情報が不足しており、趣味や娯楽活動、リラクゼーション方法について詳細な聴取が必要である。甲状腺機能亢進症の症状により、従来の休息方法が困難になっている可能性もある。
睡眠休息上の課題と看護介入
A氏の睡眠休息上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による睡眠障害の改善である。睡眠導入剤の使用により睡眠時間は改善しているが、睡眠の質や熟眠感については十分な評価と改善が必要である。第二に、精神的興奮状態や身体症状(頻脈、発汗、振戦)による睡眠の妨害要因への対応が重要である。第三に、入院環境や治療による生活リズムの変化に対する適応支援が必要である。
看護介入としては、まず睡眠パターンの詳細な評価を行い、入眠時間、睡眠時間、中途覚醒回数、起床時の状態等を記録する必要がある。睡眠の質を評価するため、熟眠感や日中の眠気、疲労感について定期的に聴取する。睡眠環境の整備として、静寂な環境の確保、適切な室温・湿度の維持、照明の調整等を行う。甲状腺機能亢進症による発汗過多への対応として、寝具の調整や室温管理を行い、快適な睡眠環境を提供する。
リラクゼーション技法の指導として、深呼吸法や軽度のストレッチング、音楽療法等を提案し、精神的興奮状態の緩和を図る。カフェインや刺激物の摂取制限について指導し、特に夕方以降の摂取を避けるよう教育する。睡眠導入剤の効果と副作用について観察し、必要に応じて医師と連携して薬物調整を検討する。
生活リズムの調整として、規則的な起床・就寝時間の確立を支援し、日中の適度な活動と夜間の休息のメリハリをつける。易疲労感を考慮した適切な活動と休息のバランスを調整し、過度な刺激や活動を避ける。また、A氏の趣味や娯楽活動、従来のリラクゼーション方法について詳細な聴取を行い、個別性を重視した休息支援計画の立案が必要である。甲状腺機能の改善に伴う睡眠パターンの変化について継続的な観察を行い、段階的な睡眠導入剤の減量についても検討する必要がある。
意識レベル、認知機能
A氏の意識レベルは清明であり、見当識や記憶力に問題は認められていない。しかし、甲状腺機能亢進症による精神的影響として、やや早口になる傾向が観察されており、精神的興奮状態や焦燥感が示唆される。思考の流れは保たれているが、甲状腺ホルモン過剰による中枢神経系への影響により、集中力の低下や注意散漫が生じている可能性がある。認知機能の詳細な評価(MMSE、HDS-R等)は実施されていないが、基本的な認知機能は保持されていると評価される。ただし、甲状腺機能亢進症では不安や抑うつ、易刺激性等の精神症状が出現することがあるため、認知機能への影響について継続的な観察が必要である。
聴力、視力
A氏の聴力に問題は認められておらず、コミュニケーション能力は良好である。視力は両眼とも1.0と良好であるが、甲状腺機能亢進症の特徴的症状である眼球突出が認められている。眼球突出は甲状腺関連眼症の症状であり、視野障害や複視、眼瞼浮腫等の合併症が生じる可能性がある。現在のところ視野障害は認められていないとされているが、詳細な眼科的評価が不足している。眼球突出により角膜の乾燥や外傷のリスクが高まるため、眼の保護と詳細な観察が必要である。また、眼球運動障害や眼瞼の機能異常についても評価が必要である。
認知機能
A氏の基本的な認知機能は保持されており、病気の説明に対する理解力や治療への協力的な姿勢が認められている。しかし、甲状腺機能亢進症による中枢神経系への影響として、集中力や注意力の低下、短期記憶への影響が生じている可能性がある。几帳面で責任感が強い性格特性と完璧主義的傾向があることから、病気による能力低下に対する不安や焦燥感が強い可能性がある。「仕事に早く復帰したい」との発言からも、認知機能の変化に対する不安が推察される。詳細な認知機能評価により、具体的な認知領域への影響を把握する必要がある。
不安の有無、表情
A氏は病気に対する不安と仕事への責任感を強く感じていることが発言から確認されている。「こんなに食べているのに痩せてしまって心配」「仕事に早く復帰したい」との表現から、身体症状への不安と社会復帰への焦りが認められる。甲状腺機能亢進症では不安や焦燥感、易刺激性等の精神症状が出現しやすく、A氏の完璧主義的傾向がこれらの症状を増強している可能性がある。表情については詳細な記録が不足しているが、精神的興奮状態や不安が表情にも現れている可能性がある。手指振戦も不安の身体的表現として捉えることができ、精神的な負担の大きさを示している。
認知知覚機能上の課題と看護介入
A氏の認知知覚機能上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による精神症状(不安、焦燥感、易刺激性)の管理である。病気への不安と仕事復帰への焦りが強く、精神的な負担が大きい状況である。第二に、眼球突出による視覚機能への影響と眼の保護が重要である。第三に、認知機能への影響の詳細な評価と、完璧主義的性格による心理的負担への対応が必要である。
看護介入としては、まず不安の程度や内容について詳細に聴取し、A氏の心理状態を定期的に評価する必要がある。病気や治療に関する正確な情報提供を行い、治療の見通しや予後について説明することで不安の軽減を図る。完璧主義的傾向を考慮し、治療には時間がかかることや段階的な改善について理解を促す。
眼球突出に対しては、眼科的な詳細評価を実施し、視野検査や眼球運動の評価を行う。角膜の保護のため、人工涙液の使用や眼鏡の着用を検討し、眼の乾燥や外傷の予防を図る。認知機能の詳細な評価(MMSE、HDS-R等)を実施し、集中力や記憶力への影響を客観的に評価する。
精神的サポートとして、カウンセリングやリラクゼーション技法の指導を行い、ストレス管理の方法を提供する。家族に対しても病気による精神症状について説明し、理解と協力を促す。また、甲状腺機能の改善に伴う精神症状の変化について継続的な観察を行い、必要に応じて精神科的な介入も検討する必要がある。仕事復帰については、段階的なアプローチの重要性を説明し、焦らずに治療に専念できるよう支援する。
性格
A氏は几帳面で責任感が強く、完璧主義的な傾向を持つ性格である。これらの性格特性は、職業である会計事務員という職種にも適合しており、普段から丁寧で正確な仕事を心がけていることが推察される。しかし、この完璧主義的傾向が現在の病気の状況において、治療効果への過度な期待や回復への焦りを生み出している可能性がある。「仕事に早く復帰したい」との発言からも、責任感の強さと同時に、休職していることへの罪悪感や不安が感じられる。甲状腺機能亢進症による精神症状(易刺激性、焦燥感)が、元来の完璧主義的性格と相互作用し、心理的負担を増大させている可能性が高い。
ボディイメージ
A氏のボディイメージは甲状腺機能亢進症の身体症状により著明に変化している。7kgの体重減少により、従来の体型から大きく変化しており、「こんなに食べているのに痩せてしまって心配」との発言からも、体重減少に対する困惑と不安が強いことが分かる。眼球突出という外見上の変化も、自己のボディイメージに大きな影響を与えている可能性がある。28歳という年齢から、外見への関心も高く、これらの身体的変化が自尊感情や自己受容に影響を与えている可能性が高い。発汗過多により1日2回のシャワー浴が必要な状況も、清潔感や身だしなみへの意識に影響を与えている可能性がある。手指振戦により巧緻性が低下していることも、自己効力感の低下につながっている可能性がある。
疾患に対する認識
A氏は医師からバセドウ病の説明を受け、抗甲状腺薬による治療の必要性については理解を示している。しかし、疾患の慢性経過や長期治療の必要性について十分な理解が得られているかは不明である。2年前に甲状腺機能の軽度異常を指摘されていたが、当時は経過観察のみであったことから、疾患の進行性や重篤性について十分な認識を持っていなかった可能性がある。現在の症状の重篤さ(頻脈、体重減少、眼球突出等)に対して困惑や不安を感じており、疾患受容の過程にあると考えられる。完璧主義的性格により、「完全に治したい」という強い思いがある一方で、治療効果が思うように現れない場合の失望や焦りも懸念される。
自尊感情
A氏の自尊感情は現在の病気により影響を受けている可能性が高い。几帳面で責任感が強い性格により、普段は職業や日常生活において高い自己効力感を持っていたと推測される。しかし、甲状腺機能亢進症による身体症状(易疲労感、手指振戦、体重減少等)により、従来できていたことができなくなり、自己効力感の低下が生じている可能性がある。休職していることへの罪悪感や、周囲への迷惑をかけているという思いが自尊感情を低下させている可能性がある。外見上の変化(体重減少、眼球突出)も自己受容や自信に影響を与えている可能性が高い。一方で、治療に対する協力的な姿勢や前向きな発言からは、基本的な自尊感情は保たれており、回復への意欲が感じられる。
育った文化や周囲の期待
A氏の育った文化的背景や周囲の期待については詳細な情報が不足している。しかし、几帳面で責任感が強い性格や完璧主義的傾向から、家庭や社会環境において「しっかりとした人」「頼りになる人」として期待されてきた可能性が高い。会計事務員という職業選択も、正確性や責任感を重視する価値観の表れと考えられる。両親と同居している状況から、家族との関係性や家庭内での役割についても確認が必要である。現在の病気により、これまで果たしてきた役割や周囲の期待に応えられない状況が、心理的な負担となっている可能性がある。日本の文化的背景において、病気による休職や周囲への迷惑に対する申し訳なさを感じやすい傾向があることも考慮する必要がある。
自己知覚自己概念上の課題と看護介入
A氏の自己知覚自己概念上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による身体変化(体重減少、眼球突出等)がボディイメージと自尊感情に与える影響への対応である。第二に、完璧主義的性格と疾患受容のギャップによる心理的負担の軽減が重要である。第三に、従来の役割や能力の変化に対する自己効力感の維持と再構築が必要である。
看護介入としては、まずA氏の性格特性や価値観について詳細に聴取し、個別性を重視したアプローチを行う必要がある。身体変化に対する不安や困惑について共感的に傾聴し、感情の表出を促す。体重減少や眼球突出等の症状が治療により改善可能であることを説明し、希望を持てるよう支援する。
完璧主義的傾向に対しては、治療には時間がかかることや段階的な改善の重要性について教育し、過度な期待や焦りを軽減する。小さな改善点や前向きな変化に焦点を当て、自己効力感の維持を図る。疾患に対する理解を深めるため、病気の経過や予後について丁寧に説明し、疾患受容を支援する。
自尊感情の維持のため、A氏ができていることや持っている強みに注目し、肯定的な自己認識を促進する。家族や職場等の周囲の期待や文化的背景について詳細に聴取し、心理的負担の要因を明確にする。必要に応じて心理カウンセリングの導入も検討し、専門的な心理的サポートを提供する。また、同じ疾患を持つ患者との交流の機会を提供し、体験の共有による心理的支援も考慮する必要がある。
職業、社会役割
A氏は会計事務所の事務員として勤務していたが、甲状腺機能亢進症の症状悪化により現在は休職中である。会計事務員という職業は正確性と責任感が求められる職種であり、A氏の几帳面で責任感が強い性格に適合した職業選択である。しかし、現在の易疲労感、手指振戦、集中力の低下等の症状により、従来の業務遂行能力が低下している状況である。「仕事に早く復帰したい」との発言からも、職業人としての役割を重要視しており、休職していることに対する責任感や焦りが感じられる。28歳という年齢から、キャリア形成の重要な時期にあり、病気による休職が将来への不安を増大させている可能性がある。社会役割については、職場での位置づけや責任の範囲、同僚との関係性等について詳細な情報が不足している。
家族の面会状況、キーパーソン
A氏は両親と同居しており、母親がキーパーソンとして関わっている。母親は「娘が急に痩せて心配で仕方がない」「きちんと治療を受けて元気になってほしい」と話しており、A氏の病気に対して強い心配と治療への協力的な姿勢を示している。家族全体として完全な回復を強く願っており、医療スタッフとの連携を大切にしたいと表明している。この状況から、家族の結束が強く、A氏に対するサポート体制が整っていることが推察される。しかし、具体的な面会頻度や面会時の様子、父親の関わり方、兄弟姉妹の有無等については詳細な情報が不足している。また、家族の心配が過度になることで、A氏にプレッシャーを与えている可能性についても考慮が必要である。
経済状況
A氏の経済状況については具体的な情報が不足している。会計事務所の事務員として勤務していたことから、一定の収入があったと推測されるが、現在は休職中であり、収入面での影響が懸念される。両親と同居していることから、経済的な支援を受けられる可能性があるが、28歳という年齢から経済的自立への意識も高いと考えられる。病気による医療費の負担や、長期治療に伴う経済的不安についても確認が必要である。健康保険の種類や傷病手当金の申請状況、職場の休職制度等についても詳細な情報収集が必要である。経済的な不安が治療への専念や心理的負担に影響を与える可能性があるため、社会資源の活用についても検討が必要である。
役割関係上の課題と看護介入
A氏の役割関係上の主要な課題は、第一に職業復帰への不安と焦りへの対応である。責任感の強い性格により、休職していることへの罪悪感や職場への迷惑に対する心配が大きい。第二に、家族の期待と心配が A氏に与える心理的影響の管理が重要である。第三に、経済的な不安や将来への懸念に対する支援が必要である。
看護介入としては、まず職場復帰に向けた段階的なアプローチの重要性について説明し、焦らずに治療に専念できるよう支援する必要がある。甲状腺機能亢進症の症状が業務遂行能力に与える影響について詳細に評価し、復職時期や勤務形態について医師と連携して検討する。職場の理解を得るため、病気について適切な情報提供を行うことの重要性を説明する。
家族に対しては、甲状腺機能亢進症の病気の特徴や治療経過について詳細に説明し、理解を深める。家族の心配や期待がA氏にプレッシャーを与えないよう、適切な関わり方について指導する。面会時の様子を観察し、家族関係が治療に与える影響を評価する。家族全体での疾患理解と治療方針の共有を図る。
経済的な側面については、社会保障制度(傷病手当金、医療費助成等)について情報提供を行い、必要に応じて社会福祉士等の専門職への相談を勧める。職場の休職制度や復職支援制度についても確認し、安心して治療に専念できる環境を整える。また、同じ疾患を持つ患者やその家族との交流の機会を提供し、体験の共有による情報収集と心理的支援を図る。
具体的な家族構成や面会状況、経済状況等の詳細な情報収集を継続し、個別性を重視した役割関係の支援計画を立案する必要がある。職場復帰については、産業医や職場の担当者との連携も検討し、段階的な復職プログラムの構築を支援する。
年齢、家族構成、更年期症状の有無
A氏は28歳の女性であり、生殖年齢期にある。更年期にはまだ早い年齢であるが、甲状腺機能亢進症は女性ホルモンの分泌や月経周期に影響を与えることが知られている。甲状腺ホルモンは性ホルモン結合グロブリンの産生を増加させ、エストロゲンやテストステロンの代謝に影響を与える可能性がある。家族構成は両親との同居であるが、パートナーの有無や結婚の予定等については情報が不足している。28歳という年齢から、将来の結婚や妊娠・出産について考慮する時期にあると推測され、甲状腺機能亢進症が生殖機能に与える影響について不安を抱いている可能性がある。
甲状腺機能亢進症では月経異常(月経不順、過少月経、無月経)が高頻度で認められるが、A氏の月経歴や現在の月経状況については詳細な情報が不足している。また、甲状腺機能亢進症は不妊のリスク要因でもあり、将来の妊娠への影響についても懸念される。現在の症状(体重減少、栄養状態の悪化)が性機能や生殖機能に与える影響についても評価が必要である。
性生殖機能上の課題と看護介入
A氏の性生殖機能上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症が月経周期や生殖機能に与える影響の評価と管理である。28歳という生殖年齢期にあり、将来の妊娠・出産への影響について不安を抱いている可能性が高い。第二に、甲状腺機能亢進症と妊娠の関係について適切な情報提供と指導が必要である。第三に、現在の治療薬が将来の妊娠に与える影響についての教育が重要である。
看護介入としては、まず月経歴の詳細な聴取を行い、甲状腺機能亢進症発症前後での月経周期の変化について評価する必要がある。月経量、月経周期、月経時の症状等について定期的に確認し、ホルモンバランスの変化を監視する。甲状腺機能亢進症が月経や妊孕性に与える影響について説明し、適切な治療により改善が期待できることを伝える。
将来の妊娠計画について聴取し、妊娠を希望する場合の注意点や治療方針について医師と連携して説明する。抗甲状腺薬の妊娠への影響や、妊娠中の甲状腺機能管理について情報提供を行う。甲状腺機能が正常化すれば月経周期や妊孕性の改善が期待できることを説明し、治療への動機づけを図る。
パートナーの有無や将来の人生設計について、プライバシーに配慮しながら聴取し、個別性を重視した支援を提供する。性生活や生殖に関する不安や疑問について、安心して相談できる環境を整備する。必要に応じて婦人科的な精査や相談を勧め、専門的な評価と指導を受けられるよう調整する。
また、甲状腺機能の改善に伴う月経周期の変化について継続的な観察を行い、正常化の過程を支援する。栄養状態の改善や体重回復が生殖機能の改善にも寄与することを説明し、包括的な健康管理の重要性を指導する必要がある。
入院環境
A氏は甲状腺機能亢進症の治療のため入院している環境にあり、慣れ親しんだ自宅環境から離れることによるストレスが生じている可能性がある。入院により生活リズムが変化し、プライバシーの制限や医療処置による日常生活の中断等が新たなストレス要因となっている。発汗過多により1日2回のシャワー浴が必要な状況であるが、入院環境でのシャワー利用の制限や他患者との共有等により不便を感じている可能性がある。また、几帳面で完璧主義的な性格により、病院の規則や時間的制約に対してストレスを感じやすい傾向があると推測される。入院環境でのストレス要因や適応状況について詳細な評価が不足している。
仕事や生活でのストレス状況、ストレス発散方法
A氏は現在休職中であるが、「仕事に早く復帰したい」との発言から、職業復帰への強い焦りと責任感によるストレスが認められる。会計事務員という職業は正確性と責任感が求められる職種であり、几帳面で完璧主義的な性格のA氏にとって、仕事は重要なアイデンティティの一部である可能性が高い。休職していることに対する罪悪感や職場への迷惑をかけているという思いが、大きな心理的負担となっている。28歳という年齢から、キャリア形成や将来への不安も加わり、複合的なストレス状況にある。
甲状腺機能亢進症による身体症状(易疲労感、手指振戦、体重減少、眼球突出等)自体も大きなストレス要因となっている。「こんなに食べているのに痩せてしまって心配」との発言からも、自分の身体の変化に対する困惑と不安が強いことが分かる。従来のストレス発散方法や趣味、リラクゼーション法については詳細な情報が不足しており、現在の状況でどのようなコーピング方法を用いているかも不明である。
家族のサポート状況、生活の支えとなるもの
A氏は両親と同居しており、特に母親がキーパーソンとして強いサポートを提供している。母親は「娘が急に痩せて心配で仕方がない」「きちんと治療を受けて元気になってほしい」と話しており、A氏の病気に対して深い心配と治療への協力的姿勢を示している。家族全体として完全な回復を強く願い、医療スタッフとの連携を重視している姿勢から、強固な家族の結束とサポート体制が確認できる。
しかし、家族の強い心配や期待が、逆にA氏にとってプレッシャーとなっている可能性も考慮する必要がある。「元気になってほしい」という家族の願いが、A氏の完璧主義的傾向と相まって、「早く治らなければならない」という強迫的な思いを強化している可能性がある。父親の関わり方や兄弟姉妹の有無、友人関係等についての詳細な情報が不足している。また、A氏にとって生活の支えとなる価値観や信念、趣味等についても確認が必要である。
コーピングストレス耐性上の課題と看護介入
A氏のコーピングストレス耐性上の主要な課題は、第一に甲状腺機能亢進症による身体症状と完璧主義的性格が相互作用して生じる心理的負担の管理である。病気への不安、職業復帰への焦り、身体変化への困惑等、複数のストレス要因が重複している。第二に、家族の期待や心配がプレッシャーとなり、ストレスを増大させている可能性への対応が重要である。第三に、効果的なストレス対処法の確立と、入院環境での適応支援が必要である。
看護介入としては、まずA氏が現在感じているストレスの内容と程度について詳細に聴取し、ストレス要因を明確にする必要がある。甲状腺機能亢進症による精神症状(不安、焦燥感、易刺激性)とストレス反応を区別し、適切な対応を行う。完璧主義的傾向に対しては、治療の段階的な進行や「完璧でなくても良い」という考え方について教育し、心理的負担の軽減を図る。
入院環境への適応支援として、A氏の個別性やプライバシーに配慮した環境調整を行う。発汗過多に対する環境整備(シャワー利用の配慮、室温調整等)を実施し、快適な療養環境を提供する。ストレス発散方法について聴取し、入院中でも実施可能なリラクゼーション法(深呼吸、軽度のストレッチング、音楽鑑賞等)を提案する。
家族に対しては、甲状腺機能亢進症の治療には時間がかかることや、過度な期待がA氏の負担となる可能性について説明する。家族の心配や愛情を適切に表現し、A氏を支えるための効果的な関わり方について指導する。必要に応じて心理カウンセリングの導入を検討し、専門的な心理的支援を提供する。
また、A氏の従来のストレス対処法や生活の支えとなるもの(趣味、価値観、信念等)について詳細に聴取し、個別性を重視したコーピング支援計画を立案する。甲状腺機能の改善に伴うストレス耐性の変化についても継続的に観察し、段階的な支援の調整を行う必要がある。
信仰、意思決定を決める価値観/信念、目標
A氏は特定の宗教的信仰はないとされているが、几帳面で責任感が強く、完璧主義的な傾向を持つ性格から、誠実さや責任感、正確性を重視する価値観を持っていることが推察される。会計事務員という職業選択も、正確性や責任感を重視する価値観の反映と考えられる。「仕事に早く復帰したい」との発言からは、職業人としての責任を果たすことや社会的役割を重要視する価値観が読み取れる。
意思決定においては、論理的で慎重なアプローチを取る傾向があると推測される。病気の治療に対しても医師の説明を理解し、協力的な姿勢を示していることから、科学的根拠に基づいた判断を重視する傾向があると考えられる。しかし、完璧主義的な性格により、「完全に治したい」「完璧な回復」を求める傾向があり、段階的な改善や部分的な回復に対して満足しにくい可能性がある。
A氏の人生目標については詳細な情報が不足しているが、28歳という年齢から、キャリア形成、将来の結婚や家庭形成、経済的安定等が重要な目標となっている可能性が高い。現在の病気により、これらの目標達成への不安や焦りが生じていると考えられる。家族全体が「完全な回復」を強く願い、「医療スタッフとの連携を大切にしたい」と表明していることから、家族の価値観も治療への積極的な取り組みと専門家への信頼を重視する傾向があることが分かる。
価値信念上の課題と看護介入
A氏の価値信念上の主要な課題は、第一に完璧主義的価値観と慢性疾患の現実との間にあるギャップへの対応である。「完全な回復」を求める価値観が、段階的な治療経過や部分的な改善に対する不満や焦りを生み出している可能性がある。第二に、責任感の強さが病気による休職や周囲への迷惑に対する過度な罪悪感を生み出している可能性への対応が重要である。第三に、現在の状況により人生目標の見直しや価値観の再構築が必要となっている可能性がある。
看護介入としては、まずA氏の価値観や人生観、重要視していることについて詳細に聴取し、個別性を重視したアプローチを行う必要がある。完璧主義的価値観に対しては、「完璧でなくても価値がある」「段階的な改善も意味がある」という視点を提供し、柔軟な価値観の形成を支援する。甲状腺機能亢進症の治療は長期間を要し、段階的な改善が特徴であることを説明し、現実的な期待の形成を促す。
責任感の強さを肯定的に評価しつつ、病気は個人の責任ではないこと、適切な治療と休息が最も責任ある行動であることを説明する。職業復帰への焦りに対しては、十分な治療と回復が長期的には最も良い結果をもたらすことを説明し、価値観と治療方針の整合性を図る。
人生目標の見直しについては、病気の経験が新たな価値観や目標を形成する機会となり得ることを説明し、前向きな意味づけを支援する。家族の価値観と本人の価値観の調和を図り、過度なプレッシャーを避けながら支援的な関係性を構築する。
宗教的な背景がない場合でも、精神的な支えとなる価値観や信念について探索し、治療過程での精神的支柱となるものを見つけられるよう支援する。必要に応じてスピリチュアルケアの専門家との連携も検討し、価値観や人生の意味についての深い探索を支援する。また、同じ疾患を持つ患者との交流を通じて、多様な価値観や対処方法に触れる機会を提供し、価値観の柔軟性を促進する必要がある。
看護計画
看護問題
甲状腺機能亢進症に伴う代謝亢進に関連した栄養摂取不足
長期目標
退院時に適正体重(50kg以上)に回復し、血清アルブミン値が基準値内(3.8g/dL以上)となる
短期目標
2週間後に体重1kg以上の増加と血清アルブミン値の改善傾向を示す
≪O-P≫観察計画
・体重の変化を毎日同一時刻に測定する
・食事摂取量と摂取カロリーを詳細に記録する
・血清総蛋白・アルブミン値の推移を確認する
・BMIの変化を週1回算出する
・上腕周囲径や下腿周囲径の測定を週1回実施する
・皮膚の張りや筋肉量の変化を観察する
・浮腫の有無と程度を確認する
・口腔内の状態と嚥下機能を観察する
・便の性状と排便回数を記録する
・発汗量と水分出納バランスを評価する
・甲状腺機能検査値の変化を確認する
・食欲の程度と食事への意欲を観察する
≪T-P≫援助計画
・高カロリー・高蛋白食を提供し摂取を促進する
・間食や栄養補助食品の提供を行う
・食事環境を整備し快適な摂食を支援する
・適切な食事時間の確保と見守りを実施する
・水分摂取量の調整と脱水予防を行う
・口腔ケアを実施し摂食機能を維持する
・体位変換や軽度な運動により消化機能を促進する
・室温調整により発汗による栄養素の損失を軽減する
・医師と連携し栄養剤の投与を検討する
・薬物療法の効果により代謝状態の改善を図る
・安静度を調整し過度なエネルギー消費を防ぐ
・ストレス軽減により食欲低下を予防する
≪E-P≫教育・指導計画
・甲状腺機能亢進症における栄養の重要性について説明する
・高カロリー・高蛋白食の必要性と食品選択について指導する
・ヨウ素制限食の内容と注意点について教育する
・適切な水分摂取量と摂取方法について説明する
・体重測定の方法と自己管理の重要性について指導する
・退院後の食事計画と栄養管理について家族を含めて教育する
看護問題
甲状腺機能亢進症に伴う頻脈・易疲労感に関連した活動耐性低下
長期目標
退院時に心拍数90回/分以下で安定し、日常生活動作が自立して行える
短期目標
2週間後に軽度な活動時の心拍数上昇が120回/分以下に抑制される
≪O-P≫観察計画
・安静時と活動時の心拍数・血圧・呼吸数を測定する
・活動時の動悸や息切れの程度を観察する
・手指振戦の程度と日常生活への影響を確認する
・易疲労感の程度と持続時間を評価する
・睡眠時間と睡眠の質を観察する
・活動量と活動時間の変化を記録する
・転倒リスクと歩行状態を評価する
・顔色や表情の変化を観察する
・発汗の程度と体温を確認する
・血液データ(ヘモグロビン値)の変化を確認する
・甲状腺機能検査値の推移を評価する
・薬物療法の効果と副作用を観察する
≪T-P≫援助計画
・活動と休息のバランスを調整し段階的な活動量増加を図る
・心拍数に応じた活動制限を実施する
・移動時の付き添いや見守りを提供する
・環境整備により安全な活動環境を確保する
・深呼吸やリラクゼーション技法により症状緩和を図る
・適切な室温調整により発汗と心拍数上昇を軽減する
・十分な睡眠時間を確保し疲労回復を促進する
・軽度なストレッチングや関節可動域訓練を実施する
・薬物療法の確実な実施により症状改善を図る
・水分補給により脱水による心拍数上昇を予防する
・ストレス軽減により交感神経刺激を抑制する
・必要時には車椅子移動や介助を提供する
≪E-P≫教育・指導計画
・甲状腺機能亢進症による循環器症状について説明する
・活動時の注意点と危険な症状について指導する
・段階的な活動量増加の重要性について教育する
・自己でのバイタルサイン測定方法について指導する
・疲労時の休息の取り方について説明する
・職場復帰に向けた段階的なアプローチについて家族を含めて教育する
看護問題
甲状腺機能亢進症に伴う身体症状・休職に関連した不安
長期目標
退院時に疾患を受容し、治療継続と職場復帰への見通しを持てる
短期目標
2週間後に不安の程度が軽減し、治療に前向きに取り組める
≪O-P≫観察計画
・不安の程度と内容を定期的に聴取する
・表情や行動の変化を観察する
・睡眠パターンと睡眠の質を確認する
・食欲や食事摂取への影響を観察する
・家族との関係性と面会時の様子を確認する
・治療への参加意欲と理解度を評価する
・職場復帰への焦りや不安の程度を聴取する
・身体症状への反応と受容状況を観察する
・ストレス症状の有無と程度を確認する
・コミュニケーションの変化を観察する
・気分の変動と感情表出の状況を評価する
・社会復帰への意欲と現実認識を確認する
≪T-P≫援助計画
・傾聴により不安や心配事の表出を促進する
・共感的な態度で接し心理的支持を提供する
・リラクゼーション技法や深呼吸法を指導する
・静かで落ち着いた環境を提供する
・家族との面会時間を確保し情緒的支援を促進する
・治療効果の改善点を具体的に伝え希望を持たせる
・個別性を尊重した関わりを継続する
・必要時には心理カウンセラーとの面談を調整する
・同疾患患者との交流機会を提供する
・趣味や娯楽活動により気分転換を図る
・段階的な目標設定により達成感を促進する
・プライバシーを配慮した相談環境を整備する
≪E-P≫教育・指導計画
・甲状腺機能亢進症の病態と治療経過について詳しく説明する
・身体症状の改善可能性と治療効果について教育する
・治療には時間がかかることと段階的改善について説明する
・職場復帰の時期と方法について現実的な計画を説明する
・ストレス管理方法と対処技術について指導する
・家族に対して病気の理解と適切な支援方法について教育する
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
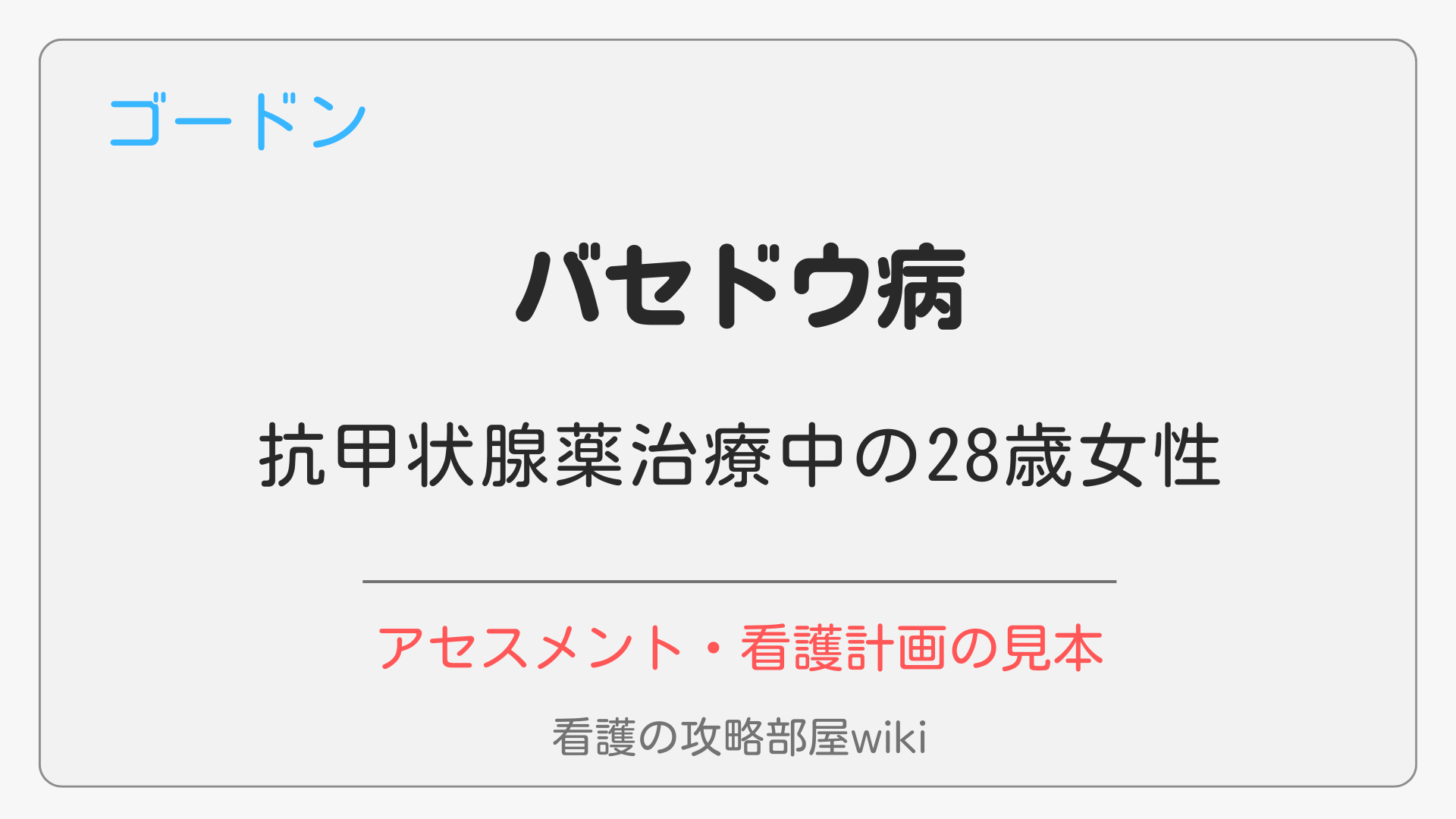
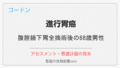
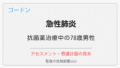
コメント