事例の要約
自宅の階段から転落し右大腿骨遠位骨折を受傷した60代男性患者の事例。入院当日に観血的骨接合術を受け、術後の疼痛管理・感染予防・早期離床を目標に看護介入を行っている。創部の治癒は良好だが、リハビリテーションへの意欲低下がみられ、退院後の生活への不安を抱えている状態である。介入日は術後10日目の5月15日(入院14日目)で、患者のADL拡大と退院支援に焦点を当てた看護計画の評価・修正を行う時期である。
基本情報
A氏は65歳の男性で、身長170cm、体重68kg(BMI 23.5)である。家族構成は妻(63歳)と二人暮らしで、キーパーソンは妻である。職業は定年退職後も建築会社で現場監督として週3日勤務していた。性格は几帳面で真面目、自分のことは自分でやりたいという自立心が強い性格である。感染症はなく、アレルギーは花粉症がある程度である。認知機能に問題はなく、意思疎通は良好である。
病名
右大腿骨遠位骨折(AO分類 33-A2)に対して観血的骨接合術(遠位大腿骨ロッキングプレート固定術)を施行した。
既往歴と治療状況
高血圧症で10年前から内服治療中であり、血圧は概ね良好にコントロールされている。5年前に脊柱管狭窄症と診断されたが、保存的治療で経過観察中である。また、3年前から脂質異常症の治療も開始している。いずれも定期的に近医を受診し、薬物療法を継続している。
入院から現在までの情報
5月1日、自宅玄関の階段(5段)から転落し、右膝に強い痛みを感じて動けなくなったため救急搬送された。X線検査で右大腿骨遠位骨折と診断され、同日緊急入院となった。翌日の5月2日に観血的骨接合術が施行された。術後は創部の経過は良好で感染兆候はないが、疼痛により安静時間が長く、リハビリに対する意欲の低下がみられた。術後3日目から理学療法士による介入が開始され、現在は平行棒内歩行訓練まで進んでいるが、右下肢への荷重制限(1/3部分荷重)があるため歩行器使用での移動となっている。退院後の生活や職場復帰に対して不安を表出しており、妻も介護に不安を感じている。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、血圧158/95mmHg、脈拍96回/分、体温36.8℃、呼吸数20回/分、SpO2 98%(room air)であった。疼痛スコアはNRS(Numerical Rating Scale)で8/10と高値を示していた。
現在(介入日)のバイタルサインは、血圧132/78mmHg、脈拍78回/分、体温36.5℃、呼吸数18回/分、SpO2 97%(room air)と安定している。疼痛スコアは安静時NRS 2/10、動作時NRS 4/10と改善している。
食事と嚥下状態
入院前は3食規則正しく摂取していた。妻の作る和食中心の食事で、時々外食を楽しんでいた。喫煙歴は20本/日×45年あるが、5年前に禁煙している。飲酒は週3回程度、ビール350ml缶を1~2本程度であった。嚥下状態に問題はない。
現在は病院食を全量摂取できている。水分摂取量は1000~1200ml/日程度である。入院による環境変化のストレスから、時に食欲低下がみられることがある。禁酒・禁煙は守れている。
排泄
入院前は1日1~2回の排便習慣があり、便性状は普通便であった。排尿は日中5~6回、夜間1回程度であった。
入院後は活動量の低下と環境変化により、排便が3日に1回程度となっている。看護師の勧めで酸化マグネシウム330mg×3回/日を内服し、排便コントロールを行っている。排尿は日中6~7回、夜間1~2回で、尿量は1500ml/日程度である。術後は尿器・ポータブルトイレを使用していたが、現在は歩行器使用でトイレまで移動し排泄できている。
睡眠
入院前は就寝時間22時、起床時間6時で、睡眠時間は7~8時間程度であった。特に睡眠に関する問題はなかった。
入院後は環境の変化や術後疼痛により入眠困難がみられ、眠剤(ゾルピデム5mg)を就寝前に服用している。現在は疼痛が軽減し、夜間の覚醒回数も減少しているが、リハビリへの不安から時折眠れない日があるという。睡眠時間は6~7時間程度である。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼があり、読書時には老眼鏡を使用している。聴力は問題なく、会話に支障はない。右下肢の術創部周囲に軽度の知覚鈍麻がある。コミュニケーションは良好で、質問に対して的確に応答できる。特定の宗教的信仰はない。
動作状況
歩行は入院前は自立していたが、現在は歩行器を使用し、右下肢1/3部分荷重制限のある状態で10m程度の歩行が可能である。移乗は見守りで行えている。排尿・排泄は歩行器使用でトイレまで移動し自立している。入浴は現在シャワー浴のみで、看護師の介助を要する。衣類の着脱は上半身は自立、下半身はズボンの着脱に介助を要する。転倒歴は今回の受傷前にはなかった。
内服中の薬
- オルメサルタン 20mg 1錠 朝食後(高血圧症治療薬)
- アトルバスタチン 10mg 1錠 夕食後(脂質異常症治療薬)
- ロキソプロフェン 60mg 1錠 疼痛時 頓服(非ステロイド性抗炎症薬)
- セレコキシブ 100mg 2錠 朝・夕食後(選択的COX-2阻害薬)
- アセトアミノフェン 500mg 1錠 1日3回 毎食後(解熱鎮痛薬)
- 酸化マグネシウム 330mg 1錠 1日3回 毎食後(便秘薬)
- ランソプラゾール 15mg 1カプセル 朝食後(胃粘膜保護薬)
- ゾルピデム 5mg 1錠 就寝前 不眠時(睡眠導入剤)
服薬状況
入院前は自己管理で内服できていたが、現在は看護師管理となっている。疼痛時の頓服薬については、A氏から訴えがあった際に看護師が確認して与薬している。退院に向けて、内服薬の理解度チェックを行ったところ、薬の名前と用途について理解できているが、食後薬・就寝前薬の区別については時々混乱がみられる。そのため、一包化した状態での退院を検討中である。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時(5月1日) | 最近(5月13日) |
|---|---|---|---|
| <血算> | |||
| WBC | 3.5-9.0×10³/μL | 10.8×10³/μL | 7.2×10³/μL |
| RBC | 4.2-5.5×10⁶/μL | 4.5×10⁶/μL | 4.2×10⁶/μL |
| Hb | 13.5-17.0g/dL | 14.2g/dL | 12.8g/dL |
| Ht | 40.0-50.0% | 42.5% | 38.5% |
| Plt | 15-35×10⁴/μL | 22.5×10⁴/μL | 24.8×10⁴/μL |
| <生化学> | |||
| TP | 6.5-8.2g/dL | 7.2g/dL | 6.8g/dL |
| Alb | 3.8-5.2g/dL | 4.1g/dL | 3.9g/dL |
| T-Bil | 0.2-1.2mg/dL | 0.8mg/dL | 0.7mg/dL |
| AST | 10-40U/L | 25U/L | 22U/L |
| ALT | 5-45U/L | 30U/L | 25U/L |
| LDH | 120-240U/L | 210U/L | 185U/L |
| ALP | 100-325U/L | 245U/L | 230U/L |
| γ-GTP | 0-75U/L | 42U/L | 38U/L |
| BUN | 8-20mg/dL | 18.5mg/dL | 17.2mg/dL |
| Cre | 0.6-1.1mg/dL | 0.9mg/dL | 0.8mg/dL |
| eGFR | ≥60mL/min | 72mL/min | 74mL/min |
| Na | 135-145mEq/L | 138mEq/L | 140mEq/L |
| K | 3.5-5.0mEq/L | 4.2mEq/L | 4.0mEq/L |
| Cl | 98-108mEq/L | 102mEq/L | 103mEq/L |
| Ca | 8.5-10.5mg/dL | 9.2mg/dL | 9.0mg/dL |
| CRP | 0-0.3mg/dL | 5.8mg/dL | 0.8mg/dL |
| <凝固系> | |||
| PT-INR | 0.85-1.15 | 1.02 | 1.05 |
| APTT | 25-40秒 | 32秒 | 30秒 |
| <脂質> | |||
| T-Cho | 130-219mg/dL | 185mg/dL | 178mg/dL |
| HDL-C | 40-80mg/dL | 45mg/dL | 48mg/dL |
| LDL-C | 70-139mg/dL | 142mg/dL | 120mg/dL |
| TG | 30-149mg/dL | 165mg/dL | 130mg/dL |
| <血糖関連> | |||
| 空腹時血糖 | 70-109mg/dL | 118mg/dL | 105mg/dL |
| HbA1c | 4.6-6.2% | 5.8% | 5.7% |
今後の治療方針と医師の指示
整形外科医の評価では、術後の骨癒合は順調に進んでおり、創部の状態も良好である。今後はリハビリテーションの強化を中心とした治療方針となっている。現在の右下肢1/3部分荷重は、術後2週間(5月16日)から1/2部分荷重へと変更予定である。その後、X線検査で骨癒合の状態を評価しながら、2週間ごとに荷重量を増やしていく計画である。全荷重は術後6週間後(約4週間後)を目標としている。退院は術後3週間目(5月23日頃)を予定しており、それまでに歩行器での移動が安定し、基本的なADLが自立していることが条件となっている。退院後は週2回の外来リハビリと、自宅でのセルフエクササイズを継続する必要がある。また、6ヶ月間は高所作業や転倒リスクの高い活動は禁止されている。職場復帰については、デスクワーク中心であれば術後2ヶ月後から可能と判断されているが、現場監督業務については術後3〜4ヶ月後と説明されている。退院時は疼痛コントロールのための内服薬を処方し、外来での定期的なフォローアップを継続する予定である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「早く元の生活に戻りたい」と頻繁に発言しており、リハビリに対して前向きな姿勢を見せることもあるが、進捗の遅さにイライラする様子も見られる。特に「このペースでは仕事に戻れるのか」と不安を抱えており、時折「自分はもう役に立たない」と落ち込む場面もある。リハビリの際には「痛みがあるからできない」と消極的になることがあり、看護師や理学療法士の励ましが必要な状況である。退院後の生活については「妻に負担をかけたくない」という思いが強く、自立への意欲は高い。
妻は毎日面会に訪れ、A氏の回復を心配している。「主人は頑固で自分でやりたがるので、無理をさせないか心配です」と看護師に相談することがある。また、「自宅は階段が多いので、帰ってからの生活が不安です」と住環境に対する懸念も表明している。一方で「私ができるサポートは何でもします」と協力的な姿勢を示しており、退院指導にも熱心に参加している。最近では「リハビリの自宅での続け方」や「転倒予防のための環境整備」について積極的に質問するようになっている。二人の会話からは、お互いを思いやる気持ちと早期回復への願いが感じられる。
アセスメント
A氏は右大腿骨遠位部骨折という下肢の長管骨末端部の骨折であり、観血的骨接合術によるプレート固定術が施行されている。この骨折は高齢者に多く、転倒などの外傷によって生じることが多い。A氏の場合も階段からの転落という外的要因によって受傷しており、典型的な受傷機転である。治療後は骨癒合までの期間、荷重制限があり、リハビリテーションによる機能回復が重要となる。
A氏は65歳の男性で、受傷前は定年退職後も建築会社で現場監督として週3日勤務するなど、社会的に活動的な生活を送っていた。BMIは23.5と標準的な体格であり、定期的な運動習慣については明確な情報がないが、職業柄、一定の身体活動量は確保されていたと推測される。高血圧症、脊柱管狭窄症、脂質異常症の既往があり、各疾患に対して薬物療法を受けている。これらの慢性疾患は骨折の直接的な原因ではないものの、特に脊柱管狭窄症は歩行時のふらつきをもたらす可能性があり、転倒リスクを高める要因となりうる。また、高齢に伴う筋力低下や反射機能の減退も転倒の背景にあると考えられる。
健康管理に関しては、定期的に近医を受診し、慢性疾患のコントロールを継続してきたことから、健康への意識は比較的高いと判断できる。喫煙歴は20本/日×45年とヘビースモーカーであったが、5年前に禁煙に成功しており、健康への取り組みがうかがえる。飲酒は週3回程度のビール350ml缶を1~2本と適度な量であり、現在は入院に伴い禁酒している。花粉症のアレルギーがあるが、呼吸器系への大きな影響はないようである。
入院前の服薬管理は自己管理であったが、現在は看護師管理となっている。退院に向けて内服薬の理解度を確認したところ、薬の名前と用途については理解できているが、服用タイミングについては混乱がみられることがある。このことから、服薬管理能力に若干の低下がみられ、退院後の服薬アドヒアランスに注意が必要である。一包化による管理方法の検討は適切であり、退院後の服薬状況を確認する仕組みも必要である。
検査データからは、入院時のCRPが5.8mg/dLと炎症反応が上昇していたが、最近の検査では0.8mg/dLと改善傾向にあり、術後の回復過程として良好であることがわかる。また、LDL-Cが入院時142mg/dLと基準値を超えていたが、治療により120mg/dLと改善している。Hbは入院時14.2g/dLから最近12.8g/dLと軽度低下しており、手術による出血の影響と考えられるが、貧血症状の有無を確認し、必要に応じて鉄分摂取の指導が必要である。
現在のA氏は「早く元の生活に戻りたい」という思いが強く、回復への意欲はあるものの、進捗の遅さにいらだつ様子もみられる。これは自己の健康状態や回復過程への理解が不十分である可能性を示唆している。特にリハビリテーションへの参加が消極的になる場面があり、痛みを理由に活動を制限する傾向がある。このことから、疼痛管理の強化と並行して、リハビリテーションの必要性や骨折の回復過程についての理解を促進する教育的介入が重要である。
また、A氏は「自分はもう役に立たない」と発言することがあり、自己効力感の低下がうかがえる。これは回復の妨げとなる可能性があるため、小さな進歩を認め、肯定的なフィードバックを提供することで自己効力感を高める支援が有効である。同時に、退院後の生活への不安や仕事復帰への懸念に対しては、具体的な見通しや段階的な活動拡大の計画を示すことが安心感につながる。
妻からは「主人は頑固で自分でやりたがる」という情報があり、A氏の自立心の強さがうかがえる。これは回復の原動力となる一方で、過度な活動による二次的な損傷のリスクも考えられる。そのため、安全な活動範囲の明確な指示と、無理をしないことの重要性を繰り返し説明する必要がある。
以上のことから、A氏の健康知覚-健康管理に関しては、慢性疾患の自己管理能力の強化、骨折の回復過程と治療方針の理解促進、適切な活動と休息のバランスの確立、および退院後の生活における健康管理計画の具体化が看護介入の焦点となる。また、妻を含めた家族の協力体制を整え、退院後の生活環境の調整や転倒予防策の実施についても支援する必要がある。
A氏は身長170cm、体重68kg、BMI 23.5と標準的な体格である。65歳男性の基礎代謝量は約1300〜1400kcal/日程度と推定され、入院前は建築現場監督として週3日勤務していたことから、身体活動レベルは中程度(PAL 1.75前後)であったと考えられる。そのため、入院前の必要エネルギー量は約2200〜2500kcal/日程度と推測される。しかし、現在は手術後の回復期であり、活動量が著しく低下していることから、必要エネルギー量は1800〜2000kcal/日程度に減少していると考えられる。
入院前の食事摂取状況は、妻の作る和食中心の食事を3食規則正しく摂取していた。嗜好や食事に関するアレルギーの情報は不足しているため、今後の栄養指導や食事提供の参考とするために、好みの食品や避けている食品について情報収集する必要がある。現在は病院食を全量摂取できており、栄養摂取状態は概ね良好と判断できる。しかし、入院による環境変化のストレスから時に食欲低下がみられる点には注意が必要である。水分摂取量は1000〜1200ml/日程度であるが、術後の回復や便秘予防の観点から、水分摂取の増加を促す必要がある。嚥下機能に問題はなく、経口摂取は安全に行えている。口腔内の状態や口腔ケアの状況については情報が不足しているため、評価を行い、必要に応じて口腔ケアの指導を行うことが重要である。
血液データでは、アルブミン値は3.9g/dLと標準範囲内であり、急性期の侵襲による影響はあるものの栄養状態は維持されていると判断できる。総タンパク質も6.8g/dLと基準値内である。ヘモグロビン値は入院時14.2g/dLから最近12.8g/dLへと低下しており、ヘマトクリット値も42.5%から38.5%へと減少している。これは手術による出血や侵襲の影響と考えられるが、貧血の進行を予防するために、鉄分を含む食品の摂取を勧めることが望ましい。電解質は、ナトリウム140mEq/L、カリウム4.0mEq/Lと正常範囲内にあり、水分電解質バランスは保たれている。
空腹時血糖は入院時118mg/dLと軽度高値を示していたが、最近では105mg/dLと改善しており、HbA1cは5.7%と正常範囲内である。しかし、高齢者では糖代謝機能が低下している可能性があるため、継続的な血糖値のモニタリングが必要である。中性脂肪は入院時165mg/dLと高値であったが、最近では130mg/dLと改善傾向にあり、総コレステロールも正常範囲内である。LDLコレステロールは入院時142mg/dLと高値であったが、治療により120mg/dLまで低下している。脂質異常症の既往があることから、食事内容については特に脂質摂取量や質に注意する必要がある。
皮膚の状態については、術創部の状態は良好で感染兆候はないと記載されているが、褥瘡の有無や皮膚の乾燥状態、浮腫の有無についての具体的情報が不足している。特に術後の活動量低下や同一体位の持続により褥瘡リスクが高まるため、褥瘡リスクアセスメントを実施し、予防的ケアを継続することが重要である。また、術後疼痛による活動制限があることから、同一体位による圧迫部位の観察と体位変換、除圧の指導が必要である。
消化器症状については、特に嘔気や嘔吐の記載はないが、鎮痛薬の使用により胃腸障害が生じる可能性があるため、胃部不快感の有無を定期的に確認することが望ましい。また、排便状況は活動量低下と環境変化により3日に1回程度となっており、酸化マグネシウムによる排便コントロールが行われている。便秘は栄養吸収に影響を与えるだけでなく、腹部膨満感から食欲低下を招く可能性があるため、水分摂取の促進や食物繊維の摂取など、薬物療法以外の便秘対策も検討する必要がある。
今後のリハビリテーション強化に伴い、エネルギー消費量は増加することが予想される。そのため、タンパク質を中心とした栄養素の適切な摂取が骨折の治癒や筋力の回復に重要となる。特に高齢者では加齢に伴う消化吸収機能の低下や代謝機能の変化により、若年者と比較して栄養素の利用効率が低下している可能性がある。このため、質の高いタンパク質や微量栄養素(カルシウム、マグネシウム、ビタミンD)の摂取を意識した食事指導が必要である。
退院後の食事管理においては、骨折の治癒を促進するための栄養摂取に加え、既往症である高血圧症や脂質異常症の管理も重要となる。塩分制限や脂質摂取の質と量のコントロールなど、複数の疾患を考慮した総合的な食事指導を行い、妻にも協力を依頼することが望ましい。A氏の「早く元の生活に戻りたい」という希望を支援するためにも、回復に必要な栄養素の重要性を説明し、食事への関心と意欲を高める働きかけが必要である。
A氏の排泄状況について、入院前は1日1~2回の排便習慣があり、便性状は普通便であった。排尿は日中5~6回、夜間1回程度であった。しかし入院後は活動量の低下と環境変化により、排便頻度が3日に1回程度と減少している。この便秘傾向に対し、酸化マグネシウム330mg×3回/日を内服し排便コントロールを行っているが、下剤に依存した排便パターンとなっていることは注意すべき点である。便秘は高齢者に多く見られる症状であり、特に65歳のA氏は加齢に伴う腸管の蠕動運動の低下、腹筋力の減弱、神経伝達機能の変化などが影響している可能性がある。また手術後の疼痛による活動制限や、オピオイド系鎮痛薬の使用(セレコキシブ、アセトアミノフェン)も便秘を助長する要因となっている。腹部膨満感や腸蠕動音については情報が不足しているため、排便アセスメントの一環として評価する必要がある。
排尿に関しては、日中6~7回、夜間1~2回で尿量は1500ml/日程度である。術後は尿器・ポータブルトイレを使用していたが、現在は歩行器使用でトイレまで移動し排泄できており、排尿の自立度は高い。バルーンカテーテルは使用していない。尿の性状については情報が不足しているため、尿混濁の有無や色調など、尿路感染症のリスク評価のためにも観察する必要がある。また、高齢男性では前立腺肥大による排尿障害が現れやすいため、排尿時の違和感や残尿感などの自覚症状についても確認することが望ましい。
水分摂取量は1000~1200ml/日とやや少なめであり、排便・排尿機能を促進するためには不十分である可能性がある。高齢者は口渇中枢の感受性低下により自発的な水分摂取が減少しがちであることを考慮し、意識的な水分補給を促す必要がある。特に下剤使用中であることから、脱水予防と排便促進の両面から水分摂取量を1500~1800ml/日程度に増やすことが望ましい。In-outバランスについては詳細な情報がないが、尿量1500ml/日に対して水分摂取量1000~1200ml/日であることから、不感蒸泄も含めると体内の水分バランスは負に傾いている可能性がある。体重変化や皮膚の乾燥状態、舌の湿潤度などから水分バランスを評価することも重要である。
血液データでは、BUN 17.2mg/dL、Cre 0.8mg/dL、eGFR 74mL/minと腎機能は正常範囲内にあり、排泄機能の顕著な低下は認められない。しかし高齢者では加齢に伴う腎機能の生理的低下(ネフロン数の減少、糸球体濾過率の低下)があることを考慮し、薬物療法の影響や脱水による腎機能への負担を最小限にするよう注意が必要である。
安静度に関しては、現在は歩行器を使用し右下肢1/3部分荷重制限のある状態で10m程度の歩行が可能である。この活動制限は腸管蠕動の低下を招き、便秘を悪化させる要因となっている。リハビリテーションの進捗に合わせた活動量の増加は、排便機能の改善にもつながると期待される。術後2週間目(5月16日)から右下肢1/2部分荷重へと変更予定であり、荷重量の増加とともに活動範囲も拡大することで、腸管機能の改善も見込まれる。
排便促進のためには、食物繊維の摂取量についても評価する必要がある。現在の食事内容における食物繊維量は不明であるが、便秘傾向にあることから不足している可能性がある。日本人の食事摂取基準によれば、65歳以上の男性の食物繊維推奨量は21g/日以上であるが、入院食でこの量を確保できているか確認し、必要に応じて食物繊維を多く含む食品の摂取を勧めることが望ましい。
看護介入としては、まず水分摂取量の増加を促すために、日中の活動時間帯に小まめに水分を提供する、好みの飲み物を把握して提供するなどの工夫が必要である。また、リハビリテーションの時間以外にも、病棟内での活動量を増やすために、ベッドサイドでの簡単な運動や、可能な範囲での自立した日常生活活動を促すことが有効である。排便については、トイレでの自然排便を促すために、毎日決まった時間にトイレに座る習慣をつけることや、腹部マッサージの指導も考慮すべきである。
退院に向けては、薬剤に依存しない自然な排便パターンの確立を目指し、下剤の調整を行いながら、水分摂取、食物繊維摂取、活動量確保の重要性について患者教育を行うことが重要である。また妻にも協力を依頼し、退院後の生活において継続可能な排泄管理方法を一緒に検討することが望ましい。
A氏は右大腿骨遠位骨折に対して観血的骨接合術を受けた65歳男性である。入院前は建築会社で現場監督として週3日勤務しており、職業上一定の身体活動量があったと推測される。しかし、特定の運動習慣についての情報は不足しているため、日常的な運動の種類、頻度、強度について確認する必要がある。
現在の活動状況は、術後のリハビリテーションにより、歩行器を使用し右下肢1/3部分荷重制限のある状態で10m程度の歩行が可能である。移乗は見守りで行えており、排泄は歩行器使用でトイレまで移動し自立している。しかし入浴はシャワー浴のみで看護師の介助を要し、更衣に関しては上半身は自立しているが下半身のズボンの着脱には介助が必要である。これらの状況から、ADLは部分介助レベルであり、特に下肢の機能制限による影響が大きい。医師の指示では、術後2週間(5月16日)から右下肢1/2部分荷重へと変更予定であり、その後X線検査で骨癒合の状態を評価しながら2週間ごとに荷重量を増やしていく計画である。全荷重は術後6週間後(約4週間後)を目標としている。
バイタルサインは現在、血圧132/78mmHg、脈拍78回/分、体温36.5℃、呼吸数18回/分、SpO2 97%(room air)と安定している。高血圧の既往があるものの、内服治療により良好にコントロールされている。呼吸機能については特記すべき問題はないが、長期喫煙歴(20本/日×45年)があるため、潜在的な呼吸機能低下の可能性に注意する必要がある。特に術後の臥床による肺合併症リスクを考慮し、深呼吸や咳嗽練習などの呼吸機能維持のためのケアが重要である。
血液データでは、赤血球数4.2×10⁶/μL、ヘモグロビン12.8g/dL、ヘマトクリット38.5%といずれも基準値下限に近い値を示している。これは手術による出血の影響と考えられるが、リハビリテーションの強化に伴う活動量増加を考慮すると、軽度の貧血が活動耐性に影響を及ぼす可能性がある。CRPは入院時5.8mg/dLから現在0.8mg/dLへと改善しており、炎症反応は沈静化傾向にある。しかし依然として基準値(0.3mg/dL以下)を超えているため、創部の状態や全身状態の継続的な観察が必要である。
転倒転落リスクについては、複数の危険因子が存在する。まず65歳という年齢自体が転倒リスクを高める要因であり、加齢に伴う筋力低下、バランス能力の低下、反応時間の遅延などが影響している可能性がある。また既往歴として脊柱管狭窄症があり、これは下肢のしびれや脱力感を引き起こし、歩行の不安定性をもたらす可能性がある。さらに現在の右下肢の荷重制限や歩行器使用による歩行パターンの変化、移動能力の制限も転倒リスクを高めている。特に術後の疼痛(動作時NRS 4/10)は動作の円滑性を妨げ、思わぬ動きによるバランス崩しを招く恐れがある。服用中の薬剤(降圧剤、睡眠導入剤)も転倒リスクを高める要因となる。これらの多角的な転倒リスク要因を考慮した予防的ケアが不可欠である。
住居環境については、妻の「自宅は階段が多い」という発言から、退院後の生活環境に転倒リスクがあることが推測される。しかし住居の構造や段差、手すりの有無、生活空間の配置など、詳細な環境アセスメントが不足しているため、退院支援計画の一環として住環境評価を行い、必要に応じた環境調整や福祉用具の導入を検討する必要がある。
看護介入としては、まず転倒予防のための環境整備が重要である。ベッド周囲の整理整頓、移動経路の確保、適切な照明の確保などの基本的な環境調整に加え、ナースコールの適切な配置と使用方法の指導が必要である。また、歩行器の正しい使用方法や安全な移動技術についての教育も重要である。特にA氏は「自分でやりたがる」という自立心の強さがあるため、無理のない範囲での活動と、必要時には援助を求めることの重要性を繰り返し説明する必要がある。
リハビリテーションに関しては、「痛みがあるからできない」と消極的になることがあるため、効果的な疼痛管理と並行して、リハビリテーションの目的や進捗状況の共有により、モチベーションを高める支援が重要である。特に短期的な目標を設定し、達成感を味わえるような関わりが効果的である。例えば、歩行距離の段階的な延長や、ADLの自立度向上など、具体的な目標設定が有効である。
また、入院による活動量低下は筋力低下や関節拘縮をもたらす可能性があるため、リハビリテーション以外の時間においても、ベッド上での可能な範囲の運動(健側の関節可動域訓練、等尺性筋収縮訓練など)を指導し、廃用症候群の予防を図ることが重要である。特に高齢者は短期間の活動制限でも著しい筋力低下が生じやすいため、早期からの介入が必須である。
退院に向けては、自宅環境に適応するための具体的な動作訓練(階段の昇降、不安定な路面での歩行など)を取り入れることや、自宅での継続的な運動プログラムの指導も重要である。また、妻を含めた家族への指導も必要であり、特に移動介助の方法や転倒時の対応、環境調整のポイントなどについて、具体的な情報提供を行うことが望ましい。
A氏の睡眠パターンは入院前後で変化がみられている。入院前は就寝時間22時、起床時間6時で、睡眠時間は7~8時間程度であり、特に睡眠に関する問題はなかった。一般的に成人の睡眠必要量は7~8時間とされているため、入院前のA氏の睡眠時間は適切であったと考えられる。しかし入院後は環境の変化や術後疼痛により入眠困難がみられている。高齢者は加齢に伴う睡眠構造の変化(深睡眠の減少、中途覚醒の増加、睡眠効率の低下)があり、65歳のA氏においても生理的な睡眠の質の低下が存在する可能性がある。それに加えて、入院環境特有の要因(騒音、照明、ケアによる中断など)や疼痛による影響が重なり、睡眠障害が生じていると考えられる。
現在はゾルピデム5mgを就寝前に服用しており、薬物療法に依存した睡眠パターンとなっている。ゾルピデムは非ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤であり、依存性は比較的低いとされているが、高齢者では薬物の代謝・排泄機能が低下しているため、日中の残存効果(ふらつき、認知機能低下など)に注意が必要である。特に転倒リスクの高いA氏においては、睡眠薬の影響による転倒リスク増大の可能性を考慮した観察が重要である。
現在の睡眠時間は6~7時間程度であり、入院前と比較するとやや短縮している。また「リハビリへの不安から時折眠れない日がある」という発言から、心理的要因による睡眠障害も存在していることがわかる。特に「早く元の生活に戻りたい」「このペースでは仕事に戻れるのか」という将来への不安が、就寝時の思考活動を活性化させ、入眠を妨げている可能性がある。熟眠感についての具体的な情報は不足しているが、心理的ストレスや疼痛による睡眠の質の低下が予測される。
日中の過ごし方については情報が乏しいが、理学療法士による介入が開始されており、現在は平行棒内歩行訓練まで進んでいることから、一定の活動時間はあると推測される。しかし「疼痛により安静時間が長く」という記述から、日中も臥床している時間が多いことが示唆される。日中の過度な安静や睡眠は夜間の睡眠質を低下させるため、適切な日中活動と休息のバランスを評価する必要がある。また、休日のリハビリテーション実施状況や余暇活動についての情報も不足しているため、日中の活動パターン全体を把握することが望ましい。
看護介入としては、まず非薬物的な睡眠促進方法の導入が重要である。就寝前のルーティンの確立(温かい飲み物の摂取、リラクセーション技法の実践など)、環境調整(適切な室温、騒音の軽減、照明の調整)、就寝前の過度な思考活動や電子機器使用の回避などが効果的である。特に就寝前の疼痛管理を徹底し、安楽な体位の工夫や適切なタイミングでの鎮痛薬投与により、疼痛による睡眠妨害を最小限にすることが重要である。
また、日中の活動量を適切に増やすことも睡眠の質改善につながる。リハビリテーション以外の時間においても、ベッド上での軽運動や、可能な範囲での自立した日常生活活動の促進、趣味や関心事を取り入れた余暇活動の提案などにより、日中の覚醒状態を維持することが望ましい。特に午後の短時間の昼寝(30分以内)は夜間睡眠を妨げない範囲で許容し、過度な疲労感の蓄積を防ぐ配慮も必要である。
心理的な不安に対しては、傾聴と情報提供による支援が有効である。特にリハビリテーションの進捗状況や回復の見通し、退院後の生活や仕事復帰への具体的なプランを医療チームで共有し、A氏の不確実性への不安を軽減することが重要である。必要に応じて、リラクセーション技法(深呼吸法、漸進的筋弛緩法など)の指導も行うことが望ましい。
睡眠薬の使用については、現在の睡眠状態を詳細にアセスメントし、非薬物的介入による効果を評価しながら、徐々に減量・中止を検討することが望ましい。特に退院に向けては、自宅での安全な睡眠環境の整備や、睡眠衛生教育を行い、薬物に依存しない健全な睡眠パターンの確立を目指すことが重要である。
A氏は65歳男性であり、意識レベルは清明で、認知機能に問題はなく意思疎通は良好である。具体的な認知機能評価スケール(MMSE、HDS-Rなど)の結果は記載されていないが、日常会話や指示理解、服薬理解度から判断すると、顕著な認知機能低下はないと推測される。しかし、高齢者では軽度の認知機能変化が現れ始める時期であるため、特に入院環境や手術による侵襲、薬物療法(鎮痛薬、睡眠薬など)の影響で一時的な認知機能の変動が生じる可能性がある。特に術後せん妄のリスク因子として、65歳以上の高齢、手術による侵襲、疼痛、睡眠障害、環境変化などが複数存在するため、継続的な観察が必要である。
視力については老眼があり、読書時には老眼鏡を使用している。高齢者の視覚変化として、調節力の低下(老視)、水晶体の混濁、暗順応の遅延、視野狭窄などが挙げられるが、A氏の場合は老視以外の視覚障害については情報が不足している。読書時以外の日常生活での視力の影響や、夜間の視認性についての評価も必要である。特に入院環境では照明条件の変化や不慣れな空間での移動があるため、安全確保の観点から視覚機能の詳細な評価が重要である。聴力は問題なく、会話に支障はないとされている。しかし高齢者では徐々に高音域の聴力低下が進行することが多いため、騒音下での会話理解や複数人での会話時の理解度についても確認することが望ましい。
知覚に関しては、右下肢の術創部周囲に軽度の知覚鈍麻があるとされている。これは術後の一時的な末梢神経障害や浮腫による影響と考えられるが、回復過程を継続的に評価する必要がある。特に知覚鈍麻は温度感覚や痛覚の低下を伴うことがあり、熱傷や圧迫による組織損傷のリスクを高めるため、患部の保護と定期的な観察が重要である。また疼痛に関しては、安静時NRS 2/10、動作時NRS 4/10と評価されており、鎮痛薬による疼痛コントロールが行われているが、痛みの質や部位、持続時間、疼痛閾値などの詳細な評価も必要である。
A氏の心理状態については、「早く元の生活に戻りたい」という思いが強い一方で、「このペースでは仕事に戻れるのか」という将来への不安を抱えており、時折「自分はもう役に立たない」と落ち込む場面も見られる。これらの発言からは、自己効力感の低下や将来に対する不確実性への不安が読み取れる。リハビリにおいても「痛みがあるからできない」と消極的になることがあり、意欲の変動がみられる。表情についての具体的記述は限られているが、これらの心理状態からは、不安や落胆の表情が観察される可能性がある。特に理学療法中や将来の話題になった際の表情変化を観察することで、心理状態をより詳細に把握できる可能性がある。
また、内服薬の理解度チェックでは、薬の名前と用途について理解できているが、食後薬・就寝前薬の区別について時々混乱がみられるという記述がある。これは軽度の記憶力低下や注意力散漫が生じている可能性を示唆しており、高齢に伴う認知機能の軽微な変化と考えられる。特に退院後の服薬管理においては注意が必要であり、一包化などの対策が検討されている点は適切である。
看護介入としては、まず不安の緩和と自己効力感の向上を図ることが重要である。具体的には、リハビリテーションの進捗状況や回復の見通しについて、わかりやすく具体的な情報提供を行うことで、将来への不確実性を減らすことが有効である。また、小さな達成を認め、肯定的なフィードバックを提供することで自己効力感を高める関わりも重要である。患者が自身の進歩を実感できるよう、リハビリテーションの目標を細分化し、達成可能な短期目標を設定することも効果的である。
コミュニケーションにおいては、A氏の視力・聴力の状態に合わせた環境調整(適切な照明、静かな環境での会話、必要時の視覚的補助など)を行い、情報伝達の正確性を確保することが重要である。特に医療上の重要な情報(服薬指導、退院指導など)は、口頭説明だけでなく、視覚的資料(文字サイズに配慮したパンフレットなど)も併用することが望ましい。
また、知覚鈍麻のある右下肢については、温度刺激や圧迫による組織損傷を予防するための教育(温度確認の方法、定期的な皮膚観察、姿勢変換など)を行い、自己管理能力を高めることが重要である。疼痛管理においては、薬物療法と非薬物療法(リラクセーション技法、注意転換など)を組み合わせた多角的アプローチが効果的であり、痛みの性質や強度の変化を継続的に評価することで、個別化された疼痛管理計画を立案することが望ましい。
認知機能については、入院環境や薬物療法の影響による一時的な変動の可能性を考慮し、オリエンテーション(日付、場所、人物)の維持を支援する関わり(カレンダーの設置、日課の構造化など)や、知的活動の促進(新聞や雑誌の提供、会話の機
A氏は65歳男性で、性格は几帳面で真面目、自分のことは自分でやりたいという自立心が強い特性を持っている。妻からも「主人は頑固で自分でやりたがる」と表現されているように、自己決定や自律性を重視する傾向がある。このような性格特性は、日本の高度経済成長期に社会人となり、仕事中心の生活を送ってきた世代の男性に共通してみられる特徴でもあり、特に職業上の責任ある立場(現場監督)を担ってきたことも、こうした性格形成に影響していると考えられる。
現在のA氏は右大腿骨遠位骨折という身体的制約により、これまで当然のように行えていた日常生活動作に制限を強いられている状態である。特に下肢のズボンの着脱に介助を要するなど、自立して行えていた基本的な身体ケアにも援助が必要な状況は、A氏のボディイメージの変化や自己概念への脅威となっている可能性が高い。「自分はもう役に立たない」という発言からは、身体機能の低下が自己価値感の低下につながっていることが示唆される。特に男性高齢者では、身体機能の低下が自尊心や男性性のアイデンティティに直結する傾向があり、A氏の職業的背景(建築現場監督)を考慮すると、身体的自立や作業能力は自己価値の重要な構成要素であったと推測される。
疾患に対する認識については、「早く元の生活に戻りたい」という発言から、現在の状態を一時的なものと捉え、回復への願望を持っていることがわかる。しかし同時に「このペースでは仕事に戻れるのか」という不安も表明しており、回復過程の遅さや将来の見通しに対する懸念や焦りも感じていると考えられる。リハビリテーションにおいて「痛みがあるからできない」と消極的になる場面があることからは、疼痛体験が心理的な抵抗感や無力感を強化している可能性がある。また、高齢者においては「若い頃なら早く治ったのに」といった、加齢に伴う回復力の低下への気づきが、さらなる自己概念の揺らぎをもたらすことも少なくない。
A氏の自尊感情については、現場監督として働き続けていたことや、家庭内でも重要な役割を担っていたと推測されることから、これまでは比較的安定した自己価値感を維持してきたと考えられる。しかし現在は「妻に負担をかけたくない」という思いを抱えながらも、実際には妻の支援を必要とする状況にあり、この役割の逆転が自尊心の低下につながっている可能性がある。特に日本の伝統的な家族観においては、男性は「家庭を支える存在」としての役割期待が強く、依存的立場に置かれることへの抵抗感が強い傾向にある。
文化的背景や周囲の期待に関する具体的情報は限られているが、A氏が定年後も仕事を継続していたことから、社会的役割や生産性を重視する価値観を内在化している可能性がある。日本社会では特に男性高齢者において、「役に立つこと」「迷惑をかけないこと」への価値付けが強い傾向があり、A氏も身体機能の制限によって、こうした文化的規範に沿った自己像の維持が難しくなっていると推測される。
看護介入としては、まず自己効力感の回復を支援することが重要である。具体的には、リハビリテーションの過程で達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねることで、「できる」という感覚を取り戻す機会を提供することが有効である。例えば、上半身の更衣や整容などの自立している活動を肯定的に評価し、段階的に自己管理領域を拡大していくアプローチが考えられる。
また、A氏の価値観や人生観を尊重した傾聴と共感的理解を示すことで、感情表出の機会を提供することも重要である。特に「自分はもう役に立たない」といった否定的な自己評価が表出された際には、その感情を否定せずに受け止めつつ、これまでの人生で培ってきた強みや資源に目を向けるよう促すことが有効である。
ボディイメージの変化に対しては、現在の身体状態を正確に理解し、受容していくプロセスを支援することが必要である。骨折の治癒過程や機能回復の見通しについて具体的な情報提供を行い、現実的な期待を形成できるよう援助することが重要である。同時に、一時的な機能制限であることを強調し、段階的な回復への見通しを示すことで、将来への希望を維持できるよう支援する。
さらに、自己価値感が役割遂行に強く依存している場合には、代替となる有意義な活動や役割を見出す援助も効果的である。例えば、入院生活において自分の経験や知識を活かせる場面(他の患者との交流、医療者とのコミュニケーションなど)を意識的に作ることで、存在価値の実感につなげることができる。
妻との関係性においては、互いの思いや期待を共有する機会を設け、依存−被依存の関係性を超えた、相互支援的なパートナーシップの再構築を促すことが有効である。特に妻の「私ができるサポートは何でもします」という協力的な姿勢を活かしながらも、A氏の自律性や決定権を尊重した支援体制を整えることが重要である。
A氏は65歳の男性で、定年退職後も建築会社で現場監督として週3日勤務していた。定年後も仕事を継続していたことから、社会的役割や職業的アイデンティティを強く保持していたことがうかがえる。特に建築現場監督という職種は、作業の進行管理や安全確保、部下の指導など責任ある立場であり、リーダーシップや判断力、問題解決能力が求められる役割である。そのため、入院による突然の職業的役割の中断は、A氏のアイデンティティや社会的存在意義に影響を与えている可能性が高い。「このペースでは仕事に戻れるのか」という発言からは、職業復帰への強い希望と同時に、回復の遅れに対する焦りや不安が表れている。医師からは職場復帰について、デスクワーク中心であれば術後2ヶ月後から可能、現場監督業務については術後3~4ヶ月後と説明されており、この期間の空白をどのように受け止め、対処するかが課題となる。
家族構成は妻(63歳)との二人暮らしであり、キーパーソンは妻である。妻は毎日面会に訪れるなど積極的にサポートしており、「私ができるサポートは何でもします」と協力的な姿勢を示している。これはA氏の回復を支える重要な社会的資源となっている。一方で、妻は「主人は頑固で自分でやりたがるので、無理をさせないか心配です」「自宅は階段が多いので、帰ってからの生活が不安です」と看護師に相談するなど、退院後の生活に対する懸念も抱えている。これらの発言からは、妻自身も介護者としての新たな役割への適応過程にあることが示唆される。特に高齢の夫婦間では、これまでの役割分担が長期にわたって固定化している場合が多く、突然の役割変更が双方に心理的負担をもたらすことがある。A氏も「妻に負担をかけたくない」という思いを抱えており、互いを思いやる気持ちがある一方で、新たな関係性への移行に戸惑いや不安を感じていることが推測される。
面会状況については、妻が毎日訪れているという情報はあるが、他の家族や友人、職場関係者の面会に関する情報は不足している。社会的支援ネットワークの広がりを評価するためにも、これらの情報収集が必要である。特に職場の同僚や上司との関係性は、職場復帰に向けた調整や心理的準備に影響を与える重要な要素となりうる。
経済状況についての具体的な情報は記載されていないが、定年退職後も継続して就労していたことから、経済的な必要性があった可能性も考えられる。高齢者世帯では年金だけでは生活が厳しい場合も少なくなく、入院や治療に伴う経済的負担に対する懸念があるかもしれない。特に長期的なリハビリテーションや通院、自宅環境の整備などには一定の費用が発生するため、経済面での不安が潜在している可能性がある。医療費の負担区分や利用可能な社会保障制度(高額療養費制度、介護保険など)についての理解度も確認する必要がある。
看護介入としては、まず職業的役割の一時的喪失に対する心理的支援が重要である。A氏の職業人としてのアイデンティティを尊重しつつ、回復期における役割移行を支援するために、段階的な職場復帰計画の具体化や、回復過程の可視化(リハビリテーションの進捗状況のフィードバックなど)を行うことが有効である。また、可能であれば職場との連携を図り、復職に向けた環境調整や業務内容の検討を早期から始めることも有益である。
家族関係については、A氏と妻の相互理解と役割調整を促進するための介入が必要である。具体的には、退院後の生活における役割分担の明確化や、互いの心配事や期待を共有する機会を設けることが効果的である。特に妻の「リハビリの自宅での続け方」「転倒予防のための環境整備」への関心を活かし、妻を回復支援の協働者として位置づけ、必要な知識や技術を提供することで、新たな役割への適応を支援することが重要である。同時に、介護者となる妻の負担が過度にならないよう、利用可能な社会資源(介護保険サービスなど)の情報提供や、レスパイトケアの重要性についての教育も行うべきである。
また、A氏の社会的つながりを維持・強化するための支援も考慮する必要がある。入院生活が長期化することで社会的孤立感が増すリスクがあるため、面会の調整や、電話・メールなどを活用した社会的交流の継続を促すことが有効である。特に同年代の友人や職場の同僚との交流は、社会的役割の連続性を感じる機会となり、心理的安定につながる可能性がある。
経済面については、A氏夫婦の経済状況を踏まえた上で、利用可能な社会保障制度や支援サービスについての情報提供を行い、必要に応じて医療ソーシャルワーカーなどの専門職と連携した支援を検討することが望ましい。特に退院後の外来リハビリテーションや自宅環境の整備、福祉用具の導入などに関する経済的見通しを立てることで、将来への不安軽減につなげることができる。
A氏は65歳の男性で、63歳の妻との二人暮らしである。子どもの有無や家族構成の詳細については情報が不足しているため、家族歴や子どもとの関係性については更なる情報収集が必要である。65歳という年齢は男性においても加齢に伴う性機能の変化が生じる時期であり、テストステロンの低下による身体的・心理的変化(筋力低下、気分の変動、性欲減退など)が起こりうる。しかし、A氏の性機能や性生活に関する具体的な情報は記載されていないため、これらの側面についての評価は困難である。
男性の加齢変化としては、50歳代以降にテストステロン分泌が徐々に低下する男性更年期(加齢男性性腺機能低下症候群)が知られており、A氏もその年齢層に該当する。症状としては疲労感、意欲低下、イライラ、うつ傾向、集中力低下などの精神・心理的症状や、発汗、ほてり、関節痛などの身体的症状、性欲減退や勃起障害などの性機能関連症状が現れることがある。A氏の「自分はもう役に立たない」という発言や、リハビリに対する消極的な姿勢は、単に骨折による身体機能の制限だけでなく、こうした加齢による心理的変化が背景にある可能性も考慮する必要がある。
また、右大腿骨遠位骨折という下肢の外傷は、移動能力だけでなく性生活にも影響を及ぼす可能性がある。特に股関節や膝関節の可動域制限や疼痛は、性行為時の体位や動作に制限をもたらし、性生活の質に影響を与えることがある。A氏と妻は二人暮らしで、お互いを思いやる関係性が観察されていることから、夫婦関係は良好であると推測されるが、骨折による身体的制限が夫婦の親密性にどのような影響を与えているかについては情報が不足している。
さらに、入院環境自体がプライバシーの制限や日常的な親密さの機会喪失をもたらすことで、性的表現や夫婦間の親密な交流に影響を与える可能性がある。特に日本の医療文化では、入院患者の性的ニーズや夫婦関係の維持に関する配慮が十分になされないことが多く、この側面でのケアは見落とされがちである。
A氏の性格は几帳面で真面目、自立心が強いとされており、こうした特性は自身の身体的変化や制限に対する受け止め方にも影響を与えると考えられる。特に男性性のアイデンティティが身体的自立や職業的役割と強く結びついている場合、骨折による一時的な依存状態は性的自己概念にも影響を及ぼす可能性がある。
看護介入としては、まずプライバシーへの配慮と夫婦の時間の確保が重要である。面会時には可能な限りカーテンを閉めるなどの配慮や、夫婦が落ち着いて会話できる環境を整えることで、親密性の維持を支援することができる。
また、性や親密性に関する話題は文化的背景や個人の価値観により非常にデリケートであるため、直接的な介入よりも、A氏や妻が必要時に相談できる開かれた姿勢を示すことが重要である。例えば「何か心配なことや質問があれば、いつでも相談してください」といった声かけにより、話題を持ち出しやすい雰囲気を作ることが有効である。
身体機能の回復に伴い、日常生活動作の自立度が向上することで、自己効力感や性的自己概念も改善することが期待される。そのため、リハビリテーションへの積極的な参加を促し、進捗を肯定的にフィードバックすることは、間接的に性的側面の改善にも寄与する可能性がある。
退院に向けては、日常生活の中での夫婦の役割再構築や親密性の維持についても考慮することが望ましい。特に「自宅は階段が多い」という環境的課題や、A氏の自立心の強さを考慮すると、退院後の生活における実際的な工夫(寝室の配置変更、補助具の活用など)が必要となる可能性がある。これらの点について夫婦間でオープンなコミュニケーションが取れるよう支援することで、退院後の生活適応を促進することができる。
また、高齢期の性や親密性は単に性行為に限定されるものではなく、身体的接触、言葉による愛情表現、共有する時間や活動など多様な形で表現されることを理解し、こうした広い意味での親密性を維持・促進するための支援も考慮すべきである。特に入院という非日常的な環境では、これらの親密性表現が制限されがちであるため、夫婦の関係性に配慮した環境調整や声かけが重要である。
A氏は右大腿骨遠位骨折で突然入院となり、これまでの生活パターンが急激に変化したことによるストレス状態にある。入院環境に関する具体的な情報は少ないが、入院による環境変化や活動制限、プライバシーの制限などが心理的ストレス要因となっている可能性がある。特に入院後の睡眠障害(入眠困難、眠剤の使用)や時折の食欲低下は、環境変化へのストレス反応と考えられる。また「リハビリへの不安から時折眠れない日がある」という記述からは、身体的回復過程への不確実性がさらなるストレス要因となっていることが示唆される。
A氏の職業は定年退職後も建築会社で現場監督として週3日勤務しており、職業的アイデンティティが自己概念の重要な部分を占めていると推測される。「このペースでは仕事に戻れるのか」という発言からは、職場復帰への不安や焦りがストレスとなっていることがわかる。特に現場監督という責任ある立場においては、長期不在による業務への影響や、復帰後の職務遂行能力への懸念があると考えられる。医師からはデスクワークであれば術後2ヶ月後、現場監督業務は3~4ヶ月後の復帰が見込まれると説明されているが、この期間の経済的影響や職場での立場の変化なども潜在的なストレス要因となる可能性がある。
ストレス対処方法については明確な情報がなく、入院前のA氏がどのようにストレスを発散していたか、どのような趣味や関心があったかなどの情報収集が必要である。入院生活におけるストレス発散の機会は限られており、特に身体活動による発散が制限されているため、代替となるコーピング方法を見出すことが重要である。A氏の性格は几帳面で真面目、自立心が強いとされているが、このような性格特性はストレス対処にも影響を与える。自立志向が強い場合、援助を求めることへの抵抗感があり、問題を一人で抱え込む傾向があるかもしれない。また完璧主義的傾向がある場合、リハビリテーションの進捗の遅れや思うように回復しない状況に対して、自己批判的になりやすい可能性もある。
家族のサポート状況については、妻が主要な支援者として毎日面会に訪れており、「私ができるサポートは何でもします」と協力的な姿勢を示している。この強い支援基盤はA氏のストレス耐性を高める重要な要素である。しかしA氏自身は「妻に負担をかけたくない」という思いを抱えており、支援を受けることへの心理的抵抗や葛藤があると推測される。この葛藤自体がストレス要因となっている可能性があり、援助を受け入れることと自律性を維持することのバランスを取ることが課題となる。
また妻も「主人は頑固で自分でやりたがるので、無理をさせないか心配です」「自宅は階段が多いので、帰ってからの生活が不安です」と看護師に相談しており、介護者としての不安やストレスを抱えていることがわかる。家族システム全体のストレス対処能力を評価し、必要に応じて家族への支援も行うことが重要である。
生活の支えとなるものについては、仕事や家族以外の社会的支援ネットワーク(友人、地域社会とのつながりなど)や、精神的支柱となる信念や価値観についての情報が不足している。これらの要素はストレス対処資源として重要であるため、A氏の社会的交流パターンや生きがいとなっている活動、価値観などについての情報収集が必要である。
加齢に伴うストレス対処能力の変化も考慮する必要がある。一般的に高齢者は長年の人生経験から培われた対処能力や適応力を持っている一方で、身体的予備力の低下や社会的役割の変化により、ストレス脆弱性が増すこともある。特に65歳という年齢は、定年退職や身体機能の変化など、複数の喪失体験が重なる時期であり、これらの変化への適応過程の途上でさらなる健康危機(骨折)が生じたことの心理的影響を評価することが重要である。
看護介入としては、まずA氏のストレス認知とコーピング方法の評価を行い、個別的な支援計画を立案することが重要である。具体的には、A氏の感情表出を促進するためのオープンな質問や傾聴の機会を意図的に設け、不安や懸念を言語化できるよう支援する。特に「自分はもう役に立たない」といったネガティブな自己評価が表出された際には、その感情を否定せずに受け止めつつ、認知の再構成を促す関わりが有効である。
入院環境に関しては、可能な限りのプライバシーの確保や、個人的な持ち物(写真や愛用品など)の使用を促進し、環境の個別化を図ることでストレス軽減につなげることができる。また、日課の構造化や選択機会の提供により、環境に対するコントロール感を高めることも重要である。
ストレス発散方法については、身体的制限があることを考慮した上で、代替となる活動(読書、音楽鑑賞、創作活動など)を提案し、入院中でも実施可能なリラクセーション法(深呼吸法、段階的筋弛緩法、イメージ療法など)の指導も効果的である。特にA氏の職業や興味関心に関連した話題を取り入れることで、意欲の向上や気分転換を図ることができる。
家族支援においては、A氏と妻が互いの期待や心配事を共有できる機会を設け、退院後の生活に向けた具体的な計画立案を共に行うことで、不確実性への不安軽減を図ることが有効である。特に妻の「リハビリの自宅での続け方」「転倒予防のための環境整備」への関心を活かし、実践的な知識や技術の習得を支援することで、自己効力感を高めることができる。
また、必要に応じて多職種連携による包括的支援を検討し、医療ソーシャルワーカーによる社会資源の調整や、臨床心理士による心理的サポート、リハビリテーション専門職による具体的な活動指導などを組み合わせた介入を行うことが望ましい。特に退院が近づくにつれて、環境移行に伴う不安が高まることが予測されるため、継続的な支援体制の構築が重要である。
A氏の信仰については「特定の宗教的信仰はない」と記載されているが、宗教的信仰がなくとも、個人の人生観や価値観を形成する信念体系は存在している。提供された情報からA氏の価値観や信念を分析すると、「自立」と「責任」を重視する傾向が強いことがうかがえる。性格は几帳面で真面目、自分のことは自分でやりたいという自立心の強さが特徴として挙げられており、妻からも「主人は頑固で自分でやりたがる」と表現されている。これらの特性は、戦後の高度経済成長期に社会人となり、仕事中心の生活を送ってきた世代の男性に共通して見られる価値観であり、自己責任や自助努力を美徳とする日本の伝統的な価値観の影響も考えられる。
また「早く元の生活に戻りたい」「妻に負担をかけたくない」という発言からは、他者への迷惑回避と自己の役割遂行を重視する価値観が読み取れる。特に日本の文化的背景においては、「迷惑をかけない」ことが重要な社会規範となっており、A氏もこの価値観を内在化していると推測される。さらに定年退職後も建築会社で現場監督として週3日勤務を継続していたことからは、仕事を通じた社会貢献や職業的アイデンティティを重視していることがうかがえる。このような価値観は、A氏の意思決定や行動選択に大きな影響を与えていると考えられる。
目標については「早く元の生活に戻りたい」という発言から、日常生活の回復と職場復帰が主要な目標であることが推測される。しかし「このペースでは仕事に戻れるのか」という不安や、時折「自分はもう役に立たない」と落ち込む様子からは、目標達成に対する懸念や自己価値への疑問が生じていることがわかる。特に65歳という年齢は、心身の変化や社会的役割の変遷により、これまでの価値観や人生目標の再評価を迫られる時期であり、今回の骨折という健康危機がこのプロセスをさらに加速させている可能性がある。
加齢に伴う価値観の変化としては、若年期・壮年期に重視されていた達成や成功といった外的価値から、人間関係の質や精神的充足といった内的価値への重点移行が知られている。A氏においても、この転換期にあることが推測されるが、依然として職業的役割や自立性に強い価値を置いている様子がうかがえる。これは日本の高齢男性に特徴的な傾向でもあり、特に「役に立つこと」に自己価値を見出す傾向が強い。
意思決定プロセスについては、A氏自身の決定権を尊重する傾向が強いと推測されるが、具体的な意思決定のパターンや、重要な決断の際の情報収集方法、家族との相談過程などの情報は不足している。特に医療に関する意思決定においては、医師の説明をどの程度理解し、どのような基準で判断しているかなど、ヘルスリテラシーや意思決定能力の評価も重要である。
看護介入としては、まずA氏の価値観や人生観を理解し尊重する姿勢が基本となる。自立を重視する価値観を踏まえ、可能な限り自己決定の機会を提供し、選択肢がある場合には意思決定への参加を促すことが重要である。例えばリハビリテーションのスケジュール調整や、日常生活の過ごし方に関して選択肢を提示し、A氏の意向を尊重することで自律性を支援することができる。
また、現在のA氏は身体機能の制限により、自立という中核的価値の実現が難しい状況にある。このような価値と現実のギャップがもたらす心理的葛藤に対して、傾聴と共感的理解を示すことが重要である。特に「自分はもう役に立たない」という自己否定的な発言に対しては、A氏の価値観(役に立つこと、自立すること)を否定せずに受け止めつつも、現在の状況を一時的なものとして捉え直す視点を提供することが有効である。
さらに、A氏の目標である「元の生活に戻る」ことについて、具体的かつ現実的な段階設定を支援することも重要である。現場監督業務への復帰は術後3~4ヶ月後と医師から説明されているが、この期間をどのように過ごし、どのようなステップで目標に近づくかという回復過程の可視化を支援することで、不確実性への不安軽減を図ることができる。
加えて、現在の身体的制限があっても実現可能な代替的な価値表現の方法を見出す支援も有効である。例えば、これまでの職業経験や知識を活かした形での社会貢献(若手への助言、経験の伝承など)や、身体的自立以外の側面での自律性の発揮(知的活動、意思決定への参加など)を促進することで、価値の実現感を維持することができる。
退院に向けては、A氏夫婦の価値観や目標に即した具体的な生活再建計画の立案を支援し、必要に応じて価値の優先順位や目標の修正を検討する機会を提供することも重要である。特に「妻に負担をかけたくない」という思いと、実際に支援を必要とする現実とのバランスをどのようにとるかについて、夫婦間での率直な対話を促すことが望ましい。
看護計画
看護問題
疼痛に関連した活動耐性の低下
長期目標
退院までに動作時の疼痛がNRS 2/10以下に軽減し、リハビリテーションに積極的に参加できる
短期目標
1週間以内に疼痛コントロール方法を理解し、動作時疼痛がNRS 3/10以下となり、指示された範囲内でのリハビリテーションに前向きに取り組むことができる
≪O-P≫観察計画
・疼痛の強さをNRSで評価し、安静時と動作時の変化を観察する
・疼痛の部位、性質、持続時間、誘発因子、緩和因子を確認する
・疼痛による表情や行動の変化を観察する
・疼痛に対する対処行動(姿勢の変化、活動の回避など)を観察する
・鎮痛薬の効果と副作用の有無を確認する
・鎮痛薬使用に対する患者の認識や抵抗感を確認する
・リハビリテーションへの参加状況と意欲を評価する
・疼痛による睡眠や休息への影響を観察する
・疼痛に対する不安や恐怖心の有無を評価する
・疼痛が日常生活動作に与える影響を観察する
・疼痛による気分や感情の変化を観察する
・非薬物的疼痛緩和法の効果を評価する
≪T-P≫援助計画
・医師と連携し、適切な時間帯に効果的な鎮痛薬投与を行う
・リハビリテーション前30分程度に予防的な鎮痛薬投与を行う
・安楽な体位の工夫と体位変換を支援する
・寝具やクッションを活用し、患部への負担軽減を図る
・温罨法や冷罨法など、医師の指示に基づいた物理療法を実施する
・リラクセーション技法(深呼吸法など)を実施する
・注意転換(音楽鑑賞や会話など)を促す
・リハビリテーション中の休息時間を適切に設ける
・過度な疲労を避けるための活動と休息のバランスを調整する
・疼痛増強を予防するための動作方法を支援する
・夜間の疼痛管理に配慮し、良質な睡眠環境を整える
・日常生活動作時の介助を適切に行い、痛みによる負担を軽減する
≪E-P≫教育・指導計画
・疼痛の発生メカニズムと回復過程について説明する
・疼痛スケール(NRS)の使用方法と自己評価の重要性を指導する
・鎴痛薬の種類、効果、適切な服用タイミングについて説明する
・疼痛悪化のサインと対処方法について指導する
・深呼吸法やイメージ療法などのリラクセーション技法を指導する
・負担の少ない動作方法や姿勢について指導する
・リハビリテーションと疼痛管理の関連性について説明する
・過度な我慢をせず、適切なタイミングで援助を求めることの重要性を説明する
看護問題
右大腿骨遠位骨折と活動制限に関連した転倒リスク
長期目標
退院までに安全な移動方法を習得し、自立した日常生活動作が行える範囲で転倒なく生活できる
短期目標
1週間以内に転倒リスク要因を理解し、移動時に適切な補助具を使用して看護師の見守りのもとで安全に移動できる
≪O-P≫観察計画
・歩行状態、バランス能力、下肢筋力を評価する
・荷重制限の理解度と遵守状況を確認する
・転倒リスクのある行動(突然の立ち上がりなど)の有無を観察する
・歩行器の適切な使用方法の習得状況を評価する
・睡眠薬や鎮痛薬による眠気やふらつきの有無を観察する
・排泄のタイミングと排泄行動の安全性を確認する
・環境認識力や空間把握能力を評価する
・血圧変動や起立時のめまい感の有無を確認する
・視力や聴力の状態を評価する
・ナースコールの使用状況と援助要請の傾向を観察する
・転倒への不安や恐怖心の程度を評価する
・脊柱管狭窄症による下肢症状(しびれなど)の有無を確認する
≪T-P≫援助計画
・ベッド周囲の整理整頓と障害物の除去を行う
・適切な照明を確保し、特に夜間のトイレ移動時の視認性を高める
・ベッドの高さを調整し、立ち上がりや移乗時の安全性を確保する
・必要物品を手の届く範囲に配置する
・歩行器の高さや安定性を定期的に点検する
・トイレ誘導を適切なタイミングで行い、排泄の予測的支援を行う
・滑り止め機能のある履物の使用を促進する
・移動時には必要に応じて見守りや介助を行う
・転倒リスクの高い時間帯(夜間、薬剤投与後など)の巡回を強化する
・移動時の安全な動作方法を実践的に支援する
・環境変化時(リハビリ室から病室へなど)は特に注意深く見守る
・転倒リスク評価を定期的に行い、リスクレベルに応じた対策を調整する
≪E-P≫教育・指導計画
・現在の荷重制限と今後の変更予定について説明する
・転倒リスク要因と予防策について具体的に説明する
・歩行器の正しい使用方法を反復して指導する
・急な姿勢変換を避け、ゆっくりと動作することの重要性を説明する
・睡眠薬や鎮痛薬の影響による転倒リスク増加について説明する
・転倒の前兆症状(めまい、ふらつきなど)を感じた際の対処法を指導する
・無理をせず援助を求めることの重要性を説明する
・退院後の住環境における転倒リスクと対策について指導する
看護問題
退院後の住環境に関連した不安
長期目標
退院までに自宅での生活に必要な知識・技術を習得し、退院後の生活に対する不安が軽減される
短期目標
1週間以内に退院後の生活に関する具体的な課題を明確にし、解決策について妻と共に考えることができる
≪O-P≫観察計画
・退院後の生活に関する発言内容や不安の表出を観察する
・自宅の住環境(階段、浴室、トイレなど)の具体的状況を確認する
・妻の介護に対する理解度や不安内容を評価する
・日常生活動作の自立度と退院後に支援が必要な領域を把握する
・自宅での継続的なリハビリテーションに対する理解度を確認する
・転倒予防に対する意識と具体的な対策の理解度を評価する
・社会資源(介護保険サービスなど)の利用意向や理解度を確認する
・服薬自己管理能力と誤薬リスクを評価する
・妻との役割分担に関する考えや希望を把握する
・職場復帰に向けての具体的な計画や不安を確認する
・退院後のフォローアップ体制に対する理解度を評価する
・経済的な不安や医療費に関する懸念の有無を確認する
≪T-P≫援助計画
・退院後の生活について具体的にイメージできるよう面談の機会を設ける
・退院前カンファレンスを開催し、多職種で情報共有と計画立案を行う
・自宅環境のアセスメントに基づいた環境調整の提案を行う
・必要な福祉用具(手すり、シャワーチェアなど)の選定を支援する
・介護保険サービスなど利用可能な社会資源の情報提供と申請支援を行う
・退院後のリハビリテーション計画について理学療法士と連携を図る
・退院時の服薬指導を薬剤師と連携して行う
・退院後の外来受診スケジュールを明確にし、診療情報提供書を作成する
・自宅での生活動作の練習を入院中から段階的に実施する
・自宅環境を模した状況での動作訓練を支援する
・妻への介助方法の実技指導の機会を設ける
・地域の訪問看護サービスなど継続的な支援体制の調整を行う
≪E-P≫教育・指導計画
・退院後の活動と休息のバランスについて具体的に説明する
・自宅での転倒予防のための環境整備方法を指導する
・安全な階段の昇降方法について実技を交えて指導する
・自宅でのセルフエクササイズの方法を図示したパンフレットを用いて説明する
・服薬管理の方法(一包化など)について具体的に指導する
・荷重制限に関する注意点と段階的な活動拡大計画を説明する
・異常症状(疼痛増強、腫脹、発熱など)と受診の目安について説明する
・妻に対して安全な介助方法と腰痛予防策を指導する
・生活リズムの整え方と規則正しい生活の重要性について説明する
・利用可能な社会資源とその申請方法について説明する
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
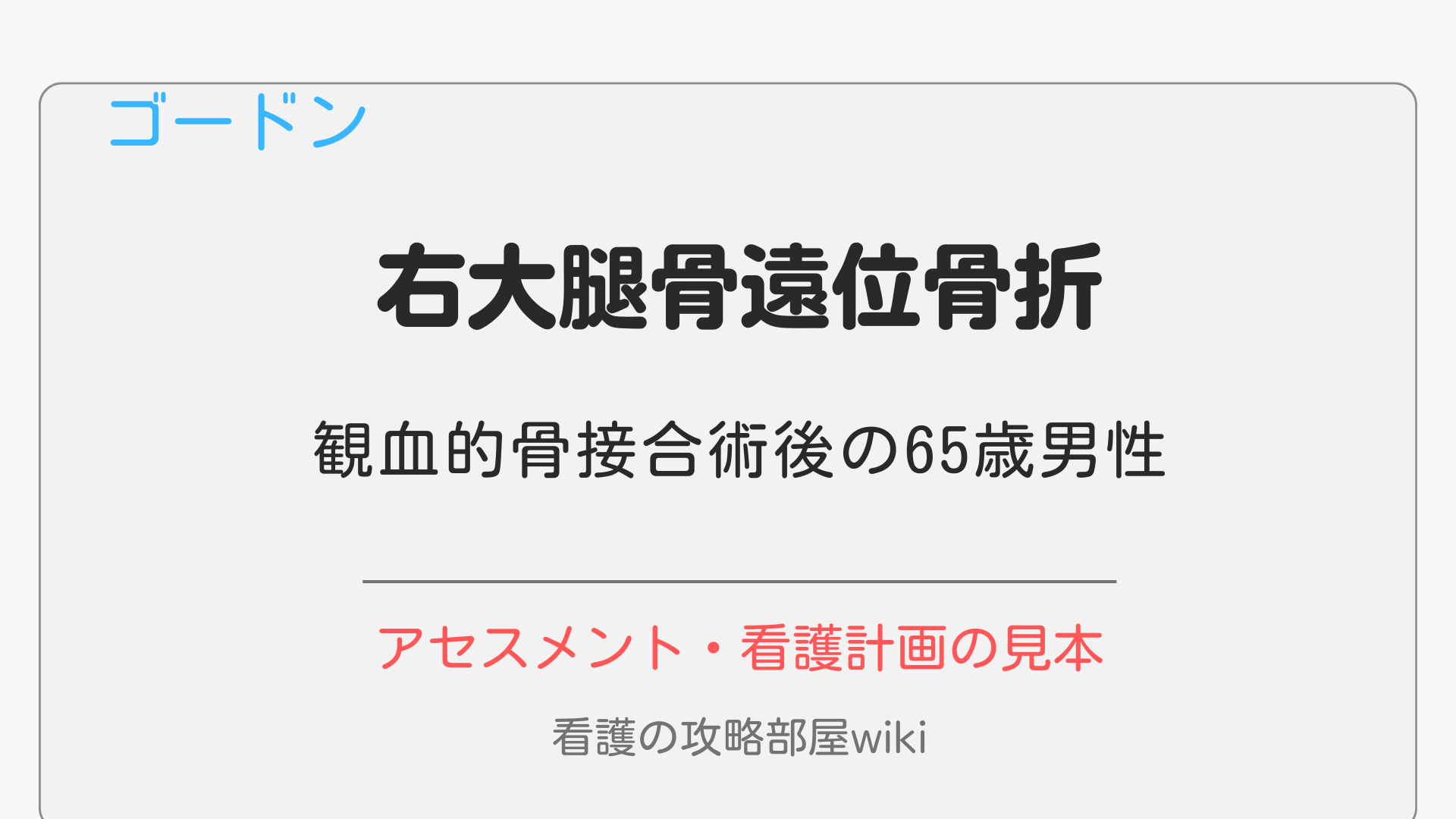
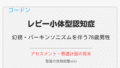
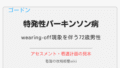
コメント