病態の概要
定義
転倒とは、意図しない体位の変化により、足底以外の身体部位が床面や地面に接触することを指します。看護の現場では、患者さんの安全を脅かす重要なリスクファクターとして位置づけられており、入院中の患者さんに起こりやすい医療安全上の問題でもありますね。
原因
転倒の原因は大きく内的要因と外的要因に分けられます。
内的要因としては、加齢による筋力低下、バランス能力の低下、視力・聴力の障害、認知機能の低下、薬剤の副作用(特に降圧薬、睡眠薬、向精神薬)、疾患による歩行障害、起立性低血圧、意識レベルの低下などが挙げられます。
外的要因では、床の濡れや段差、照明不足、適切でない履物、手すりの不備、ベッドの高さが不適切、点滴スタンドなどの医療機器による歩行の妨げなどがあります。
病態生理
正常な状態
正常な歩行や立位保持には、視覚系、前庭系、体性感覚系の3つのシステムが協調して働いています。視覚系は周囲の環境や障害物を認識し、前庭系は頭部の位置や動きを感知し、体性感覚系は足底や関節からの位置情報を脳に伝えます。これらの情報が脳で統合され、適切な筋収縮が行われることで、安定した姿勢が保たれるのです。
異常が起こる過程
転倒が起こる過程は、姿勢制御システムの破綻から始まります。まず、上記の3つのシステムのいずれか、または複数に障害が生じると、正確な身体の位置情報が得られなくなります。そのため、重心の移動に対して適切な姿勢調整ができず、バランスを崩してしまいます。さらに、筋力低下や反応時間の遅延により、バランスを崩した際の立て直しが困難になり、最終的に転倒に至るのです。
症状
現れる症状とその理由
転倒により生じる症状は、転倒時の状況や患者さんの身体状況によって様々です。最も重篤なのは頭部外傷で、特に高齢者では軽微な転倒でも硬膜下血腫を生じる可能性があります。これは加齢により脳が萎縮し、硬膜と脳の間のスペースが広がることで、橋静脈が伸展し破綻しやすくなるためです。
骨折も頻繁に見られる症状で、特に大腿骨頸部骨折、橈骨遠位端骨折、脊椎圧迫骨折が多発します。高齢者では骨密度の低下により、比較的軽微な外力でも骨折が生じやすくなっています。
また、転倒恐怖症という心理的な症状も重要です。一度転倒を経験すると、再び転倒することへの恐怖から活動量が低下し、さらなる筋力低下やバランス能力の悪化を招くという悪循環に陥ることがあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・外傷リスク状態(転倒に関連した)
・身体可動性障害
・活動耐性低下
・不安
・恐怖
・セルフケア不足
・社会的孤立
ゴードンのポイント
活動・運動パターンが最も重要な評価項目となります。歩行状態、筋力、関節可動域、バランス能力を詳細に観察し、日常生活動作の自立度を評価します。また、過去の転倒歴や転倒に対する恐怖感についても聞き取りを行い、患者さんの活動に対する意欲や自信の程度を把握することが大切です。
認知・知覚パターンでは、見当識、記憶力、判断力を評価し、転倒リスクに影響する認知機能の低下がないかを確認します。服薬状況や薬剤の副作用についても詳しく聞き取りを行います。
ヘンダーソンのポイント
「身体の位置を動かし、また良い姿勢を保持する」というニードが中心となります。患者さんの移動能力や姿勢保持能力を評価し、安全な移動方法を一緒に考えていきます。また、「学習する」というニードも重要で、転倒予防に関する知識や技術を身につけてもらうための指導を行います。
看護計画・介入の内容
・転倒リスクアセスメントツールを用いた定期的な評価
・ベッド周辺の環境整備(適切なベッドの高さ、照明の確保、床面の乾燥保持)
・適切な履物の選択と着用の指導
・歩行補助具の適切な使用方法の指導
・筋力トレーニングやバランス訓練の実施
・起立性低血圧予防のための段階的な体位変換指導
・薬剤師との連携による薬剤調整の検討
・転倒予防に関する患者・家族への教育
・多職種との連携によるリハビリテーションの実施
・心理的サポートと転倒恐怖症への対応
よくある疑問・Q&A
Q: なぜ高齢者は転倒しやすいのでしょうか?
A: 高齢者の転倒リスクが高い理由は複数あります。まず、加齢に伴い筋力が低下し、特に下肢の筋力低下により歩行時のバランス保持が困難になります。また、視力や聴覚の低下により環境の変化を察知しにくくなり、反応時間も遅くなります。さらに、複数の慢性疾患を持つことが多く、服用する薬剤の副作用も転倒リスクを高める要因となります。
Q: 転倒リスクアセスメントツールにはどのようなものがありますか?
A: 代表的なものとして、Morse Fall Scale、STRATIFY、転倒転落アセスメントシートなどがあります。これらのツールは、年齢、転倒歴、認知機能、薬剤使用状況、歩行状態、排泄状況などの項目を点数化し、転倒リスクを客観的に評価できるように設計されています。定期的な評価により、リスクの変化を早期に発見できます。
Q: 転倒予防の運動にはどのようなものが効果的ですか?
A: バランス訓練、筋力トレーニング、歩行訓練を組み合わせた多面的な運動が効果的です。具体的には、片足立ち、タンデム歩行(一直線上を歩く)、太極拳などのバランス訓練、スクワットやカーフレイズなどの下肢筋力トレーニング、階段昇降や歩行訓練などが推奨されています。重要なのは、患者さんの能力に応じて段階的に実施することです。
Q: 転倒後の対応で注意すべき点は何ですか?
A: まず、意識レベルと生命徴候を確認し、明らかな外傷がないかを観察します。特に頭部外傷の有無は重要で、意識レベルの変化、嘔気・嘔吐、麻痺の出現などに注意が必要です。また、転倒の原因を詳しく聞き取り、再発防止策を検討することが大切です。心理的なフォローも忘れずに行い、転倒恐怖症の予防に努めます。
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
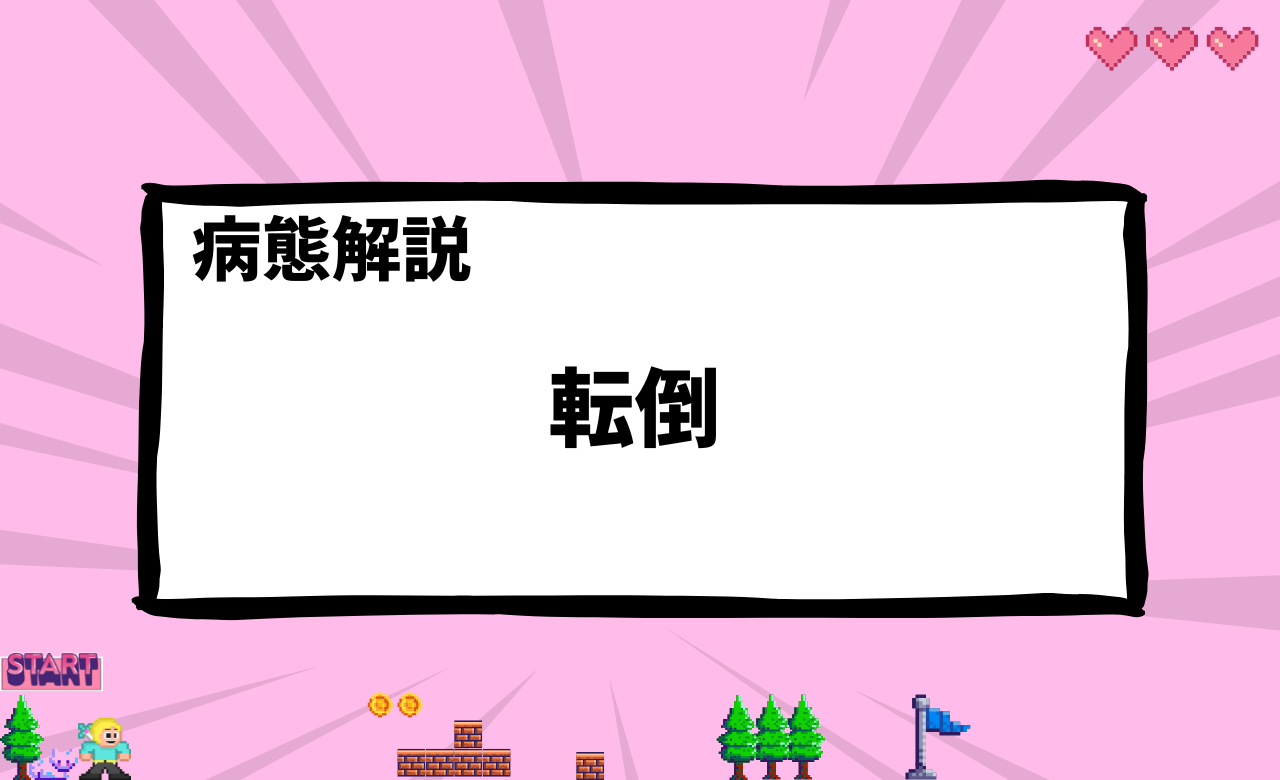


コメント