症状概要
定義
胸痛とは、胸部に感じる痛みや不快感の総称です。患者は「胸が痛い」「胸が締め付けられる」「胸が圧迫される」「胸が焼ける」「胸が刺される」など様々な表現で訴えます。胸痛は生命に関わる重篤な疾患から軽症なものまで幅広い原因により生じるため、緊急性の判断が最も重要です。特に心筋梗塞、大動脈解離、肺血栓塞栓症などは迅速な対応が生命予後を左右するため、看護師には的確なアセスメント能力が求められます。
疫学
胸痛は救急外来を受診する理由の約5〜10%を占める非常に頻度の高い症状です。そのうち生命に関わる重篤な疾患は約15〜20%程度ですが、見逃すと致命的となるため慎重な評価が必要です。年齢とともに心血管疾患による胸痛が増加し、特に50歳以上の男性や閉経後の女性では冠動脈疾患のリスクが高くなります。若年者では筋骨格系の痛みや過換気症候群が多い傾向にあります。
原因
胸痛の原因は大きく心血管系、呼吸器系、消化器系、筋骨格系、精神・神経系に分けられます。生命に関わる重篤な疾患として、急性冠症候群(心筋梗塞、不安定狭心症)、大動脈解離、肺血栓塞栓症、緊張性気胸、食道破裂などがあります。比較的頻度の高い疾患として、安定狭心症、心膜炎、胸膜炎、肺炎、逆流性食道炎、肋間神経痛、肋軟骨炎、帯状疱疹、過換気症候群などが挙げられます。高齢者や糖尿病患者では非典型的な症状を呈することがあり注意が必要です。
病態生理
胸痛のメカニズムは原因により異なります。心臓性胸痛では、冠動脈の狭窄や閉塞により心筋への血流が低下し、心筋虚血が生じて痛みとなります。虚血が持続すると心筋壊死(心筋梗塞)に至ります。大動脈解離では、大動脈の内膜が裂け、中膜に血液が流入することで激烈な痛みが生じます。肺血栓塞栓症では、肺動脈が血栓で閉塞し、肺組織の虚血や梗塞により胸膜刺激症状として胸痛が出現します。消化器系では、胃酸の逆流により食道粘膜が刺激され、心臓性と紛らわしい胸痛を生じることがあります。筋骨格系では、肋骨や肋軟骨、筋肉、神経の炎症や損傷により痛みが生じます。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
心血管系疾患では、急性心筋梗塞、不安定狭心症、安定狭心症、大動脈解離、大動脈瘤破裂、急性心膜炎、心筋炎などがあります。呼吸器系疾患では、肺血栓塞栓症、気胸、胸膜炎、肺炎、肺がんなどが挙げられます。消化器系疾患では、逆流性食道炎、食道痙攣、食道破裂、急性膵炎、消化性潰瘍などがあります。筋骨格系疾患では、肋軟骨炎、肋間神経痛、帯状疱疹、筋肉痛、肋骨骨折などが代表的です。精神・神経系では、過換気症候群、パニック障害、不安障害なども胸痛の原因となります。
評価とアセスメント
胸痛の評価で最も重要なのは緊急性の判断です。まずバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数、SpO2、体温、意識レベル)を迅速に測定します。生命に関わる危険なサインとして、冷汗、顔面蒼白、チアノーゼ、血圧低下、頻脈または徐脈、呼吸困難、意識レベル低下などがあれば緊急対応が必要です。胸痛の性状をOPQRSTで評価します。O(Onset:発症様式)は突然か徐々にか、P(Palliative/Provocative:増悪・軽快因子)は労作時か安静時か、体動や深呼吸で変化するか、Q(Quality:性質)は締め付けられる、刺されるような、焼けるようななど、R(Region/Radiation:部位・放散痛)は前胸部、左胸部、背部、顎や腕への放散の有無、S(Severity:強さ)はNRSなどで評価、T(Time:持続時間)は数秒、数分、持続的かを確認します。
対応と治療
胸痛への対応は原因により異なりますが、緊急性が疑われる場合の初期対応として、まず安静を保ち、心電図モニター装着、酸素投与(SpO2が低い場合)、静脈ルート確保を行います。急性冠症候群が疑われる場合は、12誘導心電図測定、血液検査(心筋トロポニン、CK-MBなど)、胸部X線撮影を速やかに実施し、アスピリンの投与、ニトログリセリンの舌下投与、必要に応じて冠動脈造影・PCI(経皮的冠動脈形成術)を準備します。大動脈解離が疑われる場合は、造影CTを緊急実施し、血圧管理と緊急手術の準備を行います。肺血栓塞栓症では造影CTや心エコーで診断し、抗凝固療法や血栓溶解療法を検討します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:虚血、炎症、損傷などに関連した胸部の急性疼痛
- 心拍出量減少:心筋虚血や不整脈による心機能低下
- 不安:胸痛と死の恐怖に関連した強い不安
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者が胸痛の危険性を認識しているか、冠危険因子(喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症、家族歴)の有無と管理状況を評価します。狭心症の既往がある場合は、発作の頻度や誘因の変化、ニトログリセリンの使用状況も確認します。活動-運動パターンでは、胸痛が出現する活動レベルを評価します。労作時のみか、軽労作でも出現するか、安静時にも生じるかにより、心疾患の重症度を推測できます。コーピング-ストレス耐性パターンでは、胸痛による「死ぬのではないか」という強い恐怖への対処能力を評価し、心理的支援の必要性を判断します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸するニードでは、胸痛に伴う呼吸困難の有無、呼吸数、SpO2を評価します。胸膜刺激による痛みでは深呼吸ができず、無気肺のリスクが高まります。循環のニードでは、血圧、脈拍、末梢循環(冷感、チアノーゼ)、心電図モニター、心筋マーカーなどを継続的に評価します。急性冠症候群では心不全や致死的不整脈のリスクがあるため、厳重な観察が必要です。安全なニードでは、胸痛による転倒リスク、失神のリスク、不安からの危険行動のリスクを評価します。また、ニトログリセリンや鎮痛薬使用時の血圧低下にも注意が必要です。
看護計画・介入の内容
- 胸痛の継続的評価:疼痛の程度・性状・部位・持続時間の観察、増悪・軽快因子の確認、バイタルサインの継続的モニタリング、心電図モニターによる不整脈の監視、冷汗・顔面蒼白などの随伴症状の観察
- 疼痛緩和:安静の保持(セミファーラー位など楽な体位)、酸素投与、処方された鎮痛薬・ニトログリセリンの投与と効果判定、環境調整(静かな環境、適温)、深呼吸やリラクセーション法の指導
- 不安の軽減:傾聴と共感的態度、そばにいることでの安心感の提供、病状や治療の説明、家族の付き添い調整、必要時の抗不安薬投与
よくある疑問・Q&A
Q: 心臓の痛みと筋肉痛の違いはどう見分けますか?
A: いくつかの鑑別ポイントがあります。心臓性胸痛は、締め付けられる・圧迫されるような重苦しい痛みで、労作時に出現し安静で軽快することが多く、数分から数十分持続します。顎や左腕への放散痛を伴うこともあります。一方、筋骨格系の痛みは、刺すような鋭い痛みで、体動や深呼吸、圧迫で増悪し、限局した圧痛点があることが多いです。ただし、確実な鑑別には心電図や血液検査が必要です。
Q: 胸痛があるのに心電図が正常なこともありますか?
A: はい、あります。急性心筋梗塞でも初期の心電図では変化が見られないことがあり、時間経過とともに変化が出現することがあります。また、不安定狭心症では安静時の心電図は正常なことも多いです。心電図が正常でも、症状や危険因子から心疾患が疑われる場合は、心筋マーカーの測定や心エコー、冠動脈造影などの追加検査が必要です。
Q: ニトログリセリンはどのような胸痛に効きますか?
A: ニトログリセリンは主に狭心症による胸痛に有効です。冠動脈を拡張させ心筋への血流を改善するため、通常1〜3分で効果が現れます。ただし、心筋梗塞では効果が不十分なことが多く、また食道痙攣でも効果がある場合があるため、ニトログリセリンが効いたからといって必ずしも狭心症とは限りません。使用後は血圧低下に注意が必要です。
Q: 若い人の胸痛は心配しなくてよいですか?
A: いいえ、若年者でも重篤な疾患の可能性があります。気胸は若年の痩せ型男性に多く、大動脈解離はマルファン症候群などの基礎疾患がある場合に若年でも発症します。また、肥満、喫煙、家族歴、薬物使用(覚醒剤など)がある場合は若年でも急性冠症候群のリスクがあります。年齢に関わらず、胸痛は慎重に評価する必要があります。
Q: 女性の心筋梗塞は症状が違うと聞きましたが本当ですか?
A: はい、女性は男性に比べて非典型的な症状を呈することが多いです。典型的な胸痛ではなく、息切れ、吐き気、背部痛、疲労感、めまいなどの症状のみで現れることがあります。このため診断が遅れやすく、注意が必要です。特に閉経後の女性、糖尿病患者では非典型的症状が多いため、胸部不快感や息切れなどの訴えにも注意深く対応しましょう。
Q: 胸痛のある患者への食事で注意することは?
A: 急性期の胸痛患者、特に心疾患が疑われる場合は絶食が原則です。緊急処置や検査、手術の可能性があるためです。また、食事により心臓への負担が増え症状が悪化する可能性もあります。慢性期や症状が安定している場合は、心臓に負担をかけない低脂肪・低塩分食、消化の良い食事、満腹を避けた腹八分目を心がけます。
まとめ
胸痛は生命に関わる重篤な疾患から軽症なものまで多様な原因により生じる症状です。看護師の最も重要な役割は、緊急性を迅速に判断し、適切な初期対応と医師への報告を行うことです。
胸痛のアセスメントでは、OPQRSTを用いた系統的評価とバイタルサインの継続的モニタリングが基本となります。冷汗、顔面蒼白、血圧低下、呼吸困難などの危険なサインを見逃さず、急性冠症候群、大動脈解離、肺血栓塞栓症などの致死的疾患を念頭に置いた観察が必要です。
胸痛患者の多くは「死ぬのではないか」という強い不安と恐怖を感じています。迅速で的確な対応とともに、そばにいて安心感を与える、共感的に傾聴するといった心理的支援も看護の重要な役割です。
実習では、胸痛を訴える患者に遭遇した際、まず緊急性の評価を最優先に行い、必要に応じて速やかに報告・対応できる準備をしておきましょう。また、心電図モニターの波形変化や心筋マーカーの意味を理解し、早期発見・早期対応に貢献できる観察力を養うことが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
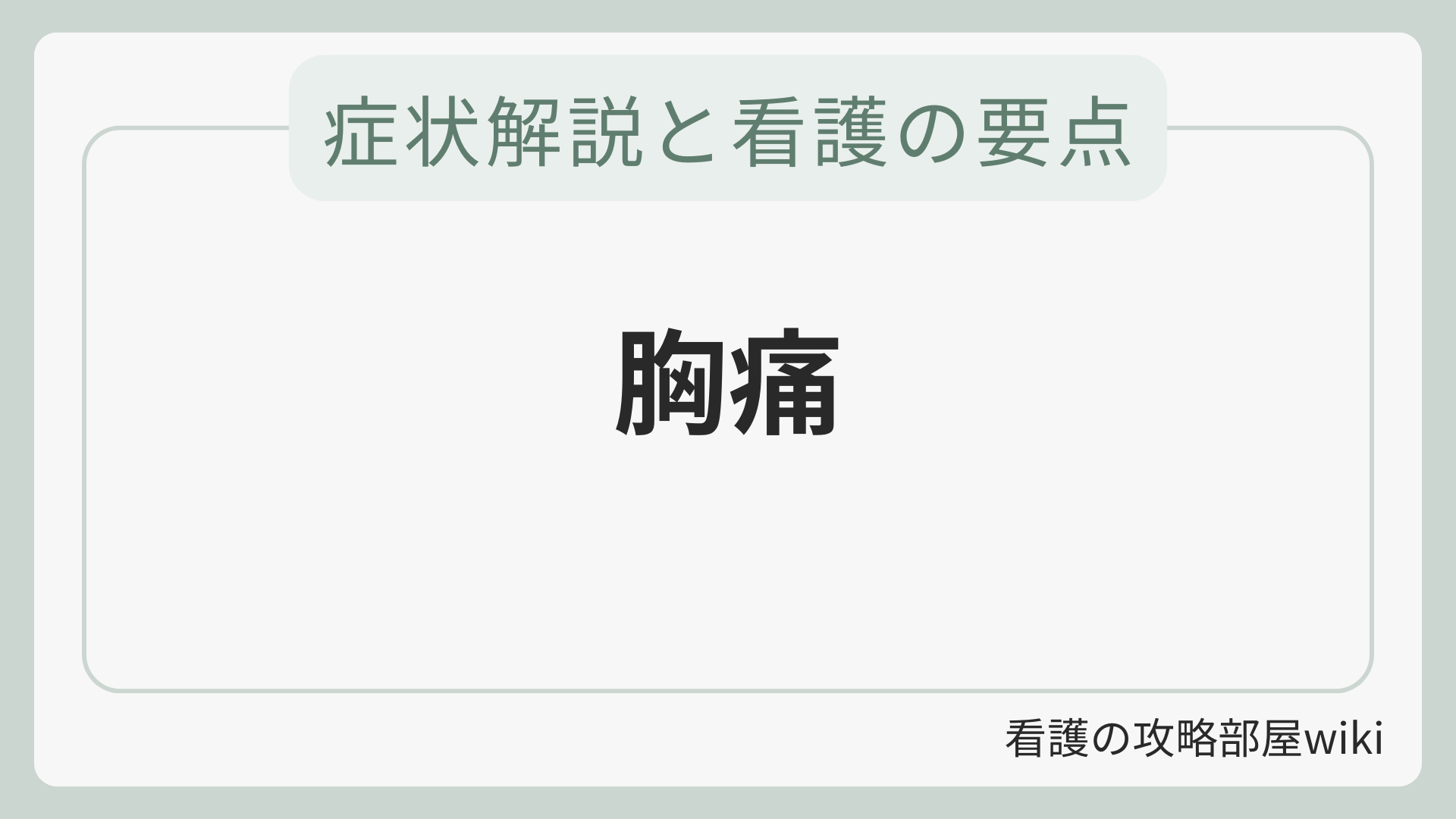
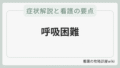
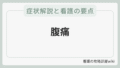
コメント