症状概要
定義
呼吸困難とは、息苦しさや呼吸のしにくさを自覚する主観的な症状です。英語でdyspnea(ディスプニア)と呼ばれ、患者は「息が苦しい」「息が詰まる」「空気が吸えない」「胸が圧迫される」などと表現します。呼吸困難は単なる呼吸数の増加とは異なり、患者が感じる不快な呼吸感覚を指します。生命維持に直結する症状であり、患者に強い不安や恐怖を与えるため、迅速かつ適切な対応が求められます。
疫学
呼吸困難は非常に頻度の高い症状で、救急外来を受診する理由の上位を占めます。急性期病院では入院患者の約20〜30%が何らかの呼吸困難を経験すると言われています。高齢化に伴い、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や心不全などの慢性疾患患者が増加しており、呼吸困難を訴える患者も増加傾向にあります。また、終末期がん患者の約50〜70%が呼吸困難を経験し、QOLに大きな影響を与えます。
原因
呼吸困難の原因は多岐にわたり、呼吸器疾患、心疾患、血液疾患、代謝性疾患、精神的要因などが関与します。主な原因疾患として、急性期では気管支喘息発作、肺炎、気胸、肺血栓塞栓症、急性心不全、ARDSなどがあります。慢性期ではCOPD、間質性肺炎、慢性心不全、貧血などが代表的です。また、過換気症候群のように不安やパニックが原因となることもあります。高齢者では複数の原因が重複していることも多く、鑑別が重要です。
病態生理
呼吸困難は、呼吸中枢への刺激、呼吸筋の過度な負荷、ガス交換の障害などにより生じます。呼吸中枢は延髄に存在し、血中の二酸化炭素濃度上昇や酸素濃度低下、pH変化により刺激されます。肺や気道の受容体からの情報も呼吸中枢に伝わり、呼吸困難感を生じさせます。換気障害では、気道閉塞や肺の拡張制限により呼吸筋が過度に働く必要があり、これが呼吸困難として認識されます。ガス交換障害では、肺胞での酸素取り込みや二酸化炭素排出が障害され、低酸素血症や高二酸化炭素血症を引き起こします。心不全では肺うっ血により肺のコンプライアンスが低下し、呼吸仕事量が増加します。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
呼吸器疾患では、気管支喘息、COPD、肺炎、気胸、肺血栓塞栓症、間質性肺炎、肺がんなどが呼吸困難の原因となります。心疾患では、急性心不全、慢性心不全の増悪、狭心症、心筋梗塞、心筋症、弁膜症などが挙げられます。その他の疾患として、貧血、甲状腺機能亢進症、代謝性アシドーシス、腎不全、神経筋疾患、肥満、過換気症候群などがあります。また、薬剤性(麻薬による呼吸抑制、β遮断薬による気管支収縮など)や環境因子(高地、高温多湿)も原因となります。
評価とアセスメント
呼吸困難の評価では、まず生命の危険性を判断することが最優先です。バイタルサイン(呼吸数、SpO2、血圧、脈拍、体温、意識レベル)を迅速に測定します。呼吸数が25回/分以上または10回/分以下、SpO2が90%以下、チアノーゼ、冷汗、意識レベル低下などは緊急対応が必要なサインです。呼吸困難の程度は修正Borg スケールやHugh-Jones分類を用いて客観的に評価します。随伴症状として、咳嗽、喀痰、胸痛、発熱、浮腫、動悸の有無を確認します。また、発症様式(急性か慢性か)、増悪因子(体動、臥位、時間帯)、既往歴なども重要な情報です。
対応と治療
呼吸困難への対応は原因により異なりますが、共通する初期対応として、まず安楽な体位(セミファーラー位や起座位)をとらせ、酸素投与を開始します。酸素投与は原則としてSpO2を90%以上に保つことを目標とします。ただし、COPD患者では高濃度酸素投与によりCO2ナルコーシスを起こす可能性があるため注意が必要です。原因疾患に対する治療として、気管支喘息では気管支拡張薬やステロイド、肺炎では抗菌薬、心不全では利尿薬や血管拡張薬などを使用します。重症例では非侵襲的陽圧換気(NPPV)や人工呼吸管理が必要となることもあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的呼吸パターン:呼吸困難による呼吸の深さ・リズムの異常
- ガス交換障害:換気血流比不均等による酸素化障害
- 不安:呼吸困難による強い不安と恐怖感
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者が呼吸困難の原因疾患を理解し、増悪因子を避ける行動がとれているかを評価します。慢性呼吸器疾患患者では、症状の悪化に気づく力や受診のタイミングを判断する能力が重要です。活動-運動パターンでは、呼吸困難が日常生活動作にどの程度影響しているかを評価します。Hugh-Jones分類などを用いて労作時呼吸困難の程度を客観的に把握します。コーピング-ストレス耐性パターンでは、呼吸困難による不安や恐怖への対処能力を評価します。呼吸困難は「死ぬのではないか」という強い恐怖を引き起こすため、心理的支援が非常に重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸するニードが最も直接的に障害されています。呼吸数、深さ、リズム、努力呼吸の有無、補助呼吸筋の使用、SpO2、動脈血ガス分析値などを継続的に評価します。安全なニードでは、呼吸困難による転倒リスク、低酸素血症による意識レベル低下のリスクを評価します。また、呼吸困難に伴う不安から危険な行動(酸素チューブを外す、ベッドから降りようとするなど)をとる可能性も考慮します。食べる・飲むニードでは、呼吸困難により食事摂取が困難になることが多く、栄養状態の評価と食事形態の工夫が必要です。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的観察:呼吸数、リズム、深さ、努力呼吸の有無、SpO2の持続モニタリング、チアノーゼの有無、意識レベル、随伴症状の観察
- 呼吸困難の緩和:安楽な体位の工夫(セミファーラー位、起座位、前傾側臥位)、酸素療法の実施と効果判定、呼吸法の指導(口すぼめ呼吸、腹式呼吸)、環境調整(室温、湿度、換気)
- 不安の軽減:傾聴と共感的態度、呼吸が楽になることへの保証、リラクセーション法の指導、家族の付き添い調整、必要時の鎮静薬投与
よくある疑問・Q&A
Q: 呼吸困難と息切れは同じですか?
A: 厳密には異なります。息切れ(breathlessness)は呼吸困難の一種ですが、主に運動時に感じる呼吸の不快感を指します。呼吸困難はより広い概念で、安静時でも感じる息苦しさを含みます。ただし、臨床現場では同じ意味で使われることも多いです。
Q: SpO2が正常なのに呼吸困難を訴える患者にどう対応すればよいですか?
A: SpO2は酸素化の指標であり、換気(二酸化炭素の排出)の状態は反映しません。また、呼吸困難は主観的な症状であり、患者が苦しいと感じていれば、それは真の呼吸困難です。過換気症候群や不安によるものでも、患者の苦痛は本物です。SpO2だけで判断せず、患者の訴えを傾聴し、他のバイタルサインや症状も含めて総合的に評価しましょう。
Q: COPD患者に高濃度酸素を投与してはいけないのはなぜですか?
A: COPD患者の一部は、呼吸中枢が二酸化炭素ではなく低酸素刺激で駆動されています(低酸素性呼吸ドライブ)。高濃度酸素を投与すると低酸素刺激がなくなり、呼吸が抑制されて二酸化炭素が蓄積し、CO2ナルコーシス(意識障害)を起こす可能性があります。ただし、生命の危険がある場合は必要な酸素を投与し、その後呼吸状態を慎重にモニタリングします。
Q: 口すぼめ呼吸はなぜ呼吸困難に有効なのですか?
A: 口すぼめ呼吸は、呼気時に口をすぼめることで気道内圧を高め、気道虚脱を防ぎます。特にCOPDでは呼気時に気道が潰れやすいため、口すぼめ呼吸により空気を効率よく排出でき、次の吸気がしやすくなります。また、呼吸をコントロールしている感覚が不安の軽減にもつながります。
Q: 呼吸困難のある患者に適した体位は?
A: 一般的にはセミファーラー位(30〜45度ヘッドアップ)や起座位(ファーラー位)が推奨されます。重力により横隔膜が下がり、肺の拡張がしやすくなります。また、前傾側臥位(オーバーテーブルに枕を置いて前屈みになる姿勢)も呼吸補助筋が使いやすく有効です。患者が最も楽だと感じる体位を優先し、頻繁に体位変換を行いましょう。
Q: 呼吸困難のある患者への食事で注意することは?
A: 呼吸困難があると食事中に息苦しさが増し、食事摂取量が減少します。対策として、少量頻回の食事、高カロリー・高たんぱく食、食べやすい形態(軟らかく、飲み込みやすいもの)、食事前の呼吸法や酸素投与、食事と食事の間に休息時間を設けるなどの工夫が有効です。また、満腹により横隔膜が挙上すると呼吸困難が悪化するため、腹八分目を心がけます。
まとめ
呼吸困難は生命維持に直結する重要な症状であり、患者に強い不安と恐怖を与えます。看護師は迅速なアセスメントと適切な初期対応により、患者の苦痛を最小限にする役割を担います。
最も重要なのは、緊急性の判断です。呼吸数、SpO2、意識レベル、チアノーゼなどから生命の危険性を素早く評価し、必要に応じて医師への報告や救急対応を行います。同時に、安楽な体位の提供、酸素投与、環境調整などの基本的な看護介入を迅速に実施しましょう。
呼吸困難は主観的な症状であり、患者の訴えを真摯に受け止めることが重要です。SpO2が正常でも患者が苦しいと訴えている場合は、その苦痛は本物です。共感的な態度で傾聴し、「そばにいる」「楽になるよう一緒に考える」という姿勢を示すことで、患者の不安は軽減されます。
実習では、継続的な呼吸状態の観察を確実に行い、わずかな変化も見逃さない観察力を養いましょう。また、口すぼめ呼吸や前傾側臥位などの具体的な呼吸困難緩和法を実践し、患者のQOL向上に貢献することが大切です。呼吸困難のある患者は常に「死の恐怖」と隣り合わせであることを理解し、心理的支援も忘れずに行いましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
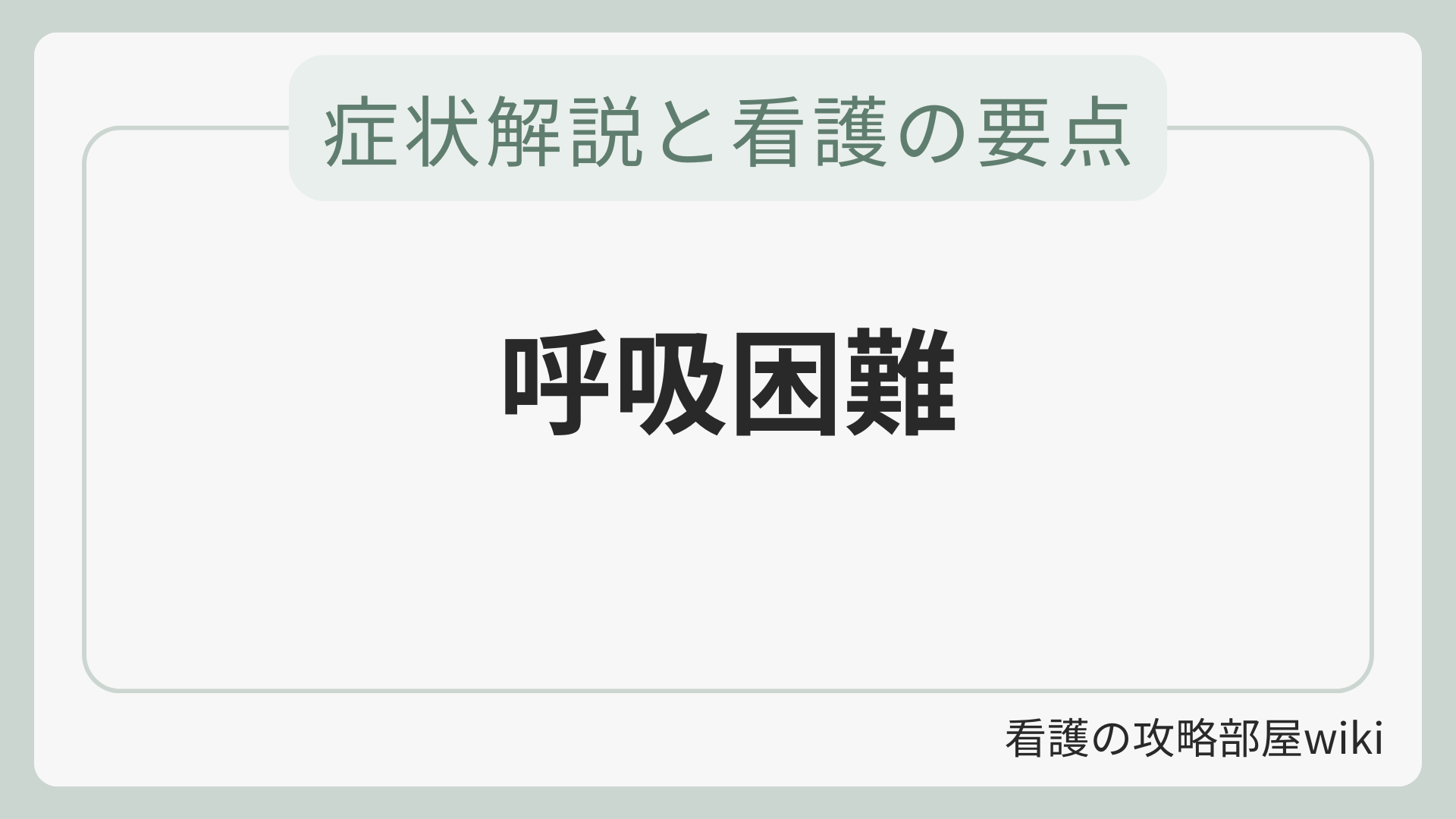
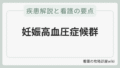
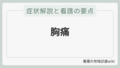
コメント