症状概要
定義
浮腫とは、組織間隙(細胞外)に過剰な体液が貯留した状態です。患者は「むくみ」「腫れぼったい」「靴がきつい」「指輪が抜けない」などと表現します。浮腫は全身性と局所性に分けられ、全身性浮腫は心不全、腎不全、肝硬変などの重篤な疾患を示唆することがあります。局所性浮腫は静脈・リンパ管の閉塞、炎症、外傷などが原因です。浮腫そのものは症状であり、原因疾患の鑑別が非常に重要です。
疫学
浮腫は非常に頻度の高い症状で、特に下肢浮腫は成人の約20〜30%が経験します。高齢者では心不全による浮腫の頻度が高く、心不全患者の約80〜90%に浮腫が認められます。慢性腎臓病(CKD)患者では約60〜70%、肝硬変患者では約50〜60%に浮腫や腹水が出現します。また、長時間の立ち仕事や座り仕事による生理的浮腫も非常に多く見られます。妊娠後期の女性では約70〜80%に下肢浮腫が出現します。
原因
浮腫の原因は多岐にわたります。全身性浮腫の原因として、心不全(うっ血性心不全)、腎疾患(ネフローゼ症候群、急性・慢性腎不全)、肝硬変、低栄養(低アルブミン血症)、甲状腺機能低下症、薬剤性(Ca拮抗薬、NSAIDs、ステロイドなど)があります。局所性浮腫の原因として、深部静脈血栓症(DVT)、静脈瘤、リンパ浮腫(がん術後、放射線治療後)、蜂窩織炎、外傷、アレルギー反応などが挙げられます。生理的浮腫として、長時間の立位・座位、月経前症候群、妊娠なども原因となります。
病態生理
浮腫はStarlingの法則により、毛細血管内外の圧較差と血管透過性により決定されます。浮腫が生じるメカニズムは、①毛細血管内圧の上昇(心不全、静脈閉塞)、②血漿膠質浸透圧の低下(低アルブミン血症)、③血管透過性の亢進(炎症、アレルギー)、④リンパ管の閉塞(リンパ浮腫)、⑤ナトリウム・水分貯留(腎不全、肝硬変)に分けられます。心不全では右心不全により静脈圧が上昇し、下肢から浮腫が始まります。ネフローゼ症候群では大量の蛋白尿により低アルブミン血症となり、顔面から浮腫が始まります。肝硬変ではアルブミン合成低下と門脈圧亢進により腹水と下肢浮腫を生じます。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
緊急対応が必要な疾患として、急性心不全(肺水腫を伴う)、深部静脈血栓症(肺血栓塞栓症のリスク)、急性腎不全、アナフィラキシー(喉頭浮腫)、上大静脈症候群などがあります。全身性浮腫の原因疾患として、うっ血性心不全、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、肝硬変、低栄養・悪液質、甲状腺機能低下症、薬剤性浮腫などが挙げられます。局所性浮腫の原因疾患として、深部静脈血栓症、下肢静脈瘤、リンパ浮腫、蜂窩織炎、外傷後浮腫、区画症候群などがあります。生理的浮腫として、長時間立位・座位、月経前症候群、妊娠性浮腫などが含まれます。
評価とアセスメント
浮腫の評価では、まず全身性か局所性かを判断します。全身性浮腫は両側対称性で重力の影響を受け、下肢、仙骨部、顔面に出現します。局所性浮腫は片側性または限局性です。バイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数、SpO2、体温)を測定し、全身状態を評価します。浮腫の程度は圧痕の有無と深さで評価し、指で10秒間圧迫後の圧痕の深さで、+(2mm未満)、++(2〜4mm)、+++(4〜6mm)、++++(6mm以上)と記録します。浮腫の部位(下肢、顔面、手指、仙骨部、全身)、左右差の有無、発症時期(急性か慢性か)、日内変動(朝悪化は腎疾患、夕方悪化は心不全や静脈うっ滞)を確認します。随伴症状として、呼吸困難、体重増加、尿量減少、腹部膨満(腹水)、疼痛、発赤、熱感も評価します。
対応と治療
浮腫への対応は原因疾患により異なります。心不全では利尿薬(ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬)、ACE阻害薬、β遮断薬などによる心不全治療、水分・塩分制限が基本です。腎疾患では利尿薬、蛋白尿に対する治療(ACE阻害薬、ARB)、透析療法を検討します。肝硬変では利尿薬(スピロノラクトン併用)、アルブミン製剤投与、腹水穿刺を行います。深部静脈血栓症では抗凝固療法と下肢挙上、弾性ストッキング装着が必要です。リンパ浮腫では圧迫療法、リンパドレナージ、運動療法を行います。生理的浮腫では下肢挙上、弾性ストッキング、適度な運動、塩分制限が有効です。一般的な浮腫管理として、水分・塩分制限、体重測定、下肢挙上、皮膚ケアが重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 体液量過剰:心不全、腎不全、肝硬変などによる体液貯留
- 皮膚統合性障害リスク:浮腫による皮膚の脆弱化と損傷リスク
- 活動耐性低下:浮腫による体動困難と呼吸困難
ゴードン機能的健康パターン
栄養-代謝パターンでは、水分・塩分摂取量、食事内容、体重変化(急激な体重増加は浮腫悪化を示唆)を評価します。低栄養による低アルブミン血症も浮腫の原因となるため、栄養状態の評価も重要です。排泄パターンでは、尿量と尿の性状(蛋白尿、血尿)を確認します。心不全や腎不全では尿量減少が浮腫悪化の指標となります。水分出納バランス(IN-OUT)の計算により体液貯留の程度を評価します。活動-運動パターンでは、浮腫により歩行困難、靴が履けない、階段昇降時の息切れなど、日常生活動作への影響を評価します。下肢浮腫は転倒リスクも高めます。認知-知覚パターンでは、浮腫部位の疼痛、圧迫感、重だるさなどの不快感を評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸するニードでは、心不全による肺うっ血・肺水腫では呼吸困難が出現するため、呼吸数、SpO2、起座呼吸の有無、湿性ラ音の有無を評価します。浮腫の悪化は呼吸状態の悪化を示唆することがあります。食べる・飲むニードでは、浮腫管理のための水分・塩分制限が必要となることが多く、制限量の遵守状況と患者の受け入れ度を評価します。腹水による腹部膨満では食事摂取が困難になることもあります。清潔と皮膚の統合性を保つニードでは、浮腫により皮膚が脆弱化し、圧迫や摩擦により容易に損傷するため、皮膚の観察と保護が非常に重要です。特に下腿の浮腫部位は褥瘡や創傷治癒遅延のリスクが高まります。
看護計画・介入の内容
- 浮腫の継続的評価:浮腫の部位・程度・左右差の観察と記録(圧痕の深さ評価)、体重測定(毎日同一条件で)、水分出納バランスの計算、腹囲測定(腹水の場合)、バイタルサインの継続的モニタリング、呼吸状態の観察(肺水腫の徴候)
- 体液バランスの管理:水分・塩分制限の遵守支援(具体的な摂取量の指導)、利尿薬の投与と効果判定、尿量測定と記録、電解質データの確認(低カリウム血症に注意)、体重増加の早期発見
- 皮膚ケアと循環促進:浮腫部位の皮膚観察(発赤、損傷、感染徴候)、保湿ケア(乾燥による亀裂予防)、下肢挙上(心臓より高い位置に30分以上、1日数回)、弾性ストッキングの着用支援、適度な運動の促進(筋ポンプ作用の活用)、圧迫や摩擦の回避
よくある疑問・Q&A
Q: 心不全の浮腫と腎疾患の浮腫の違いは何ですか?
A: 心不全の浮腫は下肢から始まり、夕方に悪化する傾向があります。重力の影響を受けるため、臥床患者では仙骨部に出現します。呼吸困難や起座呼吸を伴うことが多いです。一方、腎疾患(特にネフローゼ症候群)の浮腫は顔面、特に眼瞼から始まり、朝起床時に悪化します。全身に広がりやすく、大量の蛋白尿を伴います。ただし、慢性腎不全では心不全と同様に下肢浮腫が主体となります。
Q: 圧痕性浮腫と非圧痕性浮腫の違いは何ですか?
A: 圧痕性浮腫は指で圧迫すると圧痕が残るタイプで、心不全、腎不全、肝硬変、低栄養など、水分貯留が主体の浮腫で見られます。非圧痕性浮腫は圧迫しても圧痕が残らないタイプで、リンパ浮腫、甲状腺機能低下症(粘液水腫)、慢性静脈不全の晩期などで見られます。リンパ浮腫では蛋白成分が多く、組織が線維化しているため圧痕が残りにくくなります。
Q: 深部静脈血栓症による浮腫の特徴は?
A: 深部静脈血栓症(DVT)の浮腫は片側性で急激に発症するのが特徴です。患側の下肢全体が腫脹し、疼痛、発赤、熱感、表在静脈の怒張を伴います。Homans徴候(足関節を背屈させると腓腹部に痛みが生じる)が陽性となることがあります。DVTは肺血栓塞栓症の原因となるため、緊急対応が必要です。片側性の突然の下肢浮腫は必ずDVTを疑いましょう。
Q: リンパ浮腫はなぜ起こるのですか?
A: リンパ浮腫はリンパ管の閉塞や機能不全により、組織液(リンパ液)が適切に排出されず貯留することで生じます。原因として、がん手術でのリンパ節郭清、放射線治療によるリンパ管損傷、がんのリンパ節転移による閉塞などがあります(二次性リンパ浮腫)。また、先天的なリンパ管形成不全による一次性リンパ浮腫もあります。一度発症すると完治は困難で、圧迫療法やリンパドレナージによる継続的な管理が必要です。
Q: 浮腫のある患者への弾性ストッキングの使い方は?
A: 弾性ストッキングは朝起床前、臥床時に装着するのが最も効果的です。一晩の臥床で浮腫が最も軽減している状態で着用することで、日中の浮腫予防効果が高まります。装着時は皮膚を清潔にし、保湿剤を塗布後、しわやねじれがないように注意します。圧迫圧は症状に応じて選択し、一般的には15〜25mmHgの軽圧から始めます。深部静脈血栓症や重度の動脈閉塞性疾患、皮膚感染症がある場合は禁忌です。
Q: 浮腫患者の体重測定で注意することは?
A: 体重測定は毎日同一条件(同じ時刻、排尿後、同じ衣服)で行うことが重要です。最も正確なのは朝起床後、排尿後、朝食前の測定です。1〜2日で1〜2kg以上の急激な体重増加は体液貯留を示し、心不全の増悪などを疑います。逆に急激な体重減少は利尿薬の効果や脱水を示唆します。体重変化は浮腫の程度を客観的に評価する重要な指標です。
まとめ
浮腫は組織間隙への過剰な体液貯留により生じる症状で、その原因は心不全、腎疾患、肝硬変などの重篤な疾患から生理的なものまで多岐にわたります。看護師の重要な役割は、全身性か局所性か、両側性か片側性かを判断し、原因疾患を推測して適切な対応につなげることです。
特に、急激に発症する片側性の下肢浮腫は深部静脈血栓症を疑い緊急対応が必要です。また、急激な体重増加や呼吸困難を伴う浮腫は心不全の増悪を示唆し、早期発見と迅速な対応が求められます。
浮腫管理の基本は、体重測定、水分出納バランスの計算、浮腫の程度の客観的評価です。圧痕の深さを数値化して記録し、経時的変化を評価しましょう。また、浮腫により皮膚が脆弱化するため、スキンケアと損傷予防も重要な看護介入となります。
実習では、浮腫の観察を通じて、患者の全身状態や疾患の経過を把握する力を養いましょう。浮腫の部位・程度・性状の正確な観察と、原因疾患を意識したアセスメントを心がけることで、より質の高い看護につながります。患者にとって浮腫は不快で日常生活に支障をきたす症状であることを理解し、QOL向上を目指した包括的なケアを提供することが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
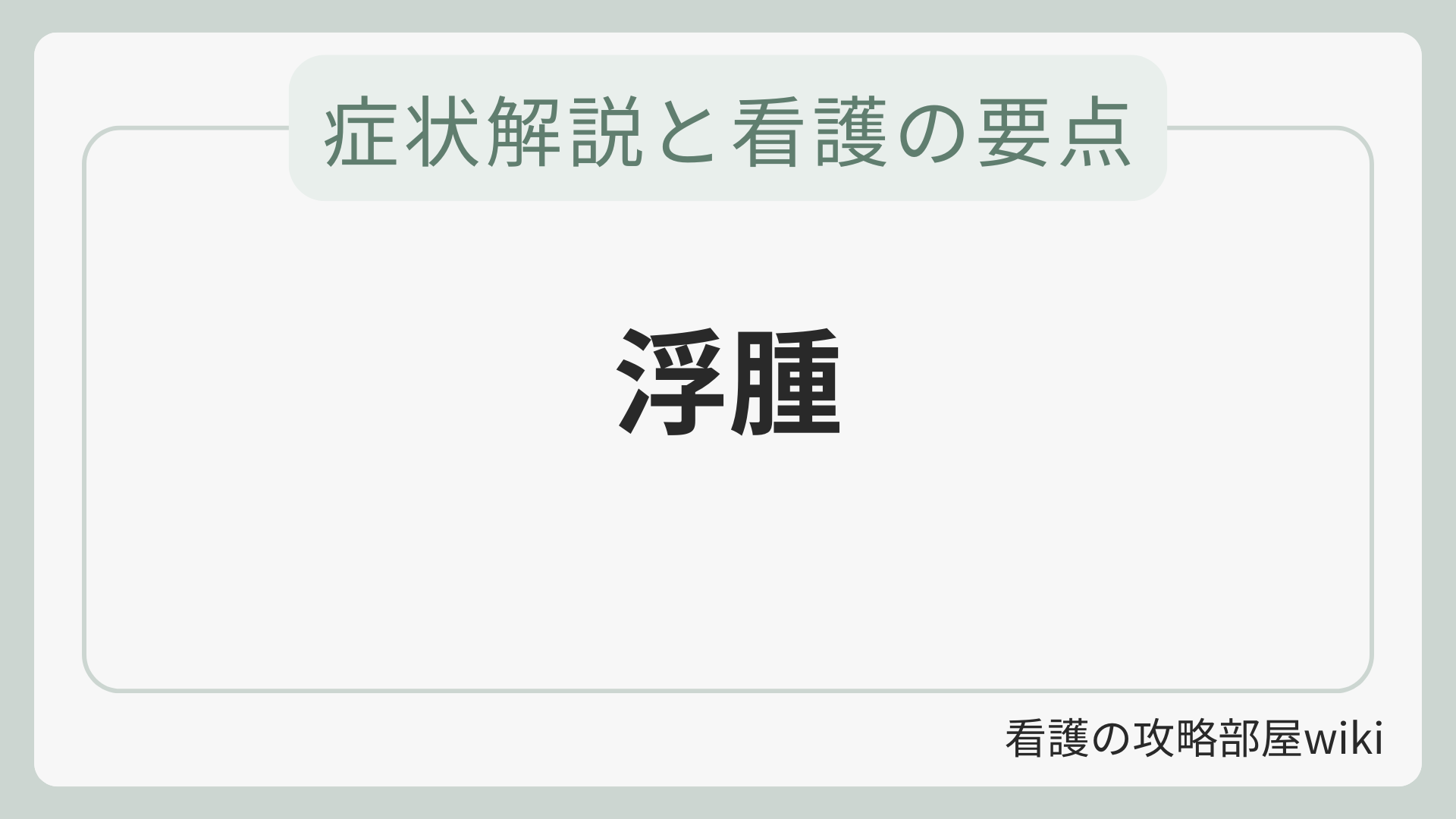
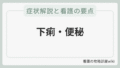
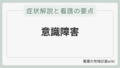
コメント