事例の要約
末期腎不全で血液透析導入となった高齢男性の事例。入院から透析導入を経て、透析生活への適応を目指している段階での介入である。介入は入院14日目に行われた。
基本情報
A氏は78歳の男性で、身長は162cm、体重は入院時58kgであったが現在は54kgである。妻と二人暮らしで、キーパーソンは妻である。長男と長女は県外に在住しており、月に1回程度帰省する。退職前は建設会社の事務職として勤務していた。性格は温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢がある。感染症はなく、アレルギーも特にない。認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。
病名
病名は末期腎不全であり、内シャント造設術を施行されている。
既往歴と治療状況
既往歴として糖尿病があり、15年前から内服治療を継続していた。また10年前には高血圧症を指摘され降圧薬を服用している。5年前から慢性腎臓病として通院していたが、この1年で腎機能が急速に悪化し、血液透析導入の方針となった。
入院から現在までの情報
入院から現在までの経過として、腎機能低下による倦怠感と食欲不振が増強したため入院となった。入院時の血清クレアチニン値は8.2mg/dLと著明に上昇しており、尿毒症症状も認められた。入院3日目に左前腕に内シャント造設術が施行され、術後経過は良好であった。入院10日目からシャント血管の発達を待って血液透析が開始された。現在は週3回、月水金の午前中に透析を実施している。透析時間は1回4時間である。透析導入後は倦怠感が軽減し、食欲も徐々に改善傾向にある。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、体温36.8℃、脈拍88回/分で整、血圧168/96mmHg、呼吸数20回/分、SpO2 96%であった。現在のバイタルサインは、透析後の測定で体温36.5℃、脈拍72回/分で整、血圧142/84mmHg、呼吸数18回/分、SpO2 98%である。透析前は血圧が152/88mmHg程度に上昇し、体重も56kg程度まで増加する傾向がある。
食事と嚥下状態
入院前の食事は、妻が腎臓病食を意識して調理していたが、蛋白質制限が中心で塩分管理は不十分であった。1日3食摂取していたが食欲低下のため摂取量は5割程度であった。嚥下機能に問題はない。現在は透析食が提供されており、カリウム制限とリン制限が中心となっている。食欲は改善し7割程度摂取できている。喫煙歴はなく、飲酒は以前は晩酌程度であったが腎機能低下後は中止している。
排泄
入院前の排泄は、排尿回数が1日4回程度と減少しており、尿量も400mL/日程度であった。排便は2日に1回程度で、便秘傾向があった。現在は尿量がさらに減少し、1日200mL程度となっている。排便は透析の影響もあり便秘が増強し、3日に1回程度である。下剤として酸化マグネシウムは使用できないため、ピコスルファートナトリウム水和物を適宜使用している。
睡眠
入院前の睡眠は23時頃に就寝し6時に起床しており、中途覚醒が1回程度あった。現在は入院環境と透析導入への不安から入眠困難があり、眠剤としてゾルピデム酒石酸塩5mgを就寝前に使用している。透析のある日は疲労感が強く、日中に傾眠傾向がある。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼があるが眼鏡を使用すれば新聞を読むことができる。聴力は正常で会話に支障はない。知覚に異常はなく、コミュニケーションは良好である。信仰は特にない。
動作状況
歩行は自立しており、病棟内は杖なしで移動可能である。移乗動作も自立している。排泄動作は自立しているが、透析後は疲労感があるためナースコールで見守りを依頼することがある。入浴は週2回の清拭と洗髪を実施しており、シャント側の上肢は濡らさないよう注意している。衣類の着脱は自立しているが、シャント側の袖を通す際には注意が必要である。転倒歴は入院後はない。
内服中の薬
内服中の薬は以下の通りである。
・アムロジピンベシル酸塩5mg 1回1錠 1日1回朝食後
・カルベジロール10mg 1回1錠 1日2回朝夕食後
・炭酸ランタン水和物250mg 1回1錠 1日3回毎食後
・沈降炭酸カルシウム500mg 1回1錠 1日3回毎食後
・エポエチンベータペゴル50μg 月2回透析時に皮下注射
・ゾルピデム酒石酸塩5mg 1回1錠 1日1回就寝前
服薬状況は、透析導入前は自己管理であったが、現在は看護師管理となっている。透析日は透析後に内服するよう調整されている。
検査データ
検査データは以下の通りである。
| 項目 | 入院時 | 最近(入院12日目) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6,800 | 6,200 | 3,300-8,600 /μL |
| RBC | 285万 | 310万 | 435-555万 /μL |
| Hb | 8.2 | 9.1 | 13.7-16.8 g/dL |
| Ht | 26.5 | 28.8 | 40.7-50.1 % |
| PLT | 18.5万 | 19.2万 | 15.8-34.8万 /μL |
| TP | 6.2 | 6.5 | 6.6-8.1 g/dL |
| Alb | 3.2 | 3.4 | 4.1-5.1 g/dL |
| BUN | 82 | 45 | 8-20 mg/dL |
| Cr | 8.2 | 4.5 | 0.65-1.07 mg/dL |
| eGFR | 5.8 | 10.2 | 60以上 mL/min/1.73m² |
| Na | 138 | 140 | 138-145 mEq/L |
| K | 5.8 | 4.9 | 3.6-4.8 mEq/L |
| Cl | 105 | 103 | 101-108 mEq/L |
| Ca | 8.2 | 8.6 | 8.8-10.1 mg/dL |
| P | 6.8 | 5.2 | 2.7-4.6 mg/dL |
| HbA1c | 6.8 | 6.5 | 4.9-6.0 % |
| CRP | 0.8 | 0.3 | 0.00-0.14 mg/dL |
今後の治療方針と医師の指示
今後の治療方針として、週3回の維持透析を継続しながら、透析間の体重増加を3kg以内に抑えることを目標とする。ドライウェイトは54kgに設定されており、透析条件は適宜調整する方針である。貧血に対してはエリスロポエチン製剤を継続し、Hb値10g/dL以上を目標とする。リン吸着薬と活性型ビタミンD製剤により二次性副甲状腺機能亢進症の予防を図る。医師からは自宅退院に向けて透析生活の確立と、シャント管理の習得が指示されている。退院後は外来透析へ移行する予定である。
本人と家族の想いと言動
本人は「こんなに大変な治療になるとは思わなかった。でも生きるためには仕方ないですね」と透析導入を受け入れつつも、今後の生活への不安を口にする。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」と家族への負担を気にする発言も聞かれる。透析日は特に疲れやすく、「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」と活動制限への懸念を示している。妻は「透析が必要になったことは残念ですが、これで少しでも元気になってくれるなら」と前向きに捉えようとしている。一方で「家での食事管理が難しそうで不安です。カリウムやリンのことをもっと勉強しなければ」と、退院後の食事管理への不安を表出している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
末期腎不全は腎臓の機能が正常の15%未満に低下した状態であり、体内の老廃物や余分な水分を排泄できなくなる。A氏は糖尿病を15年間罹患しており、糖尿病性腎症が進行して末期腎不全に至ったと考えられる。慢性腎臓病として5年前から経過観察されていたが、この1年で腎機能が急速に悪化し血液透析導入となった。末期腎不全では体液貯留による肺水腫や胸水貯留、尿毒症による心膜炎などが呼吸機能に影響を及ぼす可能性がある。また貧血の進行により酸素運搬能が低下し、呼吸器系への負担が増大する。
呼吸数、SpO2、肺雑音、呼吸機能、胸部レントゲン
A氏の来院時の呼吸数は20回/分とやや頻呼吸であり、SpO2は96%と正常範囲内であった。現在は透析後の測定で呼吸数18回/分、SpO2 98%と改善している。透析導入前は体液貯留により呼吸数が増加していたと推測されるが、透析により除水が行われたことで呼吸状態が安定してきている。78歳という高齢であることから、加齢による肺活量の低下や呼吸筋力の減弱が基礎にある可能性がある。肺雑音の有無や呼吸様式については情報が不足しており、聴診所見や呼吸の深さ、リズムの規則性などの追加情報収集が必要である。また胸部レントゲン所見についても記載がないため、心拡大や胸水貯留の有無、肺うっ血の程度を確認する必要がある。透析導入後の胸部レントゲン所見と比較することで、除水効果や循環動態の改善を評価できる。
呼吸苦、息切れ、咳、痰
A氏の自覚症状として呼吸苦や息切れ、咳、痰に関する具体的な記載がない。入院時の主訴は倦怠感と食欲不振であり、呼吸器症状は前面に出ていなかったと考えられる。しかし呼吸数20回/分という軽度の頻呼吸があったことから、体液貯留による軽度の呼吸苦や労作時の息切れがあった可能性は否定できない。透析導入後は呼吸数が改善しSpO2も上昇していることから、除水により呼吸状態が改善したと推測される。現在の呼吸器症状の有無や程度について、安静時と活動時の呼吸苦の有無、階段昇降や歩行時の息切れの程度、夜間の起座呼吸や発作性夜間呼吸困難の有無などを詳細に聴取する必要がある。また尿毒症による心膜炎や胸膜炎が生じると咳や胸痛が出現することがあるため、継続的な観察が重要である。
喫煙歴
A氏に喫煙歴はなく、呼吸器系への直接的な喫煙の影響はない。非喫煙者であることは慢性閉塞性肺疾患や肺癌のリスクが低く、呼吸機能の面では有利な因子である。ただし78歳という高齢であることから、受動喫煙の影響や過去の職業環境における粉塵曝露などの可能性については確認が必要である。建設会社の事務職として勤務していたとのことで、現場作業に従事していた場合と比較すると粉塵曝露のリスクは低いと考えられるが、職場環境について追加情報を得ることが望ましい。
呼吸に関するアレルギー
A氏にはアレルギーが特にないとされており、気管支喘息やアレルギー性鼻炎などの呼吸器系アレルギー疾患の既往はないと判断できる。これは呼吸管理において有利な因子である。ただし薬剤アレルギーの有無や食物アレルギーの詳細については明記されていないため、透析導入後に使用される薬剤に対する過敏反応の可能性を考慮し、初回投与時の観察を継続する必要がある。
ニーズの充足状況
A氏の正常に呼吸するというニーズは、現時点では概ね充足されている。透析導入により除水が行われ、呼吸数が20回/分から18回/分へと改善し、SpO2も96%から98%へと上昇している。これは体液貯留が軽減され肺への負担が減少したことを示唆している。ただし貧血が持続しており、入院時のヘモグロビン値8.2g/dLから9.1g/dLへとわずかな改善にとどまっている。正常値の13.7g/dL以上と比較すると依然として著明な貧血であり、酸素運搬能の低下により組織低酸素状態が続いている。このため活動時の息切れや易疲労感が生じやすい状態である。透析日は特に疲労感が強いとA氏が訴えていることから、透析による循環動態の変化や除水による血圧低下が呼吸や全身状態に影響している可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の呼吸に関する主な課題は、貧血による酸素運搬能の低下と透析に伴う循環動態の変化である。エリスロポエチン製剤の継続投与によりヘモグロビン値10g/dL以上を目標とする治療が行われているが、改善には時間を要する。看護介入として、透析前後のバイタルサインの詳細な観察、特に呼吸数、SpO2、呼吸様式の変化を継続的にモニタリングする必要がある。透析中の除水速度が速すぎると血圧低下や呼吸困難を引き起こす可能性があるため、透析中の症状観察も重要である。また活動耐性の評価として、日常生活動作時の息切れの程度や疲労感を定期的に聴取し、必要に応じて活動量の調整を行う。胸部レントゲン所見の確認と肺雑音の有無を含めた呼吸器系の詳細な身体所見を収集し、体液管理の適切性を評価する必要がある。透析間の体重増加を3kg以内に抑えることが指示されているため、水分制限の遵守状況と体液貯留の兆候を継続的に観察することが求められる。さらに退院後の生活を見据えて、A氏と妻に対して体液貯留の症状や呼吸困難の早期発見方法について教育を行い、セルフモニタリング能力を高めることが重要である。
食事と水分の摂取量と摂取方法
A氏は入院前、妻が腎臓病食を意識して調理した食事を1日3食摂取していたが、腎機能低下に伴う食欲不振により摂取量は5割程度に低下していた。蛋白質制限が中心の献立であったが、塩分管理は不十分であったことから、体液貯留や血圧上昇の一因となっていた可能性がある。現在は透析食が提供されており、カリウム制限とリン制限を中心とした食事内容となっている。透析導入後は倦怠感が軽減したことで食欲が改善し、現在は7割程度摂取できている。嚥下機能に問題はなく、経口摂取が自立している。水分摂取については、透析間の体重増加を3kg以内に抑える必要があるため、厳格な水分制限が求められている。透析導入前は尿量が400mL/日程度であったが、現在は200mL/日程度とさらに減少しており、水分制限の遵守が極めて重要な状況である。具体的な1日の水分摂取量や水分制限の指示量については明記されていないため、追加情報の収集が必要である。
食事に関するアレルギー
A氏には食物アレルギーは特にないとされており、食事制限においてアレルギーを考慮する必要はない。これは透析食の献立作成において有利な因子である。ただし薬剤アレルギーの詳細については明記されていないため、透析導入後に使用される薬剤や栄養補助食品に対する過敏反応の可能性を念頭に置く必要がある。
身長、体重、BMI、必要栄養量、身体活動レベル
A氏の身長は162cm、入院時体重は58kgであったが現在は54kgと4kgの体重減少を認めている。BMIは入院時22.1kg/m²、現在20.8kg/m²であり、いずれも正常範囲内であるが減少傾向にある。この体重減少は透析による除水効果が主な要因と考えられるが、入院前の食欲不振による摂取不足も影響している可能性がある。78歳という高齢であることから、加齢による筋肉量の減少やサルコペニアのリスクも考慮する必要がある。透析患者の必要栄養量は、エネルギーとして30から35kcal/kg/日、蛋白質として0.9から1.2g/kg/日が推奨される。A氏の現在の体重54kgで計算すると、エネルギーは1620から1890kcal/日、蛋白質は48.6から64.8g/日が必要となる。身体活動レベルは病棟内を歩行可能であるが、透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、活動量は低下している。透析導入により活動耐性が低下していることを考慮し、栄養摂取量と活動量のバランスを評価する必要がある。
食欲、嚥下機能、口腔内の状態
A氏は入院前、腎機能低下による尿毒症症状として食欲不振が顕著であり、摂取量は5割程度であった。透析導入後は老廃物の除去により食欲が改善し、現在は7割程度摂取できている。しかし依然として正常な摂取量には至っておらず、さらなる改善の余地がある。食欲低下の要因として、透析による疲労感や透析食の味付けの制限、入院環境でのストレスなどが考えられる。嚥下機能については問題がなく、誤嚥のリスクは低いと判断できる。口腔内の状態については具体的な記載がないため、歯の状態、義歯の有無、口腔粘膜の状態、口臭の有無などの追加情報が必要である。高齢者では口腔内の乾燥や歯周病が食欲低下や摂食障害の原因となることがあり、また透析患者では尿毒症による口腔内の不快感や口臭が食欲に影響することがある。
嘔吐、吐気
A氏の現在の状態として嘔吐や吐気に関する記載はなく、消化器症状は認めていないと考えられる。入院時は尿毒症症状として食欲不振があったが、透析導入により改善している。透析患者では透析中や透析後に血圧低下や不均衡症候群により吐気や嘔吐を生じることがあるため、透析時の消化器症状の有無を継続的に観察する必要がある。また糖尿病の既往があることから、糖尿病性胃不全麻痺による消化器症状の可能性も考慮すべきである。
血液データ(TP、Alb、Hb、TG)
総蛋白は入院時6.2g/dLから現在6.5g/dLとわずかに上昇しているが、基準値6.6から8.1g/dLと比較するとやや低値である。アルブミンは入院時3.2g/dLから現在3.4g/dLと改善傾向にあるが、基準値4.1から5.1g/dLと比較すると著明な低値であり、低栄養状態を示している。ヘモグロビンは入院時8.2g/dLから現在9.1g/dLと改善しているが、基準値13.7から16.8g/dLと比較すると著明な貧血が持続している。この貧血は腎性貧血であり、エリスロポエチン産生低下が主な原因である。トリグリセライドについては記載がないため、脂質代謝の評価のために追加情報が必要である。アルブミン低値は蛋白摂取不足や透析による蛋白喪失、慢性炎症などを反映している可能性がある。高齢者では加齢による蛋白合成能の低下も影響する。
ニーズの充足状況
A氏の適切に飲食するというニーズは部分的に充足されているが、いくつかの課題が残されている。透析導入により食欲は改善したものの、摂取量は7割程度にとどまっており、必要栄養量を十分に満たしていない可能性がある。アルブミン3.4g/dLという低値は栄養状態の改善が不十分であることを示している。体重が入院時58kgから現在54kgへと減少しており、除水効果だけでなく栄養摂取不足による体重減少の可能性も考慮する必要がある。透析食の制限により食事の嗜好性が低下していることや、透析による疲労感が食欲に影響していることが推測される。水分制限については、透析間の体重増加を3kg以内に抑えることが目標とされているが、現在の遵守状況や具体的な水分摂取量については情報が不足している。A氏は「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」と述べており、退院後の食事管理への不安を抱えている。妻も「家での食事管理が難しそうで不安です。カリウムやリンのことをもっと勉強しなければ」と食事療法への不安を表出している。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の栄養に関する主な課題は、低栄養状態の改善と透析食への適応、水分制限の遵守である。アルブミン低値と体重減少を改善するため、透析食の摂取量を増やす工夫が必要である。看護介入として、食事摂取量を毎食記録し、具体的なカロリーと蛋白質摂取量を評価する。食欲低下の要因を多角的にアセスメントし、口腔内の状態確認、食事の味付けや温度の工夫、食事時間の調整などを行う。透析日は疲労感が強いため、透析後の食事提供時間を調整したり、少量頻回の食事提供を検討する。栄養士と連携し、A氏の嗜好を取り入れた献立の工夫や、カリウムとリンを制限しながらも食べやすい食事内容を検討する。水分制限については、1日の水分摂取量を正確に記録し、透析間の体重増加を毎回測定する。水分制限の具体的な指示量を確認し、A氏がセルフモニタリングできるよう教育する。退院に向けて、A氏と妻に対して透析食の具体的な献立例や調理方法、外食時の注意点などを指導する。カリウム含有量の多い食品やリン含有量の多い食品のリストを提供し、食品選択の方法を具体的に説明する。妻の不安を軽減するため、栄養指導の機会を複数回設け、質問に丁寧に答える体制を整える。アルブミン値とヘモグロビン値の推移を継続的にモニタリングし、栄養状態と貧血の改善を評価する。必要に応じて栄養補助食品の使用も検討する。
排便回数と量と性状、排尿回数と量と性状、発汗
A氏の排便状況は、入院前から便秘傾向があり2日に1回程度であった。現在は透析の影響もあり便秘が増強し、3日に1回程度となっている。便の量や性状については具体的な記載がないため、硬便か軟便か、排便時の努責の有無、腹部膨満感の程度などの追加情報が必要である。高齢者では腸蠕動運動の低下や腹筋力の減弱により便秘が生じやすく、さらに透析患者では水分制限や活動量の低下が便秘を助長する。排尿状況は、入院前は排尿回数が1日4回程度と減少しており、尿量も400mL/日程度であった。現在は尿量がさらに減少し1日200mL/日程度となっている。これは末期腎不全の進行により腎臓の尿濃縮能と排泄機能が著しく低下していることを示している。排尿回数や尿の性状、排尿時の不快感の有無については具体的な記載がない。透析患者では残存腎機能の保持が重要であるため、尿量の推移を継続的に観察する必要がある。発汗については記載がないが、透析患者では体液貯留により発汗が減少することがある。また透析中の除水により血圧が低下すると冷汗を生じることがあるため、透析中の発汗状態の観察も重要である。
in-outバランス
A氏の水分出納バランスは末期腎不全により大きく障害されている。尿量が200mL/日程度と著明に減少しているため、摂取した水分のほとんどが体内に貯留する状態である。透析により週3回除水が行われているが、透析間の体重増加を3kg以内に抑えることが目標とされている。入院時体重58kgから現在54kgへと4kgの減少を認めており、これは透析導入による除水効果を反映している。ドライウェイトは54kgに設定されており、透析前には56kg程度まで増加する傾向がある。この2kgの増加は透析間に貯留した水分量を示している。具体的な1日の水分摂取量と不感蒸泄量、便による水分喪失量を把握し、透析による除水量との関係を詳細に評価する必要がある。体重増加が3kgを超える場合は体液過剰となり、心不全や肺水腫のリスクが高まる。入院前の血圧168/96mmHgは体液貯留による循環血液量の増加を反映していた可能性がある。
排泄に関連した食事、水分摂取状況
A氏の食事は現在透析食が提供されており、カリウム制限とリン制限が中心となっている。食物繊維の摂取状況については具体的な記載がないが、カリウム制限により野菜や果物の摂取が制限されると食物繊維摂取量が減少し、便秘を助長する可能性がある。水分摂取については厳格な制限が必要であるが、具体的な1日の水分制限量や現在の摂取量については明記されていない。便秘予防のためには適度な水分摂取が望ましいが、透析患者では水分制限との兼ね合いが困難である。入院前は妻が腎臓病食を意識して調理していたが、塩分管理が不十分であったことが体液貯留を助長していた可能性がある。現在の食事摂取量は7割程度であり、食物繊維を含む食品の摂取状況を評価する必要がある。
麻痺の有無
A氏に麻痺はなく、運動機能は保たれている。歩行は自立しており、病棟内は杖なしで移動可能である。排泄動作も自立しているため、排便や排尿の際の体位変換や努責に問題はない。ただし透析後は疲労感があるため、ナースコールで見守りを依頼することがある。麻痺がないことは排泄動作の自立において有利な因子であるが、透析による疲労感が排泄行動に影響を与えている。
腹部膨満、腸蠕動音
腹部膨満や腸蠕動音については具体的な記載がない。便秘が増強していることから、腹部膨満感の有無や程度を評価する必要がある。腸蠕動音の聴取により腸管の活動性を確認し、便秘の程度や腸閉塞のリスクを評価する。また腹部の触診により便塊の有無や圧痛の有無を確認することが重要である。透析患者では体液貯留により腹水が貯留することもあるため、腹囲の測定や腹水の有無の確認も必要である。
血液データ(BUN、Cr、GFR)
血中尿素窒素は入院時82mg/dLと著明に上昇していたが、透析導入後は45mg/dLへと改善している。しかし基準値8から20mg/dLと比較すると依然として高値であり、透析間に老廃物が蓄積していることを示している。血清クレアチニンは入院時8.2mg/dLから現在4.5mg/dLへと改善しているが、基準値0.65から1.07mg/dLと比較すると著明な高値が持続している。推定糸球体濾過量は入院時5.8mL/min/1.73m²から現在10.2mL/min/1.73m²へとわずかに上昇しているが、基準値60以上mL/min/1.73m²と比較すると著しく低値であり、腎機能は末期腎不全の状態が続いている。これらの数値は透析により老廃物の除去が行われているものの、透析間に再び蓄積することを示している。週3回の透析で老廃物の蓄積をコントロールできているか、透析条件の適切性を評価する必要がある。
ニーズの充足状況
A氏のあらゆる排泄経路から排泄するというニーズは著しく障害されている。腎臓からの排泄機能が極度に低下しており、尿量は200mL/日程度と著明に減少している。これにより老廃物と余分な水分が体内に蓄積し、血液透析による代替的な排泄手段が不可欠となっている。透析導入により血中尿素窒素とクレアチニンは改善したが、依然として高値が持続しており、透析間に老廃物が再蓄積している。体液管理の面では透析により除水が行われ、入院時の体液過剰状態は改善しているが、透析間の体重増加管理が重要な課題となっている。便秘については入院前から問題があり、現在は増強している。3日に1回程度の排便では腹部膨満感や不快感が生じる可能性があり、排便習慣の改善が必要である。下剤としてピコスルファートナトリウム水和物を適宜使用しているが、定期的な排便リズムの確立には至っていない。透析患者では酸化マグネシウムが高マグネシウム血症のリスクがあるため使用できず、下剤の選択が制限される。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の排泄に関する主な課題は、腎機能低下による排泄障害と便秘の増強、水分出納バランスの管理である。看護介入として、まず尿量を毎日正確に測定し、残存腎機能の推移を評価する。透析前後の体重測定を確実に行い、透析間の体重増加を記録する。体重増加が3kgを超えないよう、水分摂取量を毎日記録し、A氏がセルフモニタリングできるよう指導する。体液貯留の徴候として、浮腫の有無や程度、呼吸困難の有無、血圧の変動を継続的に観察する。便秘への対応として、排便日と便の性状を記録し、排便パターンを把握する。腹部の視診、聴診、触診により腹部膨満や腸蠕動の状態を評価する。食事内容を評価し、カリウム制限の範囲内で食物繊維を多く含む食品の摂取を促す。水分制限の範囲内で適度な水分摂取を促し、排便を促進する。活動量を増やすことで腸蠕動を促進するため、透析日以外は病棟内の歩行を積極的に促す。下剤の使用状況を評価し、必要に応じて医師と相談して下剤の種類や量を調整する。定期的な排便リズムの確立を目指し、起床後や食後のトイレ誘導を行う。透析条件の適切性を評価するため、血中尿素窒素とクレアチニンの推移を継続的にモニタリングする。カリウム値が4.9mEq/Lと基準値上限に近いため、高カリウム血症のリスクに注意し、食事内容との関連を評価する。退院に向けて、A氏と妻に対して水分制限の具体的な方法や体重測定の重要性、便秘予防の方法について指導する。
ADL、麻痺、骨折の有無
A氏の日常生活動作は概ね自立している。歩行は自立しており、病棟内は杖なしで移動可能である。移乗動作も自立しており、ベッドから車椅子への移動や椅子からの立ち上がりに介助を要していない。排泄動作は自立しているが、透析後は疲労感があるためナースコールで見守りを依頼することがある。入浴は週2回の清拭と洗髪を実施しており、シャント側の上肢は濡らさないよう注意している。全身浴や シャワー浴の可否については明記されていないが、シャント保護のため制限されている可能性がある。衣類の着脱は自立しているが、シャント側の袖を通す際には注意が必要である。麻痺はなく、四肢の運動機能は保たれている。骨折の既往はなく、現在も骨折はない。78歳という高齢であることから、加齢による筋力低下や骨密度の低下が懸念されるため、転倒による骨折のリスクには注意が必要である。
ドレーン、点滴の有無
A氏は入院10日目から血液透析が開始されており、左前腕に内シャントが造設されている。透析は週3回、月水金の午前中に実施され、透析時間は1回4時間である。透析中はシャント側の上肢に穿刺針が留置されるため、透析中の体動は制限される。透析終了後は穿刺部の止血を確実に行う必要があり、止血確認までは上肢の安静が求められる。日常的な点滴やドレーン類については記載がないため、透析以外の時間帯は特にルート類による行動制限はないと考えられる。ただしシャント肢の保護は常時必要であり、シャント側での血圧測定や採血、重い物の持ち上げ、圧迫などは禁忌である。
生活習慣、認知機能
A氏は退職前に建設会社の事務職として勤務しており、座位での作業が中心であったと推測される。入院前の生活習慣や運動習慣については具体的な記載がないため、日常的な運動の実施状況や活動量を確認する必要がある。認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。これは活動に関する指導内容を理解し、実践する能力があることを示している。性格は温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢があることから、活動制限や注意事項を遵守できると期待される。しかし「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」と活動制限への懸念を示しており、透析導入による生活の変化に対する不安を抱えている。
ADLに関連した呼吸機能
A氏の呼吸機能は現在安定しており、安静時の呼吸数18回/分、SpO2 98%と良好である。しかし貧血が持続しており、ヘモグロビン値9.1g/dLと基準値13.7から16.8g/dLと比較して著明に低値である。この貧血により酸素運搬能が低下しており、活動時の息切れや易疲労感が生じやすい状態である。透析日は特に疲労感が強いとA氏が訴えており、透析による循環動態の変化や除水による血圧低下が活動耐性に影響している。階段昇降や長距離歩行時の呼吸困難の有無や程度については具体的な記載がないため、活動レベルと呼吸状態の関連を詳細に評価する必要がある。高齢者では加齢による肺活量の低下や呼吸筋力の減弱があり、活動時の呼吸負担が増大しやすい。
転倒転落のリスク
A氏の転倒歴は入院後はないが、複数のリスク因子が存在する。第一に78歳という高齢であることから、加齢による平衡感覚の低下や反射神経の鈍化、筋力低下がある。第二に貧血により立ちくらみや めまいが生じやすい状態である。第三に透析前後の血圧変動があり、透析前は血圧が152/88mmHg程度に上昇し、透析後は142/84mmHgへと低下する。透析による急激な除水は起立性低血圧を引き起こし、転倒のリスクを高める。第四に透析後の疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、注意力や判断力が低下している可能性がある。第五に降圧薬としてアムロジピンベシル酸塩とカルベジロールを服用しており、これらの薬剤により血圧低下や めまいが生じることがある。第六に睡眠薬としてゾルピデム酒石酸塩を使用しており、夜間のふらつきや転倒のリスクが高まる。視力は老眼があるが眼鏡使用により補正されている。聴力は正常であり、バランス感覚への影響は少ないと考えられる。環境要因として、病院内の床の段差や濡れた床、ベッド周囲の整理整頓の状態などが転倒リスクに影響する。
ニーズの充足状況
A氏の身体の位置を動かし良い姿勢を保持するというニーズは概ね充足されているが、いくつかの制限と課題がある。日常生活動作は自立しており、歩行や移乗動作に問題はない。しかし透析導入により活動パターンが変化し、週3回の透析日には4時間の座位保持と透析後の疲労により活動量が制限されている。透析日は特に疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、自由な活動が制限されている。A氏は「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」と活動制限への懸念を示しており、透析生活における活動と休息のバランスに不安を抱いている。シャント肢の保護により左上肢の使用に制限があり、重い物を持つことや圧迫を避ける必要がある。入浴も制限されており、全身浴が可能かどうか不明確である。貧血による易疲労感や活動耐性の低下により、以前と同様の活動レベルを維持することが困難になっている可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の活動と姿勢保持に関する主な課題は、透析導入による活動パターンの変化と疲労感、転倒転落のリスク、シャント肢の保護である。看護介入として、まず透析日と非透析日の活動パターンを把握し、活動と休息のバランスを評価する。透析後の疲労感が強いため、透析日は無理な活動を避け十分な休息を取るよう指導する。一方で非透析日は可能な範囲で活動量を増やし、筋力維持と体力向上を図る。病棟内の歩行を積極的に促し、歩行距離や歩行時間を段階的に延長する。活動時のバイタルサインの変化、特に血圧と脈拍、呼吸状態を観察し、活動耐性を評価する。貧血による活動制限については、エリスロポエチン製剤の効果をヘモグロビン値の推移で評価し、貧血改善に伴う活動耐性の向上を期待する。転倒転落予防として、透析前後の血圧測定を確実に行い、起立性低血圧の有無を確認する。透析後の移動時には見守りを行い、必要に応じて付き添う。睡眠薬服用後の夜間トイレ時には転倒リスクが高いため、ナースコール使用を促し、見守りを実施する。ベッド周囲の環境整備を行い、障害物を除去し、必要な物品は手の届く範囲に配置する。夜間の照明を適切に調整し、暗い中での移動を避ける。履物は滑りにくく、かかとが固定されるものを使用するよう指導する。シャント肢の保護について、A氏と妻に対して日常生活での注意点を具体的に指導する。シャント側での血圧測定や採血、点滴の禁忌を説明し、医療者にも周知する。重い物を持つことや腕時計やアクセサリーでの圧迫を避けるよう指導する。シャント音の聴取方法を教育し、毎日のセルフチェックを促す。入浴方法について医師に確認し、可能であれば入浴の機会を増やすことで清潔保持と気分転換を図る。退院後の生活について、A氏の不安に寄り添いながら、透析と両立できる活動の工夫を一緒に考える。外来透析患者の体験談を紹介したり、透析しながら仕事や趣味を続けている患者の情報を提供することで、活動への前向きな姿勢を支援する。
睡眠時間、パターン
A氏は入院前、23時頃に就寝し6時に起床しており、睡眠時間は約7時間であった。中途覚醒が1回程度あったが、概ね睡眠は確保されていた。現在は入院環境と透析導入への不安から入眠困難が生じており、睡眠パターンが変化している。就寝時刻や起床時刻、実際の睡眠時間については現在の詳細な記載がない。入眠困難により就寝時刻が遅れている可能性や、病院の消灯時間と A氏の入眠時刻のずれが生じている可能性がある。中途覚醒の回数や早朝覚醒の有無についても追加情報が必要である。透析のある日は午前中に透析が実施されるため、早朝に起床する必要がある。透析日は疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、昼夜のリズムが乱れている可能性がある。日中の仮眠時間や頻度が夜間の睡眠に影響している可能性も考慮する必要がある。78歳という高齢であることから、加齢による睡眠の質の変化として、深睡眠の減少や中途覚醒の増加、早朝覚醒の傾向が生じやすい。
疼痛、掻痒感の有無、安静度
A氏に疼痛に関する記載はなく、現在痛みは訴えていないと考えられる。入院3日目に左前腕に内シャント造設術が施行されたが、術後経過は良好であり、術後の疼痛は軽減していると推測される。透析時の穿刺痛や透析中の不快感については情報がない。掻痒感についても具体的な記載がないが、透析患者では尿毒症性の皮膚掻痒症が高頻度に出現し、睡眠を妨げる重要な因子となる。皮膚の乾燥やリンの蓄積により掻痒感が生じることがあるため、掻痒感の有無や程度を確認する必要がある。安静度については明確な制限はなく、病棟内は自由に歩行可能である。しかし透析後は疲労感が強いため、自然と安静を取る傾向がある。シャント肢の保護のため、左上肢の使用に注意が必要であるが、これが睡眠時の体位に制限を与えているかは不明である。
入眠剤の有無
A氏は入眠困難に対して、睡眠薬としてゾルピデム酒石酸塩5mgを就寝前に使用している。ゾルピデムは超短時間作用型の非ベンゾジアゼピン系睡眠薬であり、入眠困難に対して効果がある。しかし高齢者では薬剤の代謝が遅延し、翌朝への持ち越し効果やふらつき、転倒のリスクが高まる。現在の睡眠薬の効果や副作用の出現状況について評価が必要である。入眠は改善されているか、中途覚醒は減少しているか、翌朝の眠気やふらつきはないかを確認する。また睡眠薬への依存や耐性の形成を防ぐため、非薬物的な睡眠改善策も並行して実施する必要がある。
疲労の状態
A氏は透析日に特に疲労感が強いと訴えており、日中に傾眠傾向がある。透析は1回4時間を週3回実施されており、透析中は座位を保持し続ける必要がある。透析による除水や電解質の急激な変化により、透析後に疲労感や倦怠感が生じることが多い。また貧血が持続しており、ヘモグロビン値9.1g/dLと低値であることが、易疲労感の主要な原因となっている。酸素運搬能の低下により組織の酸素供給が不足し、常に疲労を感じやすい状態である。入院前は腎機能低下による尿毒症症状として倦怠感があったが、透析導入により一定の改善を認めている。しかし透析日と非透析日で疲労の程度に差があり、透析日の疲労が強いことが睡眠パターンや日中の活動に影響している。食欲不振により摂取量が7割程度であることも、エネルギー不足による疲労の一因となっている可能性がある。
療養環境への適応状況、ストレス状況
A氏は入院環境と透析導入への不安から入眠困難が生じており、療養環境への適応に課題がある。「こんなに大変な治療になるとは思わなかった。でも生きるためには仕方ないですね」と述べており、透析導入を受け入れつつも心理的負担を感じている。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」と家族への負担を気にする発言や、「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」と活動制限への懸念を示しており、今後の生活への不安が強い。妻と二人暮らしであり、長男と長女は県外に在住しているため、退院後のサポート体制への不安もある。病院という慣れない環境での生活、他患者の物音や医療機器の音、夜間の巡回による睡眠の中断などが、睡眠の質を低下させている可能性がある。性格は温厚で真面目であり、医療者に対して不安や不満を表出しにくい可能性もある。ストレス状況として、末期腎不全という重篤な疾患の診断、生涯にわたる透析治療の必要性、食事や水分の厳格な制限、シャント管理の負担など、多くのストレス要因が存在する。
ニーズの充足状況
A氏の睡眠と休息をとるというニーズは十分に充足されていない。入眠困難により睡眠の質が低下しており、睡眠薬を使用しても十分な睡眠が得られていない可能性がある。透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、夜間の睡眠が不十分で日中の仮眠により補っている状態と考えられる。これは睡眠覚醒リズムの乱れを示唆している。入院環境と透析導入への不安が入眠困難の主な原因となっており、心理的サポートが不足している可能性がある。透析による疲労と貧血による易疲労感により、十分な休息が必要であるにもかかわらず、夜間の睡眠が不十分なため疲労が蓄積している。高齢者にとって良質な睡眠は健康維持に不可欠であり、睡眠不足は免疫機能の低下や認知機能の低下、転倒リスクの増加につながる。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の睡眠と休息に関する主な課題は、入眠困難と睡眠覚醒リズムの乱れ、透析による疲労感、透析導入への不安である。看護介入として、まず睡眠日誌をつけ、就寝時刻、入眠までの時間、中途覚醒の回数、起床時刻、日中の仮眠時間を記録し、睡眠パターンを詳細に把握する。非薬物的な睡眠改善策として、就寝前のリラクゼーション技法を指導する。深呼吸や筋弛緩法、軽いストレッチなどにより心身の緊張を緩和する。日中の活動量を増やし、日光に当たる機会を作ることで、睡眠覚醒リズムを整える。ただし透析日は無理な活動を避け、適度な休息を取る。日中の仮眠は30分以内とし、夕方以降の仮眠は避けるよう指導する。就寝前のカフェイン摂取を避け、リラックスできる環境を整える。療養環境の調整として、騒音や照明を調整し、睡眠に適した環境を提供する。室温や湿度を快適に保つ。夜間の巡回時には最小限の照明とし、睡眠を妨げないよう配慮する。心理的サポートとして、A氏の不安や懸念に耳を傾け、透析生活への適応を支援する。透析導入後の生活について具体的な情報を提供し、漠然とした不安を軽減する。同じように透析を受けながら生活している患者の体験談を紹介し、希望を持てるよう支援する。妻との面会時間を確保し、家族のサポートを得られるよう調整する。睡眠薬の効果と副作用を評価し、必要に応じて医師に相談して薬剤の調整を検討する。高齢者では睡眠薬による転倒リスクが高いため、夜間トイレ時の見守りを継続する。掻痒感の有無を確認し、皮膚の保湿ケアを行う。リン吸着薬の効果を評価し、血清リン値をコントロールすることで尿毒症性掻痒症を予防する。貧血の改善により疲労感が軽減することを説明し、エリスロポエチン製剤の継続治療の重要性を伝える。疲労の程度を定期的に評価し、活動と休息のバランスを調整する。
ADL、運動機能、認知機能、麻痺の有無、活動意欲、点滴、ルート類の有無
A氏の衣類の着脱は自立しており、日常生活動作に支障はない。上肢下肢ともに運動機能は保たれており、麻痺もないため、衣類の着脱動作に身体的な制限はない。ただしシャント側の袖を通す際には注意が必要であり、左前腕のシャント保護が重要である。シャントへの過度な圧迫や引っ張りを避けるため、袖口が狭い衣類や きつい袖の衣類は避ける必要がある。認知機能は保たれており、MMSE28点と良好であるため、衣類の選択や着脱の手順を理解し実行する能力は十分にある。活動意欲については、透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があるため、更衣への意欲が低下している可能性がある。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」と活動制限への懸念を示しており、退院後の生活への不安が活動意欲に影響している可能性がある。日常的な点滴やドレーン類については記載がないが、透析時には左前腕に穿刺針が留置されるため、透析中や透析直後の更衣には注意が必要である。透析時は通常、穿刺部にアクセスしやすい衣類を選択する必要がある。
発熱、吐気、倦怠感
A氏の現在の体温は36.5℃と平熱であり、発熱は認めていない。感染症もなく、炎症反応を示すCRP値も0.3mg/dLと基準値内に低下している。吐気については記載がなく、現在は消化器症状を訴えていないと考えられる。倦怠感については、入院前は腎機能低下による尿毒症症状として強い倦怠感があったが、透析導入により軽減している。しかし透析日は特に疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、透析日の倦怠感が更衣動作に影響している可能性がある。透析後は疲労により更衣への意欲が低下し、着替えを後回しにしたり、最小限の更衣にとどめたりする可能性がある。また貧血が持続しており、ヘモグロビン値9.1g/dLと低値であることが、易疲労感の原因となっている。更衣動作自体は自立しているが、疲労により更衣に時間がかかったり、休憩が必要になったりする可能性がある。
ニーズの充足状況
A氏の適切な衣類を選び着脱するというニーズは概ね充足されている。衣類の着脱動作は自立しており、運動機能や認知機能に問題はない。病院では病衣が提供されており、清潔な衣類を着用できている。しかしシャント肢の保護という新たな課題が加わり、衣類の選択や着脱方法に注意が必要となっている。透析日の疲労感により更衣への意欲が低下している可能性があり、清潔な衣類への更衣が十分に行われていない可能性もある。入浴は週2回の清拭と洗髪に制限されているため、発汗や汚染があっても全身の清潔を保つことが困難であり、衣類の汚染頻度や更衣の必要性に影響している。退院後の衣類の選択について、シャント保護の観点から適切な衣類を選べるか、A氏と妻が理解しているかは不明である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の衣類の着脱に関する主な課題は、シャント肢保護のための衣類の選択と着脱方法の習得、透析日の疲労による更衣意欲の低下である。看護介入として、まずシャント保護のための衣類の選択について指導する。袖口がゆったりとした衣類を選び、シャントへの圧迫を避けるよう説明する。長袖よりも半袖や七分袖を選ぶことで、シャント部分の観察がしやすく、透析時の穿刺もしやすいことを伝える。着脱時の注意点として、シャント側から先に袖を通し、脱ぐ時は健側から先に脱ぐという基本原則を指導する。袖を引っ張ったり、きつく絞ったりしないよう注意を促す。透析日の更衣について、透析前は穿刺しやすい衣類を着用し、透析後は疲労を考慮して無理のない範囲で更衣を促す。発汗や汚染があれば更衣が必要であることを説明し、清潔保持の重要性を伝える。疲労が強い場合は看護師が更衣を介助し、負担を軽減する。透析後の穿刺部の止血を確認してから更衣を行うよう指導する。病院での衣類の準備状況を確認し、清潔な衣類が十分にあるか、家族が定期的に持参しているかを把握する。退院に向けて、自宅での衣類の選択や管理について A氏と妻に指導する。シャント保護に適した衣類の具体例を示し、購入の際の参考にしてもらう。季節に応じた衣類の選択方法についても説明する。透析日の更衣パターンや着替えのタイミングについて、外来透析に移行した際の具体的な方法を一緒に考える。A氏の活動意欲を高めるため、透析生活でも身だしなみを整えることの重要性を伝え、好きな衣類を着ることで気分転換になることを説明する。
バイタルサイン
A氏の来院時の体温は36.8℃、現在の体温は36.5℃であり、いずれも正常範囲内で安定している。来院時の脈拍は88回/分、現在は透析後の測定で72回/分と正常範囲内である。来院時の血圧は168/96mmHgと高値であったが、現在は透析後142/84mmHgと改善している。透析前は血圧が152/88mmHg程度に上昇する傾向があり、体液貯留による循環血液量の増加が影響している。来院時の呼吸数は20回/分とやや頻呼吸であったが、現在は18回/分と改善している。SpO2は来院時96%、現在98%と良好である。バイタルサインの推移から、透析導入により体液管理が改善し、全身状態が安定してきていることが分かる。しかし透析前後で血圧や体重に変動があり、透析による循環動態の変化が体温調節に影響する可能性がある。
療養環境の温度、湿度、空調
療養環境の温度、湿度、空調の状態については具体的な記載がない。病院の病室は通常、適切な温度と湿度に管理されているが、A氏が快適と感じているか、寒さや暑さを訴えていないかを確認する必要がある。透析患者では体液量の変動により体温調節が不安定になることがあり、透析中や透析後に寒気を感じることがある。また透析室の温度設定が A氏に適しているかも確認が必要である。高齢者は体温調節機能が低下しており、環境温度の変化に適応しにくいため、適切な室温管理が重要である。入院は9月末の時期であり、季節の変わり目で気温の変動が大きい時期である。衣類の調整や寝具の調整により、快適な温度環境を維持できているかを評価する必要がある。
発熱の有無、感染症の有無
A氏は現在発熱を認めておらず、体温は36.5℃と平熱である。感染症はなく、感染徴候も認められない。内シャント造設術を施行されているが、術後経過は良好であり、シャント部位の感染兆候はないと考えられる。しかし透析患者は免疫機能が低下しており、感染症のリスクが高い。シャント感染、カテーテル関連血流感染、肺炎、尿路感染症などが発生しやすい。透析により週3回医療機関を訪れるため、医療関連感染のリスクもある。発熱は感染症の重要な徴候であるため、体温測定を継続し、発熱の早期発見に努める必要がある。また発熱以外の感染徴候として、シャント部位の発赤や腫脹、疼痛、排膿の有無、呼吸器症状、尿路症状などを観察する必要がある。
ADL
A氏の日常生活動作は概ね自立しており、歩行や移乗、排泄、更衣などが自立している。活動に伴う熱産生は正常に行われていると考えられる。しかし透析日は疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、活動量が低下している。活動量の低下は熱産生の減少につながり、低体温のリスクを高める可能性がある。一方で過度な活動は熱産生を増加させ、体温上昇を引き起こす可能性もある。貧血により酸素運搬能が低下しているため、活動時の代謝が効率的に行われず、体温調節に影響する可能性がある。高齢者では加齢により基礎代謝が低下し、熱産生能力が減少している。また体温調節中枢の機能低下により、環境温度の変化に対する適応が遅れる。
血液データ(WBC、CRP)
白血球数は入院時6,800/μL、現在6,200/μLであり、いずれも基準値3,300から8,600/μL内で正常範囲である。白血球数の推移から、明らかな感染症や炎症は認められないと判断できる。CRP値は入院時0.8mg/dL、現在0.3mg/dLと改善しており、基準値0.00から0.14mg/dLと比較すると入院時はわずかに上昇していたが、現在は正常範囲に近づいている。入院時の軽度のCRP上昇は、尿毒症による炎症反応や体液貯留による心血管系への負荷を反映していた可能性がある。透析導入により炎症反応が改善していることは、全身状態の改善を示している。しかし透析患者では慢性的な炎症状態が続くことがあり、今後も定期的なモニタリングが必要である。
ニーズの充足状況
A氏の体温を生理的範囲内に維持するというニーズは現時点では充足されている。体温は36.5℃と正常範囲内で安定しており、発熱や低体温は認めていない。感染症もなく、白血球数とCRP値も正常範囲内である。バイタルサインは透析導入により改善し、全身状態は安定している。しかし透析患者特有のリスク因子が存在する。免疫機能の低下により感染症のリスクが高く、シャント感染や透析関連感染の危険性がある。透析による体液量の変動や電解質の変化が体温調節に影響する可能性がある。高齢者であることから、加齢による体温調節機能の低下や基礎代謝の低下がある。環境温度の変化に対する適応能力が低下しており、適切な環境管理が必要である。貧血による酸素運搬能の低下が代謝機能に影響し、体温調節に支障をきたす可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の体温調節に関する主な課題は、感染症予防と体温の継続的なモニタリング、透析患者特有の体温調節の変化への対応である。看護介入として、まず体温測定を1日2回以上定期的に実施し、発熱の早期発見に努める。透析前後の体温測定を確実に行い、透析による体温変化を把握する。微熱や体温の変動パターンに注意し、感染症の初期徴候を見逃さないようにする。感染予防対策として、シャント部位の観察を毎日行い、発赤、腫脹、熱感、疼痛、排膿などの感染徴候がないか確認する。シャント部位の清潔保持を指導し、透析前の清拭や手指衛生の重要性を説明する。手洗いの励行を促し、面会者にも手指衛生を徹底してもらう。透析室への入室前の手洗いと、透析後の穿刺部の清潔管理を確実に行う。呼吸器感染予防として、深呼吸や咳嗽の励行、口腔ケアの徹底を指導する。尿路感染予防として、十分な排尿と陰部の清潔保持を促す。ただし水分制限があるため、過度な水分摂取は避ける。環境調整として、病室の温度と湿度を適切に管理する。A氏が寒さや暑さを訴えていないか定期的に確認し、衣類や寝具の調整を行う。透析室の温度が快適か確認し、必要に応じて毛布などを提供する。透析中や透析後に寒気を訴える場合は、保温対策を講じる。季節の変わり目であることを考慮し、気温の変化に応じた衣類の調整を促す。活動と体温調節の関係について評価し、過度な安静による熱産生の低下を防ぐため、適度な活動を促す。貧血の改善により代謝機能が向上し、体温調節能力が改善することを期待する。免疫機能を維持するため、栄養状態の改善と十分な休息を促す。白血球数とCRP値の推移を継続的にモニタリングし、感染症や炎症の早期発見に努める。退院に向けて、A氏と妻に対して感染予防の重要性を説明し、自宅での体温測定の方法や発熱時の対応について指導する。シャント部位の観察方法と感染徴候の見分け方を具体的に教育する。
自宅と療養環境での入浴回数、方法、ADL、麻痺の有無、鼻腔、口腔の保清、爪
A氏の入院前の入浴習慣については具体的な記載がないため、入浴頻度や方法、自立度について追加情報が必要である。現在は週2回の清拭と洗髪を実施しており、シャント側の上肢は濡らさないよう注意している。全身浴やシャワー浴が制限されている理由として、シャント造設後の創部保護や感染予防が考えられる。シャント造設術は入院3日目に施行されており、現在入院14日目であることから、創部は治癒過程にあると推測される。今後、全身浴やシャワー浴が可能になる時期について医師に確認する必要がある。日常生活動作は概ね自立しており、清拭や洗髪の際も自分で行える部分は自立していると考えられる。麻痺はなく、運動機能は保たれているため、清潔ケアの動作に身体的な制限はない。しかし透析日は疲労感が強く、清潔ケアへの意欲が低下している可能性がある。鼻腔の保清については記載がないが、尿毒症患者では口腔内や鼻腔の乾燥が生じやすい。口腔内の状態については具体的な記載がなく、歯の状態、義歯の有無、口腔粘膜の状態、口臭の有無などの情報が必要である。透析患者では尿毒症による口腔内の不快感や口臭が生じることがあり、口腔ケアの実施状況を確認する必要がある。爪の状態については記載がないが、高齢者では爪の肥厚や変形が生じやすく、爪切りが困難になることがある。また透析患者では末梢循環障害により爪の成長が遅くなったり、変色したりすることがある。
尿失禁の有無、便失禁の有無
A氏に尿失禁や便失禁についての記載はなく、排泄動作は自立していることから、失禁はないと考えられる。排尿排便のコントロールは保たれており、皮膚の汚染や清潔保持への影響はない。ただし尿量が200mL/日程度と著明に減少しており、排尿回数も減少していると推測される。便秘傾向があり3日に1回程度の排便であるが、便失禁のリスクは低いと考えられる。高齢者では括約筋の機能低下により失禁のリスクがあるため、今後も継続的な観察が必要である。
ニーズの充足状況
A氏の身体を清潔に保ち身だしなみを整え皮膚を保護するというニーズは部分的に充足されているが、いくつかの制限がある。現在の清潔ケアは週2回の清拭と洗髪に限定されており、全身浴やシャワー浴ができない状態である。これは毎日入浴していた場合と比較すると清潔保持が不十分であり、皮膚の爽快感や精神的なリフレッシュ効果も得られにくい。シャント肢を濡らさないという制約により、清拭の方法にも制限がある。入院環境では洗面や歯磨きなどの日常的な清潔ケアは実施できていると考えられるが、自宅での習慣と異なる可能性がある。透析日は疲労感が強く、清潔ケアへの意欲が低下している可能性があり、セルフケアが不十分になることが懸念される。皮膚の状態については具体的な記載がなく、乾燥や掻痒感、発赤、皮疹などの有無を確認する必要がある。透析患者では尿毒症性の皮膚掻痒症が高頻度に出現し、QOLを著しく低下させる。リンの蓄積や皮膚の乾燥が掻痒感の原因となり、掻破により皮膚損傷が生じることがある。また透析患者では皮膚の脆弱性が増し、些細な刺激で皮膚損傷が生じやすい。高齢者では加齢により皮膚の菲薄化や乾燥が進行しており、皮膚のバリア機能が低下している。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の清潔と皮膚保護に関する主な課題は、入浴制限による清潔保持の困難さ、シャント肢の保護、皮膚掻痒症のリスク、高齢者の皮膚の脆弱性である。看護介入として、まず現在の清潔ケアの方法を評価し、週2回の清拭と洗髪で十分な清潔が保たれているか確認する。清拭の実施方法を観察し、洗い残しや不十分な部分がないか評価する。温タオルを使用した丁寧な清拭により、皮膚の汚れを除去し、爽快感を提供する。シャント肢の清拭方法について指導し、濡らさないよう注意しながらも清潔を保つ方法を伝える。防水シートやビニール袋を使用してシャント部位を保護する方法を具体的に示す。全身浴やシャワー浴の開始時期について医師に確認し、可能になれば早期に開始する。シャワー浴が可能になった際のシャント保護方法について、防水テープの使用方法などを指導する。皮膚の観察を毎日行い、乾燥、発赤、皮疹、掻痒感、掻破痕、色素沈着などの有無を確認する。特にシャント部位、穿刺部位、圧迫されやすい部位、湿潤しやすい部位を重点的に観察する。皮膚の乾燥に対して、保湿剤を使用したスキンケアを実施する。入浴後や清拭後に全身に保湿剤を塗布し、皮膚のバリア機能を維持する。掻痒感の有無を確認し、掻痒感がある場合は原因を評価する。血清リン値のコントロールが適切か、リン吸着薬の効果を評価する。掻痒感が強い場合は医師に相談し、抗ヒスタミン薬などの使用を検討する。爪を短く整え、掻破による皮膚損傷を予防する。爪の状態を観察し、必要に応じて爪切りの介助を行う。口腔ケアの実施状況を確認し、毎食後の歯磨きや義歯の清掃を促す。口腔内の観察を行い、口腔粘膜の乾燥、出血、口臭の有無を確認する。口腔内の乾燥が強い場合は、含嗽を促したり、口腔保湿剤の使用を検討する。透析日の清潔ケアについて、透析後は疲労が強いため、無理のない範囲で実施できるよう配慮する。部分浴や洗髪のタイミングを A氏の状態に合わせて調整する。退院に向けて、自宅での入浴方法やシャント保護の具体的な方法について A氏と妻に指導する。シャワー浴時の防水方法、入浴後のシャント部位の観察方法、皮膚の保湿ケアの重要性などを説明する。外来透析に移行した際の清潔ケアのパターンを一緒に考え、生活の中に組み込めるよう支援する。
危険箇所(段差、ルート類)の理解、認知機能、術後せん妄の有無
A氏の認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。これは危険箇所の認識や安全行動の理解、指示の遵守が可能であることを示している。性格は温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢があることから、安全に関する注意事項を理解し実践できると期待される。病院環境における段差や障害物の認識、転倒リスクの理解は可能と考えられる。しかし78歳という高齢であることから、注意力の低下や判断速度の遅延が生じている可能性がある。透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、注意力や判断力が一時的に低下し、危険認識が不十分になる可能性がある。ルート類については、透析時に左前腕に穿刺針が留置されるが、透析終了後は抜針されるため、日常的にルート類が留置されている状態ではない。シャント肢の保護については理解が必要であり、シャントへの圧迫や外傷を避けることの重要性を認識できているか確認が必要である。術後せん妄については記載がなく、内シャント造設術後にせん妄を発症した様子はない。ただし睡眠薬としてゾルピデムを使用しており、高齢者では睡眠薬により見当識障害や混乱が生じることがあるため、注意が必要である。
皮膚損傷の有無
A氏の皮膚損傷については具体的な記載がない。内シャント造設術の創部は術後経過が良好とされており、創部感染や治癒遅延はないと考えられる。透析時の穿刺部位については、週3回の穿刺により皮膚損傷や血腫形成のリスクがある。穿刺部位の皮膚の状態、止血状況、血腫や皮下出血の有無を観察する必要がある。透析患者では皮膚の脆弱性が増しており、テープ剥離時の皮膚損傷や圧迫による褥瘡のリスクが高い。高齢者では加齢により皮膚が菲薄化しており、些細な刺激で皮膚損傷が生じやすい。転倒歴は入院後にないが、転倒した場合は重大な皮膚損傷や骨折のリスクがある。尿毒症性の皮膚掻痒症により掻破痕が生じている可能性もあるため、全身の皮膚の観察が必要である。
感染予防対策(手洗い、面会制限)
A氏の感染予防対策については、シャント造設後であり透析導入患者であることから、厳重な感染管理が必要である。現在の手洗いの実施状況や手指衛生の習慣については具体的な記載がない。透析患者は免疫機能が低下しており、感染症のリスクが高いため、手洗いの励行が重要である。面会制限の有無については記載がないが、妻や子どもたちの面会があると推測される。面会者の感染予防対策として、手指衛生の徹底や体調不良時の面会制限が必要である。病院の感染対策として、標準予防策が実施されているはずであるが、A氏自身の感染予防行動の実施状況を評価する必要がある。シャント部位の清潔保持、透析前の清拭、口腔ケアの実施など、日常的な感染予防行動が適切に行われているかを確認する。
血液データ(WBC、CRP)
白血球数は入院時6,800/μL、現在6,200/μLであり、いずれも基準値3,300から8,600/μL内で正常範囲である。白血球数の推移から、現時点で明らかな感染症は認められない。CRP値は入院時0.8mg/dL、現在0.3mg/dLと改善しており、炎症反応は軽減している。これらの検査データから、現在の感染リスクは比較的低いと判断できるが、透析患者では慢性的な炎症状態が続くことがあり、また免疫機能の低下により感染症に罹患しやすい状態である。今後も継続的なモニタリングが必要である。
ニーズの充足状況
A氏の環境のさまざまな危険因子を避け他人を傷害しないようにするというニーズは概ね充足されているが、複数のリスク因子が存在する。認知機能は保たれており、危険認識や安全行動は可能であるが、高齢であることや透析後の疲労により、一時的に注意力や判断力が低下する可能性がある。転倒歴は入院後にないが、転倒転落のリスク因子として、高齢、貧血、血圧変動、透析後の疲労、睡眠薬の使用などが存在する。シャント肢の保護という新たな課題があり、シャントへの外傷や感染を避ける必要がある。感染症のリスクが高く、手洗いなどの感染予防行動の徹底が必要である。皮膚の脆弱性により皮膚損傷のリスクがあり、適切なスキンケアと環境整備が必要である。他者を傷害する可能性については、認知機能が保たれており性格も温厚であることから、リスクは低いと考えられる。しかし睡眠薬使用時の見当識障害や、低血糖などによる意識障害が生じた場合は、予測不能な行動をとる可能性もある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の安全に関する主な課題は、転倒転落の予防、シャント保護、感染予防、皮膚損傷の予防である。看護介入として、まず転倒転落リスクのアセスメントを実施し、リスク因子を明確にする。転倒転落アセスメントツールを使用し、リスクレベルを評価する。高リスクと判定された場合は、ベッド周囲に転倒転落注意の表示を行い、医療スタッフ全員で注意を払う。環境整備として、ベッド周囲の整理整頓を行い、障害物を除去する。必要な物品は手の届く範囲に配置し、無理な体動を避ける。ベッドの高さを最低位に調整し、必要に応じてベッド柵を使用する。夜間の照明を適切に調整し、足元が見えるようにする。床が濡れている場合は速やかに清掃し、滑り止めマットを使用する。履物は滑りにくく、かかとが固定されるものを使用するよう指導する。血圧変動への対応として、透析前後の血圧測定を確実に行い、起立性低血圧の有無を確認する。透析後の移動時には見守りを行い、急な立ち上がりを避けるよう指導する。めまいやふらつきがある場合は、無理に動かず看護師を呼ぶよう説明する。睡眠薬服用後の夜間トイレ時には、ナースコール使用を促し、見守りを実施する。貧血の改善により活動耐性が向上し、転倒リスクが低減することを期待する。シャント保護として、シャント肢に外傷を与えないよう注意を促す。ベッド柵や車椅子のアームレストにぶつけないよう配慮する。シャント肢を下にして寝ないよう指導する。重い物を持たないこと、圧迫を避けることを再度説明する。毎日のシャント音の聴取を A氏自身が行い、異常の早期発見に努めるよう指導する。感染予防として、手洗いの重要性を説明し、食前、トイレ後、透析前後の手洗いを徹底するよう促す。正しい手洗い方法を指導し、実施状況を観察する。シャント部位の清潔保持を指導し、毎日の観察を促す。口腔ケアを毎食後に実施し、口腔内の感染を予防する。面会者にも手指衛生を徹底してもらい、体調不良時の面会を控えてもらう。白血球数とCRP値を継続的にモニタリングし、感染徴候の早期発見に努める。発熱や創部の発赤などの感染徴候が出現した場合は、速やかに医師に報告する。皮膚損傷予防として、皮膚の観察を毎日行い、発赤や損傷の有無を確認する。テープ剥離時には愛護的に行い、皮膚損傷を避ける。体位変換を適切に行い、同一部位への長時間の圧迫を避ける。保湿剤を使用して皮膚のバリア機能を維持する。退院に向けて、A氏と妻に対して自宅での安全対策について指導する。自宅内の段差の確認や手すりの設置、照明の改善など、環境整備の方法を説明する。シャント保護の重要性と日常生活での注意点を具体的に説明する。感染予防行動の継続と異常時の対応について指導する。
表情、言動、性格は問題ないか、家族や医療者との関係性
A氏の性格は温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢がある。これは医療者との良好な関係性を築く基盤となっている。表情や言動については具体的な記載が少ないが、「こんなに大変な治療になるとは思わなかった。でも生きるためには仕方ないですね」という発言から、透析導入を受け入れつつも心理的負担を感じていることが分かる。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という発言から、家族への配慮や今後の生活への不安を抱えている様子が伺える。これらの発言は自分の感情や懸念を言語化できていることを示しており、コミュニケーション能力は保たれている。しかし真面目な性格であることから、医療者に対して本音を言いにくかったり、弱音を吐けなかったりする可能性もある。妻との関係性は良好と考えられ、キーパーソンとして妻が支援している。妻も「透析が必要になったことは残念ですが、これで少しでも元気になってくれるなら」と前向きに捉えようとしており、夫婦で協力して透析生活に適応しようとしている姿勢が見られる。長男と長女は県外に在住しており、月に1回程度帰省するとのことで、日常的なサポートは期待しにくい状況である。
言語障害、視力、聴力、メガネ、補聴器
A氏に言語障害はなく、コミュニケーションは良好である。視力は老眼があるが眼鏡を使用すれば新聞を読むことができる。これは日常的な情報収集や文字によるコミュニケーションが可能であることを示している。聴力は正常であり、会話に支障はない。補聴器の使用はなく、聴覚を通じたコミュニケーションは問題ない。視覚と聴覚が保たれていることは、医療者からの説明を理解したり、パンフレットなどの教材を使用した教育を受けたりする上で有利な因子である。高齢者では感覚器の機能低下によりコミュニケーションが困難になることがあるが、A氏の場合は眼鏡使用により視力が補正されており、聴力も保たれているため、コミュニケーション手段に制限はない。
認知機能
A氏の認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。これは会話の内容を理解し、自分の考えや感情を適切に表現する能力があることを示している。記憶力、判断力、理解力が保たれているため、複雑な透析治療の説明を理解し、自己管理に必要な知識を習得することが可能である。透析導入という大きな生活の変化に対して、「生きるためには仕方ないですね」と現実的な判断を示しており、認知機能が適切に機能している。しかし透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、一時的に集中力や注意力が低下する可能性がある。また入院環境と透析導入への不安から入眠困難が生じており、睡眠不足が認知機能に影響している可能性も考慮する必要がある。
面会者の来訪の有無
面会者については、妻がキーパーソンであり定期的に面会に来ていると推測される。長男と長女は県外に在住しており月に1回程度帰省するとのことで、頻繁な面会は困難である。面会の頻度や時間、面会時の様子については具体的な記載がない。妻との面会時には、今後の生活や食事管理についての話し合いが行われていると考えられる。妻は「家での食事管理が難しそうで不安です」と述べており、退院後の生活への不安を共有している。面会は A氏にとって精神的な支えとなり、孤独感の軽減や療養意欲の向上につながる重要な機会である。面会制限の有無や面会時間の制約については記載がないが、コロナ禍などの状況によっては面会が制限されている可能性もある。
ニーズの充足状況
A氏の自分の感情や欲求を表現して他者とコミュニケーションを持つというニーズは概ね充足されているが、いくつかの課題がある。言語機能、視力、聴力、認知機能が保たれており、コミュニケーションの基本的な能力は十分である。医療者の説明を真剣に聞く姿勢があり、指示を理解し実行することができる。自分の不安や懸念を言語化して表現しており、「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」といった心情を伝えることができている。妻との関係性は良好で、キーパーソンとして支援を受けている。しかし性格が温厚で真面目であることから、本音を言いにくい傾向がある可能性がある。医療者に対して弱音を吐けなかったり、遠慮して要望を伝えられなかったりすることが懸念される。透析導入という大きな変化に対して、「生きるためには仕方ないですね」と受け入れる姿勢を示しているが、その裏には諦めや無力感が隠れている可能性もある。長男と長女は県外に在住しており、日常的なコミュニケーションや支援が限られている。入院環境では他の患者との交流機会もあるはずだが、その状況については記載がない。透析日の疲労や睡眠不足により、コミュニケーションへの意欲が低下している可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のコミュニケーションに関する主な課題は、透析導入への不安や心理的負担の表出を促すこと、妻との協力関係の強化、医療者との信頼関係の構築である。看護介入として、まず A氏が自分の感情や不安を自由に表現できる雰囲気を作る。真面目な性格であることを理解し、弱音を吐いてもよいこと、不安を感じることは当然であることを伝える。定期的に A氏と面談する時間を設け、じっくりと話を聞く姿勢を示す。「何か困っていることはありませんか」「心配なことがあれば何でも話してください」といった開かれた質問を使用し、本音を引き出す。A氏の発言を否定せず、共感的に傾聴する。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」という発言に対しては、家族が支えたいと思っていることや、一緒に乗り越えていく方法があることを伝える。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という不安に対しては、透析と両立できる活動の具体例を示し、希望を持てるよう支援する。透析導入患者の体験談や、透析しながら仕事や趣味を続けている患者の情報を提供する。妻との面会時間を確保し、夫婦で一緒に教育を受ける機会を作る。妻の不安にも耳を傾け、退院後の生活について一緒に考える。栄養士による食事指導、薬剤師による服薬指導など、多職種が関わる機会を設け、様々な視点からのサポートを提供する。長男と長女に対しても、可能な範囲で情報提供を行い、遠方からでもできる支援方法を一緒に考える。電話やビデオ通話を活用したコミュニケーションを提案する。他の透析患者との交流機会があれば紹介し、同じ境遇の人との情報交換や精神的支えを得られるよう支援する。透析日の疲労を考慮し、無理のない範囲でコミュニケーションを図る。透析後は十分な休息を取り、回復してから話し合いの時間を持つなど、タイミングを配慮する。睡眠が改善することでコミュニケーションへの意欲も向上する可能性があるため、睡眠改善への支援を継続する。非言語的コミュニケーションにも注意を払い、表情や仕草から読み取れる感情を察する。落ち込んでいる様子や不安そうな様子が見られた場合は、積極的に声をかける。認知機能が良好であることを活かし、パンフレットや図表を使用した視覚的な教材を提供し、理解を深める。疑問点や不明点があればいつでも質問できることを伝え、双方向のコミュニケーションを促進する。退院後も外来透析の際に医療者とコミュニケーションを取る機会があることを説明し、継続的なサポート体制があることを伝える。
信仰の有無、価値観、信念、信仰による食事
A氏の信仰は特にないとされており、特定の宗教的実践や礼拝の必要性はない。これは治療方針の決定や日常生活において、宗教的制約を考慮する必要がないことを意味している。価値観や信念については、「こんなに大変な治療になるとは思わなかった。でも生きるためには仕方ないですね」という発言から、生命を大切にする価値観と現実を受け入れる姿勢が伺える。また「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」という発言から、家族を大切に思い、他者に負担をかけたくないという価値観が読み取れる。性格が温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢があることから、規範を守り、責任を果たすことを重視する価値観を持っていると考えられる。退職前は建設会社の事務職として勤務しており、仕事を通じて社会に貢献してきた経験が価値観の形成に影響している可能性がある。信仰による食事制限はなく、透析食の制限のみを遵守すればよい。宗教的理由による特定の食品の禁忌や、断食などの習慣を考慮する必要はない。
治療法の制限
A氏には信仰による治療法の制限はない。血液透析は人工的な医療処置であり、一部の宗教では受け入れられない場合があるが、A氏の場合は特にそのような制約はない。輸血についても宗教的理由による拒否はないと考えられる。貧血が持続しており、ヘモグロビン値9.1g/dLと低値であるが、エリスロポエチン製剤による治療を受けている。重度の貧血により輸血が必要になった場合でも、宗教的理由による制限はない。透析に使用される薬剤や処置についても、信仰による制限はなく、医学的に必要な治療を全て受けることができる。臓器移植についても、将来的に腎移植が検討される場合、宗教的理由による制限はないと考えられる。
ニーズの充足状況
A氏の自分の信仰に従って礼拝するというニーズについては、特定の信仰を持っていないため、宗教的実践の必要性はない。したがってこのニーズは該当しないか、あるいは充足されていると考えられる。ただし信仰がないことと、スピリチュアルなニーズがないことは異なる。人生の意味や目的、希望、苦悩への対処といったスピリチュアルな側面は、信仰の有無にかかわらず全ての人に存在する。A氏は末期腎不全という重篤な疾患の診断を受け、生涯にわたる透析治療が必要になった。この状況は人生観や価値観に大きな影響を与え、「なぜ自分がこのような病気になったのか」「これからどのように生きていけばよいのか」といった実存的な問いに直面している可能性がある。「こんなに大変な治療になるとは思わなかった」という発言には、予期しなかった人生の変化への戸惑いが表れている。「でも生きるためには仕方ないですね」という発言は、現実を受け入れようとする姿勢を示しているが、その裏には諦めや無力感が隠れている可能性もある。妻と二人暮らしで、長男と長女は県外に在住しており、家族との関係性が A氏の生きる意味や支えとなっている。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」という発言は、家族への配慮であると同時に、自分の存在価値や役割についての懸念を反映している可能性がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の信仰と価値観に関する主な課題は、特定の宗教的実践の必要性はないが、スピリチュアルペインへの対応と人生の意味の再構築である。看護介入として、まず A氏が信仰を持たないことを尊重し、宗教的な押しつけを避ける。同時にスピリチュアルなニーズに配慮し、A氏が人生の意味や目的について考える機会を提供する。透析導入により生活が大きく変化したことについて、A氏がどのように感じているか、じっくりと話を聞く。「こんなに大変な治療になるとは思わなかった」という発言の背景にある感情を探る。失望、怒り、悲しみ、不安など、様々な感情があることを認め、それらを表出してもよいことを伝える。「でも生きるためには仕方ないですね」という発言に対しては、現実を受け入れようとする姿勢を評価しつつ、本当にそう思っているのか、他に感じていることはないかを確認する。無理に前向きになろうとしていないか、本音を抑圧していないかに注意を払う。「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」という発言に対しては、家族が支えたいと思っていることや、互いに支え合うことが夫婦の絆を深めることを伝える。A氏の存在自体が妻や子どもたちにとって大切であることを伝え、自己価値感を高める。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という不安に対しては、透析と両立できる活動や役割があることを具体的に示す。退職後の生活において、A氏がどのような活動に意味を見出してきたか、今後どのような生活を送りたいかを一緒に考える。透析導入患者の中には、透析を機に人生を見つめ直し、新たな生きがいを見つけた人もいることを伝える。A氏が大切にしている価値観や信念を尊重し、それらを維持できるよう支援する。家族を大切にする価値観、規範を守る姿勢、責任を果たそうとする態度を評価する。妻や子どもたちとの時間を大切にし、家族との絆を深める機会を提供する。面会時間を十分に確保し、家族と一緒に今後の生活について話し合う機会を作る。スピリチュアルペインが強い場合や、実存的な問いに苦しんでいる様子が見られる場合は、必要に応じて臨床宗教師やチャプレン、心理士などの専門家への相談を提案する。信仰を持たない人でも、自然、芸術、音楽、文学などを通じてスピリチュアルな充足を得ることができるため、A氏の興味や嗜好に合わせた活動を提案する。病室で新聞を読んだり、テレビを見たり、音楽を聴いたりする機会を提供し、心の安らぎを得られるよう配慮する。退院後の生活において、地域のコミュニティや患者会などに参加することで、同じ境遇の人々との交流や支え合いが得られることを説明する。透析しながらも充実した人生を送っている人々の情報を提供し、希望を持てるよう支援する。
職業、社会的役割、入院
A氏は退職前に建設会社の事務職として勤務していた。事務職は座位での作業が中心であり、書類作成、データ入力、電話対応、来客対応などの業務を行っていたと推測される。現在78歳であることから、定年退職後すでに10年以上が経過していると考えられる。退職後の社会的役割や活動については具体的な記載がないため、地域活動やボランティア、趣味のサークルなどに参加していたかは不明である。妻と二人暮らしであり、家庭内での役割として夫としての役割、父親としての役割を担っている。長男と長女は県外に在住しており、月に1回程度帰省するとのことで、祖父としての役割もあると考えられる。入院により、これまでの日常的な役割や活動から離れることを余儀なくされている。入院生活は受動的な立場に置かれることが多く、自己決定の機会が減少し、達成感や有用感を得にくい状況である。
疾患が仕事と役割に与える影響
A氏は既に退職しており、現在は職業には就いていないため、疾患が仕事に与える直接的な影響はない。しかし透析導入により、退職後の生活における役割や活動に大きな影響が生じている。週3回、1回4時間の透析が必要であり、透析日は午前中が透析で占められる。透析後は疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、透析日の活動は大きく制限される。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という A氏の発言は、透析導入により役割や活動が制限されることへの懸念を示している。家庭内での役割として、買い物や家事の一部を担っていた可能性があるが、透析日はこれらの活動が困難になる。妻との関係において、対等なパートナーとしての役割が果たせなくなり、「妻に迷惑をかけてしまうのが心配です」という発言につながっている。退職後に趣味や地域活動に参加していた場合、透析のスケジュールにより参加が困難になったり、頻度が減少したりする可能性がある。体力的な制限により、これまで行っていた活動ができなくなることもある。父親や祖父としての役割についても、県外に住む子どもたちを訪ねることが難しくなったり、孫の世話をする体力がなくなったりする可能性がある。社会的な役割の喪失は、自己価値感や生きがいの低下につながる重要な問題である。
ニーズの充足状況
A氏の達成感をもたらすような仕事をするというニーズは十分に充足されていない。既に退職しており職業には就いていないが、退職後の生活における役割や活動を通じて達成感や有用感を得ていた可能性がある。しかし透析導入により、これらの役割や活動が大きく制限されている。入院生活では受動的な立場に置かれることが多く、自己決定の機会が少ない。日常生活動作は概ね自立しているが、入浴は週2回の清拭に制限され、透析スケジュールに生活が左右される。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という不安は、役割の喪失や有用感の低下への懸念を示している。妻に対して「迷惑をかけてしまうのが心配です」と述べており、家庭内での役割を果たせないことへの罪悪感や無力感を感じている。性格が温厚で真面目であることから、これまで責任を持って役割を果たしてきた人物と推測され、役割を果たせないことが自己価値感の低下につながっている可能性が高い。透析日の疲労感により活動意欲が低下しており、達成感を得られる活動に取り組む余裕がない状態である。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の仕事と役割に関する主な課題は、透析導入による役割の変化への適応、新たな役割や活動の発見、自己価値感の維持である。看護介入として、まず A氏が退職後にどのような役割や活動を大切にしてきたかを聴取する。家庭内での役割、地域活動、趣味、友人との交流など、A氏にとって意味のある活動を把握する。透析導入により、これらの活動がどのように影響を受けるか、どのような調整が可能かを一緒に考える。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という不安に対しては、透析と両立できる活動が多くあることを具体的に示す。透析患者の中には、仕事を続けている人、趣味を楽しんでいる人、ボランティア活動をしている人など、様々な形で社会的役割を果たしている人がいることを伝える。透析のスケジュールを活動に組み込む方法を一緒に考える。週3回の透析日は午前中が制限されるが、午後や非透析日には活動が可能であることを説明する。疲労を考慮しながら、無理のない範囲で活動を計画する方法を提案する。入院中でも達成感を得られる機会を提供する。透析管理や食事管理、服薬管理などのセルフケア行動を習得することは、重要な達成目標である。シャント管理の方法を習得したり、水分制限を守れたり、適切な食事選択ができたりすることを評価し、達成感を持てるよう支援する。A氏の自律性を尊重し、可能な範囲で自己決定の機会を提供する。透析時間の希望、食事の選択、日課の決定など、小さなことでも自分で決められることを増やす。病棟内での役割を見つける。他の患者との交流の中で、透析導入の先輩として助言を与えたり、励ましたりする役割を果たすことも有意義である。妻との関係において、対等なパートナーシップを維持できるよう支援する。「妻に迷惑をかけてしまう」という罪悪感に対しては、互いに支え合うことが夫婦の絆であることを伝える。A氏ができることを見つけ、役割を果たせる機会を提供する。妻と一緒に透析食について学んだり、退院後の生活計画を立てたりする過程で、A氏の意見や希望を尊重する。退職前の職業経験を活かせる活動を提案する。事務職として培った能力や知識を、何らかの形で活用できる機会があるかもしれない。患者会の事務局を手伝ったり、透析に関する情報をまとめたりすることも、有意義な活動となり得る。子どもや孫との関係を維持する方法を一緒に考える。電話やビデオ通話を活用したコミュニケーション、手紙やメールでの交流など、距離を超えてつながる方法を提案する。透析のスケジュールに合わせて、子どもたちが帰省しやすいタイミングを調整することも検討する。リハビリテーションや運動療法を通じて、体力の維持向上を図る。貧血が改善し、体力が回復することで、活動の幅が広がる可能性がある。理学療法士と連携し、適切な運動プログラムを提供する。退院後の生活において、新たな役割や活動を見つけられるよう支援する。地域の透析患者会への参加を勧め、同じ境遇の人々との交流や情報交換の機会を提供する。透析しながら充実した生活を送っている患者の体験談を紹介し、希望とモデルを提供する。A氏の強みや能力を認め、評価する。真面目に治療に取り組む姿勢、妻を思いやる気持ち、現実を受け入れようとする態度など、A氏の持つ肯定的な特性を言語化し、自己価値感を高める。
趣味、休日の過ごし方、余暇活動
A氏の趣味や休日の過ごし方、余暇活動については具体的な記載がない。78歳という年齢と退職後の生活を考えると、何らかの趣味や余暇活動を持っていた可能性が高いが、詳細な情報収集が必要である。視力は老眼があるが眼鏡を使用すれば新聞を読むことができることから、読書が趣味である可能性がある。聴力は正常であることから、音楽鑑賞やテレビ視聴も可能である。建設会社の事務職として勤務していたことから、几帳面で計画的な性格が推測され、園芸や日曜大工、将棋や囲碁などの趣味を持っていた可能性もある。妻と二人暮らしであり、夫婦で散歩に出かけたり、買い物に行ったり、旅行を楽しんだりしていた可能性がある。長男と長女は県外に在住しているが、月に1回程度帰省するとのことで、孫と遊ぶことが楽しみであったかもしれない。喫煙歴はなく、飲酒は以前は晩酌程度であったが腎機能低下後は中止しており、健康的な生活習慣を心がけていたと考えられる。
入院中と療養中の気分転換方法
入院中の気分転換方法については具体的な記載がない。病室でテレビを見たり、新聞を読んだりすることは可能と考えられる。面会時には妻との会話が気分転換になっていると推測される。しかし入院環境と透析導入への不安から入眠困難が生じており、心理的ストレスが高い状態である。透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、積極的にレクリエーション活動に参加する余裕がない可能性がある。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という発言は、楽しみや気分転換の機会が失われることへの懸念も含まれている可能性がある。病院によっては患者向けのレクリエーション活動や集団プログラムが提供されているが、A氏がそれらに参加しているかは不明である。入院生活では時間が長く感じられることも多く、適切な気分転換が重要である。
運動機能障害
A氏に運動機能障害はなく、麻痺もない。歩行は自立しており、病棟内は杖なしで移動可能である。移乗動作や排泄動作も自立しているため、身体的にはレクリエーション活動に参加する能力がある。しかし貧血が持続しており、ヘモグロビン値9.1g/dLと低値であることが、活動耐性を低下させている。酸素運搬能の低下により、活動時の息切れや易疲労感が生じやすい。透析日は特に疲労感が強く、日中に傾眠傾向があることから、活動への参加が制限される。透析前後の血圧変動もあり、透析前は152/88mmHg程度、透析後は142/84mmHgと変化する。体重も透析前には56kg程度まで増加し、透析後は54kgへと減少する。この体液量の変動が身体的負担となり、運動やレクリエーション活動への参加を困難にしている。高齢者では加齢による筋力低下や持久力の低下があり、長時間の活動や激しい運動は困難である。
認知機能、ADL
A氏の認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。これはレクリエーション活動の内容を理解し、ルールを守って参加する能力があることを示している。日常生活動作は概ね自立しており、歩行、移乗、排泄、更衣などが自立している。これらの能力は、様々なレクリエーション活動に参加する基盤となる。視力は眼鏡使用により補正されており、聴力も正常であることから、視覚的・聴覚的な情報を活用するレクリエーション活動にも参加可能である。性格は温厚で真面目であり、集団での活動にも適応できると考えられる。ただし透析日の疲労や睡眠不足により、一時的に集中力や意欲が低下する可能性がある。
ニーズの充足状況
A氏の遊びやレクリエーションに参加するというニーズは十分に充足されていない。入院前の趣味や余暇活動についての情報が不足しており、それらの活動がどの程度継続できているかが不明である。入院により日常生活から切り離され、自宅で行っていた趣味や活動ができなくなっている可能性が高い。入院中の気分転換方法も限られており、テレビや新聞以外のレクリエーション活動への参加状況が不明である。透析導入という大きなストレスを抱えている中で、適切な気分転換やストレス解消の機会が不足している可能性がある。透析日の疲労により、レクリエーション活動への意欲が低下している。「家に帰ってから何もできなくなるのではないか」という不安は、今後の生活における楽しみや趣味の喪失への懸念を反映している。運動機能は保たれているが、貧血や疲労により活動耐性が低下しており、以前のような活動レベルを維持することが困難になっている。高齢者にとって、趣味や余暇活動は生きがいや生活の質に直結する重要な要素であり、これらが失われることは精神的健康に大きな影響を与える。
健康管理上の課題と看護介入
A氏のレクリエーションに関する主な課題は、入院により趣味や余暇活動が制限されていること、透析導入による活動パターンの変化への適応、適切な気分転換方法の確立である。看護介入として、まず A氏の趣味や余暇活動、入院前の楽しみについて詳しく聴取する。どのような活動に意味を見出していたか、何が楽しかったかを理解する。それらの活動が入院中や透析導入後にどのように継続できるか、あるいは代替できるかを一緒に考える。入院中でも可能な趣味や活動を提案する。読書が好きであれば、図書の貸し出しサービスを利用する。音楽鑑賞が好きであれば、ラジオやポータブル音楽プレーヤーを活用する。テレビ番組の中で興味のあるものを見つけ、楽しみにできるよう支援する。病院で提供されているレクリエーション活動があれば、参加を促す。ただし透析日の疲労を考慮し、無理のない範囲での参加を勧める。他の患者との交流を通じて、新たな趣味や活動を発見する機会を提供する。透析日と非透析日で活動パターンを調整する方法を一緒に考える。透析日は休息を優先し、非透析日に趣味や活動を楽しむというメリハリをつける。午前中に透析がある日でも、午後や夕方に気分転換の時間を作れるよう支援する。妻との面会時間を活用し、一緒に楽しめる活動を提案する。会話、写真を見る、テレビを一緒に見るなど、二人で過ごす時間を大切にする。子どもや孫からの手紙や写真、ビデオメッセージなどを楽しむ機会を作る。退院後の生活において、趣味や余暇活動を継続する方法を具体的に計画する。透析のスケジュールに合わせて、趣味の時間を組み込む。透析患者でも参加できるサークルや患者会の情報を提供する。体力に合わせた活動レベルの調整方法を説明する。貧血が改善することで活動耐性が向上することを伝え、治療への意欲を高める。適度な運動やリハビリテーションを通じて、体力の維持向上を図る。理学療法士と連携し、A氏の体力や興味に合わせた運動プログラムを提供する。散歩や軽い体操など、日常的に取り組める活動を提案する。気分転換としての効果だけでなく、体力維持や血圧コントロール、便秘予防などの健康面での利点も説明する。透析しながら趣味や旅行を楽しんでいる患者の体験談を紹介する。透析施設は全国にあり、旅行先での透析も可能であることを説明する。透析導入によって全てが制限されるわけではなく、工夫次第で多くの活動が可能であることを伝え、希望を持てるよう支援する。A氏の興味や価値観に合わせて、新たな趣味や活動を提案する。入院や透析導入を機に、新しいことに挑戦することも一つの選択肢である。手芸、絵画、俳句、書道など、座位で楽しめる趣味を紹介する。ストレス解消やリラクゼーションの方法を教育する。深呼吸、音楽療法、アロマセラピーなど、簡単に取り組める方法を提案する。これらは睡眠改善にも役立つ可能性がある。
発達段階
A氏は78歳であり、エリクソンの心理社会的発達理論における老年期に該当する。この段階の発達課題は統合対絶望であり、人生を振り返り、自分の人生に意味と価値を見出すことが重要となる。A氏は建設会社の事務職として勤務し、退職後は妻と二人暮らしをしながら生活してきた。長男と長女がおり、孫もいることから、家族関係を築き、次世代を育てるという中年期の課題も達成してきたと考えられる。しかし末期腎不全の診断と透析導入という大きな健康上の変化により、人生の最終段階における発達課題への取り組みが影響を受けている可能性がある。「こんなに大変な治療になるとは思わなかった」という発言は、予期しなかった困難に直面した時の動揺を示している。老年期の発達において、健康の維持と喪失への適応は重要な課題である。慢性疾患を抱えながら、どのように生活の質を保ち、人生の意味を見出していくかが問われている。
疾患と治療方法の理解
A氏の認知機能は保たれており、MMSE28点と良好である。これは疾患や治療方法について学習し、理解する能力があることを示している。性格は温厚で真面目であり、医療者の説明を真剣に聞く姿勢がある。しかし疾患と治療方法についての具体的な理解度は記載されていない。末期腎不全とは何か、なぜ透析が必要なのか、透析の仕組みはどうなっているのか、といった基本的な知識を持っているかを確認する必要がある。透析の種類や方法、血液透析の利点と欠点、腹膜透析との違いなどについて理解しているかも重要である。シャントの役割と管理方法、穿刺部位のケア、シャント音の聴取方法などの実践的な知識の習得状況を評価する必要がある。食事療法については、妻が「家での食事管理が難しそうで不安です。カリウムやリンのことをもっと勉強しなければ」と述べており、カリウム制限やリン制限の具体的な方法についての理解が不十分である可能性がある。水分制限の重要性や具体的な方法、透析間の体重増加を3kg以内に抑える必要性について理解しているかも確認が必要である。服薬管理については、現在は看護師管理となっているが、退院後は自己管理または妻の管理が必要となる。各薬剤の目的や副作用、服薬のタイミングなどについての理解を確認する必要がある。
学習意欲、認知機能、学習機会への家族の参加度合い
A氏の学習意欲については、医療者の説明を真剣に聞く姿勢があることから、ある程度の学習意欲があると考えられる。しかし「こんなに大変な治療になるとは思わなかった」という発言や、透析導入への不安から入眠困難が生じていることから、心理的負担が学習意欲に影響している可能性がある。透析日は疲労感が強く日中に傾眠傾向があることから、学習に集中できる時間や体力が制限されている。認知機能は保たれており、MMSE28点と良好であるため、学習能力自体は問題ない。視力は眼鏡使用により補正されており、聴力も正常であることから、視覚教材や口頭での説明を理解することができる。家族の参加については、妻がキーパーソンであり、「カリウムやリンのことをもっと勉強しなければ」と述べていることから、学習への意欲がある。妻も一緒に教育を受けることで、退院後の生活管理がより効果的に行えると期待される。長男と長女は県外に在住しており月に1回程度の帰省であるため、日常的な学習機会への参加は困難である。
ニーズの充足状況
A氏の正常な発達および健康を導くような学習をするというニーズは部分的に充足されているが、改善の余地がある。認知機能が保たれており、学習能力は十分にある。医療者の説明を真剣に聞く姿勢があり、学習への基本的な態度は良好である。しかし疾患と治療方法についての理解度が十分かは不明であり、体系的な教育プログラムが提供されているかも記載がない。シャント管理、食事療法、水分制限、服薬管理など、退院後の自己管理に必要な知識と技術の習得状況を評価する必要がある。A氏自身だけでなく、妻も一緒に学習する必要があるが、妻の理解度や技術習得の状況も不明である。透析日の疲労や心理的負担が学習の障壁となっている可能性があり、学習のタイミングや方法を工夫する必要がある。高齢者の学習においては、一度に多くの情報を提供するのではなく、段階的に繰り返し教育することが効果的である。また実践的な演習を通じて技術を習得することが重要である。老年期の発達課題として、疾患を抱えながらも人生の意味を見出し、統合を達成することが求められている。透析という新たな治療を受け入れ、それを生活の一部として統合していく過程を支援する必要がある。
健康管理上の課題と看護介入
A氏の学習と発達に関する主な課題は、透析管理に関する知識と技術の習得、退院後の自己管理能力の向上、老年期の発達課題への適応支援である。看護介入として、まず A氏と妻の現在の理解度をアセスメントする。疾患、治療方法、自己管理について、何を知っていて何を知らないかを明確にする。体系的な教育プログラムを計画し、段階的に実施する。一度に多くの情報を提供するのではなく、優先順位をつけて教育する。まずは生命に関わる重要な事項から教育し、徐々に詳細な知識を提供する。教育の方法として、口頭での説明だけでなく、パンフレットや図表などの視覚教材を活用する。A氏は眼鏡使用により新聞を読むことができるため、文字情報も効果的である。実物を見せたり、実際に触れたりする機会を提供する。シャント管理については、シャント音の聴取を実際に体験してもらい、毎日のセルフチェックの方法を習得してもらう。穿刺部位の観察方法や異常の見分け方を具体的に教育する。食事療法については、栄養士と連携して教育を行う。カリウム含有量の多い食品とリン含有量の多い食品のリストを提供し、食品選択の方法を具体的に説明する。実際の食事を見ながら、適切な量や組み合わせを学習する機会を作る。調理方法の工夫により、カリウムを減らす方法なども教育する。水分制限については、1日の水分摂取量の目標を明確にし、具体的な測定方法を教育する。コップ1杯の水の量、食事に含まれる水分量など、実践的な情報を提供する。透析間の体重増加を記録し、水分摂取量との関係を理解してもらう。服薬管理については、各薬剤の目的と効果、副作用、服薬のタイミングを説明する。薬剤一覧表を作成し、視覚的に分かりやすく提示する。お薬カレンダーやピルケースの使用方法を提案し、飲み忘れを防ぐ工夫を一緒に考える。教育のタイミングを工夫し、A氏の体調や疲労度に合わせて実施する。透析日の午後や非透析日など、比較的元気な時間帯を選ぶ。一回の教育時間は短めにし、集中力が続く範囲で行う。教育後は理解度を確認し、必要に応じて繰り返し説明する。ティーチバック法を使用し、A氏に説明した内容を自分の言葉で言い直してもらうことで、理解度を確認する。妻も一緒に教育を受ける機会を設け、夫婦で協力して管理できるよう支援する。妻の理解度も確認し、不安や疑問に丁寧に答える。退院前には、自宅での生活を想定したシミュレーションを行う。1日の生活スケジュールを立て、透析日と非透析日の過ごし方を具体的に計画する。食事の準備、服薬、シャントチェック、体重測定など、必要な行動を生活の中に組み込む方法を一緒に考える。緊急時の対応についても教育する。シャント閉塞の兆候、感染の徴候、高カリウム血症の症状など、異常を早期に発見する方法を教育する。異常があった場合の連絡先や対応方法を明確にする。外来透析施設の見学や、外来透析の流れについての説明を提供する。退院後も継続的に学習できる機会があることを伝える。透析患者会や患者向けの学習会の情報を提供する。老年期の発達課題への支援として、A氏が透析という新たな治療を受け入れ、それを人生の一部として統合していく過程を支援する。これまでの人生経験や価値観を尊重し、透析導入後も A氏らしい生活を送れるよう支援する。「生きるためには仕方ないですね」という発言の背景にある感情を理解し、人生の意味を見出せるよう対話を重ねる。学習を通じて自己効力感を高め、透析管理を自分でコントロールできるという感覚を持てるよう支援する。小さな成功体験を積み重ね、達成感を感じられるよう関わる。
看護計画
看護問題
末期腎不全による体液貯留に関連した体液量過剰
長期目標
退院後も透析間の体重増加を3kg以内に維持し、体液管理を自己管理できる
短期目標
2週間以内に水分制限の方法を理解し、透析間の体重増加を3kg以内にコントロールできる
≪O-P≫観察計画
・透析前後の体重測定値と体重増加量
・1日の水分摂取量と排泄量
・浮腫の有無と程度(下腿、足背、顔面、手指)
・透析前後の血圧値の変動
・呼吸状態(呼吸数、呼吸困難の有無、SpO2値)
・心音の聴取と心拍数の変動
・尿量の推移
・口渇の訴えや程度
・体液貯留に関連する自覚症状(倦怠感、息切れ、動悸)
・血液データ(BUN、Cr、電解質、特にナトリウム値)
・水分制限の遵守状況
・食事摂取量と水分を多く含む食品の摂取状況
≪T-P≫援助計画
・透析前後の体重測定を確実に実施し、記録する
・1日の水分摂取量を記録し、制限内に収まるよう調整する
・浮腫のある部位を挙上し、循環を促進する
・透析スケジュールに合わせた生活リズムを整える支援をする
・口渇時の対処方法として、氷を舐める、うがいをするなどの工夫を提案する
・水分を多く含む食品のリストを提供し、摂取量の調整を支援する
・体重増加が目標を超えた場合は、原因を一緒に分析する
・透析中の除水速度が適切か、医師と連携して調整する
・呼吸困難や浮腫の増強がある場合は速やかに医師に報告する
・栄養士と連携し、水分制限を考慮した食事内容を調整する
・妻と一緒に水分管理の方法を考え、家族の協力体制を整える
・体液貯留の徴候が出現した際の対応方法を確認する
≪E-P≫教育・指導計画
・水分制限の必要性と体液貯留のリスクについて説明する
・1日の水分摂取量の目標値と測定方法を指導する
・食事に含まれる水分量の計算方法を教育する
・体重測定の重要性と毎日同じ条件で測定する方法を指導する
・浮腫や呼吸困難など体液貯留の徴候を自己観察する方法を教育する
・透析間の体重増加を3kg以内に抑える具体的な方法を妻と一緒に学習する
看護問題
末期腎不全による腎性貧血に関連した活動耐性低下
長期目標
退院時にヘモグロビン値10g/dL以上を維持し、日常生活活動を疲労なく行える
短期目標
2週間以内に活動と休息のバランスを理解し、透析日と非透析日の活動パターンを確立できる
≪O-P≫観察計画
・ヘモグロビン値とヘマトクリット値の推移
・活動時と安静時のバイタルサイン(脈拍、血圧、呼吸数、SpO2)
・活動後の疲労感の程度と回復に要する時間
・顔色や皮膚粘膜の色調
・めまいや立ちくらみの有無と頻度
・日中の活動内容と活動量
・透析日と非透析日の疲労感の差
・睡眠の質と日中の傾眠状態
・食事摂取量と栄養状態
・エリスロポエチン製剤の投与状況と効果
・鉄剤の投与状況と血清鉄、フェリチン値
・活動に対する意欲や発言内容
≪T-P≫援助計画
・活動と休息のバランスを考慮した日課を一緒に計画する
・透析日は無理な活動を避け、十分な休息時間を確保する
・非透析日は適度な活動を促し、体力維持を図る
・病棟内歩行を段階的に促し、活動耐性を評価する
・活動時は付き添い、めまいや転倒を防止する
・起立時はゆっくりと動作するよう声かけし、起立性低血圧を予防する
・疲労が強い場合は休息を促し、無理をさせない
・エリスロポエチン製剤の投与を確実に実施する
・鉄剤の投与が必要な場合は医師に報告し、適切に投与する
・栄養状態の改善のため、食事摂取量を増やす工夫をする
・理学療法士と連携し、適切な運動プログラムを提供する
・貧血改善の経過を本人と妻に説明し、治療継続への意欲を高める
≪E-P≫教育・指導計画
・腎性貧血の原因とエリスロポエチン製剤の効果について説明する
・貧血による活動耐性低下は治療により改善することを伝える
・活動と休息のバランスの重要性を説明する
・めまいや立ちくらみがある場合の対処方法を指導する
・透析日と非透析日の活動パターンの調整方法を教育する
・退院後も外来でエリスロポエチン製剤の投与が継続されることを説明する
看護問題
透析導入と生活変化に関連した不安
長期目標
退院時に透析生活に適応し、前向きな気持ちで自宅生活を送ることができる
短期目標
1週間以内に不安な気持ちを表出でき、透析導入後の生活について具体的なイメージを持てる
≪O-P≫観察計画
・不安に関する言動や表情の変化
・睡眠状態(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒の有無)
・食欲や食事摂取量の変化
・透析に対する理解度と受け入れ状況
・家族への配慮や心配に関する発言
・退院後の生活に関する懸念の内容
・医療者や他患者とのコミュニケーション状況
・妻との会話内容や面会時の様子
・透析前後の精神状態の変化
・睡眠薬の使用状況と効果
・趣味や気分転換活動への関心度
・質問や疑問の内容と頻度
≪T-P≫援助計画
・定期的に面談の時間を設け、じっくりと話を聞く
・不安な気持ちを自由に表出できる雰囲気を作る
・共感的に傾聴し、A氏の感情を受け止める
・透析導入は大きな変化であり、不安を感じることは自然であることを伝える
・透析しながら充実した生活を送っている患者の情報を提供する
・妻との面会時間を十分に確保し、夫婦で話し合う機会を作る
・退院後の生活について具体的に一緒に計画し、漠然とした不安を軽減する
・睡眠が改善するよう、非薬物的な睡眠改善策を提供する
・透析患者会の情報を提供し、同じ境遇の人との交流機会を紹介する
・A氏の強みや肯定的な面を言語化し、自己価値感を高める
・多職種カンファレンスを開催し、チーム全体で心理的支援を行う
・必要に応じて臨床心理士への相談を提案する
≪E-P≫教育・指導計画
・透析導入後の生活について具体的な情報を提供する
・透析と両立できる活動や趣味があることを説明する
・外来透析の流れと透析日の過ごし方について説明する
・シャント管理や食事管理など、自己管理の方法を段階的に教育する
・退院後も外来で継続的にサポートが受けられることを伝える
・不安や疑問があればいつでも相談できることを説明する
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
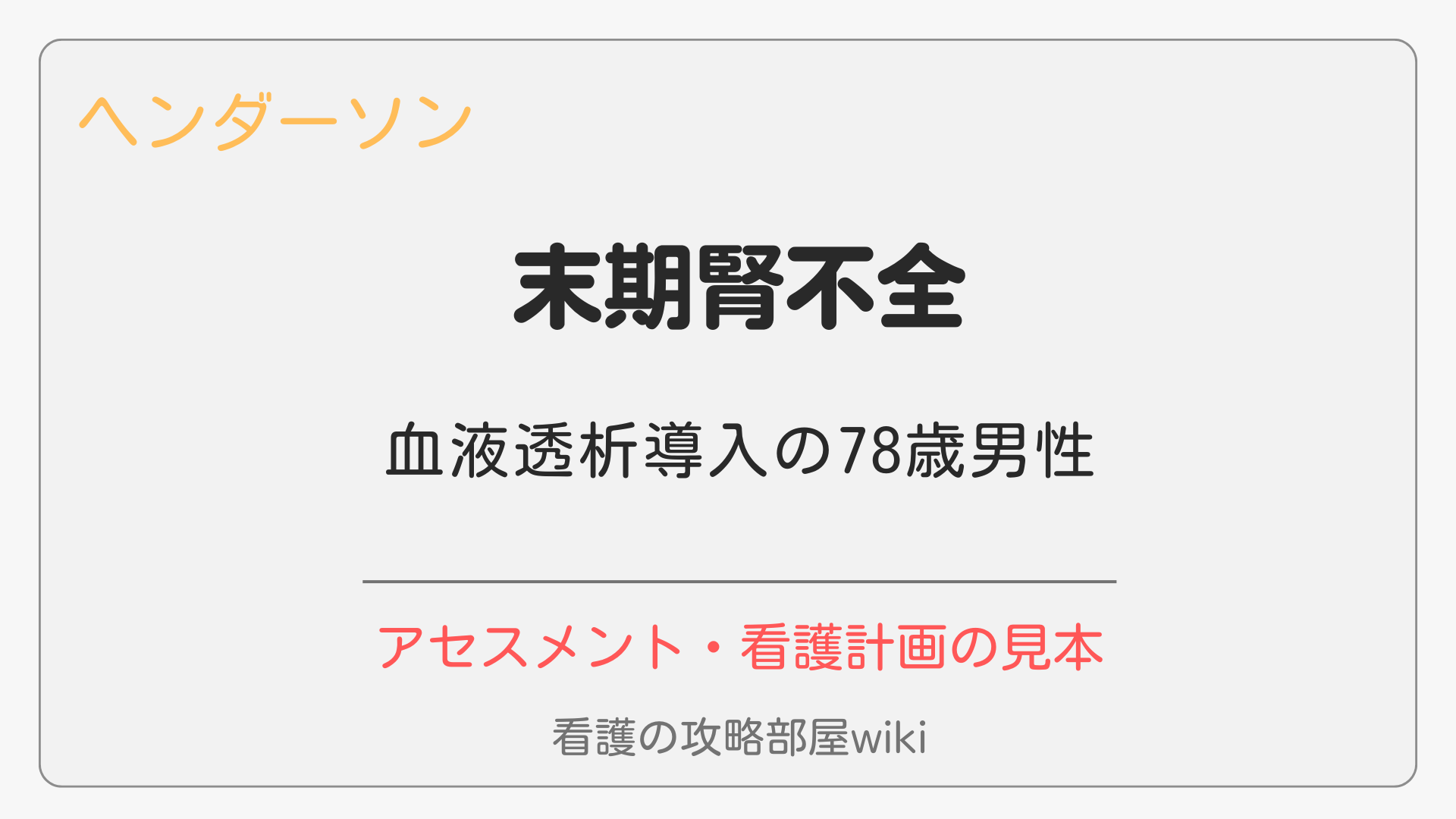
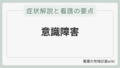
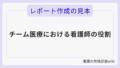
コメント