事例の要約
レビー小体型認知症により有料老人ホームに入居中の高齢者で、幻視や認知機能の変動、パーキンソン症状を呈しながらも家族との絆を大切にしている事例。介入日は8月15日で入居から127日目である。
基本情報
A氏は82歳の女性で、身長152cm、体重42kgである。家族構成は夫が3年前に他界しており、長女が県内に在住しキーパーソンとなっている。長男は県外在住で月に1回程度面会に訪れる。元小学校教師として38年間勤務し、退職後は地域の読み聞かせボランティアに参加していた。性格は几帳面で真面目、人との交流を好む社交的な面があったが、最近は不安が強くなる傾向がある。感染症はなく、アレルギーも特にない。認知機能はMMSE 18点、HDS-R 16点で中等度の認知障害を認める。
病名
病名はレビー小体型認知症である。
既往歴と治療状況
既往歴として10年前に高血圧症、7年前に脂質異常症の診断を受け、降圧薬とスタチン系薬剤で治療を継続している。5年前に変形性膝関節症で整形外科を受診し、現在も経過観察中である。3年前から物忘れが目立ち始め、2年前に認知症専門外来を受診し当初はアルツハイマー型認知症と診断されたが、その後幻視や認知機能の変動、パーキンソン症状が出現したため、レビー小体型認知症と診断が変更された。
入院から現在までの情報
入居から現在までの経過として、A氏は自宅での生活が困難となり4月10日に当有料老人ホームへ入居した。入居当初は環境の変化に戸惑い、夜間に「知らない人が部屋にいる」と訴える幻視が頻繁にみられ、不穏状態となることがあった。また日中でも認知機能に波があり、午前中は比較的会話が成立するが、午後から夕方にかけて見当識障害が強くなる傾向がある。入居から1ヶ月後にはホームの環境に徐々に慣れ、スタッフの顔も覚え始めたが、日によって認知機能の変動が大きい。6月下旬から歩行時の前傾姿勢や小刻み歩行が目立つようになり、転倒リスクが高まっている。7月に入ってからは表情が乏しくなり、動作緩慢が進行している。8月に入り気温の上昇とともに食欲が低下し、体重が入居時の45kgから42kgへ減少した。現在は日中の活動量を増やし、夜間の睡眠リズムを整えるケアを継続している。
バイタルサイン
入居時のバイタルサインは、血圧142/86mmHg、脈拍78回/分・整、呼吸数18回/分、体温36.4℃、SpO2 97%(室内気)であった。現在のバイタルサインは血圧138/82mmHg、脈拍74回/分・整、呼吸数16回/分、体温36.6℃、SpO2 98%(室内気)であり、概ね安定している。
食事と嚥下状態
入居前の食事は長女が調理したものを自宅で摂取していたが、食事の準備を忘れたり、食べたことを忘れて何度も食事を求めることがあった。1日3食を摂取していたが、食事量にムラがあった。嚥下機能は保たれていたが、時折むせることがあった。喫煙歴はなく、飲酒は夫の存命中に晩酌として日本酒を少量嗜む程度であったが、夫の死後は飲酒していない。現在の食事は常食で一口大に調理されたものを提供しており、自力摂取が可能である。しかし認知機能の変動により、食事に集中できない日があり、摂取量は5割から8割程度と日によって変動する。嚥下状態は概ね良好だが、注意が散漫になるとむせが生じることがある。
排泄
入居前の排泄は日中はトイレで自立していたが、夜間は尿意を感じにくくなっており、ポータブルトイレを使用していた。排便は2日に1回程度で、時折便秘傾向があった。現在の排泄は日中はトイレ誘導により排尿が可能だが、尿意の訴えが曖昧なため定時誘導を行っている。夜間はリハビリパンツとパッドを使用しており、1回程度の交換が必要である。排便は3日に1回程度と便秘傾向が続いており、酸化マグネシウム330mgを1日3回毎食後に内服している。それでも排便がない場合は浣腸を施行することがある。
睡眠
入居前の睡眠は夜間に幻視が出現することがあり、不安から十分な睡眠がとれていなかった。就寝時刻は22時頃であったが、夜中に何度も目を覚まし、「誰かいる」と長女を起こすことが頻繁にあった。現在の睡眠は21時頃に就寝し、6時頃に起床するリズムが確立されつつある。しかし夜間に2から3回覚醒することがあり、幻視により不穏となることがある。エスゾピクロン2mgを就寝前に内服しているが、効果は限定的である。日中の傾眠も時々みられる。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は加齢による視力低下があり、眼鏡を使用している。聴力は軽度の難聴があるが、補聴器は使用しておらず、ゆっくりとした会話であれば理解可能である。知覚は四肢末梢の感覚が若干鈍いが、日常生活に支障はない。コミュニケーションは認知機能の良い時には会話が成立し、昔の教師時代の話を楽しそうに語ることがある。しかし認知機能が低下している時には、話の内容が支離滅裂になったり、同じことを繰り返し尋ねることがある。信仰は特になし。
動作状況
歩行は杖と見守りがあれば可能だが、前傾姿勢と小刻み歩行がみられ、すくみ足も出現している。転倒リスクが高いため、移動時は必ず付き添いを行っている。移乗は見守りがあれば可能だが、動作が緩慢で時間がかかる。排尿と排便は前述の通り、日中はトイレ誘導により可能である。入浴は週2回の介助浴を実施しており、洗身や洗髪は介助が必要である。衣類の着脱は声かけと見守りがあれば可能だが、ボタンの留め外しに時間がかかる。転倒歴は入居後に2回あり、いずれも夜間にトイレへ向かう際に転倒したものである。幸い大きな外傷はなかったが、その後より転倒に対する恐怖心が強くなっている。
内服中の薬
- ドネペジル塩酸塩5mg 1日1回朝食後
- アムロジピンベシル酸塩5mg 1日1回朝食後
- ロスバスタチンカルシウム2.5mg 1日1回夕食後
- 酸化マグネシウム330mg 1日3回毎食後
- エスゾピクロン2mg 1日1回就寝前
- レボドパ・カルビドパ配合剤100mg 1日3回毎食後
服薬状況は看護師管理となっており、毎食後と就寝前に配薬し、確実な内服を確認している。
検査データ
検査データは以下の通りである。
| 項目 | 入居時(4月10日) | 最近(8月10日) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6,200/μL | 5,800/μL | 3,300-8,600/μL |
| RBC | 398万/μL | 380万/μL | 386-492万/μL |
| Hb | 12.1g/dL | 11.5g/dL | 11.6-14.8g/dL |
| Ht | 36.8% | 35.2% | 35.1-44.4% |
| PLT | 22.4万/μL | 21.8万/μL | 15.8-34.8万/μL |
| TP | 6.8g/dL | 6.5g/dL | 6.6-8.1g/dL |
| Alb | 3.8g/dL | 3.4g/dL | 4.1-5.1g/dL |
| AST | 24U/L | 22U/L | 13-30U/L |
| ALT | 18U/L | 16U/L | 7-23U/L |
| BUN | 18mg/dL | 20mg/dL | 8-20mg/dL |
| Cr | 0.68mg/dL | 0.72mg/dL | 0.46-0.79mg/dL |
| Na | 140mEq/L | 138mEq/L | 138-145mEq/L |
| K | 4.2mEq/L | 4.0mEq/L | 3.6-4.8mEq/L |
| Cl | 104mEq/L | 103mEq/L | 101-108mEq/L |
| 血糖 | 98mg/dL | 102mg/dL | 73-109mg/dL |
| HbA1c | 5.6% | 5.7% | 4.9-6.0% |
| TC | 198mg/dL | 185mg/dL | 142-248mg/dL |
| LDL-C | 118mg/dL | 108mg/dL | 65-163mg/dL |
| HDL-C | 58mg/dL | 55mg/dL | 40-96mg/dL |
| TG | 110mg/dL | 110mg/dL | 40-234mg/dL |
今後の治療方針と医師の指示
今後の治療方針として、嘱託医は現在の薬物療法を継続しながら、認知機能の変動と幻視への対応、パーキンソン症状の進行予防、転倒予防を重点的に行う方針である。ドネペジルは現在の用量を維持し、レボドパ・カルビドパ配合剤の効果を観察しながら、必要に応じて用量調整を検討する。食欲低下と体重減少に対しては、栄養状態の改善を図るため、食事形態の工夫や補助食品の導入を検討する。また日中の活動量を増やし、夜間の睡眠リズムを整えるため、ホーム内で実施される個別のレクリエーションプログラムを継続する。転倒予防のため、訪問リハビリテーションによる歩行訓練と筋力強化訓練を週2回実施する指示が出ている。夜間の幻視と不穏に対しては、環境調整と傾聴を基本とし、エスゾピクロンの効果が不十分な場合は抗精神病薬の少量投与も検討するが、パーキンソン症状の悪化に注意が必要である。
本人と家族の想いと言動
本人は「ここは自分の家じゃないけど、みんな優しくしてくれるからありがたい」とホームでの生活を受け入れている様子を見せる。しかし認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」「娘はどこにいるの」と不安を訴えることがある。夜間に幻視が出現した際には「知らない人が窓の外から覗いている」「部屋に子どもがいる」と訴え、恐怖心から興奮することがある。長女は「母には穏やかに過ごしてほしい。転倒だけは本当に心配」と話し、週に3回程度面会に訪れている。長女が面会に来ると、A氏は表情が明るくなり、「あなたが来てくれると安心する」と喜びを示す。長男は「姉に負担をかけて申し訳ない。できる限り協力したい」と話し、月に1回の面会時には母親と散歩をしたり、昔の写真を見ながら思い出話をする時間を大切にしている。家族はホームでの看取りも視野に入れており、今後も本人が安心して生活できるよう医療スタッフと連携していきたいと希望している。
アセスメント
現在のアセスメント
A氏はレビー小体型認知症と診断されており、幻視、認知機能の変動、パーキンソン症状という特徴的な三徴候を呈している。当初はアルツハイマー型認知症と診断されていたが、症状の経過から診断が変更された経緯がある。レビー小体型認知症は進行性の疾患であり、現在のMMSE 18点、HDS-R 16点という結果は中等度の認知障害を示している。
健康状態としては、既往歴に高血圧症、脂質異常症、変形性膝関節症があり、いずれも長期にわたる管理が必要な慢性疾患である。高血圧症と脂質異常症については降圧薬とスタチン系薬剤で治療が継続されており、現在のバイタルサインは血圧138/82mmHg、脈拍74回/分と概ね安定している。検査データではHb 11.5g/dL、Alb 3.4g/dLと軽度の貧血と低栄養状態が認められ、体重が入居時45kgから42kgへ3kg減少していることから、栄養状態の悪化が懸念される。
服薬状況については、ドネペジル塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシウム、酸化マグネシウム、エスゾピクロン、レボドパ・カルビドパ配合剤の6種類を内服しており、看護師管理により確実な服薬が確保されている。認知機能障害により自己管理は困難であるが、スタッフによる適切な管理体制が整っている。
身長152cm、体重42kgで、BMIは18.2kg/m2と低体重に分類される。入居前は地域のボランティア活動に参加するなど活動的であったが、現在は歩行時の前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足といったパーキンソン症状により活動量が制限されている。訪問リハビリテーションによる歩行訓練と筋力強化訓練を週2回実施しているが、転倒への恐怖心も強く、自発的な運動は限定的である。
呼吸に関するアレルギーはなく、SpO2は98%と良好である。喫煙歴はなく、飲酒も夫の存命中に少量嗜む程度で、夫の死後は飲酒していない。
疾患や治療への理解については、認知機能の変動により理解度にムラがある。認知機能が良好な時には「ここは自分の家じゃないけど、みんな優しくしてくれるからありがたい」とホームでの生活を受け入れる発言がみられるが、認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」と見当識障害を示す発言もある。自身の病状や服薬の必要性について十分な理解を得ることは困難な状態である。
課題
認知機能の変動により疾患や治療への理解が不安定であり、自己管理能力が低下している。MMSE 18点、HDS-R 16点という中等度の認知障害に加え、日内変動が著しいため、午前中と午後から夕方にかけての理解度に差がみられる。このため自身の病状認識が曖昧であり、服薬の必要性や治療の意義を十分に理解できていない。また幻視が出現した際には恐怖心から興奮し、「知らない人が窓の外から覗いている」などと訴えることから、現実と幻視の区別がつかず精神的な不安定さが増している。
パーキンソン症状の進行により活動量が低下し、転倒リスクが高い状態にある。前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足といった症状により歩行の安定性が損なわれており、杖と見守りがあっても転倒の危険性は高い。実際に入居後2回の転倒歴があり、いずれも夜間のトイレ移動時であったことから、夜間の転倒リスクが特に高いと考えられる。転倒経験により本人の恐怖心が強くなり、活動への意欲が低下していることも、筋力低下や廃用症候群のリスクを高める要因となっている。レボドパ・カルビドパ配合剤を内服しているものの、症状の完全なコントロールには至っていない。
食欲低下と体重減少により低栄養状態と軽度の貧血が生じており、さらなる健康状態の悪化が懸念される。入居時45kgから現在42kgへと3kgの体重減少があり、BMI 18.2kg/m2と低体重である。Alb 3.4g/dLと基準値を下回っており、蛋白質の摂取不足が示唆される。Hb 11.5g/dL、RBC 380万/μLと軽度の貧血も認められ、これらは免疫機能の低下や創傷治癒の遅延、さらなる筋力低下につながる可能性がある。食事摂取量が5割から8割と日によって変動し、認知機能が低下している時には食事に集中できないことが低栄養の主な原因と考えられる。また夏季の気温上昇も食欲低下に影響している可能性がある。
看護の方向性
認知機能の変動を考慮し、服薬管理は引き続き看護師管理を継続し、毎食後と就寝前の配薬時に確実な内服確認を行う。本人の理解度に応じて、認知機能が比較的良好な午前中に、わかりやすく具体的な言葉で服薬の必要性や効果について説明を行う。一度に多くの情報を伝えることは避け、短い言葉で繰り返し説明することで理解を促す。幻視が出現した際には否定せず、本人の不安や恐怖心を受け止めた上で、「ここは安全な場所です」「スタッフがそばにいます」と安心感を与える声かけを行う。環境調整として照明を適切に保ち、幻視を誘発する要因を減らすよう配慮する。
転倒予防のため、歩行時は必ず付き添いを行い、本人のペースに合わせてゆっくりと移動する。環境整備として居室内の動線を確保し、つまずきの原因となる物品を除去する。夜間は足元灯を設置し、視認性を高める。訪問リハビリテーションと密に連携し、歩行訓練と筋力強化訓練を週2回継続するとともに、訓練の効果や症状の変化について情報共有を行う。転倒への恐怖心を軽減するため、「スタッフが一緒にいるから大丈夫」「ゆっくりで良いですよ」といった肯定的な声かけを行い、小さな成功体験を積み重ねることで自信を回復させる。夜間のトイレ誘導を徹底し、定時での誘導とナースコールの使用を促すことで、一人での移動を避ける。レボドパ・カルビドパ配合剤の効果について嘱託医と情報共有し、必要に応じて用量調整の検討を依頼する。転倒リスクアセスメントを定期的に実施し、リスクの変化を継続的に評価する。
栄養状態の改善に向けて、食事摂取量を毎食詳細に記録し、摂取量が少ない日のパターンや要因を分析する。摂取量が5割以下の場合は、栄養補助食品の提供や嗜好に合わせた食事内容の調整を行う。認知機能が比較的良好な午前中や午後早い時間に食事を提供し、食事に集中できる静かな環境を整える。食事介助時には声かけや促しを行い、食べることへの注意を向けさせる。嘱託医と連携し、貧血の原因について鉄欠乏性貧血や慢性疾患に伴う貧血などの鑑別を行い、必要に応じて鉄剤投与などの治療を検討する。体重測定を週1回実施し、体重の推移を観察するとともに、継続的な体重減少がみられる場合は速やかに嘱託医に報告する。また家族と協力し、本人の嗜好する食品や以前よく食べていた食事について情報を収集し、食欲を刺激する工夫を行う。水分摂取量も併せて観察し、脱水予防にも努める。
現在のアセスメント
A氏の食事は常食で一口大に調理されたものが提供されており、自力摂取が可能である。しかし認知機能の変動により食事への集中力が低下し、摂取量は5割から8割と日によって変動が大きい。特に認知機能が低下する午後から夕方にかけては食事に集中できず、摂取量が減少する傾向がある。水分摂取については具体的な量の記載はないが、食事摂取量の変動から水分摂取も不安定である可能性が考えられる。好きな食べ物や食事に関するアレルギーについての情報は得られていない。
身長152cm、体重42kgで、BMIは18.2kg/m2と低体重に分類される。入居時45kgから3kgの体重減少がみられており、栄養状態の悪化が進行している。基礎代謝量は約900kcal程度と推定され、身体活動レベルは低下しているものの、1日の必要エネルギー量は1200から1400kcal程度と考えられる。現在の食事摂取量が5割から8割であることから、必要栄養量を十分に満たせていない可能性が高い。
食欲は8月に入り気温の上昇とともに低下している。嚥下機能は概ね良好であるが、注意が散漫になるとむせが生じることがあり、誤嚥のリスクが存在する。口腔内の状態については具体的な記載がないため、口腔衛生状態や歯牙の状態について情報収集が必要である。嘔吐や吐気の訴えは現時点ではみられていない。
皮膚の状態については具体的な記載がないが、低栄養状態により皮膚の脆弱性が増している可能性がある。褥瘡の有無についても明確な情報がないため、観察と評価が必要である。活動量の低下と体重減少により褥瘡発生のリスクは高まっていると考えられる。
血液データではAlb 3.4g/dL、TP 6.5g/dLと蛋白質栄養状態の低下を示している。Albは基準値4.1から5.1g/dLを下回っており、蛋白質の摂取不足または消費亢進が示唆される。RBC 380万/μL、Hb 11.5g/dL、Ht 35.2%と軽度の貧血がみられ、鉄欠乏性貧血や慢性疾患に伴う貧血の可能性がある。電解質ではNa 138mEq/L、K 4.0mEq/Lと基準値内であるが、Naは基準値下限に近く、水分バランスや食事摂取量との関連について注意が必要である。脂質代謝ではTG 110mg/dL、TC 185mg/dLと基準値内であり、ロスバスタチンカルシウムによる治療効果が得られている。HbA1c 5.7%、血糖102mg/dLと耐糖能は良好である。
課題
認知機能の変動により食事摂取量が不安定であり、1日の必要栄養量を満たせていないことから、低栄養状態が進行している。Alb 3.4g/dL、TP 6.5g/dLという低値は免疫機能の低下や創傷治癒の遅延、筋肉量の減少につながり、さらなる活動量の低下や感染リスクの上昇を招く可能性がある。入居時から3kgの体重減少があり、BMI 18.2kg/m2という低体重は転倒時の骨折リスクや褥瘡発生リスクを高める要因となっている。
注意が散漫になると嚥下時にむせが生じることから、誤嚥性肺炎のリスクが存在する。認知機能の変動により食事中の注意力が低下しやすく、特に午後以降は誤嚥のリスクが高まると考えられる。
軽度の貧血があり、Hb 11.5g/dLという値は易疲労感や活動耐性の低下を引き起こし、ADLのさらなる低下につながる可能性がある。貧血の原因が不明確であり、鉄欠乏性貧血や慢性疾患に伴う貧血などの鑑別が必要である。
看護の方向性
食事摂取量を毎食詳細に記録し、5割以下の場合は栄養補助食品の提供を行う。認知機能が比較的良好な午前中に主たる栄養摂取ができるよう、朝食と昼食の栄養配分を調整することを検討する。食事時は静かな環境を整え、テレビや音楽などの刺激を最小限にし、食事に集中できるよう配慮する。食事介助時には声かけや促しを行い、「今はご飯の時間ですよ」「一口ずつゆっくり食べましょう」といった具体的な指示を出すことで、食事行動を導く。本人の嗜好について家族から情報を収集し、好きな食べ物を取り入れることで食欲を刺激する工夫を行う。
嚥下機能については毎食観察を継続し、むせの頻度や状況を記録する。食事前に嚥下体操や発声練習を行い、嚥下機能の維持を図る。食事中は姿勢を整え、顎を引いた姿勢で摂取できるよう見守りと声かけを行う。むせが頻繁にみられる場合は、食事形態をより嚥下しやすいものに変更することを嘱託医や管理栄養士と検討する。水分摂取時にはとろみ剤の使用も検討する。
体重測定を週1回実施し、体重の推移をモニタリングする。継続的な体重減少がみられる場合は速やかに嘱託医に報告し、栄養補助食品の追加や栄養剤の投与について検討を依頼する。血液データについては月1回程度の定期的な評価を行い、Alb、TP、Hb、RBCなどの栄養指標と貧血指標の推移を観察する。
貧血の原因精査のため、嘱託医に鉄代謝検査や便潜血検査などの追加検査を依頼する。鉄欠乏性貧血が確認された場合は鉄剤の投与を検討し、慢性疾患に伴う貧血の場合は原疾患の管理を強化する。食事内容では鉄分を多く含む食品の提供を心がける。
口腔内の状態について歯科衛生士による評価を依頼し、口腔ケアを徹底する。毎食後の口腔ケアを実施し、義歯の有無や歯牙の状態、口腔粘膜の状態を観察する。口腔内の問題が食事摂取に影響している場合は、歯科受診を検討する。
皮膚の状態を全身観察し、特に骨突出部の発赤や褥瘡の有無を確認する。褥瘡予防のため体位変換を定期的に行い、除圧マットレスの使用を検討する。皮膚の保湿ケアを行い、皮膚の脆弱性を軽減する。
現在のアセスメント
A氏の排尿は日中トイレ誘導により可能であるが、尿意の訴えが曖昧なため定時誘導を実施している。夜間はリハビリパンツとパッドを使用しており、1回程度の交換が必要である。排尿回数や1回排尿量についての具体的な記載はないが、夜間1回の交換が必要ということから、夜間排尿が1回以上あると推測される。尿失禁の頻度や尿の性状についても明確な情報がなく、観察が必要である。
排便は3日に1回程度と便秘傾向が続いている。入居前は2日に1回程度であったことから、入居後に便秘が悪化している。便の性状についての記載はないが、便秘傾向があることから硬便である可能性が高い。酸化マグネシウム330mgを1日3回毎食後に内服しているが、それでも3日に1回の排便ペースとなっており、下剤の効果が十分ではない。排便がない場合は浣腸を施行することがあるが、浣腸の頻度については明記されていない。
in-outバランスについては具体的な記録がなく、水分摂取量と尿量の詳細な把握ができていない。食事摂取量が5割から8割と変動していることから、食事からの水分摂取も不安定であり、水分摂取不足の可能性がある。水分摂取不足は便秘を悪化させる要因となる。
排泄に関連した食事内容では、食物繊維の摂取状況についての情報がない。活動量の低下も腸蠕動を低下させ、便秘を助長する要因となっている。パーキンソン症状により自律神経機能が影響を受け、腸蠕動が低下している可能性も考えられる。安静度については、杖と見守りがあれば歩行可能であるが、活動量は制限されている。バルーンカテーテルは留置されていない。
腹部膨満や腸蠕動音についての記載はなく、腹部の観察と評価が必要である。便秘が続いている場合、腹部膨満や腸蠕動音の減弱がみられる可能性がある。
血液データではBUN 20mg/dLと基準値上限であり、脱水や腎機能の軽度低下の可能性を示唆している。Cr 0.72mg/dLは基準値内であるが、高齢女性で筋肉量が少ないことを考慮すると、実際の腎機能は軽度低下している可能性がある。GFRの記載はないが、年齢と性別、Cr値から推定GFRを計算すると60mL/min/1.73m2前後と考えられ、軽度の腎機能低下が示唆される。
課題
便秘が慢性化しており、排便が3日に1回程度と排便コントロールが不良である。酸化マグネシウムを1日3回内服しているにもかかわらず効果が十分でなく、浣腸を必要とすることもある。便秘の長期化は腹部膨満や食欲不振、イレウスのリスクを高め、QOLの低下につながる。活動量の低下、水分摂取不足、パーキンソン症状による腸蠕動の低下が便秘を助長している。
尿意の訴えが曖昧であり、定時誘導が必要な状態である。認知機能の変動により尿意を適切に感じ取れない、または訴えることができない可能性がある。夜間は尿失禁がみられ、リハビリパンツとパッドを使用しているが、尿失禁により皮膚トラブルや尿路感染症のリスクが高まる。また尿失禁は本人の自尊心を傷つける可能性もある。
BUN 20mg/dLと基準値上限であり、脱水傾向の可能性がある。水分摂取量の詳細な把握ができておらず、食事摂取量の変動から水分摂取も不安定であると推測される。脱水は便秘をさらに悪化させ、腎機能の低下や転倒リスクの増加、認知機能の悪化にもつながる可能性がある。
看護の方向性
排便状況を詳細に記録し、排便の回数、量、性状、排便時の状態を観察する。腹部の観察を毎日実施し、腹部膨満の有無、腸蠕動音の聴取、腹部の圧痛の有無を確認する。排便が3日以上ない場合は腹部の状態を詳細に評価し、必要に応じて嘱託医に報告する。
便秘の改善に向けて、水分摂取量を増やす取り組みを行う。1日の水分摂取目標を1000から1500mL程度に設定し、食事時以外にも定期的に水分を提供する。本人の嗜好に合わせた飲み物を用意し、飲水を促す。食事内容では食物繊維を多く含む食品の提供を管理栄養士と相談し、便秘改善に効果的な食事内容を検討する。
活動量を増やすため、日中のレクリエーションや散歩を促し、腸蠕動を刺激する。訪問リハビリテーションと連携し、腸蠕動を促進する運動や腹部マッサージを取り入れる。可能であれば食後の軽い運動を習慣化する。
酸化マグネシウムの効果が不十分であるため、嘱託医に下剤の種類や用量の見直しを相談する。刺激性下剤の追加や整腸剤の併用、酸化マグネシウムの増量などを検討する。浣腸の使用頻度を記録し、頻回に浣腸が必要な場合は排便コントロールの方法を見直す。
排尿については定時誘導を継続し、2から3時間ごとにトイレ誘導を行う。排尿パターンを把握するため、排尿時刻と量を記録し、適切な誘導間隔を設定する。夜間は就寝前と夜間1回のトイレ誘導を行い、尿失禁の軽減を図る。リハビリパンツとパッドの使用は継続するが、皮膚の状態を毎日観察し、陰部の清潔保持を徹底する。尿失禁後は速やかに交換し、陰部洗浄を行う。
水分摂取量と尿量を記録し、in-outバランスを把握する。BUN、Crを定期的に測定し、脱水や腎機能の変化をモニタリングする。BUNが上昇傾向にある場合は脱水の可能性を考慮し、水分摂取の強化や点滴による補液を嘱託医と検討する。
尿路感染症の予防のため、陰部の清潔保持を徹底し、定期的な尿検査を実施する。尿混濁や尿臭の変化、発熱などの感染兆候がみられた場合は速やかに嘱託医に報告する。
現在のアセスメント
A氏のADL状況は、歩行は杖と見守りがあれば可能であるが、前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足といったパーキンソン症状により歩行の安定性が大きく損なわれている。移乗は見守りがあれば可能だが、動作が緩慢で時間がかかる。排尿と排便は日中トイレ誘導により可能であるが、自立はしていない。入浴は週2回の介助浴を実施しており、洗身や洗髪は介助が必要である。衣類の着脱は声かけと見守りがあれば可能だが、ボタンの留め外しに時間がかかり、巧緻動作の低下がみられる。全体として部分介助から介助が必要なレベルであり、日常生活動作の自立度は低下している。
運動機能については、レビー小体型認知症に伴うパーキンソン症状により、筋強剛、動作緩慢、姿勢反射障害が生じている。レボドパ・カルビドパ配合剤100mgを1日3回内服しているが、症状のコントロールは不十分である。7月以降、表情が乏しくなり動作緩慢が進行していることから、パーキンソン症状が徐々に悪化していると考えられる。入居前は地域の読み聞かせボランティアに参加するなど活動的であったが、現在は活動量が著しく制限されている。訪問リハビリテーションによる歩行訓練と筋力強化訓練を週2回実施しているが、転倒への恐怖心が強く、自発的な活動意欲は低下している。
安静度については特に制限はないが、転倒リスクが高いため移動時は必ず付き添いが必要である。移動と移乗方法は前述の通り、杖と見守りによる歩行、見守りでの移乗となっている。
バイタルサインは血圧138/82mmHg、脈拍74回/分・整、呼吸数16回/分、体温36.6℃、SpO2 98%と安定している。高血圧症の既往があるが、アムロジピンベシル酸塩5mgの内服により血圧は良好にコントロールされている。呼吸機能については具体的な検査データはないが、SpO2 98%と良好であり、呼吸困難の訴えもない。
職業は元小学校教師として38年間勤務しており、立ち仕事や児童への対応など、身体的にも精神的にも活動的な職業であった。住居環境については、現在は有料老人ホームの個室に入居しており、居室内の動線は確保されている。自宅での生活環境についての詳細は不明である。
血液データではRBC 380万/μL、Hb 11.5g/dL、Ht 35.2%と軽度の貧血がみられ、易疲労感や活動耐性の低下につながっている可能性がある。CRPの記載はないが、現時点で発熱や感染徴候がないことから、炎症反応は上昇していないと推測される。
転倒転落のリスクは極めて高い。入居後すでに2回の転倒歴があり、いずれも夜間のトイレ移動時であった。パーキンソン症状による歩行障害、認知機能の変動、夜間の幻視による不穏、環境認識の低下などが複合的に転倒リスクを高めている。転倒後は大きな外傷はなかったものの、転倒への恐怖心が強くなり、活動意欲がさらに低下している。
課題
パーキンソン症状の進行により運動機能が低下しており、ADLの自立度が低下している。前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足、動作緩慢、巧緻動作の低下などにより、日常生活動作全般に介助が必要となっている。レボドパ・カルビドパ配合剤の効果が不十分であり、症状のコントロールが困難である。今後さらに症状が進行する可能性があり、ADLの低下と介護負担の増加が予測される。
転倒転落のリスクが極めて高く、すでに入居後2回の転倒を経験している。パーキンソン症状による歩行障害、認知機能の変動、夜間の幻視、転倒への恐怖心などが複合的にリスクを高めている。転倒による骨折や頭部外傷は、生命予後やQOLに重大な影響を及ぼす可能性がある。特に夜間のトイレ移動時のリスクが高い。
活動量の低下により筋力低下と廃用症候群のリスクが高まっている。転倒への恐怖心から自発的な活動が減少し、さらなる筋力低下と活動耐性の低下を招く悪循環に陥っている。低栄養状態と軽度の貧血も活動耐性の低下に影響している。活動量の低下は便秘の悪化、褥瘡リスクの上昇、認知機能のさらなる低下にもつながる。
看護の方向性
転倒予防を最優先課題とし、多面的なアプローチを実施する。歩行時は必ず付き添いを行い、本人のペースに合わせてゆっくりと移動する。「ゆっくりで大丈夫ですよ」「一緒に歩きましょう」といった声かけを行い、焦りや不安を軽減する。すくみ足が出現した場合は、床に目印をつける、リズムをとる、一歩の大きさを指示するなどの工夫を行う。
環境整備として、居室内の動線を確保し、つまずきの原因となる物品を除去する。夜間は足元灯を設置し、視認性を高める。トイレまでの経路にも照明を確保し、手すりの位置を確認する。ベッドの高さを調整し、立ち上がりやすい高さに設定する。
夜間のトイレ誘導を徹底し、就寝前と夜間1回程度の定時誘導を実施する。ナースコールの使用方法を繰り返し説明し、一人で移動しないよう促す。ポータブルトイレの使用も検討するが、移乗時の転倒リスクとのバランスを評価する。
訪問リハビリテーションと密に連携し、歩行訓練と筋力強化訓練の効果を評価する。週2回の訓練を継続し、必要に応じて頻度の増加を検討する。リハビリテーションの内容や進捗状況について情報共有を行い、訓練で獲得した動作を日常生活に取り入れる。理学療法士から転倒予防に効果的な運動や歩行のポイントについて指導を受け、日常のケアに活かす。
転倒への恐怖心を軽減するため、小さな成功体験を積み重ねる。「今日は上手に歩けましたね」「昨日より歩くのが安定していますね」といった肯定的なフィードバックを行い、自信を回復させる。転倒予防の取り組みについて本人に説明し、可能な範囲で協力を求める。
パーキンソン症状のコントロールについて嘱託医と相談し、レボドパ・カルビドパ配合剤の用量調整や他の薬剤の追加を検討する。薬剤の効果と副作用を観察し、症状の変化を詳細に記録する。パーキンソン症状の日内変動についても観察し、症状が軽減する時間帯に活動やリハビリテーションを実施する。
活動量を増やすため、日中のレクリエーションプログラムへの参加を促す。本人が以前楽しんでいた読み聞かせや読書などの活動を取り入れ、興味関心を刺激する。座位でできる運動や作業を提供し、無理のない範囲で活動を継続する。
ADLの評価を定期的に実施し、能力の変化を把握する。できることは見守りのもと本人に実施してもらい、過介助にならないよう注意する。動作に時間がかかっても待つ姿勢を持ち、本人のペースを尊重する。しかし転倒リスクが高い動作については安全を最優先し、適切な介助を行う。
貧血の改善により活動耐性の向上を図る。栄養状態の改善と貧血治療を並行して進め、Hb値の上昇をモニタリングする。活動後の疲労感や息切れの有無を観察し、活動量を調整する。
現在のアセスメント
A氏の睡眠時間は21時頃就寝、6時頃起床と、約9時間の睡眠時間が確保されており、睡眠リズムは徐々に確立されつつある。入居当初は環境の変化により睡眠リズムが不安定であったが、入居から4ヶ月が経過し、生活リズムは整いつつある。しかし夜間に2から3回覚醒することがあり、中途覚醒が頻繁にみられている。覚醒時には幻視により「知らない人が窓の外から覗いている」「部屋に子どもがいる」などと訴え、恐怖心から不穏状態となることがある。このため夜間の睡眠の質は低く、熟眠感は得られていないと推測される。
入居前は22時頃就寝していたが、夜中に何度も目を覚まし、幻視により「誰かいる」と長女を起こすことが頻繁にあった。入居後は就寝時刻が1時間早まり、生活リズムの改善がみられているが、夜間覚醒と幻視による不穏は継続している。
睡眠導入剤としてエスゾピクロン2mgを就寝前に内服しているが、効果は限定的である。入眠は比較的スムーズであると推測されるが、中途覚醒の改善には至っていない。エスゾピクロンは非ベンゾジアゼピン系睡眠薬であり、高齢者にも比較的安全に使用できるが、A氏の場合は十分な効果が得られていない状況である。
日中の過ごし方については、日中の傾眠も時々みられる。これは夜間の睡眠の質が低く、十分な休息が得られていないことの現れと考えられる。日中傾眠があることで、夜間の睡眠がさらに浅くなるという悪循環に陥っている可能性がある。ホーム内で実施される個別のレクリエーションプログラムに参加しているが、認知機能の変動により参加状況にムラがあると推測される。活動量が低下していることも、適度な疲労感が得られず、夜間の睡眠の質に影響している可能性がある。
休日の過ごし方については特に記載がないが、有料老人ホームでの生活であり、平日と休日の区別は明確ではないと考えられる。家族の面会は長女が週3回、長男が月1回程度あり、面会時には表情が明るくなることから、家族との交流が精神的な安定と休息につながっている。
課題
夜間の睡眠の質が低く、中途覚醒が2から3回あり、熟眠感が得られていない。幻視により恐怖心から不穏状態となることがあり、これが睡眠を妨げる主要な要因となっている。レビー小体型認知症の特徴的な症状である幻視は、特に夜間の暗い環境で出現しやすく、本人に強い不安と恐怖をもたらしている。睡眠不足は日中の認知機能の低下、転倒リスクの増加、免疫機能の低下などを引き起こし、全体的な健康状態の悪化につながる。
エスゾピクロン2mgの内服にもかかわらず、中途覚醒の改善が得られていない。睡眠薬の効果が不十分であり、用量調整や他の薬剤への変更が必要である可能性がある。しかしレビー小体型認知症では、抗精神病薬や一部の睡眠薬によりパーキンソン症状が悪化するリスクがあるため、薬剤選択には慎重な判断が必要である。
日中の傾眠がみられ、夜間の睡眠不足と日中の活動量低下により、昼夜逆転のリスクがある。日中傾眠により夜間の睡眠がさらに浅くなるという悪循環に陥っている可能性がある。適度な日中の活動と覚醒が不足しており、睡眠覚醒リズムの乱れが生じている。
看護の方向性
夜間の睡眠環境を整備し、幻視の出現を最小限に抑える工夫を行う。居室内の照明を適度に保ち、完全な暗闇を避ける。足元灯やナイトライトを使用し、目が覚めた時にも見当識を保ちやすい環境を作る。窓にカーテンをしっかりと閉め、外からの光や影が幻視を誘発しないよう配慮する。居室内の物品配置を整理し、影ができにくいようにする。
夜間の巡視を定期的に実施し、覚醒時には速やかに訪室して不安を軽減する。幻視が出現した際には、否定せず「怖かったですね」「大丈夫ですよ」と本人の気持ちを受け止める。「ここは安全な場所です」「スタッフがすぐそばにいます」と安心感を与える言葉かけを行う。必要に応じて一緒に居室内を確認し、「誰もいませんね」と現実を穏やかに伝える。背中をさするなどの身体接触により、安心感を提供する。
就寝前のルーティンを確立し、入眠を促す。就寝前に温かい飲み物を提供する、リラックスできる音楽を流す、軽いマッサージを行うなど、本人が落ち着ける方法を見つける。就寝時刻を一定にし、生活リズムを整える。
エスゾピクロンの効果が不十分であることを嘱託医に報告し、用量調整や薬剤変更について相談する。レビー小体型認知症では薬剤選択が重要であり、パーキンソン症状を悪化させない薬剤の選択が必要である。メラトニン受容体作動薬や他の睡眠薬の使用について検討する。幻視に対する薬物療法として、抗精神病薬の少量投与も検討されているが、パーキンソン症状の悪化に注意しながら慎重に判断する。
日中の活動量を増やし、適度な疲労感を得ることで夜間の睡眠の質を向上させる。午前中から午後早い時間にかけて、レクリエーションプログラムへの参加を促す。散歩や体操など、身体を動かす活動を取り入れる。訪問リハビリテーションの時間を午前中に設定し、日中の覚醒レベルを高める。
日中の傾眠を最小限にするため、傾眠がみられた際には声かけや軽い活動への誘導を行う。午後の仮眠は30分以内に制限し、長時間の昼寝を避ける。日中は居室ではなく、共有スペースで過ごす時間を増やし、覚醒レベルを維持する。
睡眠状況を詳細に記録し、就寝時刻、覚醒回数と時刻、覚醒時の状況、幻視の有無、日中の傾眠の時間と頻度を記録する。睡眠パターンを分析し、より効果的な介入方法を検討する。睡眠の質の改善がみられない場合は、睡眠専門医への相談も検討する。
現在のアセスメント
A氏の意識レベルは清明であるが、認知機能は中等度に障害されており、MMSE 18点、HDS-R 16点という結果が示されている。レビー小体型認知症の特徴的な症状として、認知機能の著しい日内変動がみられる。午前中は比較的会話が成立し、昔の教師時代の話を楽しそうに語ることができるが、午後から夕方にかけては見当識障害が強くなり、話の内容が支離滅裂になったり、同じことを繰り返し尋ねることがある。この変動性は時間帯だけでなく、日によっても差があり、認知機能が良好な日と低下している日がある。
見当識については、認知機能が良好な時には人物や場所の見当識はある程度保たれているが、時間の見当識は不確かである。認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」「娘はどこにいるの」という発言がみられ、場所や状況の理解が困難になっている。記銘力と記憶力は低下しており、最近の出来事を忘れやすく、食べたことを忘れて何度も食事を求めることが以前はあった。
幻視はレビー小体型認知症の中核症状の一つであり、A氏にも頻繁に出現している。特に夜間に「知らない人が窓の外から覗いている」「部屋に子どもがいる」という具体的で生々しい幻視を訴える。入居当初は「知らない人が部屋にいる」という訴えが頻繁にみられ、不穏状態となることがあった。幻視は本人にとって現実と区別がつかず、強い恐怖心や不安をもたらしている。照明の調整や環境整備により幻視の頻度は減少しているが、完全には消失していない。
聴力は軽度の難聴があるが、補聴器は使用していない。ゆっくりとした会話であれば理解可能であり、大きな声で話しかける必要はない。騒がしい環境では聞き取りにくさが増すと推測される。難聴により会話が十分に理解できない場合、孤立感や不安が増す可能性がある。
視力は加齢による視力低下があり、眼鏡を使用している。眼鏡使用により日常生活に必要な視力は確保されていると考えられる。しかし幻視の存在により、実際に見えているものと幻視の区別が困難になっている。視力低下と幻視が相互に影響し、環境認識を困難にしている可能性がある。
不安は強く、特に認知機能が低下している時や幻視が出現した時に顕著である。「いつ家に帰れるの」という発言には、現在の状況への不安や戸惑いが表れている。夜間の幻視により恐怖心から興奮することもある。表情については、7月以降パーキンソン症状の進行により表情が乏しくなっている。仮面様顔貌がみられ、感情表現が読み取りにくくなっている。しかし長女の面会時には表情が明るくなることから、感情そのものは保たれており、表情筋の動きが制限されていると考えられる。
疼痛については特に訴えがなく、変形性膝関節症による膝の痛みも現時点では問題となっていない。しかし認知機能障害により疼痛を適切に訴えられない可能性があり、観察が必要である。
課題
認知機能の著しい日内変動により、ケアの提供が困難な時間帯がある。午前中は比較的コミュニケーションが可能であるが、午後から夕方にかけては理解力や判断力が低下し、指示が伝わりにくくなる。この変動により、食事摂取量の変動、転倒リスクの増加、服薬管理の困難さなど、様々な問題が生じている。認知機能の予測が難しく、その時々の状態に応じた柔軟な対応が求められる。
幻視が頻繁に出現し、特に夜間に本人に強い恐怖心と不安をもたらしている。幻視は本人にとって現実と区別がつかず、「知らない人が窓の外から覗いている」という訴えは本人にとって真実である。幻視により不穏状態となり、睡眠が妨げられ、QOLが著しく低下している。幻視への対応が不適切な場合、本人の不安や恐怖がさらに増強される可能性がある。
見当識障害により、現在の状況や場所の理解が困難になっている。「いつ家に帰れるの」という発言は、ホームを自分の居場所として認識できていないことを示している。見当識障害は不安や焦燥感を引き起こし、精神的な安定を損なっている。
軽度の難聴があり、コミュニケーションが十分に取れない可能性がある。認知機能障害と難聴が重なることで、コミュニケーション障害がさらに増強され、孤立感や疎外感が生じる可能性がある。補聴器の使用については検討されていないが、認知機能障害があるため、補聴器の管理が困難である可能性もある。
表情が乏しくなり、感情表現が読み取りにくくなっている。仮面様顔貌により、本人の気持ちや不快感を表情から判断することが困難である。疼痛や不調があっても表情に表れにくく、訴えも曖昧である可能性があるため、見逃しのリスクがある。
看護の方向性
認知機能の日内変動を考慮し、重要なケアや説明は午前中の認知機能が比較的良好な時間帯に実施する。服薬の説明、治療方針の説明、意思確認などは午前中に行う。午後から夕方にかけては無理に複雑な指示を出さず、シンプルで具体的な言葉かけを心がける。認知機能の状態を毎日観察し、その日の状態に応じてケアの方法を調整する。
幻視への対応として、まず幻視を否定せず、本人の気持ちを受け止める。「怖かったですね」「不安でしたね」と共感を示す。その上で「ここは安全な場所です」「スタッフがそばにいます」と安心感を与える。必要に応じて一緒に居室内を確認し、「誰もいませんね」と穏やかに現実を伝える。幻視の出現パターンを記録し、出現しやすい時間帯や状況を把握する。環境調整として、照明を適切に保ち、影ができにくい環境を作る。幻視が頻繁で本人の苦痛が強い場合は、嘱託医と相談し、薬物療法の調整を検討する。
見当識を補うため、カレンダーや時計を見やすい位置に設置する。日課を視覚的に示すスケジュール表を作成し、見当識の維持を支援する。しかし無理に現実を押し付けず、「いつ家に帰れるの」という発言には「今日はここでゆっくり休みましょう」と穏やかに対応する。ホームを安心できる場所として認識できるよう、馴染みのある物品を居室に配置したり、写真を飾るなどの工夫を行う。
コミュニケーションの工夫として、ゆっくりと明瞭に話しかけ、一度に多くの情報を伝えない。短い文章で具体的に伝え、理解を確認しながら会話を進める。静かな環境で会話を行い、騒音を最小限にする。必要に応じて筆談やジェスチャーを併用する。補聴器の使用については、本人と家族の意向を確認し、導入が可能か検討する。しかし認知機能障害により補聴器の管理が困難な場合は、スタッフによる管理体制を整える。
表情が乏しくなっているため、表情以外の観察ポイントを重視する。身体の動き、声のトーン、呼吸パターン、発汗、顔色などから、不快感や疼痛の有無を推測する。定期的に「どこか痛いところはありませんか」「体調はいかがですか」と具体的に尋ね、言語的な訴えを引き出す。変形性膝関節症による膝の痛みについても定期的に確認し、疼痛がある場合は鎮痛薬の使用を嘱託医と相談する。
認知機能の評価を定期的に実施し、MMSEやHDS-Rを3から6ヶ月ごとに測定する。認知機能の変化を把握し、ケアの方法を適宜調整する。ドネペジル塩酸塩5mgの効果についても評価し、認知機能の著しい低下がみられる場合は、用量調整や他の治療法について嘱託医と相談する。
家族との情報共有を密にし、本人の認知機能の状態や幻視の出現状況について説明する。家族の面会時には、本人の認知機能が良好な状態で会えるよう、面会時間を午前中に調整することを提案する。家族にも幻視への対応方法を伝え、一貫したケアを提供する。
現在のアセスメント
A氏の性格は几帳面で真面目、人との交流を好む社交的な面があったとされている。小学校教師として38年間勤務した経歴から、責任感が強く、きちんとした生活習慣を重視する性格であったと推測される。退職後も地域の読み聞かせボランティアに参加していたことから、人の役に立つことに喜びを感じ、社会とのつながりを大切にしていた人物像が浮かぶ。しかし現在は不安が強くなる傾向があり、認知機能の低下やパーキンソン症状の進行により、以前の自分らしさを保つことが困難になっている。
ボディイメージについては、体重が入居時45kgから42kgへ減少し、BMI 18.2kg/m2と痩せている。パーキンソン症状により前傾姿勢、小刻み歩行、動作緩慢、表情の乏しさがみられ、身体の動きが以前とは大きく変化している。歩行には杖と見守りが必要であり、入浴や衣類の着脱にも介助が必要となっている。元々活動的であった自分と、現在の介助を必要とする自分との間にギャップを感じている可能性がある。夜間はリハビリパンツとパッドを使用しており、尿失禁があることで自尊心が傷ついている可能性がある。
疾患に対する認識は、認知機能の変動により不安定である。認知機能が良好な時には「ここは自分の家じゃないけど、みんな優しくしてくれるからありがたい」とホームでの生活を受け入れている様子を見せるが、認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」と訴え、現在の状況を十分に理解できていない。自身がレビー小体型認知症であることや、進行性の疾患であることについての理解は限定的であると考えられる。幻視については本人にとって現実と区別がつかず、「知らない人が窓の外から覗いている」という体験は、本人にとって恐怖そのものである。
自尊感情については、元小学校教師として長年社会に貢献してきた誇りがあったと推測される。しかし現在は日常生活動作の多くに介助が必要となり、自分でできることが減少している。転倒への恐怖心が強くなっており、転倒経験により自信を喪失している可能性がある。尿失禁や便秘、食事介助の必要性など、身体機能の低下により、自尊感情が低下している可能性がある。しかし長女の面会時には「あなたが来てくれると安心する」と喜びを示すことから、家族との絆が自尊感情を支える重要な要素となっている。
育った文化については詳細な情報はないが、昭和18年頃の生まれであり、戦後の教育を受けて教師となった世代である。教師として児童の教育に尽力し、地域社会に貢献してきた背景がある。几帳面で真面目という性格は、この世代の教師に求められた価値観を反映している可能性がある。周囲の期待としては、教師として地域から尊敬され、退職後もボランティア活動を通じて社会貢献を続けることが期待されていたと考えられる。しかし現在は認知症により以前のような役割を果たせず、周囲の期待に応えられない自分への葛藤がある可能性がある。
課題
身体機能の低下とADLの低下により、自己効力感と自尊感情が低下している可能性がある。元々活動的で社会的な役割を持っていたA氏にとって、現在の介助を必要とする状態は、アイデンティティの喪失につながっている可能性がある。特に教師として長年社会に貢献してきた誇りがある中で、現在の自分の状態を受け入れることは困難であると推測される。転倒への恐怖心、尿失禁、食事や入浴の介助など、日常生活の様々な場面で自立性が損なわれており、自尊感情の低下が懸念される。
認知機能の変動により、疾患に対する認識が不安定であり、現在の状況を十分に理解できていない。「いつ家に帰れるの」という発言は、ホームを自分の居場所として受け入れられていないことを示している。自分の状況が理解できないことは、不安や混乱を増強させ、精神的な苦痛をもたらしている。
幻視により、現実と幻覚の区別がつかず、自己の認知や判断に対する信頼が損なわれている可能性がある。「知らない人が窓の外から覗いている」という体験は、本人にとって現実であり、自分の認識を信じられなくなることは、自己概念の混乱につながる。
ボディイメージの変化に対する適応が困難である可能性がある。パーキンソン症状による姿勢や動作の変化、体重減少、表情の乏しさなど、身体的な変化が著しく、以前の自分と現在の自分との乖離が大きい。自分の身体をコントロールできないという感覚は、自己効力感の低下につながる。
看護の方向性
A氏の自尊感情を支えるため、できることを見つけ、それを継続できるよう支援する。元教師であったという経歴を尊重し、「先生」と呼びかけることで、本人のアイデンティティを支える。認知機能が良好な時には、昔の教師時代の話を傾聴し、「たくさんの子どもたちを教えてこられたのですね」「素晴らしいお仕事をされてきたのですね」と肯定的なフィードバックを行う。過去の功績や経験を認め、尊重する姿勢を示す。
日常生活において、本人ができることは見守りのもと自分で行ってもらい、過介助を避ける。衣類の着脱やボタンの留め外しなど、時間がかかっても本人のペースを尊重し、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と声かけを行う。できたことに対しては「ご自分で上手にできましたね」と肯定的に評価し、自己効力感を高める。小さな成功体験を積み重ね、「できる」という感覚を取り戻せるよう支援する。
尿失禁については、本人の自尊心を傷つけないよう配慮する。交換時には「お手洗いに行きましょう」とさりげなく誘導し、「失禁」という言葉は使用しない。陰部の清潔保持を徹底し、不快感を最小限にする。定時誘導により失禁の頻度を減らし、本人の自信を回復させる。
転倒への恐怖心を軽減するため、「スタッフが一緒にいるから大丈夫」「ゆっくりで良いですよ」と安心感を与える声かけを行う。転倒予防の取り組みにより実際に転倒が減少すれば、自信の回復につながる。歩行訓練での進歩を具体的に伝え、「前よりも歩くのが安定してきましたね」と肯定的なフィードバックを行う。
ホームでの生活を自分の居場所として受け入れられるよう、環境を整える。居室に自宅で使用していた馴染みの物品や家族の写真を配置し、安心感を提供する。認知機能が良好な時に「ここはあなたの部屋ですよ」「ここで安心して過ごしていただけます」と繰り返し説明する。しかし「いつ家に帰れるの」という訴えに対しては、無理に現実を押し付けず、「今日はここでゆっくり休みましょう」と穏やかに対応する。
幻視については否定せず、本人の体験を受け止める。「怖かったですね」と共感を示し、「でも今は大丈夫ですよ」「スタッフがそばにいます」と安心感を与える。幻視は病気の症状であることを家族には説明するが、本人には「間違った認識」として指摘せず、不安を軽減することを優先する。
家族との交流を大切にし、面会時間を確保する。長女の面会時には表情が明るくなることから、家族の存在が自尊感情を支える重要な要素となっている。家族との絆を維持し、「娘さんが来てくれて嬉しいですね」と本人の気持ちに寄り添う。家族からも本人の功績や良いところについて話してもらい、本人の自己価値を再確認する機会を作る。
レクリエーションプログラムでは、本人の興味や経験に合わせた活動を取り入れる。読み聞かせや読書など、以前楽しんでいた活動を提供し、「先生が読んでくださると、とても良い声ですね」と肯定的に評価する。他の入居者との交流の場も設け、社交的な面を活かせるよう支援する。
身だしなみを整えることで、自己イメージを維持する。整容や更衣の際には本人の好みを尊重し、「このお洋服、お似合いですね」と肯定的な声かけを行う。鏡を見る機会を提供し、自分の姿を確認できるようにする。しかしパーキンソン症状による表情の変化や体重減少により、自分の姿に戸惑いを感じる可能性もあるため、本人の反応を観察しながら慎重に対応する。
認知機能の低下や身体機能の低下を本人が認識している場合は、その気持ちを受け止める。「できないことが増えて悔しいですね」「不安な気持ちもありますよね」と共感を示し、否定せずに寄り添う。しかし過度に障害を強調せず、できることに焦点を当てる姿勢を保つ。
現在のアセスメント
A氏の職業は元小学校教師であり、38年間という長期にわたり教育現場で児童の指導に携わってきた。教師という職業は社会的に重要な役割であり、A氏にとってもアイデンティティの中核をなすものであったと考えられる。退職後も地域の読み聞かせボランティアに参加していたことから、社会との関わりを持ち続け、何らかの形で人の役に立つことに喜びを感じていた。しかし現在は認知機能の低下とパーキンソン症状の進行により、これらの社会的役割を果たすことができなくなっている。
家族構成は、夫が3年前に他界しており、現在は子どもとの関係が中心となっている。長女が県内に在住しキーパーソンとなっており、週3回程度と頻繁に面会に訪れている。長女は「母には穏やかに過ごしてほしい。転倒だけは本当に心配」と話しており、母親への深い愛情と心配を示している。A氏も長女が面会に来ると表情が明るくなり、「あなたが来てくれると安心する」と喜びを表現している。長女との関係は良好であり、A氏にとって精神的な支えとなっている。
長男は県外在住で、月に1回程度の面会となっている。長男は「姉に負担をかけて申し訳ない。できる限り協力したい」と話しており、姉である長女への配慮と母親への思いを示している。月1回の面会時には母親と散歩をしたり、昔の写真を見ながら思い出話をする時間を大切にしている。長男との関係も良好であり、面会を楽しみにしていると推測される。
家族全体としては、ホームでの看取りも視野に入れており、今後も本人が安心して生活できるよう医療スタッフと連携していきたいと希望している。これは家族が現実的に母親の状態を理解し、長期的な視点で関わろうとしていることを示している。家族の協力体制は良好であり、長女と長男が役割分担をしながら母親を支えている。
夫との関係については、3年前に他界しているが、夫の存命中は晩酌を共にするなど、夫婦の時間を大切にしていた様子がうかがえる。夫の死後は飲酒をしなくなったことから、夫との思い出が深く、喪失感があったと推測される。夫の死が認知症の発症や進行の契機となった可能性もある。
社会的な役割については、現在は有料老人ホームでの生活となっており、かつての教師やボランティアとしての役割は喪失している。ホーム内でのレクリエーションプログラムに参加しているが、認知機能の変動により参加状況にムラがあると推測される。他の入居者との交流についての具体的な記載はないが、元々社交的な性格であったことから、交流の機会があれば喜ぶ可能性がある。
経済状況については具体的な記載はないが、有料老人ホームに入居していることから、一定の経済的基盤があると推測される。教師としての退職金や年金により、経済的な不安は少ないと考えられる。経済的な問題は現時点では明らかではない。
課題
教師やボランティアとしての社会的役割を喪失しており、これがアイデンティティの危機につながっている可能性がある。38年間教師として社会に貢献してきたA氏にとって、現在の何も役割がない状態は、自己価値の低下や生きがいの喪失につながっている可能性がある。元々人との交流を好む社交的な性格であったにもかかわらず、現在はホーム内での限られた交流しかなく、社会的孤立のリスクがある。
長女に介護の負担が集中している可能性がある。週3回の面会は頻繁であり、長女の生活や仕事への影響が懸念される。長男は県外在住のため物理的な距離があり、月1回の面会が精一杯であると推測される。長男は「姉に負担をかけて申し訳ない」と話しており、家族内での役割の偏りを自覚している。長女の介護負担が過重になると、介護疲れや燃え尽きのリスクがあり、家族関係にも影響を及ぼす可能性がある。
夫の死による喪失体験が十分に処理されていない可能性がある。夫の死後3年が経過しているが、認知症の発症と進行により、悲嘆のプロセスが中断されている可能性がある。夫との思い出や喪失感について語る機会が必要かもしれない。
ホーム内での新たな役割や居場所が確立されていない。認知機能の変動や身体機能の低下により、他の入居者との交流が十分にできていない可能性がある。社交的な性格を活かせる場が少なく、孤立感や疎外感を感じている可能性がある。
看護の方向性
A氏が教師としての経験や知識を活かせる場を提供する。レクリエーションプログラムで読み聞かせの時間を設け、他の入居者や訪問する子どもたちに本を読んでもらう機会を作る。認知機能が良好な時間帯を選び、負担にならない範囲で実施する。「先生の読み聞かせは本当に素晴らしいです」と肯定的に評価し、役割を持つことで自己価値を感じられるよう支援する。
他の入居者との交流の機会を増やす。共有スペースでの活動に参加を促し、他者との関わりを持てるよう支援する。元々社交的な性格であったことを活かし、「○○さんと一緒にお茶を飲みませんか」と具体的に提案する。しかし認知機能の変動により疲労しやすいため、短時間の交流から始め、本人の状態に応じて調整する。
家族との面会時間を大切にし、面会しやすい環境を整える。長女の週3回の面会が継続できるよう、面会時間の柔軟な対応を行う。面会時には本人が安定した状態で会えるよう、認知機能が比較的良好な午前中の面会を提案する。面会時にはプライバシーが保たれる場所を提供し、ゆっくりと家族の時間を過ごせるよう配慮する。
長女の介護負担を軽減するため、ホームでのケアの状況を詳細に伝え、安心感を提供する。「お母様は穏やかに過ごされていますよ」「食事もしっかり召し上がっています」と具体的な情報を伝える。長女が面会に来られない日でも、本人の様子を電話やメールで伝え、離れていても母親の状態を把握できるよう支援する。長女の心配事や不安を傾聴し、医療スタッフとして適切な助言を行う。
長男の月1回の面会も大切にし、面会時には本人が喜ぶ活動を提案する。散歩や写真を見ながらの思い出話など、本人と長男が楽しめる時間を過ごせるよう支援する。長男にも母親の状態を定期的に報告し、遠方からでも関わりを持てるよう配慮する。
家族会議の機会を設け、長女と長男が一緒に母親のケアについて話し合える場を提供する。看取りを視野に入れていることから、今後の治療方針や本人の意向について家族で話し合う時間が重要である。嘱託医や看護師も同席し、医療的な観点からの情報提供を行う。家族の負担や役割分担についても話し合い、長女への負担集中を軽減する方法を一緒に考える。
夫との思い出について語る機会を提供する。認知機能が良好な時に「ご主人とはどんな方でしたか」と尋ね、夫との思い出を語ってもらう。夫の写真を居室に飾り、いつでも夫を身近に感じられるようにする。夫への思いを表現できる機会を作ることで、喪失体験の処理を支援する。
ホーム内での居場所作りを支援する。本人の居室を安心できる空間にするため、馴染みの物品や家族の写真を配置する。共有スペースでも本人の定位置を作り、「ここは先生の席ですよ」と伝えることで、所属感を高める。スタッフ全員が本人の経歴や性格を理解し、一貫して尊重した関わりを行う。
現在のアセスメント
A氏は82歳の女性であり、閉経後約30年以上が経過している。更年期はすでに終了しており、現在は閉経後の老年期にある。更年期症状についての記載はないが、年齢から考えて、ホットフラッシュや情緒不安定などの更年期症状は過去のものとなっている。
家族構成は、夫が3年前に他界しており、現在は配偶者がいない状態である。夫婦関係は良好であったと推測され、夫の存命中は晩酌を共にするなど、夫婦の時間を大切にしていた。夫の死後は飲酒をしなくなったことから、夫との絆が深く、夫の存在が生活の一部であったと考えられる。3年前の夫の死は大きな喪失体験であり、その後認知症が顕在化したことから、配偶者の死が精神的ストレスとなり、認知症の進行に影響した可能性がある。
子どもは長女と長男の2人がおり、いずれも成人して独立している。長女は県内に在住し、長男は県外に在住している。孫の有無についての記載はないが、子どもたちが成人していることから、孫がいる可能性もある。家族関係は良好であり、長女は週3回、長男は月1回面会に訪れている。
性的な関心や性的な問題についての記載はなく、現在の年齢や認知機能の状態から、性的な問題は顕在化していないと考えられる。しかし夫の死による喪失感や寂しさは存在する可能性がある。
女性としてのアイデンティティについては、長年教師として社会で活躍し、妻として夫を支え、母として子どもを育ててきた。退職後もボランティア活動に参加するなど、自立した女性として生活してきた。しかし現在は身体機能の低下により、入浴や更衣に介助が必要となり、尿失禁もみられる。これらは女性としての尊厳に関わる問題であり、配慮が必要である。
生殖に関しては、82歳という年齢から生殖機能は喪失している。婦人科的な問題についての記載はなく、現時点で婦人科受診の必要性は示されていない。
課題
配偶者である夫を3年前に亡くし、長年のパートナーを失った喪失感が存在する可能性がある。夫の死後認知症が顕在化したことから、喪失体験が十分に処理されていない可能性がある。認知機能の低下により、夫の死を理解できない時があったり、夫がまだ生きていると思い込む可能性もある。
尿失禁や入浴介助など、プライバシーに関わるケアが必要であり、女性としての尊厳が損なわれる可能性がある。特に男性スタッフによるケアの場合、羞恥心や抵抗感を感じる可能性がある。認知機能の低下により、羞恥心を適切に表現できない場合もあるが、内面では不快感を感じている可能性がある。
高齢女性として、骨粗鬆症や泌尿器系の問題のリスクが高まっている。体重減少と低栄養状態により、骨密度の低下が懸念される。尿失禁は尿路感染症や皮膚トラブルのリスクを高める。
看護の方向性
女性としての尊厳を守るケアを徹底する。入浴介助や陰部ケア、更衣の介助などの際には、プライバシーを最大限に保護する。できる限り女性スタッフが対応し、やむを得ず男性スタッフが対応する場合は、必ず本人に説明し、同意を得る。カーテンやタオルを使用し、必要以上に身体を露出しないよう配慮する。「少し失礼します」「お体を拭かせていただきますね」と一つ一つ声かけを行い、尊重した態度で接する。
尿失禁については、本人の羞恥心に配慮した対応を行う。「失禁」という言葉を使わず、「お手洗いに行きましょう」とさりげなく誘導する。交換や清拭の際にはプライバシーを守り、手際よく実施する。清潔保持を徹底し、陰部の皮膚トラブルや尿路感染症を予防する。
夫への思いを大切にし、夫との思い出を語る機会を提供する。認知機能が良好な時に「ご主人とはどんな思い出がありますか」と尋ね、夫婦の思い出を語ってもらう。夫の写真を居室に飾り、いつでも夫を身近に感じられるようにする。夫を思い出して涙を流すことがあれば、その感情を否定せず、「寂しいですね」と共感を示す。
身だしなみを整え、女性らしさを保てるよう支援する。髪型や服装を整え、「今日のお洋服、素敵ですね」と肯定的な声かけを行う。化粧品の使用を希望する場合は、軽いメイクを支援する。爪の手入れや肌の保湿など、身体のケアを丁寧に行い、女性としての美しさを保つ支援を行う。
骨粗鬆症の予防のため、栄養管理を徹底する。カルシウムとビタミンDを多く含む食品の提供を心がける。日光浴の機会を作り、ビタミンDの生成を促す。転倒予防は骨折予防の観点からも重要であり、引き続き徹底する。必要に応じて骨密度測定を嘱託医に依頼し、骨粗鬆症治療薬の使用を検討する。
泌尿器系の健康管理として、尿路感染症の予防を徹底する。陰部の清潔保持、適切な水分摂取、定期的な尿検査を実施する。尿失禁のパターンを把握し、定時誘導により失禁の頻度を減らす。骨盤底筋訓練が可能であれば、訓練を取り入れる。
家族との関係を大切にし、母親として、祖母としての役割を継続できるよう支援する。長女や長男との面会時間を大切にし、家族の絆を維持する。孫がいる場合は、孫との交流の機会も提供する。母親として子どもたちを育ててきた誇りを尊重し、「お子さんたちが立派に育っていらっしゃいますね」と肯定的に評価する。
現在のアセスメント
A氏の入居環境は有料老人ホームの個室であり、4月10日の入居から現在まで約4ヶ月が経過している。入居当初は環境の変化に戸惑い、夜間に「知らない人が部屋にいる」と訴える幻視が頻繁にみられ、不穏状態となることがあった。自宅から施設への環境変化は大きなストレスとなり、見当識障害が強く表れた。しかし入居から1ヶ月後には徐々にホームの環境に慣れ、スタッフの顔も覚え始めた。現在は「ここは自分の家じゃないけど、みんな優しくしてくれるからありがたい」と発言することがあり、ある程度環境への適応が進んでいる。しかし認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」と訴え、環境への適応は不安定である。
仕事や生活でのストレス状況については、現在は有料老人ホームでの生活となっており、仕事に関するストレスはない。しかし認知機能の低下、パーキンソン症状の進行、身体機能の低下という疾患に伴う多くのストレス要因が存在する。幻視により「知らない人が窓の外から覗いている」「部屋に子どもがいる」と訴え、恐怖心から不穏となることは、本人にとって大きなストレスである。夜間に2から3回覚醒し、幻視により不安を感じることは、睡眠を妨げ、疲労とストレスを蓄積させている。
転倒への恐怖心が強くなっていることも、日常生活における大きなストレス要因である。入居後すでに2回転倒を経験しており、転倒時の恐怖や転倒後の不安が、活動意欲の低下につながっている。歩行時に常に転倒の不安を感じながら生活することは、精神的な負担が大きい。
ADLの低下により、入浴、更衣、排泄などの日常生活動作に介助が必要となっていることも、ストレス要因となっている可能性がある。元々几帳面で自立した生活を送っていたA氏にとって、他者の助けが必要な現在の状態は、ストレスフルな状況である。特に尿失禁は羞恥心を伴い、精神的な負担となっている可能性がある。
ストレス発散方法については、入居前は地域の読み聞かせボランティアに参加し、社会との交流を通じてストレスを発散していたと推測される。しかし現在はそのような活動ができなくなっている。ホーム内で実施される個別のレクリエーションプログラムに参加しているが、認知機能の変動により参加状況にムラがある。認知機能が良好な時には、昔の教師時代の話を楽しそうに語ることがあり、これが本人にとってのストレス発散となっている可能性がある。
家族のサポート状況は良好である。長女が週3回、長男が月1回面会に訪れており、家族との交流が本人にとって大きな支えとなっている。長女が面会に来ると表情が明るくなり、「あなたが来てくれると安心する」と喜びを示すことから、家族の存在が最大のサポートとなっている。長男も月1回の面会時には母親と散歩をしたり、昔の写真を見ながら思い出話をする時間を大切にしており、これらの活動が本人の精神的な安定につながっている。
生活の支えとなるものは、家族との絆が最も大きいと考えられる。また元教師としての誇りや、過去の教師時代の思い出も、本人のアイデンティティを支える要素となっている。スタッフからの優しい関わりも、生活の支えとなっている。
課題
認知機能の低下、幻視、パーキンソン症状、転倒への恐怖、ADLの低下など、多重のストレス要因が存在し、ストレス耐性が低下している。レビー小体型認知症の特徴的な症状である幻視は、本人に強い恐怖と不安をもたらし、日常的なストレスとなっている。認知機能の変動により、ストレスを適切に認識したり、言語化したりすることが困難である。
環境への適応が不完全であり、認知機能が低下している時には「いつ家に帰れるの」と訴え、ホームを自分の居場所として受け入れられていない。環境への不適応は慢性的なストレス状態を引き起こし、精神的な安定を損なっている。
効果的なストレス発散方法が限られている。入居前に行っていたボランティア活動などのストレス発散方法が使えなくなり、新たなコーピング方法が確立されていない。認知機能の低下により、意識的にストレス対処を行うことが困難である。レクリエーションプログラムへの参加も不安定であり、十分なストレス発散の機会が得られていない。
不安が強くなる傾向があり、性格的にもストレスを感じやすくなっている。几帳面で真面目な性格は、自分の状態をコントロールできないことへのストレスを増幅させている可能性がある。
睡眠の質が低く、夜間に2から3回覚醒することで、十分な休息が得られていない。睡眠不足はストレス耐性をさらに低下させ、日中の認知機能の低下や情緒不安定につながる悪循環を形成している。
看護の方向性
ストレス要因を可能な限り軽減する。幻視への対応として、環境調整と傾聴を基本とし、本人の恐怖心を受け止める。照明を適切に保ち、幻視を誘発する要因を減らす。幻視が出現した際には「怖かったですね」と共感を示し、「でも今は大丈夫ですよ」「スタッフがそばにいます」と安心感を与える。夜間の巡視を定期的に実施し、覚醒時には速やかに訪室する。
転倒への恐怖心を軽減するため、転倒予防対策を徹底する。歩行時は必ず付き添い、「一緒にいるから大丈夫」と声かけを行う。環境整備として動線を確保し、夜間は照明を確保する。転倒予防の取り組みにより実際に転倒が減少すれば、恐怖心が軽減され、ストレス耐性の向上につながる。
ADL低下に伴うストレスを軽減するため、できることは本人に行ってもらい、自己効力感を維持する。過介助を避け、本人のペースを尊重する。時間がかかっても待つ姿勢を持ち、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と声かけを行う。できたことに対しては「ご自分で上手にできましたね」と肯定的に評価し、達成感を感じられるよう支援する。
環境への適応を促進するため、居室を安心できる空間にする。自宅で使用していた馴染みの物品や家族の写真を配置し、「ここはあなたの部屋ですよ」と繰り返し説明する。スタッフは一貫して温かく接し、本人が安心できる関係を築く。日課を一定にし、生活リズムを整えることで、予測可能性を高め、不安を軽減する。
新たなストレス発散方法を見つけ、提供する。認知機能が良好な時には、昔の教師時代の話を傾聴し、思い出を語ることでストレスを発散できるよう支援する。「先生の時代のお話、とても興味深いです」と肯定的に反応し、本人が語りやすい雰囲気を作る。レクリエーションプログラムでは、読み聞かせや読書など、本人が以前楽しんでいた活動を取り入れる。音楽療法や園芸療法など、リラックスできる活動を提供する。
家族との交流を最大限に活用し、精神的サポートを強化する。長女の週3回の面会、長男の月1回の面会を継続できるよう支援する。面会時には本人が安定した状態で会えるよう、認知機能が良好な時間帯を提案する。面会時にはプライバシーが保たれる場所を提供し、ゆっくりと家族の時間を過ごせるよう配慮する。家族との散歩や写真を見ながらの思い出話など、本人が喜ぶ活動を促す。
睡眠の質を改善し、十分な休息が得られるよう支援する。夜間の睡眠環境を整備し、幻視の出現を最小限に抑える。就寝前のリラックスできるルーティンを確立する。日中の活動量を増やし、適度な疲労感を得ることで、夜間の睡眠の質を向上させる。エスゾピクロンの効果が不十分な場合は、嘱託医と相談し、薬剤調整を検討する。
ストレスのサインを早期に発見するため、日々の観察を徹底する。表情、言動、行動、バイタルサインなどから、ストレスレベルを評価する。不穏状態や興奮がみられた際には、その前後の状況を詳細に記録し、ストレス要因を分析する。ストレスが高まっている時には、静かな環境で休息を取る、好きな音楽を聴く、温かい飲み物を提供するなど、即座に対応する。
認知機能の良好な時には、本人の気持ちや不安について傾聴する時間を持つ。「何か心配なことはありませんか」「困っていることはありませんか」と尋ね、本人の思いを引き出す。訴えがあれば真摯に受け止め、できる範囲で対応する。認知機能が低下している時には、無理に話を引き出さず、そばに寄り添い、安心感を提供することを優先する。
スタッフ間で情報共有を徹底し、一貫したケアを提供する。本人のストレス要因、効果的なストレス対処方法、避けるべき状況などをスタッフ全員が理解し、統一したアプローチを行う。スタッフ自身もストレスを感じながらケアを提供することがないよう、スタッフのメンタルヘルスにも配慮する。
薬物療法についても、ストレス軽減の観点から評価する。幻視や不安が強い場合は、嘱託医と相談し、抗不安薬や抗精神病薬の少量投与を検討する。しかしレビー小体型認知症ではパーキンソン症状の悪化に注意が必要であり、慎重に判断する。薬剤の効果と副作用を観察し、本人のQOL向上につながる薬物療法を目指す。
現在のアセスメント
A氏の信仰については特になしと記載されており、特定の宗教を信仰していない。日本の一般的な高齢者として、仏教や神道の習慣に触れてきた可能性はあるが、熱心な信仰者ではないと考えられる。信仰がないことは、終末期や死に対する価値観にも影響している可能性がある。
意思決定を決める価値観や信念については、明確な記載はないが、A氏の人生歴から推測できる部分がある。小学校教師として38年間勤務したという経歴から、教育への情熱、子どもたちへの愛情、社会への貢献を大切にしてきたと考えられる。几帳面で真面目という性格は、責任感の強さ、誠実さ、規律を重んじる価値観を示している。退職後も地域の読み聞かせボランティアに参加していたことから、人の役に立つこと、社会とのつながりを重視する価値観があったと推測される。
人との交流を好む社交的な面があったことから、人間関係や絆を大切にする価値観を持っていたと考えられる。夫の存命中は晩酌を共にし、夫婦の時間を大切にしていたことから、家族との絆を重視していた。現在も長女が面会に来ると「あなたが来てくれると安心する」と喜びを示すことから、家族との関係が本人にとって最も重要な価値であることがわかる。
家族はホームでの看取りも視野に入れており、今後も本人が安心して生活できるよう医療スタッフと連携していきたいと希望している。これは家族が本人の穏やかな最期を望んでいることを示している。本人自身の終末期に対する意向については明確な記載がないが、認知機能の低下により、現時点で終末期の意思決定を本人が行うことは困難である可能性がある。家族の意向が本人の意向を代弁していると考えられる。
目標については、具体的な記載はない。認知機能の低下により、明確な目標を設定することは困難であると推測される。しかし「ここは自分の家じゃないけど、みんな優しくしてくれるからありがたい」という発言から、現在の生活に感謝する気持ちがあり、穏やかに過ごすことを望んでいると考えられる。長女が面会に来ることを喜び、「あなたが来てくれると安心する」と述べることから、家族との時間を大切にすることが本人にとっての目標である可能性がある。
生きがいについては、元教師としてのアイデンティティ、家族との絆、人との交流が中心であったと推測される。しかし現在は認知機能の低下とパーキンソン症状の進行により、これらの生きがいを十分に実現できていない状況にある。
課題
認知機能の低下により、本人の価値観や信念、意向を明確に把握することが困難である。終末期に関する意思決定についても、本人が十分な判断能力を持って決定することは難しい状況にある。事前指示書やアドバンス・ケア・プランニングの機会がなかったため、本人の真の意向が不明確である。
教育への情熱や社会貢献という本人の価値観を実現する機会が失われている。元教師としてのアイデンティティや、人の役に立つことへの喜びを感じる機会が少なく、生きがいの喪失につながっている可能性がある。
家族の意向と本人の意向が一致しているか確認が困難である。家族はホームでの看取りを視野に入れているが、本人自身がどのような最期を望んでいるかについては、認知機能が良好であった時期に確認されていない可能性がある。
人生の最終段階における生活の質をどのように保つかについて、具体的な方針が明確でない。穏やかに過ごすことを目標とすることは良いが、より具体的に何を大切にし、何を優先するかについての指針が必要である。
信仰がないことで、死や終末期に対する精神的な支えが限られている可能性がある。宗教的な儀式や祈りによる慰めが得られないため、別の形での精神的支援が必要である。
看護の方向性
本人の価値観を尊重したケアを提供するため、人生歴や経歴を大切にする。元教師であったことを尊重し、「先生」と呼びかけることで、本人のアイデンティティを支える。教師時代の話を傾聴し、「たくさんの子どもたちを教えてこられたのですね」「素晴らしいお仕事をされてきたのですね」と肯定的に評価する。
人の役に立つことへの価値観を実現する機会を提供する。レクリエーションプログラムで読み聞かせの時間を設け、他の入居者や訪問する子どもたちに本を読んでもらう機会を作る。他の入居者との交流を促し、社会的なつながりを維持する。小さな役割を持ってもらうことで、「まだ人の役に立てる」という実感を持てるよう支援する。
家族との絆を最優先し、家族との時間を大切にする。長女の週3回の面会、長男の月1回の面会を継続できるよう支援し、面会時には本人が安心して家族と過ごせる環境を整える。家族の写真を居室に飾り、いつでも家族を身近に感じられるようにする。家族との思い出を語る機会を提供し、家族との絆を再確認できるよう支援する。
終末期に関する意思決定について、家族と十分に話し合う機会を持つ。家族が「ホームでの看取りも視野に入れている」という意向を持っていることを踏まえ、具体的な終末期ケアの方針について話し合う。延命治療の希望、苦痛緩和の方法、最期を迎える場所などについて、家族の意向を確認する。可能であれば、本人の認知機能が比較的良好な時に、本人の意向についても確認を試みる。「これからもここで穏やかに過ごしていただきたいと思っています」と説明し、本人の反応を観察する。
アドバンス・ケア・プランニングの概念を家族に説明し、今後の治療やケアについて継続的に話し合う機会を持つ。状態が変化する中で、その都度家族と相談し、本人にとって最善のケアを一緒に考えていく姿勢を示す。
生活の質を最大限に保つため、本人が穏やかに過ごせることを最優先する。苦痛や不快感を最小限にし、安心感と安全感を提供する。幻視や不安に対して適切に対応し、精神的な安定を図る。転倒予防を徹底し、身体的な苦痛を避ける。栄養状態を改善し、体力を維持する。
信仰がないことを踏まえ、精神的な支えとして家族との絆やスタッフとの信頼関係を重視する。スタッフは一貫して温かく接し、本人が安心できる存在となる。「ここにいて良いのだ」「大切にされている」という実感を持てるよう、尊重した態度で接する。
人生の最終段階において、尊厳を保ちながら穏やかに過ごせることを目標とする。認知機能の低下があっても、一人の人間として尊重され、大切にされることで、尊厳ある最期を迎えられるよう支援する。本人らしさを大切にし、その人らしい生活を最期まで送れるよう、個別性を重視したケアを提供する。
定期的に家族と情報共有を行い、本人の状態の変化について説明する。終末期が近づいた際には、家族が後悔のない看取りができるよう、十分な時間を一緒に過ごせるよう配慮する。家族の希望があれば、最期の時に家族が付き添えるよう柔軟に対応する。
看護計画
看護問題
レビー小体型認知症に伴うパーキンソン症状と認知機能の変動に関連した転倒のリスク
長期目標
入居中、転倒することなく安全に生活できる
短期目標
2週間以内に、歩行時の付き添いと環境整備により転倒せずに移動できる
≪O-P≫観察計画
・歩行状態の観察(前傾姿勢、小刻み歩行、すくみ足の有無と程度)
・転倒リスクアセスメントスコアの評価
・認知機能の日内変動の観察(午前中と午後以降の違い)
・バイタルサインの測定(血圧、脈拍、体温、呼吸数、酸素飽和度)
・起立性低血圧の有無の確認
・レボドパ・カルビドパ配合剤の効果と副作用の観察
・夜間の幻視の出現頻度と内容
・夜間の覚醒回数と覚醒時の状態
・転倒への恐怖心の程度と活動意欲の変化
・ナースコールの使用状況
・居室内と廊下の環境状態(動線の確保、照明、障害物の有無)
・下肢筋力の低下の程度
・ふらつきの有無と程度
・視力と眼鏡の使用状況
・履物の状態と適合性
≪T-P≫援助計画
・歩行時は必ず付き添い、本人のペースに合わせてゆっくりと移動を支援する
・「一緒にいるから大丈夫」「ゆっくりで良い」と声かけを行い、安心感を提供する
・すくみ足が出現した際は、床に目印をつける、リズムをとる、一歩の大きさを指示する
・居室内の動線を確保し、つまずきの原因となる物品を除去する
・夜間は足元灯とナイトライトを設置し、視認性を高める
・トイレまでの経路の照明を確保し、手すりの位置を確認する
・ベッドの高さを調整し、立ち上がりやすい高さに設定する
・夜間のトイレ誘導を徹底し、就寝前と夜間1回程度の定時誘導を実施する
・ナースコールをベッドサイドの手の届く位置に設置し、使用方法を繰り返し説明する
・訪問リハビリテーションと連携し、歩行訓練と筋力強化訓練を週2回継続する
・リハビリテーションで獲得した動作を日常生活に取り入れる
・転倒予防に効果的な運動や歩行のポイントについて理学療法士から指導を受ける
・「今日は上手に歩けた」「昨日より安定している」と肯定的なフィードバックを行い、自信を回復させる
・レボドパ・カルビドパ配合剤の効果について嘱託医と情報共有し、必要に応じて用量調整を依頼する
・幻視が出現した際は、本人の気持ちを受け止め、「ここは安全な場所」と安心感を与える
・適切な履物を使用し、滑りにくく脱げにくい靴を選ぶ
≪E-P≫教育・指導計画
・本人に対して、一人で移動せず必ずスタッフを呼ぶよう繰り返し説明する
・ナースコールの使用方法を認知機能が良好な時間帯に説明し、実際に押してもらう
・家族に対して、転倒リスクが高い状態であることを説明する
・家族に対して、面会時に一緒に歩く際の注意点を説明する(急がせない、手を引かない、見守る等)
・家族に対して、転倒予防のための取り組み内容を説明し、協力を依頼する
・家族に対して、夜間の転倒リスクが特に高いことを説明する
・家族に対して、転倒が起きた場合の対応について説明する
看護問題
レビー小体型認知症に伴う認知機能の変動と幻視に関連した不安と恐怖
長期目標
入居生活に適応し、不安や恐怖を感じることなく穏やかに過ごせる
短期目標
1週間以内に、幻視出現時の適切な対応により、不穏状態の持続時間が短縮される
≪O-P≫観察計画
・認知機能の日内変動の観察(午前中と午後以降の状態の違い)
・MMSE・HDS-Rのスコアの定期的な評価
・幻視の出現頻度、時間帯、内容、持続時間
・幻視出現時の本人の反応と訴え
・不穏状態の有無と程度(興奮、徘徊、大声など)
・不安の訴えの内容と頻度(「いつ家に帰れるの」「娘はどこにいるの」等)
・表情の変化(恐怖、不安、困惑等)
・睡眠状況(入眠時刻、覚醒回数、覚醒時の状態、総睡眠時間)
・エスゾピクロンの効果と副作用
・見当識の状態(人物、場所、時間の見当識)
・居室内の環境(照明の明るさ、影の有無、物品の配置)
・日中の活動量と傾眠の頻度
・ドネペジル塩酸塩の効果と副作用
・家族の面会時の表情と発言内容
≪T-P≫援助計画
・幻視を否定せず、「怖かった」「不安だった」と本人の気持ちを受け止める
・「ここは安全な場所」「スタッフがそばにいる」と安心感を与える言葉かけを行う
・必要に応じて一緒に居室内を確認し、「誰もいない」と穏やかに現実を伝える
・背中をさするなどの身体接触により、安心感を提供する
・居室内の照明を適切に保ち、完全な暗闇を避ける
・足元灯やナイトライトを使用し、目が覚めた時にも見当識を保ちやすい環境を作る
・窓にカーテンをしっかりと閉め、外からの光や影が幻視を誘発しないよう配慮する
・居室内の物品配置を整理し、影ができにくい環境を作る
・夜間の巡視を定期的に実施し、覚醒時には速やかに訪室する
・幻視の出現パターンを記録し、出現しやすい時間帯や状況を把握する
・日中の活動量を増やし、レクリエーションプログラムへの参加を促す
・認知機能が比較的良好な午前中に、昔の教師時代の話を傾聴する
・カレンダーや時計を見やすい位置に設置し、見当識の維持を支援する
・自宅で使用していた馴染みの物品や家族の写真を居室に配置する
・「いつ家に帰れるの」という訴えには、「今日はここでゆっくり休む」と穏やかに対応する
・就寝前に温かい飲み物を提供し、リラックスできるルーティンを確立する
・エスゾピクロンの効果が不十分な場合は、嘱託医に報告し薬剤調整を依頼する
・幻視が頻繁で本人の苦痛が強い場合は、嘱託医と相談し薬物療法の調整を検討する
≪E-P≫教育・指導計画
・家族に対して、レビー小体型認知症の特徴的な症状である幻視について説明する
・家族に対して、幻視は本人にとって現実と区別がつかないことを説明する
・家族に対して、幻視への対応方法(否定しない、受け止める、安心させる)を説明する
・家族に対して、認知機能の日内変動があることを説明し、午前中の面会を提案する
・家族に対して、本人が安心できる声かけの方法を具体的に伝える
・家族に対して、昔の思い出話を一緒にすることが本人の安心につながることを説明する
・本人に対して、認知機能が良好な時に「ここはあなたの部屋」と繰り返し説明する
看護問題
レビー小体型認知症に伴う認知機能の変動と食欲低下に関連した低栄養状態
長期目標
適切な栄養摂取により、体重が44キログラム以上に回復し維持できる
短期目標
1週間以内に、食事摂取量が毎食8割以上となる
≪O-P≫観察計画
・食事摂取量の記録(主食、副食、汁物の割合)
・食事に要する時間
・食事中の集中力と注意力
・食事中のむせの有無と頻度
・食欲の有無と訴え
・嗜好と好きな食べ物
・体重測定(週1回)
・血液データ(アルブミン、総蛋白、ヘモグロビン、赤血球数)
・皮膚の状態と弾力性
・口腔内の状態(歯牙の状態、口腔粘膜、舌の状態)
・嚥下機能の状態
・嘔気や嘔吐の有無
・腹部の状態(腹部膨満、腸蠕動音)
・排便状況との関連
・認知機能の日内変動と食事時間との関係
・水分摂取量
・活動量と疲労感
≪T-P≫援助計画
・食事摂取量を毎食詳細に記録し、5割以下の場合は栄養補助食品を提供する
・認知機能が比較的良好な午前中に主たる栄養摂取ができるよう、朝食と昼食の栄養配分を調整する
・食事時は静かな環境を整え、テレビや音楽などの刺激を最小限にする
・食事介助時には「今はご飯の時間」「一口ずつゆっくり食べる」と具体的な指示を出す
・本人の嗜好について家族から情報を収集し、好きな食べ物を取り入れる
・食事前に嚥下体操や発声練習を行い、嚥下機能の維持を図る
・食事中は姿勢を整え、顎を引いた姿勢で摂取できるよう見守りと声かけを行う
・むせが頻繁にみられる場合は、食事形態の変更を嘱託医や管理栄養士と検討する
・水分摂取時にはとろみ剤の使用を検討する
・体重測定を週1回実施し、体重の推移をモニタリングする
・継続的な体重減少がみられる場合は、速やかに嘱託医に報告する
・血液データを月1回程度評価し、栄養指標と貧血指標の推移を観察する
・貧血の原因精査のため、嘱託医に鉄代謝検査や便潜血検査を依頼する
・鉄欠乏性貧血が確認された場合は、鉄剤の投与を検討する
・食事内容では鉄分を多く含む食品の提供を心がける
・毎食後の口腔ケアを実施し、口腔内の状態を観察する
・歯科衛生士による口腔内の評価を依頼し、必要に応じて歯科受診を検討する
・日中のレクリエーションや散歩を促し、適度な活動により食欲を刺激する
≪E-P≫教育・指導計画
・家族に対して、現在の栄養状態と体重減少について説明する
・家族に対して、本人の嗜好する食品や以前よく食べていた食事について情報提供を依頼する
・家族に対して、面会時に一緒に食事をすることが食欲刺激につながることを説明する
・家族に対して、栄養改善のための取り組み内容を説明する
・家族に対して、食事摂取量や体重の推移について定期的に報告する
・本人に対して、認知機能が良好な時に「しっかり食べることが元気につながる」と説明する
・本人に対して、「美味しい」と感じたものがあれば教えてもらうよう伝える
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
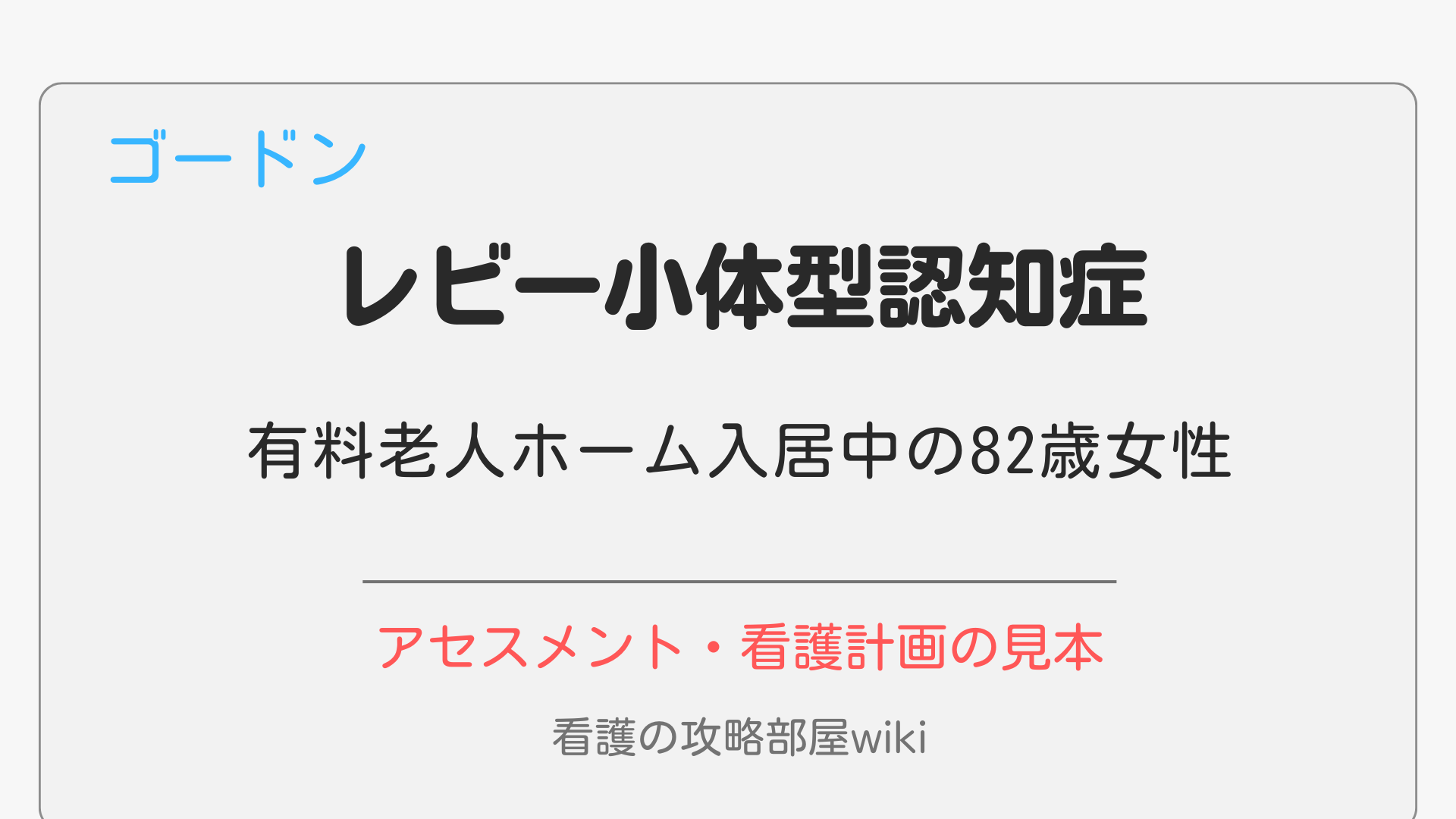
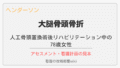
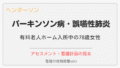
コメント