事例の要約
早期胃癌ステージⅠA(T1b、N0、M0)に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した高齢男性の事例。介入日は3月15日。現在:術後5日目
基本情報
A氏は72歳の男性で、身長165cm、体重58kgである。家族構成は妻と長男夫婦との4人家族で、キーパーソンは妻となっている。職業は元会社員で現在は年金生活を送っており、性格は真面目で几帳面、やや心配性な傾向がある。感染症の既往はなく、薬物アレルギーも特に認められない。認知機能は良好で、MMSE 28点、HDS-R 27点と正常範囲内である。
病名
早期胃癌 ステージⅠA(T1b、N0、M0) に対し、腹腔鏡下幽門側胃切除術(Billroth-I法再建)を施行した。
既往歴と治療状況
既往歴として高血圧症があり、10年前から降圧薬による治療を継続している。また、5年前に脂質異常症を指摘され、スタチン系薬剤を服用中である。その他、特記すべき手術歴や重篤な疾患の既往はない。
入院から現在までの情報
3月13日に胃内視鏡検査で早期胃癌を指摘され、精査加療目的で入院となった。入院時は特に症状はなく、全身状態は良好であった。3月15日に腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行し、手術時間は3時間30分、出血量は少量で経過は良好であった。術後1日目より水分摂取を開始し、術後3日目から流動食を開始している。現在術後5日目で、創部の治癒経過は良好で感染徴候は認められない。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、体温36.5℃、血圧138/82mmHg、脈拍72回/分、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在のバイタルサインは、体温36.8℃、血圧152/88mmHgとやや高値、脈拍80回/分、呼吸数18回/分、SpO2 97%(室内気)となっている。
食事と嚥下状態
入院前は通常の食事を摂取しており、嚥下機能に問題はなかった。喫煙歴は20歳から50歳まで1日1箱程度、現在は禁煙している。飲酒は晩酌程度で日本酒1合程度を週3回程度摂取していた。現在は術後5日目で5分粥食を開始しており、嚥下機能は良好で誤嚥のリスクは低い。食事摂取量は約6割程度で、術後の胃切除による早期満腹感を訴えている。
排泄
入院前は自立した排泄が可能で、排便は1日1回規則的であった。現在は術後の影響で便秘傾向にあり、術後3日目より酸化マグネシウム330mgを1日3回服用している。排尿は自立しており、尿意・尿失禁等の問題はない。
睡眠
入院前は22時頃就寝し6時頃起床する規則正しい睡眠リズムを保っていた。現在は術後の不安や創部痛により入眠困難を訴えており、必要時にゾルピデム5mgを服用している。中途覚醒は少なく、朝の覚醒感は比較的良好である。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は老眼があるが眼鏡使用で問題なく、聴力も正常範囲内である。知覚機能に異常はなく、コミュニケーション能力も良好で看護師との会話も円滑に行える。宗教的信仰は特になく、一般的な仏教的価値観を持っている。
動作状況
歩行は自立しており転倒歴はない。移乗動作も問題なく、排尿・排便も自立している。入浴は現在創部保護のため清拭対応としている。衣類の着脱は自立しているが、術後創部痛のため上衣の着脱時に軽度の介助を要している。
内服中の薬
アムロジピン5mg 1日1回 朝食後
ロスバスタチン2.5mg 1日1回 夕食後
酸化マグネシウム330mg 1日3回 毎食後
ゾルピデム5mg 1日1回 就寝前(頓用)
服薬状況
入院前は自己管理で服薬しており、飲み忘れもほとんどなかった。現在は看護師管理とし、服薬確認を行っている。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時 | 最近(術後5日目) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6,800 | 10,200 | 3,500-9,000 |
| RBC | 4.2 | 3.8 | 4.0-5.5 |
| Hb | 13.2 | 10.8 | 12.0-16.0 |
| Plt | 248 | 186 | 150-400 |
| TP | 7.1 | 6.2 | 6.5-8.0 |
| Alb | 4.0 | 3.2 | 3.8-5.3 |
| BUN | 18 | 22 | 8-20 |
| Cr | 0.9 | 1.0 | 0.6-1.2 |
| CRP | 0.2 | 2.8 | <0.3 |
今後の治療方針と医師の指示
術後の経過は概ね良好であり、創部感染や縫合不全等の合併症は認められない。今後は段階的に食事形態を上げ、術後10日目頃の退院を予定している。退院後は外来でのフォローアップを継続し、3か月毎の内視鏡検査と腫瘍マーカー検査を実施する方針である。また、胃切除後のダンピング症候群や貧血の予防について指導を行う予定となっている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「手術は成功したと聞いて安心しているが、これからの食事が心配だ」と述べており、術後の食生活に対する不安を抱いている。また「家族に迷惑をかけたくない」という思いが強く、早期の社会復帰を希望している。妻は「主人が元気になってくれれば何でもする」と述べ、退院後の食事管理や生活支援に対して積極的な姿勢を示している。長男夫婦も協力的で、「父の回復のために家族一丸となって支えたい」と話している。
アセスメント
疾患の簡単な説明
A氏は早期胃癌ステージⅠAと診断され、腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行された。病期分類はT1b、N0、M0であり、癌が粘膜下層に留まり、リンパ節転移や遠隔転移のない早期癌である。幽門側胃切除により胃の約3分の2が切除され、Billroth-I法による再建が行われている。この術式により消化機能の変化が予想され、術後の食事摂取量減少や早期満腹感、ダンピング症候群などの合併症に注意が必要である。
健康状態
術後5日目の現在、創部の治癒経過は良好であり感染徴候は認められない。しかし、白血球数10,200/μL、CRP2.8mg/dLと軽度の炎症反応の上昇が見られ、術後の正常な生体反応と考えられるが継続的な観察が必要である。血圧152/88mmHgとやや高値を示しており、既往の高血圧に加えて手術侵襲や疼痛による影響が考えられる。ヘモグロビン10.8g/dL、赤血球数3.8×10⁶/μLと軽度の貧血を呈しており、手術時の出血や術後の摂食不良の影響が示唆される。
受診行動、疾患や治療への理解、服薬状況
A氏は胃内視鏡検査で早期癌を指摘された際に適切に精査加療を受けており、健康問題に対する受診行動は良好である。疾患や治療に対する理解度は高く、看護師との会話も円滑で質問にも適切に答えることができる。入院前は高血圧症と脂質異常症の内服薬を自己管理で服用しており、飲み忘れもほとんどなかった。現在は看護師管理下で確実な服薬が行われている。しかし、術後の食生活に対する不安を強く抱いており、「これからの食事が心配だ」と述べている。
身長、体重、身体指数、運動習慣
身長165cm、体重58kgで身体指数は21.3kg/m²と標準範囲内である。72歳という年齢を考慮すると適正な体重を維持していると評価できる。運動習慣については詳細な情報が不足しているため、退院に向けて日常的な運動習慣や活動レベルについて追加の情報収集が必要である。術後の体重変化や栄養状態の推移についても継続的な観察が重要である。
呼吸に関するアレルギー、飲酒、喫煙の有無
呼吸器系のアレルギーや薬物アレルギーは特に認められない。喫煙歴は20歳から50歳まで1日1箱程度と30年間の喫煙歴があるが、現在は禁煙している。22年間の禁煙期間があることから、喫煙による呼吸器系への影響は軽減されていると考えられるが、術後の肺合併症リスクについては注意深い観察が必要である。飲酒は晩酌程度で日本酒1合を週3回程度と適度な範囲内であった。
既往歴
高血圧症の既往が10年前からあり、降圧薬による治療を継続している。現在の血圧値152/88mmHgはやや高値であり、術後のストレスや疼痛の影響も考慮した血圧管理が必要である。脂質異常症の既往が5年前からあり、スタチン系薬剤による治療を受けている。72歳という年齢を考慮すると、動脈硬化の進行や心血管系合併症のリスクについて留意が必要である。その他の重篤な疾患や手術歴はなく、比較的健康な状態を維持してきたと評価できる。
健康管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の栄養管理と食事指導が挙げられる。現在5分粥食を6割程度しか摂取できておらず、早期満腹感を訴えている。胃切除後の消化機能の変化に対応した食事指導と栄養状態の改善が急務である。血圧管理についても、既往の高血圧に加えて術後の血圧上昇が見られるため、降圧薬の調整や生活指導が必要である。貧血の改善に向けて、鉄分摂取の指導や必要に応じた鉄剤の投与を検討する必要がある。
術後合併症の予防として、ダンピング症候群や逆流性食道炎の予防に関する指導が重要である。また、「家族に迷惑をかけたくない」という思いから無理をする可能性があるため、適切な療養行動についての指導と家族を含めた支援体制の構築が必要である。
継続的な観察項目
創部の治癒状態と感染徴候の有無、血圧値の推移、貧血の改善状況について継続的な観察が必要である。食事摂取量と体重変化、排便状況についても毎日の観察を継続し、必要に応じて医師への報告と治療方針の調整を行う。退院に向けて、本人と家族の疾患理解度と自己管理能力についても継続的に評価し、必要な指導を実施していく必要がある。
食事と水分の摂取量と摂取方法
現在術後5日目で5分粥食を開始しており、摂取量は約6割程度に留まっている。胃切除後の影響により早期満腹感を強く訴えており、一回の食事摂取量が制限されている状況である。水分摂取については術後1日目より開始され、現在は特に制限なく経口摂取が可能である。摂取方法は経口摂取で、嚥下機能に問題はなく誤嚥のリスクは低い。入院前は通常の食事を問題なく摂取していたが、幽門側胃切除により貯留機能が低下し、食事形態と摂取量の調整が必要な状態である。
好きな食べ物と食事に関するアレルギー
食事に関するアレルギーは特に認められない。好きな食べ物や食事の嗜好については詳細な情報が不足しており、退院後の食事指導に向けて追加の情報収集が必要である。和食を中心とした食生活を送っていたと推測されるが、術後の食事制限や消化機能の変化に対応した食品選択について指導が重要である。
身長・体重・身体指数・必要栄養量・身体活動レベル
身長165cm、体重58kgで身体指数21.3kg/m²と標準範囲内を維持している。72歳男性の基礎代謝量は約1,200kcal/日と推定され、現在の活動レベルを考慮すると必要栄養量は約1,600-1,800kcal/日程度と考えられる。しかし、術後の摂食不良により必要栄養量を十分に確保できていない状況である。身体活動レベルについては術後の安静により低下しており、段階的な活動量の増加と共に栄養必要量の再評価が必要である。
食欲・嚥下機能・口腔内の状態
食欲については術後の影響で低下しており、早期満腹感により十分な摂取ができない状況である。嚥下機能は良好で誤嚥のリスクは低いと評価される。口腔内の状態については詳細な観察情報が不足しているため、口腔ケアの状況や歯牙の状態、義歯の使用状況について追加の情報収集が必要である。高齢者においては口腔機能の低下が栄養摂取に影響するため、継続的な観察が重要である。
嘔吐・吐気
現在のところ嘔吐や吐気の症状は認められていない。しかし、胃切除後はダンピング症候群や逆流性食道炎による嘔吐・吐気が起こりやすいため、継続的な観察が必要である。食事摂取時の症状の有無や食後の体位変換時の症状について詳細な観察を継続する必要がある。
皮膚の状態、褥創の有無
皮膚の状態については詳細な情報が不足しているが、現在のところ褥創の発生は認められていない。72歳という年齢と術後の安静により褥創発生のリスクが高まる可能性があるため、定期的な皮膚観察と体位変換が重要である。栄養状態の低下が皮膚の脆弱性を高める可能性があり、栄養改善と皮膚ケアの両面からのアプローチが必要である。
血液データ
アルブミン3.2g/dL(基準値3.8-5.3)、総蛋白6.2g/dL(基準値6.5-8.0)と低栄養状態を示している。赤血球数3.8×10⁶/μL(基準値4.0-5.5)、ヘモグロビン10.8g/dL(基準値12.0-16.0)と軽度の貧血が認められる。これらの値は術後の侵襲と摂食不良による影響と考えられる。電解質、血糖値、脂質代謝に関するデータは提示されていないため、栄養状態の詳細な評価に向けて追加の検査データが必要である。
栄養管理上の課題と看護介入
主要な課題として、胃切除後の摂食不良による低栄養状態の改善が挙げられる。早期満腹感に対しては、少量頻回食の指導と消化の良い食品選択について指導が必要である。アルブミンと総蛋白の低値に対しては、質の良い蛋白質摂取の促進と必要に応じた栄養補助食品の活用を検討する。
貧血の改善に向けて、鉄分を含む食品の積極的摂取指導と、胃切除後のビタミンB12吸収障害を考慮した定期的な検査が必要である。ダンピング症候群の予防として、糖質の摂取方法や食事のタイミングについて指導を行う。
継続的な観察項目
体重変化、食事摂取量、血液データ(特にアルブミン、ヘモグロビン値)の推移について継続的な観察が必要である。嘔吐・吐気の有無、食後の腹部症状、皮膚の状態についても毎日観察し、栄養状態の改善状況を評価していく。退院に向けて、本人と家族への食事指導と栄養管理に関する教育を継続的に実施する必要がある。
排便と排尿の回数と量と性状
排便については術後の影響で便秘傾向にあり、入院前の1日1回規則的な排便から変化している。術後3日目以降排便が見られていない状況で、便性状や量についての詳細な情報収集が必要である。排尿については自立しており、回数や量、性状に特に問題は認められていない。尿意や尿失禁等の問題もなく、膀胱機能は良好に保たれている。72歳という年齢を考慮すると、前立腺肥大症等による排尿障害のリスクがあるが、現在のところ症状は認められていない。
下剤使用の有無
術後3日目より酸化マグネシウム330mgを1日3回服用している。これは術後の便秘に対する予防的な投与と考えられるが、現在までの排便効果については評価が必要である。下剤の効果判定と必要に応じた用量調整や薬剤変更について継続的に検討する必要がある。入院前は下剤の使用はなく、規則的な排便習慣を維持していた。
水分出納バランス
術後1日目より水分摂取を開始し、現在は経口摂取が可能である。しかし、具体的な水分摂取量や尿量の記録が不足しており、正確な水分出納バランスの評価のために詳細な記録が必要である。胃切除後は一回の摂取量が制限されるため、水分摂取不足の可能性があり、脱水予防の観点からも注意深い観察が重要である。
排泄に関連した食事・水分摂取状況
現在5分粥食を約6割摂取している状況で、食物繊維の摂取量が不足している可能性がある。水分摂取についても具体的な摂取量の把握が必要であり、便秘の要因として食事内容と水分摂取量の関連性を評価する必要がある。胃切除後の消化機能の変化により、排便パターンの変化も予想される。
安静度・バルーンカテーテルの有無
現在バルーンカテーテルは留置されておらず、自然排尿が可能である。安静度については術後5日目で歩行可能な状況にあるが、詳細な活動レベルについての情報が不足している。活動量の低下は腸蠕動の低下を招き、便秘の要因となるため、段階的な活動量の増加が重要である。
腹部膨満・腸蠕動音
腹部膨満や腸蠕動音に関する詳細な観察情報が不足している。術後の麻痺性イレウスや腸閉塞の可能性を早期に発見するため、腹部症状の継続的な観察が重要である。便秘が続いている状況を考慮すると、腹部膨満の有無や腸蠕動音の聴取による腸管機能の評価が必要である。
血液データ
BUN 22mg/dL(基準値8-20)とやや高値を示しており、軽度の脱水や腎機能への影響が示唆される。クレアチニン1.0mg/dL(基準値0.6-1.2)は正常範囲内であるが、72歳という年齢を考慮すると腎機能の軽度低下の可能性がある。糸球体濾過量の情報が不足しており、腎機能の詳細な評価のために追加データが必要である。
排泄管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後便秘の改善が挙げられる。酸化マグネシウムの効果判定を行い、必要に応じて下剤の種類や用量の調整を検討する必要がある。便秘の要因として、活動量の低下、食物繊維摂取不足、水分摂取不足が考えられるため、これらの改善に向けた総合的なアプローチが必要である。
水分摂取量の正確な把握と適切な水分補給により、脱水の予防と便秘の改善を図る必要がある。腹部マッサージや体位変換による腸蠕動の促進も有効である。腎機能についてはBUN高値を踏まえ、水分バランスと腎機能の継続的な評価が重要である。
継続的な観察項目
排便の有無、便性状、腹部症状(膨満、疼痛)について毎日観察し、下剤の効果判定を行う必要がある。水分摂取量と尿量の正確な記録により水分出納バランスを評価し、BUNやクレアチニン値の推移を監視する。腸蠕動音の聴取と腹部の触診により腸管機能の回復状況を評価し、必要に応じて医師への報告と治療方針の調整を行う必要がある。
日常生活動作の状況、運動機能、運動歴、安静度、移動・移乗方法
現在術後5日目で歩行は自立しており、移乗動作も問題なく行える状況である。術前は日常生活動作に支障はなく、72歳という年齢を考慮しても良好な身体機能を維持していた。運動歴については詳細な情報が不足しているが、元会社員として勤務していた背景から一定の活動レベルを保っていたと推測される。現在の安静度は術後の状況に応じて段階的に拡大されており、病棟内歩行が可能となっている。移動は独歩で可能であり、移乗時の介助は不要である。
バイタルサイン、呼吸機能
現在のバイタルサインは体温36.8℃、血圧152/88mmHgとやや高値、脈拍80回/分、呼吸数18回/分、SpO2 97%(室内気)となっている。血圧の上昇は既往の高血圧に加えて術後のストレスや疼痛の影響が考えられる。呼吸機能については酸素飽和度は良好であるが、過去の喫煙歴(30年間)を考慮すると潜在的な呼吸器機能の低下の可能性がある。22年間の禁煙により改善されているが、術後の肺合併症予防のため継続的な観察が重要である。
職業、住居環境
元会社員で現在は年金生活を送っており、定期的な通勤や肉体労働はない状況である。住居環境については詳細な情報が不足しているが、妻と長男夫婦との4人家族での生活であり、家族からのサポートが期待できる環境にある。退院後の生活環境については、階段の有無や手すりの設置状況、浴室の構造など、安全な生活を送るための環境整備について追加の情報収集が必要である。
血液データ
赤血球数3.8×10⁶/μL(基準値4.0-5.5)、ヘモグロビン10.8g/dL(基準値12.0-16.0)と軽度の貧血が認められ、酸素運搬能力の低下により運動耐容能に影響を与える可能性がある。CRP 2.8mg/dL(基準値<0.3)と炎症反応の上昇が見られるが、術後の正常な生体反応と考えられる。貧血の程度は軽度であるが、活動時の易疲労性や息切れの原因となる可能性があり、活動レベルの調整が必要である。
転倒転落のリスク
現在のところ転倒歴はないが、72歳という年齢、術後の状況、軽度の貧血により転倒リスクが存在する。血圧がやや高値であることから起立性低血圧のリスクもあり、体位変換時の注意が必要である。病院環境に慣れていないことや夜間の視力低下も転倒リスク要因となる。真面目で几帳面な性格から無理をする可能性があり、安全な活動範囲について指導が重要である。
活動・運動管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の段階的な活動量増加と運動耐容能の向上が挙げられる。現在は病棟内歩行が可能であるが、退院に向けてより長距離の歩行や階段昇降などの日常生活に必要な活動レベルまで段階的に向上させる必要がある。軽度の貧血により易疲労性が予想されるため、活動時のバイタルサイン監視と適切な休息の確保が重要である。
転倒予防として、履物の確認、夜間照明の確保、急激な体位変換の回避について指導する必要がある。血圧がやや高値であることから、活動前後の血圧測定と活動強度の調整が必要である。退院後の生活を見据えて、家事動作や外出時の注意点について指導を行う。
継続的な観察項目
活動時のバイタルサイン変化、特に血圧と脈拍数、酸素飽和度の変化について観察し、運動耐容能を評価する必要がある。活動後の疲労感や息切れの程度、下肢の浮腫の有無についても継続的に観察する。転倒リスクの評価として、歩行時のふらつきや下肢筋力の状態を定期的に評価し、必要に応じて理学療法士との連携を図る。貧血の改善状況と活動耐容能の関連性についても継続的に評価していく必要がある。
睡眠時間、熟眠感、睡眠導入剤使用の有無
入院前は22時頃就寝し6時頃起床する規則正しい睡眠リズムを保っており、約8時間の睡眠時間を確保していた。現在は術後の不安や創部痛により入眠困難を訴えており、睡眠の質の低下が認められる。中途覚醒は比較的少なく、朝の覚醒感は良好であるが、入眠までに時間を要している状況である。必要時にゾルピデム5mgを就寝前に頓用で使用しており、服用時は入眠が改善されている。しかし、睡眠導入剤への依存や転倒リスクの増加について注意が必要である。
日中・休日の過ごし方
入院前は年金生活者として比較的自由な時間を過ごしており、日中の活動についての詳細な情報が不足している。現在は病院という環境で過ごしており、日中の活動量や休息のパターンが変化している可能性がある。72歳という年齢を考慮すると、日中の適度な活動が夜間の良質な睡眠につながるため、日中の過ごし方と夜間睡眠の関連性を評価する必要がある。病室での過ごし方や面会時間、テレビ視聴などの日課についても睡眠に影響を与える要因として考慮が必要である。
睡眠・休息管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の不安と疼痛による睡眠障害の改善が挙げられる。創部痛については適切な疼痛管理により軽減を図り、睡眠の質の向上につなげる必要がある。術後の不安に対しては、手術の成功や今後の治療方針について十分な説明を行い、精神的な安定を図ることが重要である。
睡眠導入剤の使用については、必要最小限の使用とし、非薬物的な睡眠促進方法の併用を検討する必要がある。睡眠環境の整備として、適切な室温・湿度の維持、騒音の軽減、照明の調整を行う。日中の適度な活動量の確保により、夜間の自然な入眠を促進する。
継続的な観察項目
睡眠時間、入眠までの時間、中途覚醒の回数、朝の覚醒感について毎日評価し、睡眠の質の改善状況を観察する必要がある。睡眠導入剤使用時の効果と副作用、特に翌朝の眠気やふらつきの有無について観察する。日中の活動量と夜間睡眠の関連性を評価し、適切な活動スケジュールの調整を行う。退院に向けて、家庭での睡眠環境や睡眠習慣の確立について指導を継続していく必要がある。
意識レベル、認知機能
意識レベルは清明で、MMSE 28点、HDS-R 27点と正常範囲内を示しており、72歳という年齢を考慮しても良好な認知機能を維持している。見当識は時間、場所、人物すべてにおいて保たれており、看護師との会話も円滑に行うことができる。記憶機能、注意力、判断力に特に問題は認められず、治療や看護ケアに対する理解力も十分である。しかし、術後の環境変化や身体的ストレスが認知機能に与える影響について継続的な観察が必要である。
聴力、視力
聴力は正常範囲内であり、日常会話に支障はない。視力については老眼があるが眼鏡使用で問題なく、読書や書字も可能である。72歳という年齢を考慮すると、加齢による視聴覚機能の低下が進行する可能性があり、安全性の確保や情報提供の方法について配慮が必要である。夜間や薄暗い環境での視力低下により転倒リスクが高まる可能性があるため、環境整備と注意喚起が重要である。
認知機能
認知機能検査の結果は良好であり、疾患や治療に対する理解力も高い。複雑な医療情報についても適切に理解し、質問にも的確に答えることができる。しかし、術後の食生活に対する不安を強く抱いており、「これからの食事が心配だ」と述べている。この不安は合理的なものであり、認知機能の問題ではなく適応的な反応と考えられる。新しい情報の学習能力も保たれており、退院指導の理解も期待できる。
不安の有無、表情
術後の食生活に対する強い不安を抱いており、表情にも心配そうな様子が見られる。「家族に迷惑をかけたくない」という思いも強く、責任感の強い性格が不安を増強させている可能性がある。しかし、手術の成功については安心感を示しており、「手術は成功したと聞いて安心している」と述べている。不安の内容は具体的で現実的であり、適切な情報提供と指導により軽減可能と考えられる。
認知・知覚管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の不安に対する適切な情報提供と心理的支援が挙げられる。認知機能は良好であるため、疾患や治療に関する詳細な説明と理解の促進が可能である。食事に関する不安については、胃切除後の食事指導を段階的に行い、具体的な方法と注意点を明確に説明することで不安の軽減を図る必要がある。
視聴覚機能については、現在問題はないが加齢による変化を考慮し、安全な環境の確保と適切な照明の提供が重要である。夜間の転倒予防として、適切な照明の確保と動線の整備を行う。
継続的な観察項目
認知機能の変化、特に術後の混乱や見当識障害の有無について継続的に観察する必要がある。不安レベルの変化と表情の観察により、心理状態の推移を評価する。視聴覚機能については、日常生活動作への影響や安全性の確保について定期的に評価する。退院指導時の理解度と情報の保持能力についても継続的に評価し、必要に応じて繰り返し説明を行う必要がある。
性格
A氏は真面目で几帳面、やや心配性な傾向がある性格である。これらの性格特性は治療への取り組みや自己管理において良い面として作用する一方で、過度な心配や責任感により精神的負担を増加させる可能性がある。「家族に迷惑をかけたくない」という発言からも、他者への配慮が強く、自分の負担を軽視する傾向が窺える。72歳という年齢で培われてきた性格であり、急激な変化は期待できないため、この性格特性を理解した上での看護介入が重要である。
ボディイメージ
胃の約3分の2を切除する手術を受けており、身体の変化に対する受容過程にある。現在のところ身体イメージの大きな混乱は見られないが、術後の機能変化や食事制限により、今後ボディイメージの変化が生じる可能性がある。72歳という年齢を考慮すると、これまでの身体機能の変化に対する適応経験があると推測されるが、手術による急激な変化は新たな適応を要求するものである。創部の治癒状況や外見的な変化についての詳細な情報収集が必要である。
疾患に対する認識
早期癌であることを理解しており、手術の成功について安心感を示している。「手術は成功したと聞いて安心している」という発言から、疾患の深刻さと治療の必要性について適切に理解していると評価できる。しかし、「これからの食事が心配だ」という発言から、今後の生活への影響について強い関心と不安を抱いている。疾患に対する理解は良好であるが、長期的な影響や予後についてより詳細な情報提供が必要である。
自尊感情
長年にわたり会社員として勤務してきた経歴があり、一定の社会的役割を果たしてきた自負があると推測される。現在は年金生活者として家族と共に生活しており、家族内での役割についても重要性を感じている。「家族に迷惑をかけたくない」という発言は、自立した存在でありたいという自尊感情の表れと考えられる。しかし、疾患や手術により一時的に依存的な状況になることへの抵抗感も窺える。
育った文化や周囲の期待
72歳という年齢を考慮すると、伝統的な日本の家族観や価値観の中で育ってきたと推測される。家族に迷惑をかけることを避けたいという思いや、自分のことは自分で管理したいという考えは、この世代に特徴的な価値観の表れである。家族からの期待としては、健康を回復し元の生活に戻ることが求められていると感じている可能性がある。妻や長男夫婦からの支援の申し出に対しても、遠慮や申し訳なさを感じている可能性がある。
自己知覚・自己概念管理上の課題と看護介入
主要な課題として、疾患や手術による自己概念の変化への適応支援が挙げられる。真面目で責任感の強い性格を活かしながら、過度な自責感や責任感による負担を軽減する必要がある。「家族に迷惑をかけたくない」という思いに対しては、家族の支援を受けることの重要性と、それが家族にとっても意味のあることであることを説明する。
ボディイメージの変化については、段階的な受容を支援し、新しい身体機能に適応するための具体的な方法を提示する必要がある。自尊感情の維持のため、A氏の経験や知識を尊重し、治療や看護ケアにおいても可能な限り自己決定を促進する。
継続的な観察項目
疾患や手術に対する認識の変化、特に不安や恐怖の増加の有無について継続的に観察する必要がある。自尊感情の変化として、自信の喪失や無力感の表出がないか注意深く観察する。家族への依存に対する抵抗感や罪悪感の程度についても評価し、必要に応じて心理的支援を提供する。退院に向けて、新しい生活スタイルへの適応状況と自己概念の再構築過程についても継続的に評価していく必要がある。
職業、社会役割
A氏は元会社員で現在は年金生活を送っており、長年にわたり社会人としての役割を果たしてきた経歴がある。72歳という年齢で退職後の生活に移行しており、現役時代とは異なる役割の再構築が必要な時期にある。地域社会での役割や社会参加の状況については詳細な情報が不足しているため、退院後の社会復帰や生きがいの確保について追加の情報収集が必要である。疾患や手術により一時的に社会的役割が制限される可能性があり、段階的な社会復帰の支援が重要である。
家族の面会状況、キーパーソン
家族構成は妻と長男夫婦との4人家族で、キーパーソンは妻となっている。妻は「主人が元気になってくれれば何でもする」と述べており、積極的な支援意欲を示している。長男夫婦も協力的で「父の回復のために家族一丸となって支えたい」と話しており、良好な家族関係と強い結束力が窺える。面会状況の詳細については情報が不足しているが、家族からの精神的支援は十分に得られている状況と評価できる。
経済状況
年金生活者であることから、現役時代と比較して収入は減少していると推測される。しかし、長男夫婦との同居により生活の安定性は確保されていると考えられる。医療費や治療費に関する不安について詳細な情報が不足しており、経済的な心配が治療への取り組みに影響を与えていないか確認が必要である。退院後の通院費用や食事療法に伴う費用負担についても考慮が必要である。
役割・関係管理上の課題と看護介入
主要な課題として、疾患による家族内役割の変化への適応支援が挙げられる。A氏は「家族に迷惑をかけたくない」という思いが強く、家族からの支援を受けることに対する心理的負担を感じている可能性がある。家族の支援を素直に受け入れられるよう、支援を受けることの重要性と家族にとっての意味について説明する必要がある。
妻と長男夫婦の協力的な姿勢を活かし、効果的な家族支援体制の構築を図る必要がある。退院後の食事管理や生活支援について、家族全体で取り組める具体的な方法を提示し、役割分担を明確にする。A氏の自立性を尊重しながら、必要な支援を適切に受けられる関係性の調整が重要である。
継続的な観察項目
家族との関係性の変化、特に依存に対する抵抗感や家族への負担感について継続的に観察する必要がある。面会時の家族とのやり取りや表情の変化により、関係性の質を評価する。経済的な不安の有無や退院後の生活に対する心配について定期的に確認し、必要に応じて相談窓口の紹介や支援制度の活用について情報提供を行う。家族の介護負担や支援疲れの兆候についても注意深く観察していく必要がある。
年齢、家族構成、更年期症状の有無
A氏は72歳の男性であり、生殖機能については既に生殖期を過ぎた年齢である。家族構成は妻と長男夫婦との4人家族で、長年にわたり夫婦関係を維持してきた経歴がある。男性の更年期症状については、一般的に50歳代後半から60歳代にかけて出現することが多いが、現在72歳という年齢を考慮すると、更年期症状は既に経過している可能性が高い。しかし、加齢に伴うテストステロンの低下による身体的・精神的影響については継続的に存在する可能性がある。
性機能については、年齢的要因に加えて手術侵襲や全身麻酔、術後の身体的ストレスにより一時的な影響を受ける可能性がある。また、既往症である高血圧症の治療薬であるアムロジピンなどの降圧薬は性機能に影響を与える可能性があるが、これらについての詳細な情報は不足している。
夫婦関係については、妻が「主人が元気になってくれれば何でもする」と述べていることから、良好な夫婦関係を維持していると評価できる。しかし、疾患や手術による身体的変化が夫婦関係や親密性に与える影響については、プライベートな内容のため直接的な情報収集は困難である。
性・生殖管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の身体的変化が性機能や夫婦関係に与える影響の評価が挙げられる。72歳という年齢を考慮すると、性機能よりも夫婦間の親密性や情緒的なつながりの維持がより重要である可能性が高い。手術による身体的負担や疲労感が夫婦関係に一時的な影響を与える可能性があるため、段階的な回復過程において適切な配慮が必要である。
プライバシーに配慮しながら、必要に応じて性機能や夫婦関係に関する相談窓口の情報提供を行う。また、術後の身体的回復に伴い、夫婦間の親密性も段階的に回復していくことを説明し、無理のない関係性の再構築を支援する。
継続的な観察項目
夫婦関係の質的変化について、面会時の様子や会話の内容から間接的に評価する必要がある。術後の疲労感や身体的不調が夫婦関係に与える影響について注意深く観察し、必要に応じて適切な相談窓口への紹介を検討する。退院後の生活において、夫婦間の役割分担や親密性の回復について、プライバシーに配慮しながら支援を継続していく必要がある。
入院環境
現在術後5日目で病院という慣れない環境での生活を送っており、環境の変化によるストレスが予想される。病室の環境や同室者との関係、医療スタッフとの関わりについての詳細な情報が不足している。72歳という年齢を考慮すると、新しい環境への適応に時間を要する可能性があり、環境適応に関するストレスが存在すると考えられる。病院の規則や制約、プライバシーの制限なども心理的負担となっている可能性がある。
仕事や生活でのストレス状況、ストレス発散方法
現在は年金生活者であり、現役時代のような職業上のストレスは軽減されていると推測される。しかし、今回の疾患診断と手術という大きな生活上の出来事により、相当なストレスを経験していると考えられる。特に「これからの食事が心配だ」という発言から、将来への不安が主要なストレス要因となっている。
従来のストレス発散方法については詳細な情報が不足しており、晩酌(日本酒1合程度を週3回)が一つのストレス解消法であった可能性がある。現在は入院により従来のストレス発散方法が制限されており、新たな対処方法の確立が必要である。真面目で几帳面な性格であることから、問題解決型のコーピングを好む傾向があると推測される。
家族のサポート状況、生活の支えとなるもの
家族からの強力なサポート体制が確立されている。妻は「主人が元気になってくれれば何でもする」と述べ、長男夫婦も「父の回復のために家族一丸となって支えたい」と協力的な姿勢を示している。このような家族の結束と支援は、A氏にとって大きな心理的支えとなっていると評価できる。
生活の支えとなるものについては、家族との関係が最も重要な要素と考えられる。長年にわたる夫婦関係と家族の絆が、現在の困難な状況を乗り越える原動力となっている。しかし、「家族に迷惑をかけたくない」という思いから、家族の支援を素直に受け入れることへの葛藤も存在している。
コーピング・ストレス耐性管理上の課題と看護介入
主要な課題として、術後の不安とストレスに対する効果的な対処方法の確立が挙げられる。将来への不安については、具体的で現実的な情報提供により軽減を図る必要がある。胃切除後の食事管理について段階的に指導し、実際に管理可能であることを実感してもらうことが重要である。
家族サポートの活用については、A氏の自立性と家族の支援のバランスを調整し、適切な依存関係の構築を支援する必要がある。家族に迷惑をかけることへの罪悪感を軽減し、相互扶助の意味について説明する。
新たなストレス対処方法として、深呼吸法やリラクゼーション技法の指導、適度な運動や趣味活動の推奨を行う。真面目で几帳面な性格を活かし、構造化された問題解決アプローチを提示することで、ストレス管理能力の向上を図る。
継続的な観察項目
ストレスレベルの変化について、表情や言動、睡眠状況、食欲などから総合的に評価する必要がある。新たな対処方法の習得状況と効果について継続的に観察し、個人に適した方法を見つけていく。家族との関係性の変化やサポートの受け入れ状況についても定期的に評価する。退院に向けて、家庭でのストレス管理方法と家族との協力体制について継続的に支援していく必要がある。
信仰、意思決定を決める価値観・信念、目標
A氏は宗教的信仰は特になく、一般的な仏教的価値観を持っていると記載されている。72歳という年齢を考慮すると、戦後復興期から高度経済成長期を経験してきた世代であり、勤勉さや家族を大切にする価値観、自立と責任感を重視する傾向があると推測される。「家族に迷惑をかけたくない」という発言は、自立と他者への配慮を重視する価値観の表れであり、この世代に特徴的な考え方である。
意思決定については、真面目で几帳面な性格から、慎重で合理的な判断を行う傾向があると考えられる。今回の疾患に対しても適切に医療機関を受診し、必要な治療を受け入れていることから、健康問題に対しては現実的で建設的な対応を取る価値観を持っていると評価できる。しかし、家族への依存を避けたいという思いが強く、時として無理をする可能性もある。
現在の目標については、「手術は成功したと聞いて安心している」という発言から、治療の成功と健康の回復が主要な目標となっている。さらに、早期の社会復帰と家族への負担軽減も重要な目標として位置づけられていると推測される。長期的な目標としては、胃切除後の新しい生活様式への適応と、家族との良好な関係の維持が挙げられる。
価値・信念管理上の課題と看護介入
主要な課題として、自立を重視する価値観と現実的な支援の必要性とのバランス調整が挙げられる。A氏の自立性を尊重しながら、必要な支援を適切に受け入れられるよう価値観の調整を支援する必要がある。家族に迷惑をかけることを避けたいという思いに対しては、相互扶助の価値や家族の絆の意味について説明し、支援を受けることの積極的な意義を伝える。
治療や看護ケアにおいては、A氏の自己決定権を最大限尊重し、可能な限り選択肢を提示して主体的な参加を促進する。胃切除後の生活管理についても、A氏の価値観に沿った実現可能な目標設定を行い、段階的な達成により自信と希望を維持できるよう支援する。
宗教的信仰は特にないとされているが、人生の意味や生きがいについて考える機会を提供し、新しい生活様式の中での価値の発見を支援することも重要である。
継続的な観察項目
価値観や信念の変化、特に疾患や手術による人生観の変化について継続的に観察する必要がある。自立に対するこだわりと現実的な支援の必要性との間での葛藤の程度を評価し、適切なバランスを見つけるための支援を継続する。目標設定の変化や治療への取り組み姿勢についても定期的に評価し、必要に応じて目標の修正や新たな価値の発見を支援する。退院後の生活において、新しい価値観や生きがいの確立についても継続的に支援していく必要がある。
看護計画
看護問題
胃切除術に伴う消化機能の変化に関連した栄養摂取不足
長期目標
退院時までに1日の必要栄養量の8割以上を摂取でき、体重減少を最小限に抑制できる
短期目標
1週間以内に食事摂取量を現在の6割から7割以上に増加させ、早期満腹感を軽減できる
≪O-P≫観察計画
・食事摂取量と摂取にかかる時間の変化
・早期満腹感や腹部不快感の程度と出現時間
・体重と身体計測値の推移
・血清アルブミンと総蛋白値の変化
・血色素量と赤血球数の推移
・嘔吐や吐気の有無と誘因
・腹部膨満感や腹痛の程度
・食後の腹部症状と持続時間
・水分摂取量と尿量のバランス
・皮膚の弾力性と粘膜の状態
・活動時の疲労感や息切れの程度
・食事に対する意欲と関心の変化
≪T-P≫援助計画
・少量頻回食による食事提供と摂取支援
・食事時間の延長と個人のペースに合わせた摂取援助
・消化の良い食品選択と食事形態の段階的調整
・食前の口腔ケアと食欲増進のための環境整備
・食後の適切な体位保持と安楽確保
・栄養補助食品の適切な活用と摂取支援
・食事摂取量の正確な記録と評価
・腹部症状軽減のためのマッサージや温罨法
・水分摂取の分散化と適切な補給援助
・医師と連携した栄養管理方針の調整
・管理栄養士との連携による食事内容の最適化
・家族との食事摂取支援方法の共有
≪E-P≫教育・指導計画
・胃切除後の消化機能の変化と食事への影響の説明
・少量頻回食の重要性と具体的な実践方法の指導
・早期満腹感に対する対処方法と食事のコツの指導
・ダンピング症候群の予防と症状出現時の対応方法の説明
・退院後の食事管理と栄養バランスの取り方の指導
・家族に対する食事支援の方法と注意点の説明
看護問題
術後の身体的変化と将来への不安に関連した睡眠・休息障害
長期目標
退院時までに睡眠導入剤に頼らずに自然な入眠ができ、質の良い睡眠を6時間以上確保できる
短期目標
1週間以内に入眠までの時間を30分以内に短縮し、中途覚醒を週3回以下に減少させる
≪O-P≫観察計画
・入眠までの時間と睡眠時間の推移
・中途覚醒の回数と覚醒時間
・睡眠導入剤使用の頻度と効果
・日中の眠気や疲労感の程度
・不安の内容と程度の変化
・創部痛の程度と疼痛パターン
・夜間の腹部症状や身体的不快感
・睡眠環境に対する反応と適応状況
・表情や言動による精神状態の変化
・朝の覚醒感と活動意欲の程度
・日中の活動量と休息のバランス
・家族面会時の精神状態の変化
≪T-P≫援助計画
・適切な疼痛管理と鎮痛薬の効果的な使用
・就寝前のリラクゼーション技法の実施支援
・睡眠環境の調整と騒音・照明の管理
・日中の適度な活動と夜間の安静の確保
・不安軽減のための傾聴と精神的支援
・温罨法や軽いマッサージによるリラクゼーション
・睡眠導入剤の適切な使用と段階的減量支援
・夜間の安全確保と転倒予防対策
・就寝前の清潔ケアと快適な寝具の提供
・医師と連携した睡眠障害の治療方針調整
・家族との面会時間調整による精神的安定の確保
・必要時の臨床心理士や精神科医師との連携
≪E-P≫教育・指導計画
・術後の睡眠障害の原因と改善過程の説明
・睡眠衛生に関する知識と実践方法の指導
・リラクゼーション技法の習得支援
・不安に対する適切な対処方法の指導
・睡眠導入剤の適切な使用方法と注意点の説明
・家族に対する患者の精神的支援方法の指導
看護問題
胃切除術に伴う腸蠕動機能の低下に関連した便秘
長期目標
退院時までに下剤に依存せずに2日に1回以上の自然排便ができ、腹部不快感が軽減される
短期目標
1週間以内に下剤使用下で毎日1回の排便を確保し、腹部膨満感を軽減できる
≪O-P≫観察計画
・排便の回数と便の性状・量の変化
・腹部膨満感や腹痛の程度と部位
・腸蠕動音の聴取と腸管機能の評価
・下剤の効果と副作用の出現状況
・水分摂取量と電解質バランス
・食物繊維摂取量と食事内容
・活動量と歩行状況の変化
・腹部マッサージや体位変換の効果
・排便時の努責や困難感の程度
・肛門周囲の皮膚状態と清潔保持
・血液検査データの推移
・患者の便秘に対する不安や困惑の程度
≪T-P≫援助計画
・下剤の適切な使用と効果判定
・腹部マッサージと腸蠕動促進ケア
・適切な水分摂取の促進と摂取量管理
・病棟内歩行や軽い運動の実施支援
・食物繊維を含む食品の段階的導入
・排便を促す体位の指導と環境整備
・温罨法による腹部の温め効果の活用
・プライバシーに配慮した排泄環境の提供
・排便パターンの記録と評価
・医師と連携した下剤の種類や用量調整
・便意を感じた際の迅速な排便支援
・肛門周囲の清潔ケアと皮膚保護
≪E-P≫教育・指導計画
・術後便秘の原因と改善過程の説明
・水分摂取の重要性と適切な摂取方法の指導
・腹部マッサージの方法と実施タイミングの指導
・適度な運動と活動の便秘改善効果の説明
・食物繊維の効果的な摂取方法と注意点の指導
・家族に対する便秘改善のための生活支援方法の説明
この記事の執筆者

・看護師と保健師免許を保有
・現場での経験-約15年
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
コピペ可能な看護過程の見本
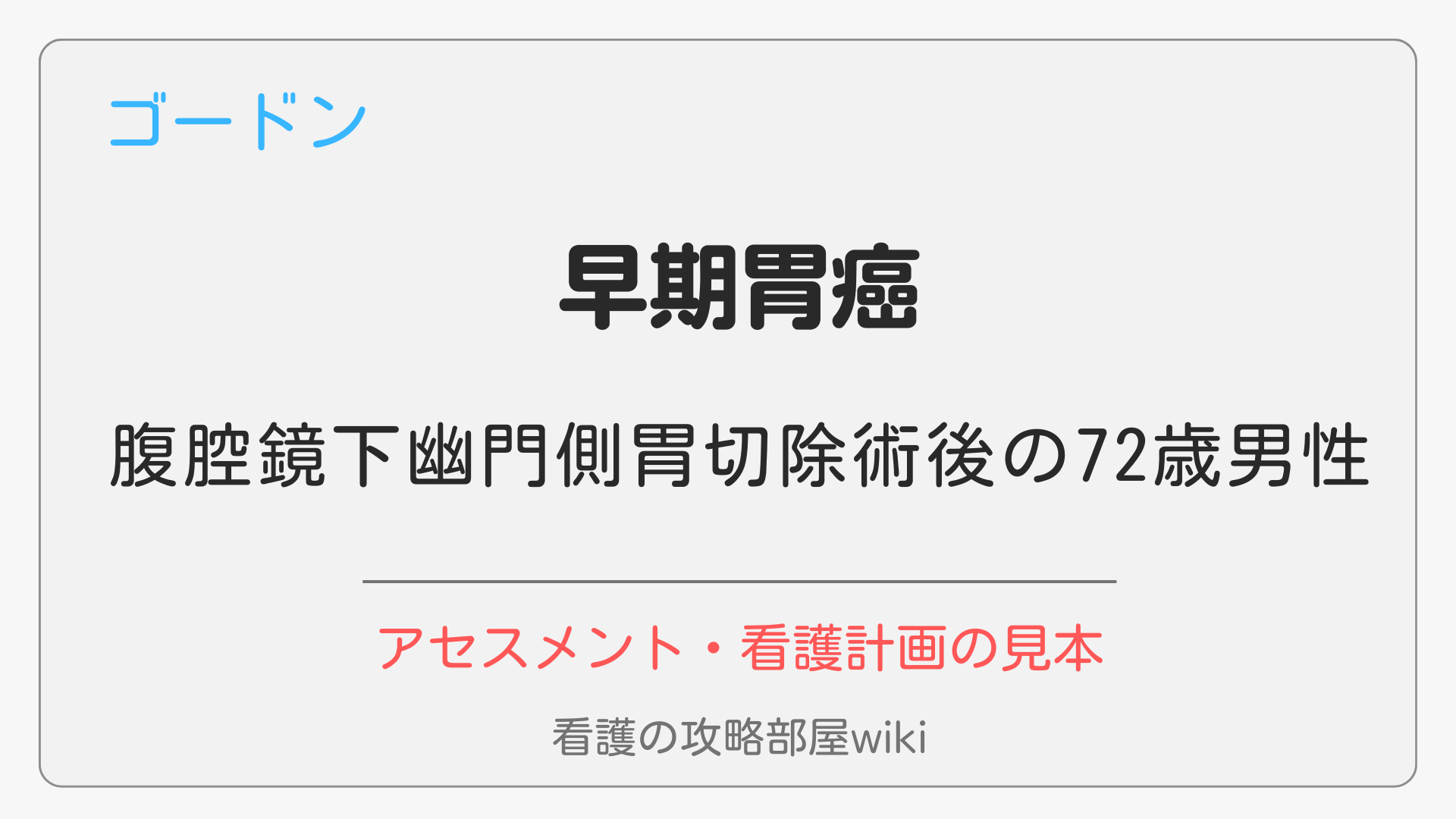
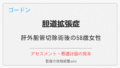
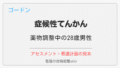
コメント